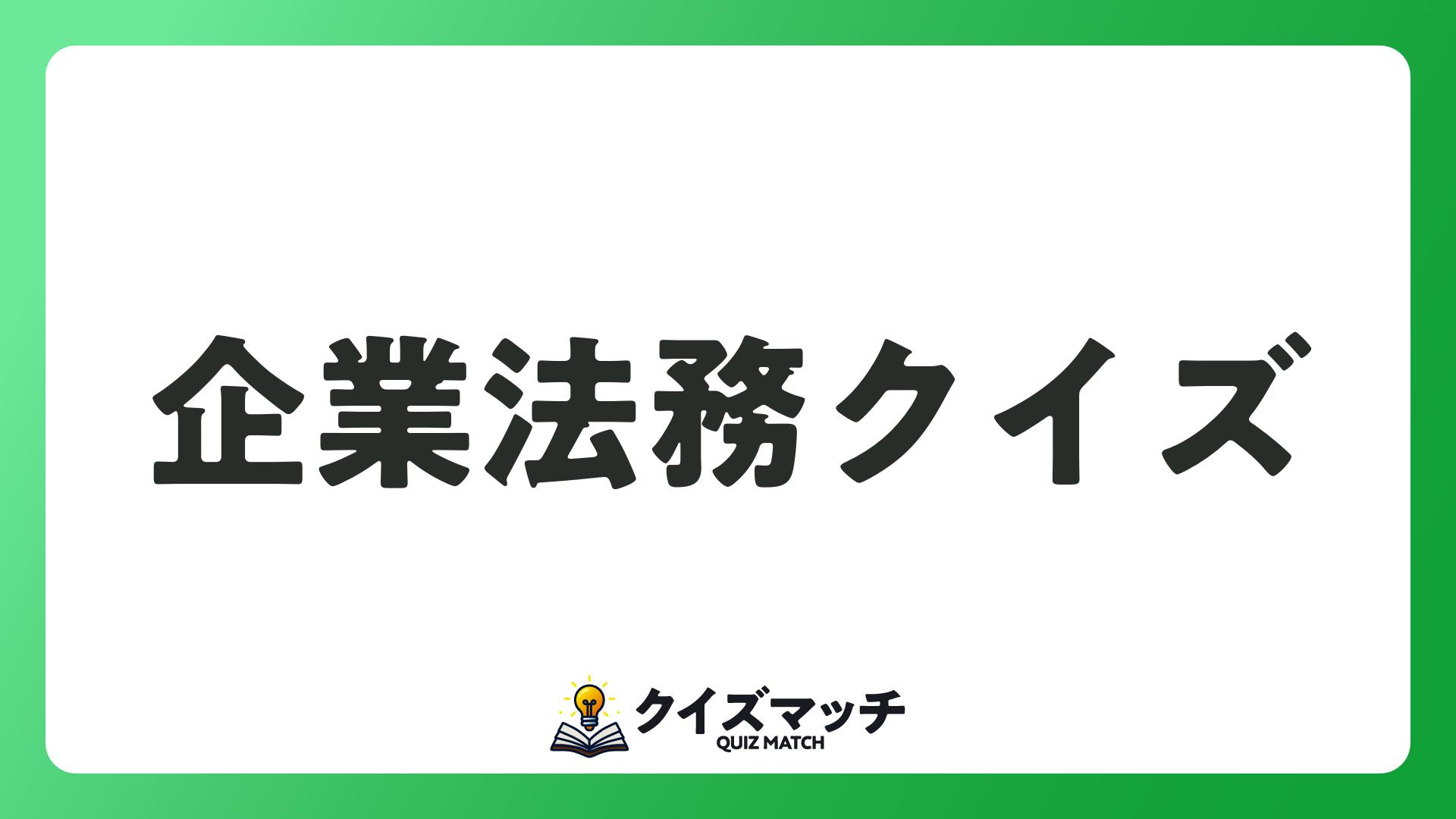企業法務に関する知識を試すクイズ特集です。企業活動においては、会社法や独占禁止法、労働法など様々な法規制に留意する必要があります。本記事では、企業法務に関する基礎知識を問う10問のクイズを用意しました。取締役会や株主総会、営業秘密の管理、独占禁止法の規制内容など、企業経営に欠かせない重要なポイントを確認できます。法務担当者はもちろん、経営者やビジネスパーソンの方々にも役立つ内容となっています。実践的な企業法務クイズにぜひチャレンジしてみてください。
Q1 : 秘密保持契約(NDA)において、不正開示となりうる行為はどれか?
秘密保持契約(NDA)において、情報提供元の承認なく第三者に情報を開示することは契約違反、つまり不正開示となります。許可がある場合や、既知の情報、法令・命令に基づく開示は通常契約違反には該当しません。不正開示は損害賠償や信頼失墜につながる重大な契約違反行為です。
Q2 : 会社法における株主代表訴訟で、株主がまず行うべきことは?
会社法では、株主が会社に損害を与えた取締役等に対して訴えを起こしたい場合、まず会社に訴訟提起を請求する必要があります(代表訴訟)。これに会社が応じない場合に限り、株主が自ら訴訟を提起できます。いきなり裁判所に訴えることはできません。
Q3 : 独占禁止法に基づき、課徴金が課される対象となる行為はどれか?
独占禁止法による課徴金の対象は主に価格カルテルや入札談合などの不当な取引制限行為です。私的独占や再販売価格維持、優越的地位の濫用も独禁法違反となりますが、課徴金の対象は基本的に価格カルテル等に限定されています。
Q4 : 役員が会社の利益を害して自社と取引をした場合、その利益相反取引について必要な手続きは何か?
取締役が会社と自ら取引(利益相反取引)を行う場合は、会社法であらかじめ取締役会の承認を得ることが義務付けられています。これは、会社の利益より個人の利益が優先されることを防ぐためです。取締役会設置会社においては、株主総会ではなく取締役会の承認が必要です。
Q5 : 下請法(下請代金支払遅延等防止法)に違反するとどうなるか?
下請法に違反した場合、中小企業庁や公正取引委員会から行政指導や勧告を受けることになります。その後も是正されない場合は、企業名公表や命令が行われることもあります。刑事罰だけに限られるのではなく、まずは行政措置が中心です。
Q6 : 株主総会の普通決議で必要な議決権の過半数はどれか?
株主総会の普通決議は、会議に出席した株主の議決権の過半数による決議が必要です。したがって、例えば全議決権の過半数ではなく、出席者に基づくため欠席株主の議決権はカウントされません。定款に別段の定めがある場合はこの原則が変わることもあります。
Q7 : 労働契約終了後の競業避止義務に関して、最も正しい記述はどれか?
労働契約終了後の競業避止義務は、公序良俗に反しない範囲で有効とされますが、必ずしも一律に有効ではありません。期間、地域、職務内容などが著しく広範または長期間の場合、無効とされる可能性もあります。そのため、個別の事情を考慮したうえで、有効性が判断されます。
Q8 : 独占禁止法が規制する主な行為はどれか?
独占禁止法は、事業者間の競争を公正に保つことを目的としており、特にカルテル(一部企業による価格協定などの協定行為)や市場支配的行為、入札談合などを主に規制しています。他の選択肢は別の法令によって規制されており、たとえばインサイダー取引は金融商品取引法が規制対象です。
Q9 : 営業秘密の不正使用に該当しないものはどれか?
営業秘密は、不正競争防止法により不正使用が禁止されていますが、正当な手段で独自に開発した場合は不正使用になりません。盗用や、元社員の持ち出し、秘密保持契約違反による利用は不正使用にあたります。独自開発による同一技術の利用は、たとえ結果として同じ技術になっても、不正な入手・使用でない限り違法ではありません。
Q10 : 会社法において、取締役会設置会社に義務付けられている機関はどれか?
会社法において、取締役会設置会社には、少なくとも株主総会、取締役会、取締役、及び監査役(または監査等委員会等)といった機関設計が義務付けられています。特に株主総会は会社の基本的意思決定機関として必ず存在しなければなりません。他の選択肢である監査役会や会計監査人は必須とは限りませんが、規模や会社形態によって必要となる場合があります。
まとめ
いかがでしたか? 今回は企業法務クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は企業法務クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。