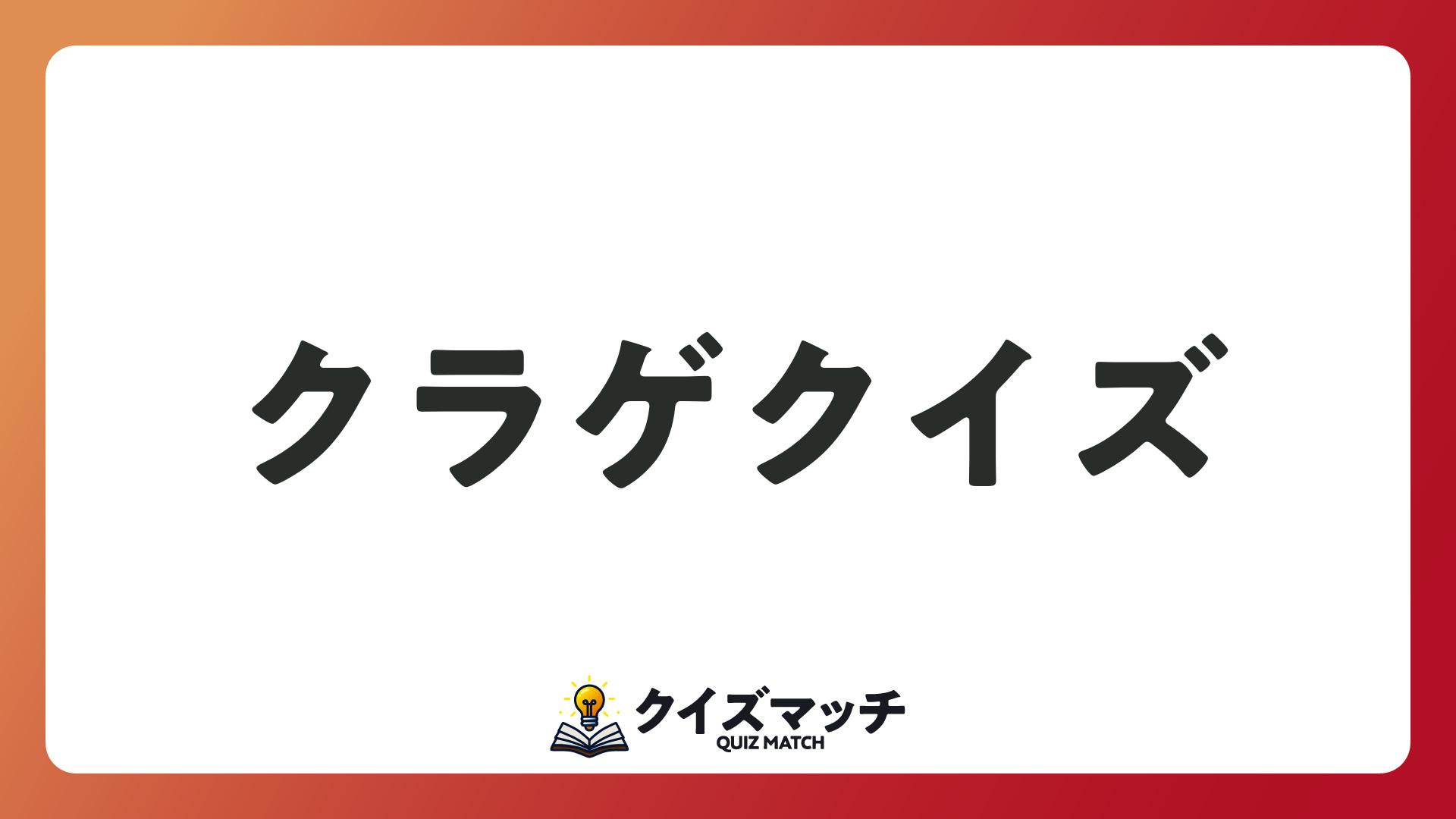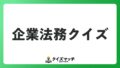クラゲは私たちの身近な海の生き物ですが、実は知られていないことが多いのが現状です。本記事では、クラゲの驚くべき特徴や生態について、クイズ形式で10問ご紹介します。水分が95%以上を占める驚異的な体内構造から、巨大な種類の存在、強力な毒針の秘密まで、クラゲの魅力的な側面を一挙に知ることができるはずです。海のふしぎな生き物、クラゲについて、ぜひ楽しみながら学んでみてください。
Q1 : クラゲの生態で、赤ちゃん(幼生)の名前として最も正しいものは?
クラゲの受精卵から孵化する幼生は「プラヌラ」と呼ばれます。プラヌラは泳いだ後、固着してポリプとなり、やがて成長してクラゲの形(メデューサ)に変態します。この複雑なライフサイクルがクラゲの大きな特徴です。
Q2 : クラゲの一部種類が持つ発光性は何のためと考えられていますか?
クラゲの中には発光する種類もあり、これは主に外敵から逃げたり威嚇したりするためと考えられています。突然光ることで捕食者を驚かせたり、擬態として自分の姿を隠したりする効果があるとされます。
Q3 : クラゲの英語名は次のうちどれでしょう?
クラゲの英語名は「Jellyfish(ジェリーフィッシュ)」です。魚ではありませんが、水中を浮遊するゼリー状の見た目が由来とされています。
Q4 : クラゲの主な消化方法はどれですか?
クラゲは口から取り込んだ餌を消化管内に入れ、内部で消化して栄養を吸収します。消化の仕組みは単純ですが、消化管と呼ばれる袋状の部分で酵素分解を行っています。一部のクラゲは口腕でも摂食補助を行います。
Q5 : クラゲが移動するとき、主にどの器官を使って推進力を得ますか?
クラゲの代表的な動きは、傘と呼ばれる部分を収縮・拡張させることで水を押し出して推進力を得ることです。この構造はクラゲ独特のもので、水中での浮遊やゆっくりとした移動に適しています。
Q6 : 刺されると命の危険がある猛毒クラゲ「ハブクラゲ」が多く見られるのは日本のどの地域でしょうか?
ハブクラゲは日本では主に沖縄周辺の南西諸島で見られます。このクラゲは毒性が非常に強く、人が刺されると呼吸困難や心肺停止など命の危険を及ぼす場合があります。特に夏場の海水浴シーズンは注意が必要とされています。
Q7 : クラゲの仲間として次のうち正しいものはどれ?
イソギンチャクはクラゲと同じ刺胞動物門に属しており、同じく刺胞を持っています。カブトクラゲは「クシクラゲ類」という別のグループで、外見は似ていますが分類上は異なります。カタツムリは軟体動物門、サンゴも刺胞動物門ですが、クラゲの直接の仲間はイソギンチャクです。
Q8 : クラゲが持つ毒針細胞(刺胞)は何という器官内にあるでしょうか?
クラゲの毒針細胞は『刺胞(しほう)』と呼ばれる細胞に含まれており、この刺胞が相手に触れることで瞬時に毒液を注入します。刺胞はクラゲの触手などに多数存在し、餌の捕獲や外敵への防御に使われています。
Q9 : 日本の海で最も大きくなるクラゲ「エチゼンクラゲ」の最大直径は約どれくらいでしょうか?
エチゼンクラゲは日本近海で見られる非常に大型のクラゲで、最大で直径2メートルにも達します。また、重さも200kgを超える個体も報告されることがあり、その巨大さから漁業に大きな影響を及ぼすことでも知られています。
Q10 : クラゲの体の大部分を占めている成分はどれですか?
クラゲの体は約95%以上が水でできており、残りはタンパク質やミネラルなどの成分です。多くの種類のクラゲは非常にみずみずしい見た目をしており、これはその高い水分含有率によるものです。そのため、干からびると姿形がほとんどなくなってしまうほど水分が多いのが特徴です。
まとめ
いかがでしたか? 今回はクラゲクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回はクラゲクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。