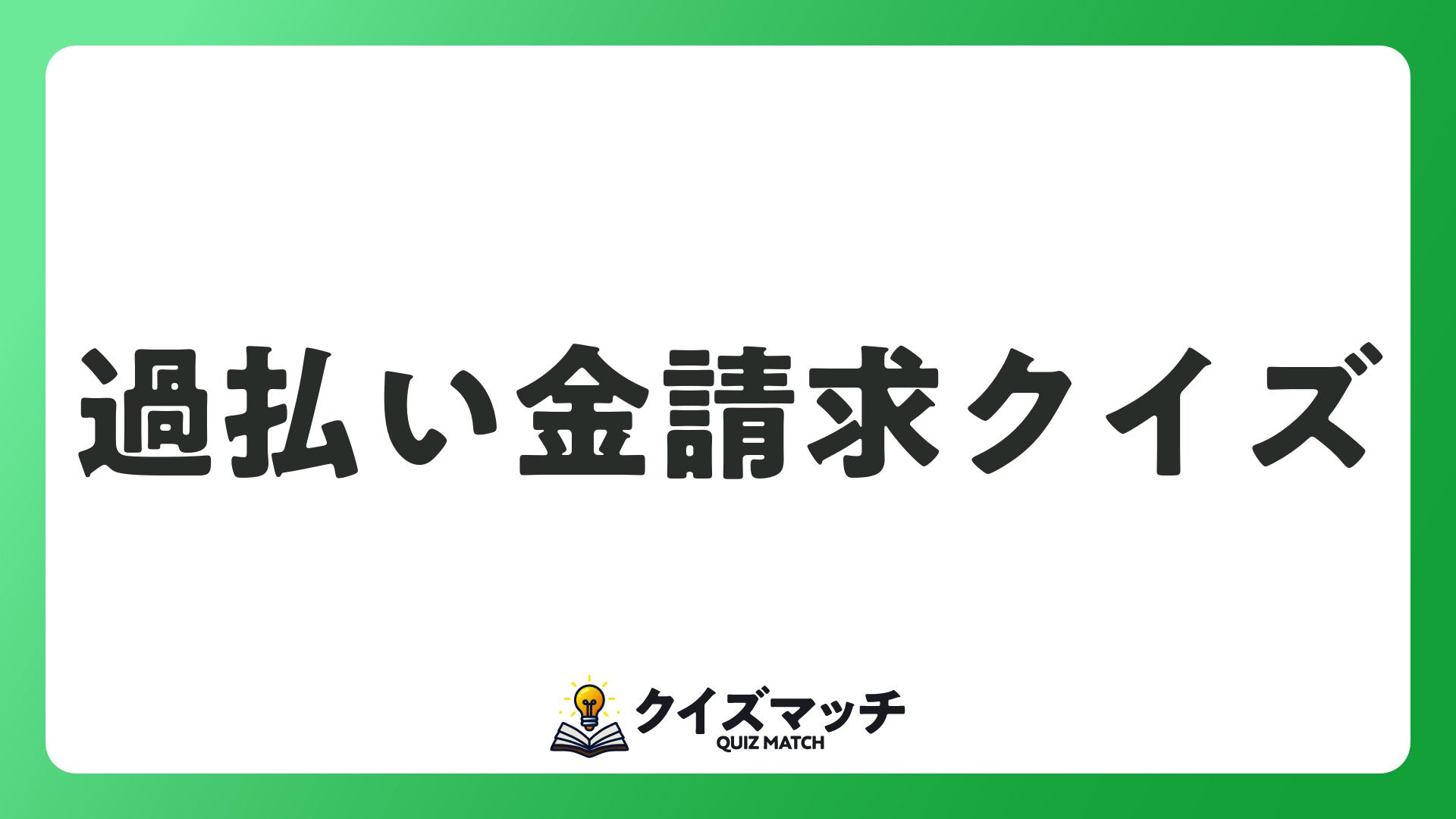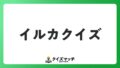過払い金請求は多くの消費者にとって重要な権利ですが、その実務に関する知識はまだ十分とはいえません。本記事では、過払い金請求に関するクイズを通じて、この権利の対象や手続き、留意点などを具体的に解説します。消費者金融などから違法な高金利で借入れをしていた方は、この機会に自身の状況を確認し、適切な過払い金請求を検討してみてはいかがでしょうか。
Q1 : 過払い金の返還請求で、相手業者と示談せず裁判になる場合、通常どの裁判所へ提訴されるか?
過払い金に関する民事訴訟は、請求金額が140万円以下なら簡易裁判所、140万円超なら地方裁判所が管轄します。ただし、多くの過払い金請求案件は140万円以下であることが多いため、簡易裁判所が利用されるケースが圧倒的です。場合によっては地方裁判所も選択されます。
Q2 : 過払い金請求の対象とならないものはどれ?
過払い金が発生するのは、利息が高く設定されていた消費者金融のローンやクレジットカードのキャッシング等です。住宅ローンのような低金利(利息制限法の範囲内)・長期のものは過払いの対象外となります。何に対して過払い請求ができるか理解することが重要です。
Q3 : 過払い金請求をした場合の主なデメリットはどれ?
過払い金請求をしただけでは、信用情報に事故情報として載る(俗にいうブラックリスト入りする)わけではありません。ただし、その業者からは今後の貸付けが拒否されるケースがほとんどです。過払い金で返済済みになってもすべての借金が消えるわけでもないので注意が必要です。
Q4 : 過払い金請求の手続きで、過去の取引履歴を取得するために貸金業者に対して出す書面を何と呼ぶか?
『取引履歴開示請求書』は、過払い金請求をするために過去の借入・返済履歴を貸金業者に提出・開示させるための書面です。履歴の開示は債権者に義務づけられており、この履歴に基づいて専門家が利息制限法で再計算することで、過払い金の額が確定します。
Q5 : 過払い金請求を弁護士・司法書士に依頼した場合、依頼人が最終的に支払う報酬体系で正しいものは?
弁護士や司法書士へ過払い金請求を依頼すると、着手金と成功報酬という報酬体系が一般的です。着手金は案件開始時に、成功報酬は過払い金が実際に回収できた場合に回収額の一定割合を支払う形が多いです。完全成功報酬や相談無料の事務所も増えていますが、多くは着手金+成功報酬制です。
Q6 : 借入金利が『グレーゾーン金利』と呼ばれていた範囲はどれにあたるか?
グレーゾーン金利は、利息制限法の上限(15〜20%)と出資法の上限(29.2%)の間、20%〜29.2%の利率を指します。2006年前後には多くの消費者金融等がこの範囲で貸付をしていましたが、このゾーンが後に違法と認定され、過払い請求につながる根拠となりました。
Q7 : 過払い金請求権が認められないケースは次のうちどれか?
過払い金は、利息制限法の上限を超えた利息を支払い続けていた場合に発生します。そもそも契約が最初から法律の範囲内の利率だった場合は、過払い金は存在しません。完済後の時効や他の条件もありますが、利率が違法でない限り請求権そのものが存在しません。
Q8 : 過払い金請求ができる時効(消滅時効)期間は原則として何年か?
過払い金請求の消滅時効は、民法改正前と改正後で異なりますが、一般に「最後の取引から10年」が原則です。2019年4月1日以前は民法による10年、以降は法律改正により複雑な要素もありますが、多くの実務では一律10年と考えられています。請求が遅れると権利を失うため注意が必要です。
Q9 : 利息制限法の上限金利は、元本10万円未満の部分で何%か?
利息制限法では、元本10万円未満は年20%以下と定められています。元本10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%となっています。これを超える利率は法律上無効となり、超過分は過払い金として返還請求できます。金利を理解しておくことが過払い金請求知識の基礎となります。
Q10 : 過払い金請求の対象となる貸金業者からの借入について、過払い金請求のきっかけとなった最高裁判決の年はどれ?
過払い金請求のきっかけとなったのは、2006年1月13日の最高裁判決です。この判決により、利息制限法を超えて支払った利息部分が過払い金(返還請求権の対象)であることが明確化されました。貸金業法などの改正もこれに続き、過払い金請求が一般化し多くの人で認知されるようになりました。
まとめ
いかがでしたか? 今回は過払い金請求クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は過払い金請求クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。