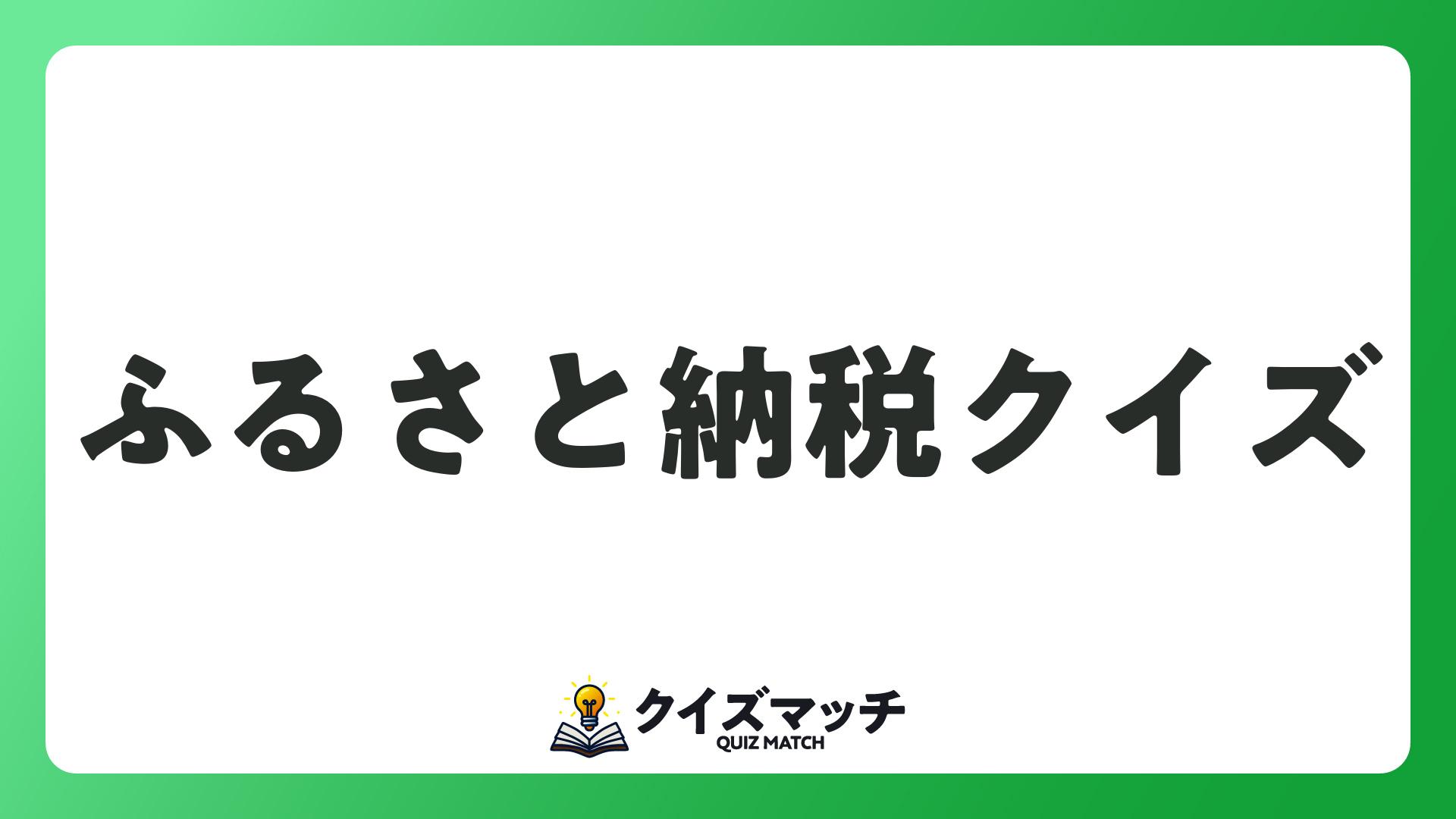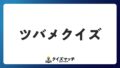ふるさと納税は、地方自治体への寄附を行うことで、翌年の所得税や住民税の一部を控除できる制度です。2,000円の自己負担で、残りの寄附金が税金から控除されるのが特徴です。しかし、その仕組みやルールは複雑で、意外と知られていないことも多いのが現状です。そこで今回は、ふるさと納税についての基礎知識をテストする10問のクイズをお届けします。ふるさと納税の仕組みを理解し、上手に活用する機会にしていただければと思います。
Q1 : ふるさと納税のメリットとして『税金の二重控除』が発生しない理由は?
ふるさと納税の控除は、住民税・所得税などから決まった額だけが控除される制度設計となっており、申告書類や自治体管理でチェックが入るため、同じ寄附で税金の二重控除が起きないようになっています。制度上の安全策です。
Q2 : ふるさと納税の寄附先で、応援の用途を指定できる制度を何と呼ぶ?
ふるさと納税では、お金の「使い道」や応援したい事業(福祉、教育、災害復興など)を指定する「使い道指定制度」を設けている自治体が多いです。寄附者の意思が活かされる仕組みです。
Q3 : ふるさと納税の寄附金控除を受ける場合、必要な書類はどれ?
ふるさと納税の控除申請には、ワンストップ特例制度利用なら「ワンストップ特例申請書(マイナンバー確認書類等を添付)」、確定申告の場合は「寄附金受領証明書」が必要です。領収書や広報誌、印鑑証明などは控除申請に用いません。
Q4 : ワンストップ特例制度で寄附した場合、税控除は何から行われるか?
ワンストップ特例制度では、寄附控除が翌年度住民税からのみ全額控除されます。確定申告時は寄附額が所得税・住民税、両方の控除になりますが、ワンストップ特例は住民税控除のみで、所得税還付はありません。
Q5 : ふるさと納税の申込方法として使えないものはどれか?
ふるさと納税の申込は、インターネット上のふるさと納税サイト(さとふる、ふるさとチョイス等)や自治体窓口、郵送で行えますが、電話受付は原則行われていません。正確な入力・管理が必要なため、電話での寄附申請は使えないのが一般的です。
Q6 : ふるさと納税の寄附先に選ぶことができる自治体は?
ふるさと納税は「どの自治体にも寄附できる」制度です。自分の出身地や応援したい地方自治体、全国すべての市区町村や都道府県など自由に選ぶことができます。ただし、自分の住んでいる自治体に寄附しても、お礼の品はもらえないケースが多いです。
Q7 : ふるさと納税のお礼の品として認められていない代表的なものはどれか?
観光地の地元の農産物や伝統工芸品、海産物などは、お礼の品として認められていますが、お金に換金しやすい旅行券や金券類、プリペイドカード等は2019年6月の法改正により原則禁止となっています。
Q8 : ふるさと納税の『ワンストップ特例制度』が適用されるのは、1年間で何自治体まで寄附した場合か?
ワンストップ特例制度は、確定申告をしない給与所得者などが、1年間に5自治体以内の寄附で適用できます。6自治体以上寄附した場合や確定申告をする必要がある人はこの制度が使えず、確定申告が必要です。
Q9 : ふるさと納税で寄附すると、自己負担が原則いくらになるか?
ふるさと納税は基本的に2,000円を超える部分が税金控除の対象となります。2,000円は自己負担となり、その分のみは控除されません。2,000円は「自己負担額」と呼ばれ、この金額を除いた寄附額が住民税や所得税から控除されます。
Q10 : ふるさと納税による控除の対象となる寄附金額の上限を何と呼ぶでしょう?
ふるさと納税では、所得や家族構成などによって決まる「控除上限額」までの寄附であれば、実質2,000円の自己負担でお礼の品を受け取ることができ、残りの金額は翌年の所得税や住民税から控除されます。控除可能な金額のシミュレーションも各サイトで計算できます。
まとめ
いかがでしたか? 今回はふるさと納税クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回はふるさと納税クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。