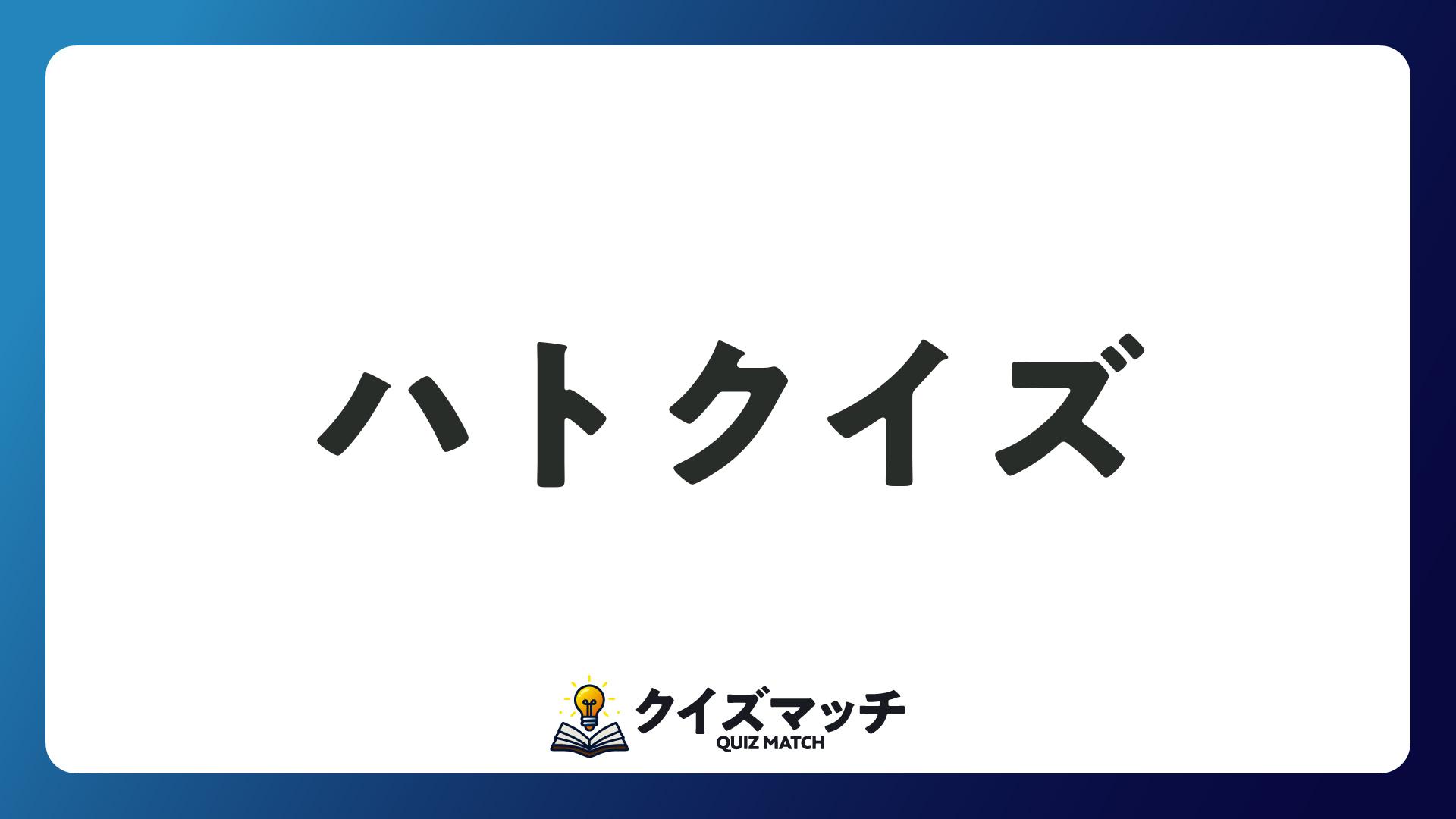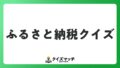ハトはとても身近な鳥です。都市部を中心に、私たちの生活空間の中で見かけることが多いですね。そんなハトについて、その特徴や習性、生態などを10問のクイズを通して紹介します。ハトの正式名称から、餌の食べ方、繁殖の様子、帰巣本能の秘密まで、ハトについて楽しく学べる内容となっています。ハトは身近な存在ですが、実は意外な一面も持っているのかもしれません。ぜひ、このクイズを通してハトの魅力を発見してみてください。
Q1 : ハトが人間の生活圏で増加したもっとも大きな理由は?
ハトは人間の生活圏、特に都市部で餌が多く外敵も少ないため、個体数が増加しました。公園などで人々から餌をもらいやすく、安全な巣づくり場所も多いため、都市での生息数が増えたとされています。他の理由は副次的なものです。
Q2 : ハトの餌として一般的にふさわしくないものはどれ?
ハトには本来、穀物や種子、豆類が主な餌ですが、パンくずは塩分や添加物が多く、ハトの健康には適していません。パンくずを与える行為が問題視されている自治体もあり、野生動物には本来の餌を与えるのが適切です。
Q3 : 日本に自生するハトの仲間で、青い羽根が特徴なのはどれ?
日本に生息するアオバトは体の大部分が美しい青緑色の羽で覆われています。山地や森に住み、「アオバト」の名の通り青い羽色が最大の特徴です。他の種類ではこの鮮やかな色は見られません。
Q4 : ハトの羽音がフラップ音として人間に聞こえるのはなぜ?
ハトは飛び立つ際や飛行時に、羽ばたきが非常に早いため、羽音(フラップ音)が「バサバサ」と大きく聞こえます。この音はハトの特徴的な飛び方によるもので、特に驚いて飛び立つ時によく感じられます。
Q5 : ハトが「帰巣本能」でよく知られている理由は?
ハトは非常に強い帰巣本能を持ち、遠く離れた場所からも自分の巣へ戻る能力があります。この特性を利用して伝書鳩が生まれました。複雑な歌や渡りとは関係なく、何百キロ離れても戻る能力が他の鳥と異なる点です。
Q6 : 日本で一般的に「ハト」といえばどの種を指すことが多い?
日本で「ハト」と言うと、ほとんどの場合都市部で最も見かける“ドバト(カワラバト)”を指します。キジバトなども生息していますが、野生では郊外や林で見かけることが多く、一般に親しまれているのはドバトです。
Q7 : ハトのひな(雛)はふつう外で見かけない理由は?
ハトの巣はほとんどが建物の高い場所や木の上、橋の下など人目につきにくい場所につくられます。そのため、雛を見る機会はほとんどありません。また、巣立ち直前まで巣にいるため外で雛を見かけることは稀です。
Q8 : ハトの仲間で日本国内で最も古くから伝書鳩などに利用されたのは何バト?
日本で伝書鳩として用いられてきたのは主にカワラバト(ドバト)です。カワラバトは高い帰巣本能を持っているため、古来より連絡や通信の手段として世界各国で使われてきました。キジバトやアオバトも日本に生息しますが、伝書鳩にはなりません。
Q9 : ハトが餌を食べるときによくする動作はどれ?
ハトは歩くときや餌を食べるときに首を前後や上下に振る独特の動作をします。これは視界を安定させるためであり、人間には愛らしく映ります。他の選択肢もハトがする行動ですが、餌に関しては首を振るのが特徴的です。
Q10 : ハトの正式な和名はどれですか?
日本で最も見かける「ハト」はドバト(カワラバト)と呼ばれています。正式な和名は「ドバト」です。ドバトは都市部などで見かける灰色のハトで、伝書鳩やレース鳩としても利用されています。カワバトやヒメバト、キジバトは別種のハト科の鳥ですが、街中で最もなじみ深いのはドバトです。
まとめ
いかがでしたか? 今回はハトクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回はハトクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。