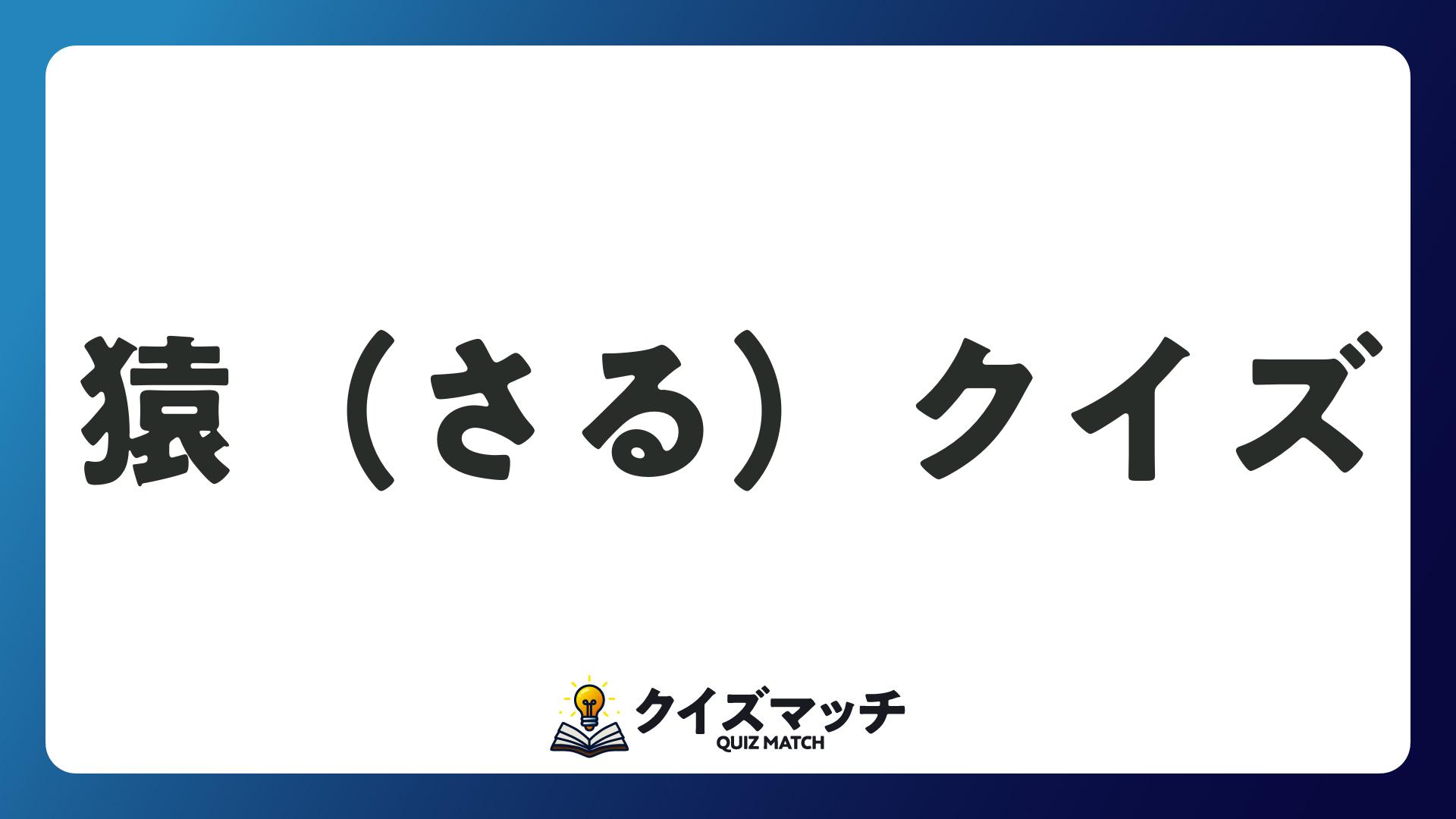日本に生息する野生のサルは、ニホンザルただ一種です。この小型のサルは、世界で最も北に分布するサルの仲間として知られています。ニホンザルは、雪深い地域でも生活できる寒さに強い特徴があり、「見ざる、言わざる、聞かざる」の三猿像で有名な日光東照宮にも生息しています。本記事では、ニホンザルを中心とした「猿クイズ」10問をお楽しみいただけます。サルの不思議な習性や文化的な意義について、クイズを通じて学んでいただければと思います。
Q1 : 猿の毛繕い(グルーミング)の主な目的は?
グルーミング(毛繕い)は、猿にとって単に清潔を保つための行為だけでなく、社会的な絆や信頼関係を強める重要な意味があります。毛繕いを通じて互いの関係を確認し、群れの安定やストレスの軽減にもつながります。したがって、社会的行動として非常に大きな役割を果たします。
Q2 : ニホンザルの主な群れの構成はどのようになっている?
ニホンザルの社会は、多くのメスとその子供たち、そして少数の成熟したオスから構成される母系社会です。メスは生まれた群れに一生とどまるのが普通で、オスは成長すると群れを離れます。一夫一婦制やオスのみで構成される群れではありません。
Q3 : 新世界ザルと旧世界ザルの違いとして正しいものは?
新世界ザル(中南米産)と旧世界ザル(アジア・アフリカ産)の主な違いは鼻の形状や尾の特徴にあります。新世界ザルは外側に開いた幅広い鼻孔、一部で物をつかめる尾をもつ種がいます。旧世界ザルは鼻孔が前向きで、尾で物をつかめることはありません。他の特徴は必ずしもすべてに当てはまりません。
Q4 : 日本では古来より猿はどのような役割で信仰されてきたか?
日本では、猿は神の使い(特に山の神の使い)や、災厄除けの神聖な動物として信仰されてきました。特に申歳や田の神、厄除けなどと結びついている例が多いです。日枝神社の祭神「大山咋神(おおやまくいのかみ)」の眷属とされ、神社の狛犬の代わりに猿の像が置かれることもあります。
Q5 : メスの猿がボスになることがある種の名前は?
ボノボは、アフリカ中部に生息するサルの一種であり、社会の主導権をメスが握ることで有名です。一般的な霊長類社会ではオスがボスになるケースが多いですが、ボノボは母系社会であり、メスの連帯によって群れがまとめられます。他の種では基本的にオスが支配的です。
Q6 : 世界に現存する猿の主なグループは何種類ある?
世界のサルには旧世界ザル(アジア、アフリカ)と新世界ザル(中南米)の二つの主なグループが存在します。形態・習性など多くの相違点があり、例えば尾が長いものや指の使い方などで違いがみられます。ゴリラや人間だけでなく、本来『サル』と『類人猿』『ヒト』は区別されます。
Q7 : ニホンザルが冬眠しない理由はどれでしょう?
ニホンザルは冬眠しません。その理由は、積雪の多い地域でも木の実や芽、樹皮、昆虫などを巧みに探し出して食料を確保できるためです。また体温調節が比較的うまく、雪の上や寒い中でも活動できる能力を持ちます。他の理由は冬眠の有無と直接関係しません。
Q8 : ニホンザルが生息している最南端の島はどこでしょう?
ニホンザルの自生している日本の最南端は屋久島(鹿児島県)です。屋久島は亜熱帯的な気候に加えて、豊かな森林が広がり、ニホンザルの繁殖も盛んに行われています。沖縄をはじめ南西諸島には野生のサルは自然分布していません。屋久島のサルは「ヤクザル」とも呼ばれ、少し小柄なのが特徴です。
Q9 : 「見ざる、言わざる、聞かざる」の三猿像があることで有名な世界遺産は?
「見ざる、言わざる、聞かざる」の三猿像は、栃木県の日光東照宮の神厩舎に彫られた有名な彫刻です。人が生きる上で「悪事を見ない、言わない、聞かない」ことの象徴とされています。三匹の猿がそれぞれ目・口・耳を手で隠している姿は日本を代表する文化的なモチーフです。他の選択肢には三猿像がありません。
Q10 : 日本に生息している猿の種類は次のうちどれでしょう?
日本で自然分布している唯一のサルはニホンザル(Macaca fuscata)です。北海道を除く日本全国に生息し、世界で最も北に分布するサルとしても知られています。他の選択肢のヒヒ、テナガザル、リスザルは日本の野生環境には生息していません。ニホンザルは雪深い場所でも生活できるなど、寒さに強い特徴があるのも有名です。
まとめ
いかがでしたか? 今回は猿(さる)クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は猿(さる)クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。