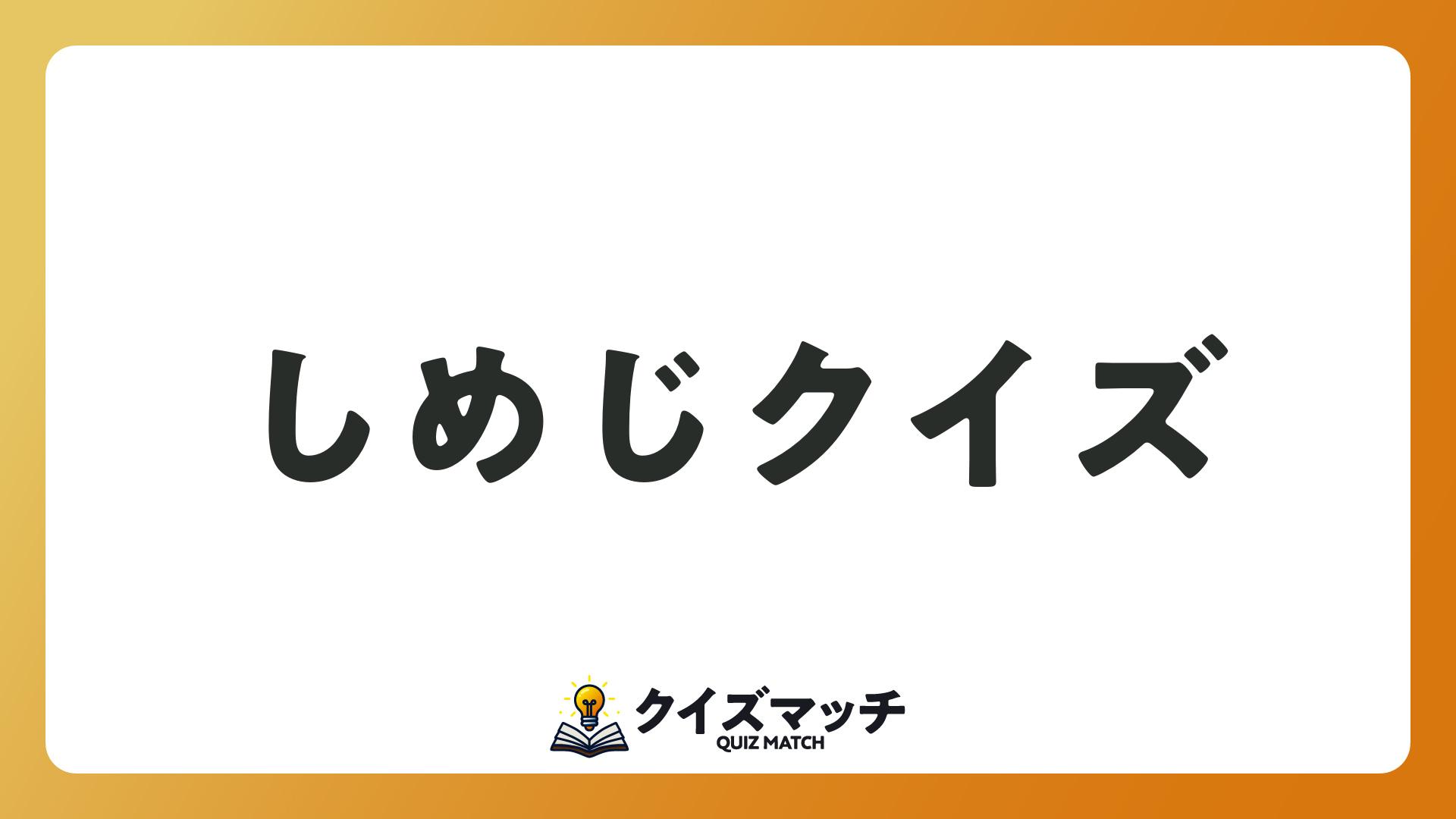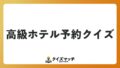しめじは秋が旬とされ、自然界で特に見られるのもこの時期です。現在は一年中栽培されていますが、味や香りが最も豊かになるのが秋とされています。しめじはキノコ類に分類される菌類で、主に菌床栽培で生産されています。ブナシメジの名前は、ブナ科の木によく発生するためです。近年、品種改良が進み、特有の苦味が改善され、旨味と香りが豊かな製品が主流となっています。
Q1 : パッケージに「本しめじ」と記載されたものがスーパーで売られていますが、この「本しめじ」とは?
スーパーで「本しめじ」と表示されているものは、天然の本しめじではなく、人工的に栽培されたものです。近年、技術が進歩し人工栽培の本しめじが流通しています。天然物は非常に希少となっています。
Q2 : しめじに多く含まれる成分で、特徴的なのはどれでしょう?
しめじをはじめとしたキノコ類には食物繊維が豊富に含まれています。食物繊維は腸内環境を整える働きがあり、現代人の健康維持に役立つ成分です。ビタミンCはあまり含まれていません。
Q3 : しめじを保存するのに最適な方法は?
しめじは冷蔵庫の野菜室で袋に入れたまま保存すると鮮度が比較的保てます。水に漬けると傷みやすくなり、直射日光も風味の劣化や乾燥を招くため適しません。袋のまま保存するのが基本です。
Q4 : 次のうち、しめじが特に良く利用される料理はどれでしょう?
しめじは多用途のキノコですが、特に味噌汁の具材として人気があります。他にも鍋料理や炊き込みご飯、炒めものに使われますが、和食の定番である味噌汁との相性は抜群です。
Q5 : 天然の本しめじと市販のぶなしめじの違いとして正しいのは?
本来の「本しめじ」は天然ものが希少で高価です。市販の「しめじ」はブナシメジが主流となっています。本しめじはとても香り豊かで高級とされていますが、ぶなしめじは流通量が多く、日常的に手に入ります。
Q6 : 一般的な栽培用のしめじの味の特徴はどれですか?
近年のしめじ(ブナシメジ)は、以前特有の苦味がネックでしたが、品種改良が進み「旨味と香りが豊か」なものが主流となっています。そのため炒め物や鍋料理など様々な料理で重宝されています。
Q7 : ブナシメジの名前の意味として正しいものはどれですか?
ブナシメジは自然界ではブナ科の木の倒木や切株などに多く発生するためその名がついています。実際の市販品は菌床栽培によるものが主流ですが、野生ではブナ林付近によく見られます。
Q8 : しめじの栽培方法として主に使われているものは何でしょう?
しめじの市販品の多くは「菌床栽培」と呼ばれる方法で育てられています。オガクズなどに栄養を加えたブロック状の菌床に種菌を植えつけて栽培する方法で、安定した品質と大量生産が可能です。
Q9 : しめじはどのような植物に分類されるでしょうか?
しめじはキノコ類に分類される菌類のひとつです。野菜や果物とは異なり、光合成を行わず、朽ち木などに菌糸を伸ばして栄養を取るのが特徴です。ブナシメジやヒラタケ科のものが多く出回っています。
Q10 : しめじ(ブナシメジ)の主な旬の時期はいつでしょうか?
しめじは一般的に秋が旬とされており、自然界で特によく見られるのは秋の涼しい時期です。現在は一年中栽培されていますが、味や香りが最も豊かになるのが秋とされています。天然物もこの時期に多く収穫されます。
まとめ
いかがでしたか? 今回はしめじクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回はしめじクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。