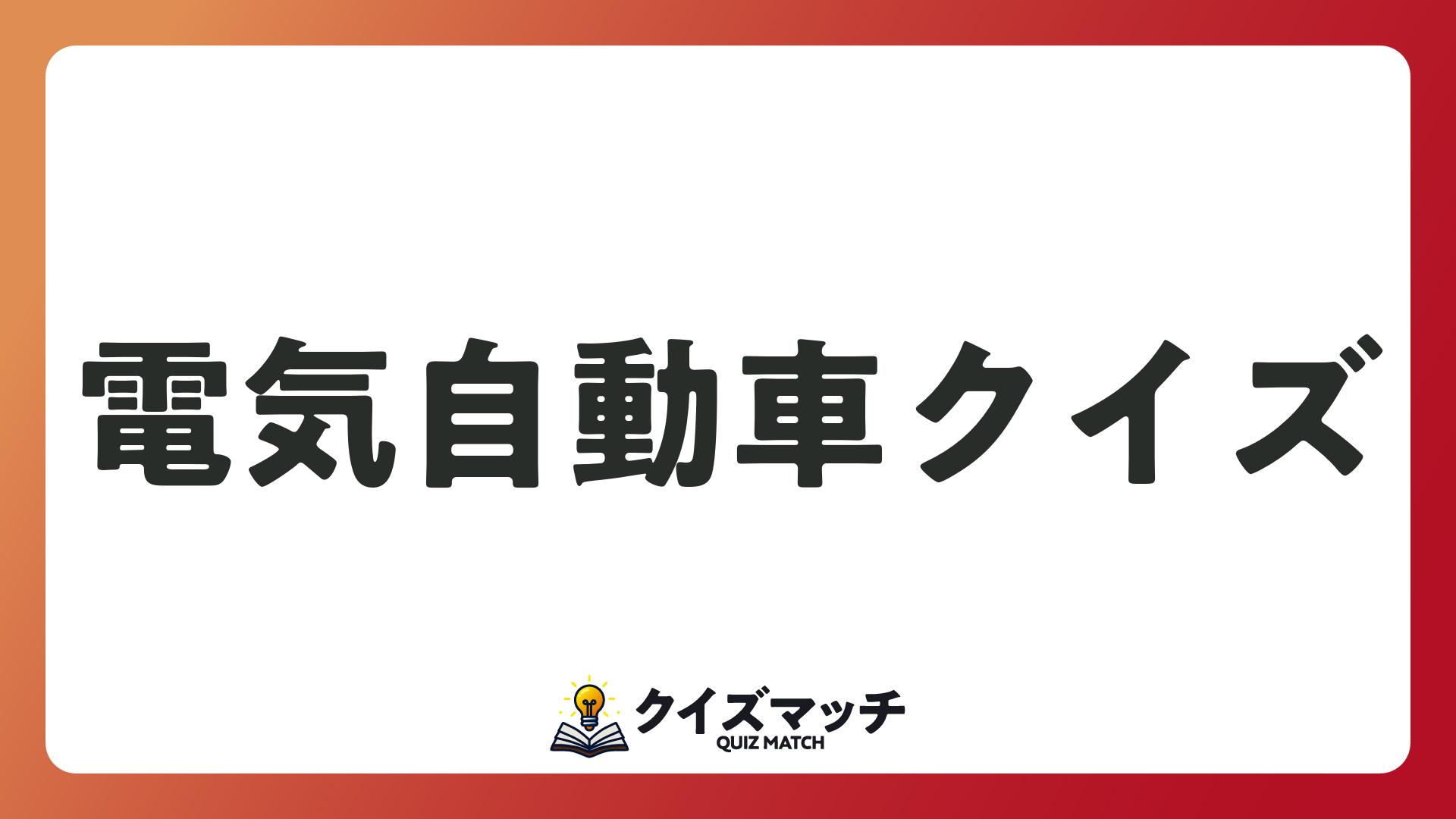電気自動車(EV)の利便性や未来性に注目が集まっている中、その技術的な特徴や普及動向を知ることは重要です。本記事では、EVの駆動方式、バッテリー、発売車種、メリット、充電規格、機能特性など、EVに関する10の基本的な知識をクイズ形式で紹介します。EV初心者から熟練ユーザーまで、EVの理解を深められる内容となっています。EVの技術革新と普及拡大の最新動向を、クイズを通して確認しましょう。
Q1 : 電気自動車の普及促進政策として、日本政府が2035年に掲げている目標はどれ?
日本政府は2035年までに新車販売の「電動車100%化」を目標としています。ここでの電動車はEVのみならず、ハイブリッドカーやプラグインハイブリッド車、燃料電池車も含みます。完全なEV化やガソリン車販売禁止よりも現実的な移行案として定められています。
Q2 : EVへの家庭用充電で標準的に使われる200Vコンセントの名称は?
家庭用で主に設置される200VのEV充電設備は「普通充電器」と呼ばれています。急速充電器は公共の充電スポットなどで使用され、家庭用では原則として取り付けできません。普通充電は長時間を要しますが、家庭の夜間電力を活用できるというメリットがあります。
Q3 : 2023年現在、日本の新車EVシェアがもっとも高いのはどの地域?
関東地方、特に東京都・神奈川県・千葉県などの大都市部は充電インフラが整備されていることや、各種の助成金制度なども後押しし、日本国内で最も新車EVの販売シェアが高い地域として知られています。
Q4 : EV走行中の静粛性の高さが特に課題となるのは次のうちどれ?
電気自動車はエンジン車に比べて非常に静かに走行できるため、住宅街や歩行者の多い場所で徐行する際などには、歩行者が車の接近に気付きにくい「静かすぎる問題」が生じます。これに対策するため、EVには擬似エンジン音や警告音が付与される場合があります。
Q5 : 電気自動車で一般的に実現しやすい機能はどれ?
電気自動車はモーターで駆動することから、減速時にモーターを発電機として利用し、バッテリーに電力を回収する「回生ブレーキ」が標準的機能として実装されています。これにより燃費向上や効率化が可能となります。自動運転は車両構成に依存せず、水素燃料補給やエンジン暖房はEVの特徴ではありません。
Q6 : 電気自動車を急速充電できる世界的標準規格の一つは?
電気自動車の急速充電規格には複数の標準がありますが、欧米を中心に広く採用されているのがコンボ(CCS: Combined Charging System)規格です。チャデモは日本や一部アジアで主流ですが、国際的にはCCSの割合が高まっています。テスラスーパーチャージャーはテスラ専用です。
Q7 : 電気自動車(EV)が持つ、エンジン車と比べた際の最大の長所はどれか?
電気自動車最大の長所は「走行時に排出ガスを出さない」ことで、地球温暖化防止や都市部の空気環境改善に貢献しています。加速性能や維持コストの低さも特徴ですが、最も象徴的な恩恵はCO2や有害物質の排出ゼロであるという点です。
Q8 : 日本国内で最初に量産型電気自動車として発売された車種は?
三菱i-MiEVは2009年に日本で最初に量産型として一般販売された電気自動車です。日産リーフは2010年発売ですが、三菱i-MiEVが先行して市場に登場しました。i-MiEVの登場は、日本市場における本格的EV開発レースの火付け役とも評価されています。
Q9 : 電気自動車の蓄電池に最も一般的に使われているバッテリーは?
現在主流の電気自動車のほとんどは、エネルギー密度や寿命、充電効率に優れるリチウムイオン電池を採用しています。リチウムイオン電池は小型軽量化が進み、急速充電も比較的可能なため、電気自動車のバッテリーとして理想的です。鉛蓄電池やニッケル水素電池は主に一世代前のEVやハイブリッド車で多用されていました。
Q10 : 電気自動車(EV)の駆動方式として一般的に使われているものはどれ?
電気自動車はモーターの搭載場所や設計の自由度が高いため、FF、FR、4WDのいずれの駆動方式も利用されています。特にモーターと駆動輪の関係がシンプルなため、FFのみならず、加速性能やトラクションを重視したFRや4WDという選択肢も多く、各メーカーが車種ごとに最適な駆動方式を採用しています。
まとめ
いかがでしたか? 今回は電気自動車クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は電気自動車クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。