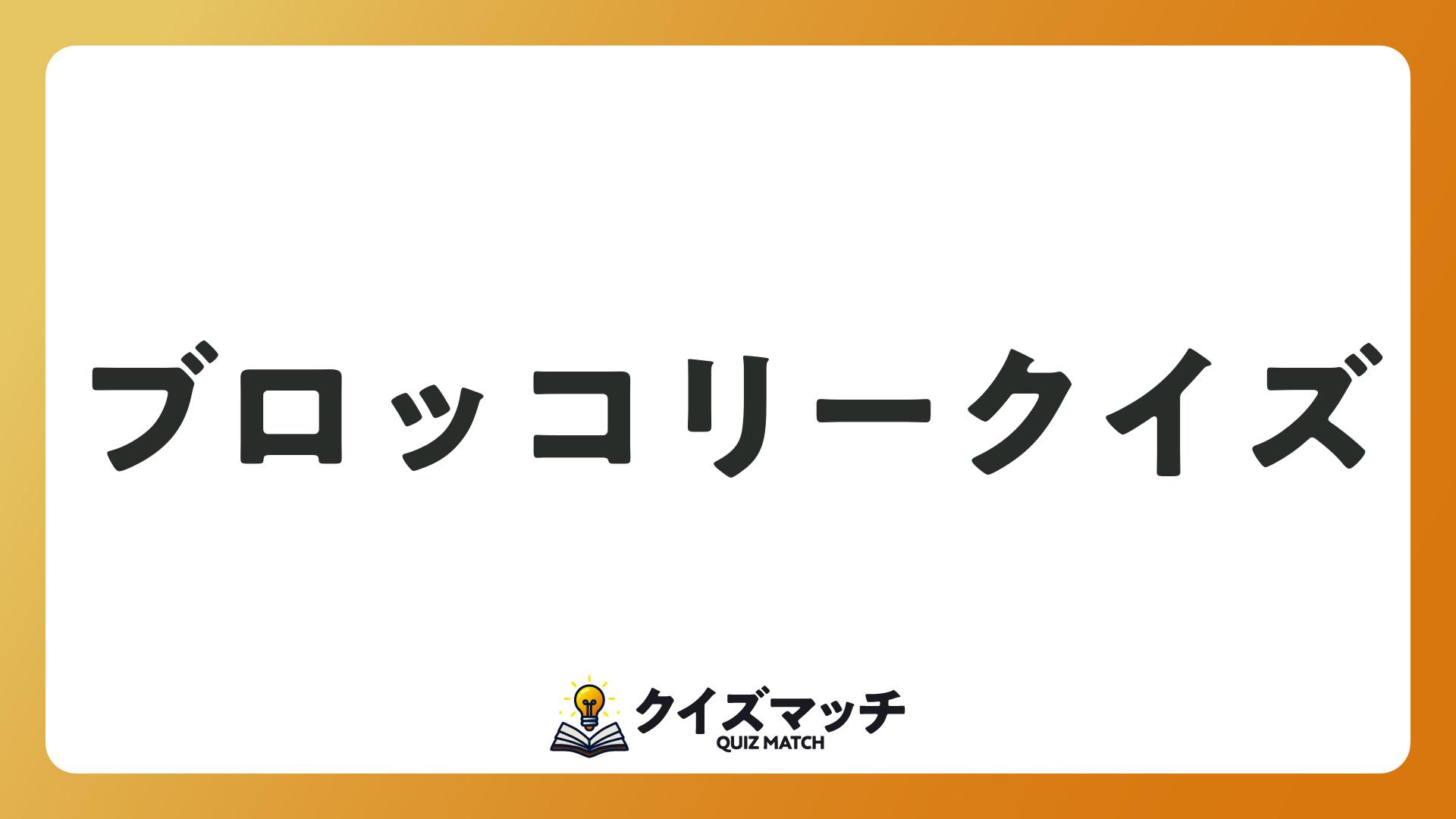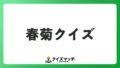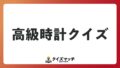ブロッコリーはビタミンやミネラルが豊富な栄養価の高い野菜として人気を集めていますが、意外と知られていないその歴史や特徴も多数あります。この「ブロッコリークイズ」では、ブロッコリーの原産地や日本への伝来、調理のポイントなど、さまざまな知識を問うクイズを10問ご用意しました。ブロッコリーについてもっと詳しく知りたい方は、ぜひチャレンジしてみてください。
Q1 : 次のうち、ブロッコリーの栽培で重要な気温はどれ?
ブロッコリーは冷涼な気候を好むため、栽培に適した気温は10~20℃程度です。高温だと花蕾の形成が悪くなったり、品質が低下するため通常は春や秋に栽培されます。暑さに弱い性質で、適温を守ることで柔らかく美味しいブロッコリーができます。
Q2 : ブロッコリーとカリフラワーの色の違いは主に何に由来する?
ブロッコリーが緑色なのはクロロフィル(葉緑素)が含まれているためです。一方、カリフラワーはクロロフィルが少なく白色となります。これらの違いは主に色素によるもので、成分の違いが色の違いを生み出していますが、どちらも同じアブラナ科で、栄養価には共通点も多くあります。
Q3 : ブロッコリーの名前の由来は何語でしょう?
ブロッコリーの名前はイタリア語の「broccolo(ブロッコロ)」に由来しています。これは「小さな突起」や「芽」を意味しており、ブロッコリーの花蕾が集まっている姿からその名がつきました。英語ではbroccoliと表記し、そのまま世界中に広まりました。
Q4 : ブロッコリーを美味しく茹でる最適な時間は?(小房の場合)
ブロッコリーの小房は1~2分茹でるのが最適とされています。それ以上茹でると食感や色、栄養素が失われやすくなります。サッと茹でて火を通すことで、シャキッとした食感と鮮やかな緑色が保たれ、ビタミンの損失も少なくなります。茹で過ぎると柔らかくなりすぎるため注意が必要です。
Q5 : ブロッコリーに多く含まれる健康成分スルフォラファンは、どんな働きがある?
スルフォラファンはブロッコリースプラウトなどに多く含まれ、強い抗酸化作用を持つフィトケミカルの一種です。体内の解毒酵素を活性化させ、がん予防や生活習慣病の予防に寄与するとされています。また、肝機能の向上など健康全般に良い影響が知られています。
Q6 : ブロッコリーと同じアブラナ科に含まれる野菜はどれ?
ブロッコリーはアブラナ科の野菜で、キャベツやカリフラワー、ケール、コマツナなどと同じ仲間です。キャベツとは特に形や味の面でも近い特徴があり、これらはすべて野生カンランから品種改良されて育てられました。栄養素も似ている部分が多いのが特徴です。
Q7 : ブロッコリーはどの部分を食べる野菜?
ブロッコリーは「つぼみ」の部分を主に食べます。緑色の花蕾(つぼみ)が集まった部分が特徴的で、これを茎ごと収穫します。花が咲く前の状態で収穫し、加熱や生食で美味しく食べられます。茎の部分も食用可能で、皮をむいて調理すると甘みや柔らかさが楽しめます。
Q8 : 日本にブロッコリーが本格的に普及したのはいつ頃?
日本にブロッコリーが一般家庭で多く食べられるようになったのは1970年代以降です。それまでは主にカリフラワーが主流でしたが、アメリカからの輸入や国内栽培の普及により、明るい緑色と栄養価の高さから人気が高まっていきました。以降、サラダや付け合わせとして広く使われています。
Q9 : ブロッコリーが豊富に含むビタミンはどれ?
ブロッコリーにはビタミンCが豊富に含まれています。100gあたり120mg前後で、レモンと同じくらい多い量です。免疫力向上や美肌効果、抗酸化作用が期待できます。また他にもビタミンKや葉酸なども含みますが、特にビタミンCの含有量は野菜の中でもトップクラスです。
Q10 : ブロッコリーの原産地はどこでしょう?
ブロッコリーの原産地は地中海沿岸部、特にイタリアです。古代ローマ時代から栽培された記録があり、長い歴史を持ちます。のちに西欧各地やアメリカにも伝わり、世界中で食べられるようになりました。特にイタリアでは伝統的な食材として有名であり、日本にブロッコリーが伝わったのも1970年代と比較的最近のことです。
まとめ
いかがでしたか? 今回はブロッコリークイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回はブロッコリークイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。