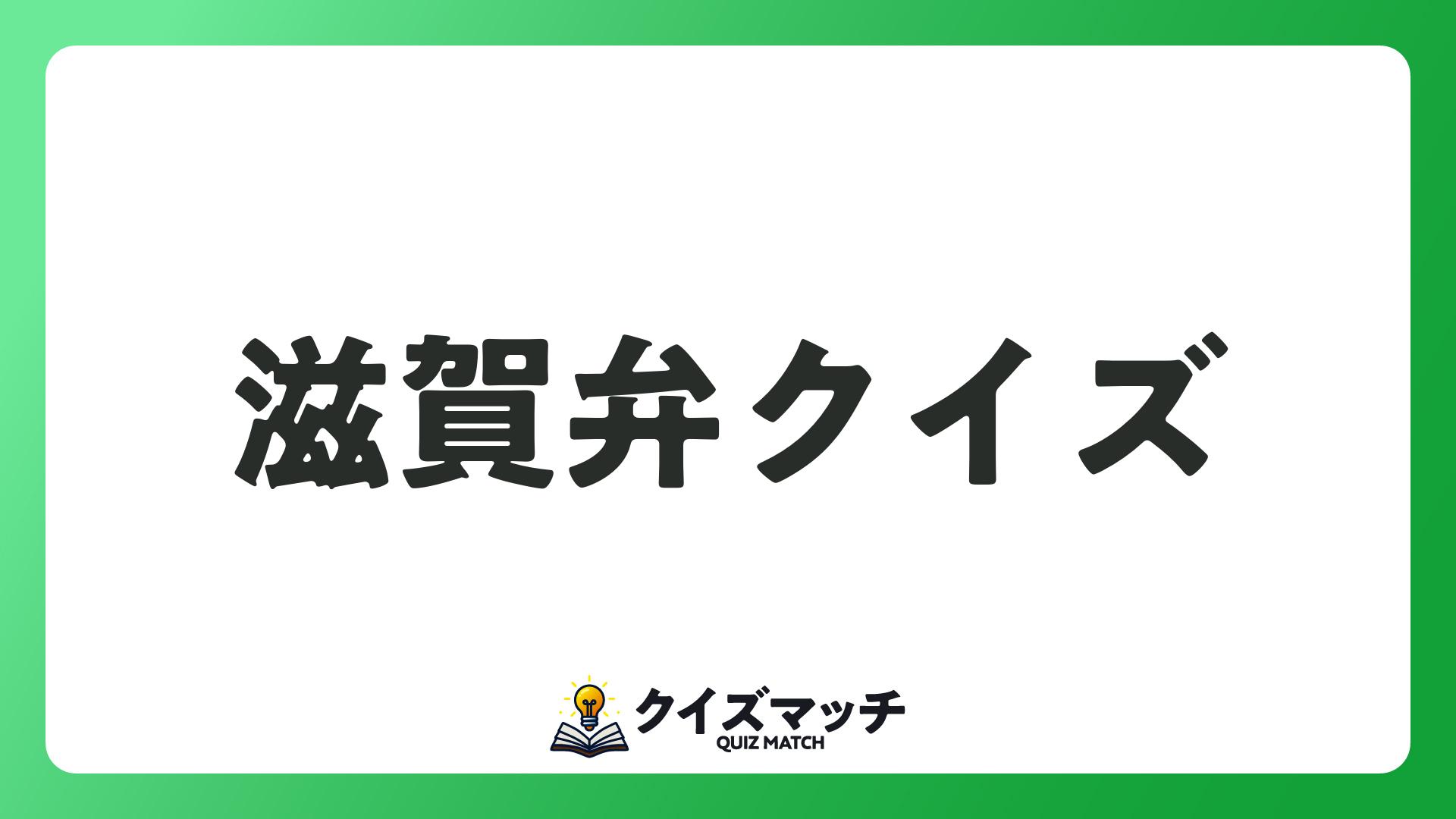滋賀県特有の方言「滋賀弁」は、その独特な言い回しや意味の違いから、地元の人々の生活や文化を感じさせてくれます。今回は、そんな滋賀弁の魅力を10問のクイズで紹介します。「ほかす」は「捨てる」、「なおす」は「片付ける」、「えらい」は「疲れている」など、標準語とは異なる滋賀弁ならではの表現に注目しましょう。これらの言葉から見える、滋賀の人々の生活感と人情味を感じ取っていただければ幸いです。
Q1 : 「ぎょうさん」と滋賀弁で言った場合の意味は?
「ぎょうさん」は「たくさん」という意味で、滋賀を含む関西一帯で使われる言葉です。「ぎょうさん魚が釣れた」など、多くのものや量が多いことを表します。「行商(ぎょうしょう)」からきたともされ、古くから使われている方言です。
Q2 : 「よばれる」は滋賀弁でどんな意味?
滋賀弁では「よばれる」は「ごちそうになる」という意味を持ちます。「よばれに行く」は「おもてなしを受けて食事をする」ことを指します。この表現は全国の方言でも使われますが、滋賀や近畿地方で特によく聞かれる言い方です。
Q3 : 「ごつい」という滋賀弁の意味は?
「ごつい」は滋賀弁で「すごい」「とても」という意味です。「ごつい美味しい」「ごつい速い」など、物事の度合いが強いことや、驚きを表現する際によく使われます。標準語の「ごつい=大きい」が語源の一つですが、意味が派生して広くなっています。
Q4 : 滋賀弁で「まんだ」はどんな意味?
「まんだ」は「まだ」という意味で、滋賀県で使われる方言です。「まんだそんなこと言ってるの?」のように、「まだ~してるの?」と伝える時に使われます。これは漢字の「未だ(いまだ)」が変化した方言表現と考えられています。
Q5 : 「はよしぃや」は滋賀弁でどんな意味?
「はよしぃや」は「早くしなさい」という意味です。「はよ」は「早く」、「しぃや」は「しなさい」という命令の形です。年配の方が子どもに対してよく使う言い方で、滋賀らしいイントネーションとセットで使われます。
Q6 : 滋賀弁の「かんにんしてや」は何と言う意味?
「かんにんしてや」は「許してね、ごめんね」という意味です。関西の方言でも共通ですが、滋賀県でも相手に対して謝ったり、許しを乞う場面でよく使われています。「かんにん」は「勘弁」が語源であり、「悪いことをしてごめん」のニュアンスを含みます。
Q7 : 「~しやん」と滋賀弁で使われた場合、どのような意味?
滋賀弁で「しやん」というと「しない」という否定の意味になります。「食べやん」=「食べない」、「行きやん」=「行かない」など、標準語の否定文とは異なる独自の表現です。特に若い世代でも日常的に使われており、分かりやすい滋賀の方言の一つです。
Q8 : 「えらいなあ」と滋賀の人に言われたときの意味は?
「えらいなあ」と滋賀弁で言われると「疲れている」という意味になります。標準語での「えらい」は「素晴らしい」「偉い」ですが、滋賀や関西の方言では「えらい」は「しんどい」「疲れている」という意味になるので、ニュアンスが大きく異なります。「今日はえらいわ」と言われたら「今日は疲れた」という意味になります。
Q9 : 滋賀弁で「なおす」と言ったらどんな意味?
滋賀弁で「なおす」とは「片付ける」という意味です。一般的に「直す」は標準語では「修理する」という意味ですが、滋賀や関西圏では「おもちゃをなおして」「カバンをなおして」と言うと「おもちゃやカバンを片付ける」という意味になります。この方言は滋賀だけでなく関西地方の広い範囲で使われています。
Q10 : 滋賀弁で「ほかす」とはどういう意味?
滋賀弁の「ほかす」は「捨てる」という意味です。関西の一部地域でも使われますが、滋賀では特に日常的に使われています。標準語では「捨てる」となる動作を、滋賀弁話者は「ゴミをほかしてきて」などと言います。「ほかす」は「他す(ほかす)」が語源との説もありますが、広く関西に分布し、滋賀県民の日常会話では馴染み深い表現です。
まとめ
いかがでしたか? 今回は滋賀弁クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は滋賀弁クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。