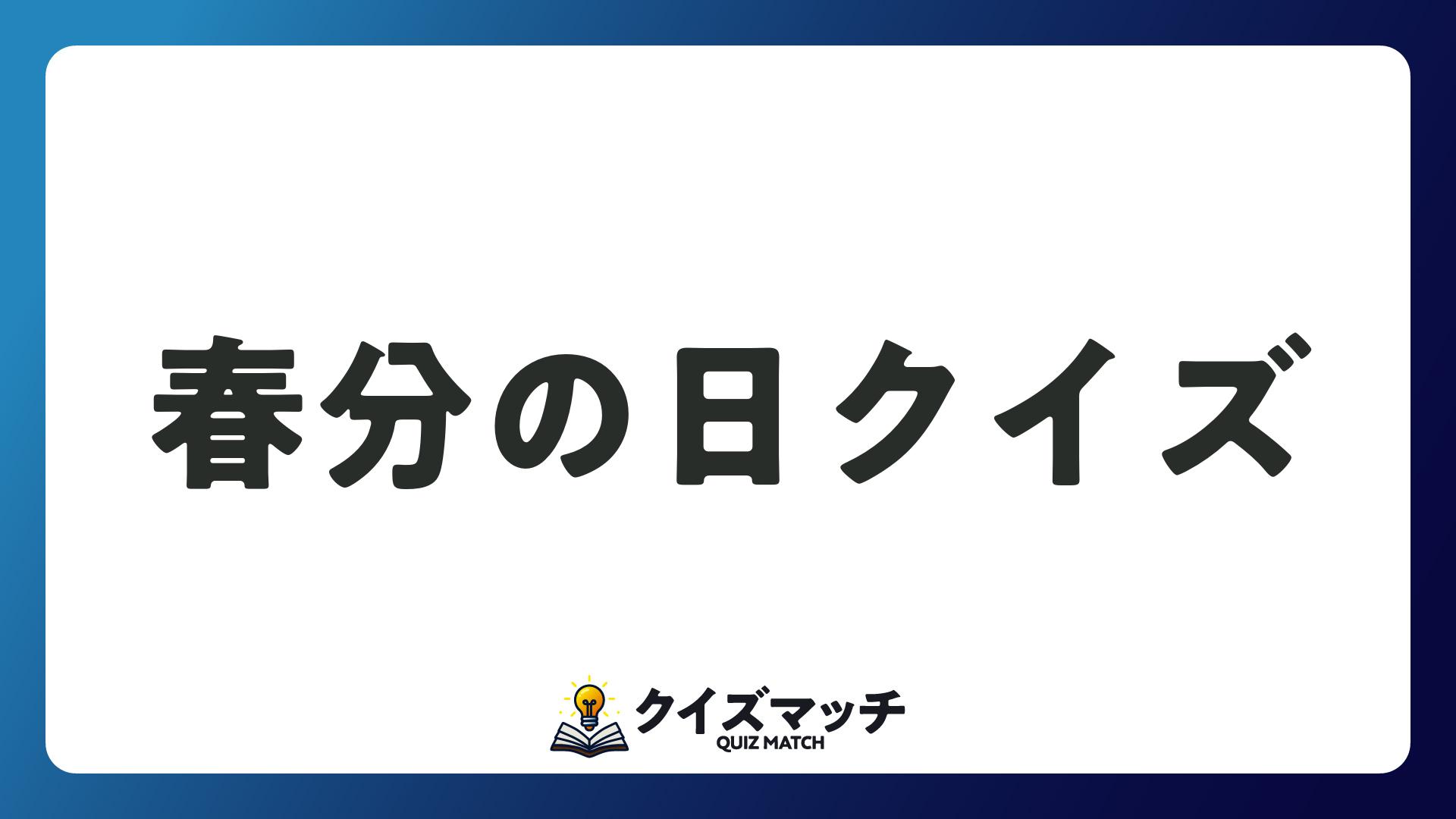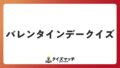春分の日は、毎年3月頃に日本の国民の祝日として定められています。この日は、地球が公転する際に昼と夜の長さがほぼ等しくなる「春分点」を迎える時期で、自然と先祖を敬う日とされています。本記事では、この春分の日にまつわる様々な知識や習慣について、10問のクイズを通してご紹介します。春分の日の意義や歴史、関連する行事やおいしい春の和菓子など、春の訪れとともに楽しめる内容となっております。季節の変わり目を感じながら、春分の日について学んでみませんか。
Q1 : 春分の日を中心とした「彼岸」の期間は何日間続くでしょうか?
「彼岸」は前後3日ずつと春分の日の合計7日間を指します。最初の日を「彼岸の入り」、最後の日を「彼岸明け」と言い、先祖供養や墓参りなどの風習が行われます。春分や秋分を中心に1週間というのが一般的です。
Q2 : 2024年の日本の春分の日は何月何日でしょうか?
2024年の春分の日は3月20日です。年によって3月20日または21日になることがありますが、国立天文台の計算に基づいて政府が毎年正確な日付を発表します。
Q3 : 春分の日の時期、昼と夜の長さがほぼ同じになるのはどこの地域ですか?
春分や秋分は、地球のどこでもほぼ昼と夜の長さが等しくなります。ただし、細かなズレはありますが、基本的には全地域で同じ現象が観測されるため、春分は全地球的な現象です。
Q4 : 春分の日と関連が深い仏教の言葉はどれでしょうか?
「彼岸」は仏教の言葉で、煩悩にまみれたこの世(此岸/しがん)に対し、悟りの世界(彼岸/ひがん)を指し、春分の日は太陽が真西に沈むことから西方極楽浄土を偲び、先祖供養が盛んになるのです。
Q5 : 春分の日が、法的に日本で国民の祝日になったのはいつからでしょうか?
春分の日は1948年に施行された祝日法(国民の祝日に関する法律)によって正式に国民の祝日となりました。それ以前にも春分は重要視されていましたが、祝日法で明確に定められたのは1948年です。
Q6 : 春分の日に食べることが多い和菓子といえば?
春分の日には「ぼたもち」を食べる習慣があります。春を象徴する牡丹の花にちなみ、小豆餡で包んだもちがぼたもちと呼ばれるのです。秋分の日には萩の花にちなんで「おはぎ」と呼ぶことが多いですが、素材はほぼ同じです。
Q7 : 次のうち、春分の日の前後に仏事として多く行われる行事はどれでしょうか?
春分の日を中心とした前後7日間は「春彼岸」と呼ばれ、先祖の霊を供養するために墓参りをする風習が日本全国で広く見られます。お彼岸は春分の日、お盆は8月、七五三や成人式は異なる時期です。
Q8 : 春分の日は、日本の国民の祝日法で何とされているでしょうか?
国民の祝日法では、春分の日は「自然をたたえ、生物をいつくしむ」ことを趣旨としています。また、この日は先祖を敬い、お墓参りをする風習も深く根付いています。そのため、春分の日は自然と先祖を大切にする日と位置づけられています。
Q9 : 春分の日はどのような自然現象を基に日付が決められていますか?
春分の日は地球が公転する際に太陽が赤道の真上に来る日で、昼と夜の長さがほぼ等しくなる自然現象を基に日付が決められています。この天文現象を春分と呼び、日本では天文学的な計算から毎年日付が決まります。
Q10 : 春分の日は、一般的に何月に設定される国民の祝日でしょうか?
春分の日は太陽が真東から昇り真西に沈む日で、日本では毎年3月20日頃に設定されています。これは地球が公転する際に、昼と夜の長さがほぼ等しくなる「春分点」を迎える時期です。そのため、春分の日は国民の祝日として3月中に制定されています。
まとめ
いかがでしたか? 今回は春分の日クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は春分の日クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。