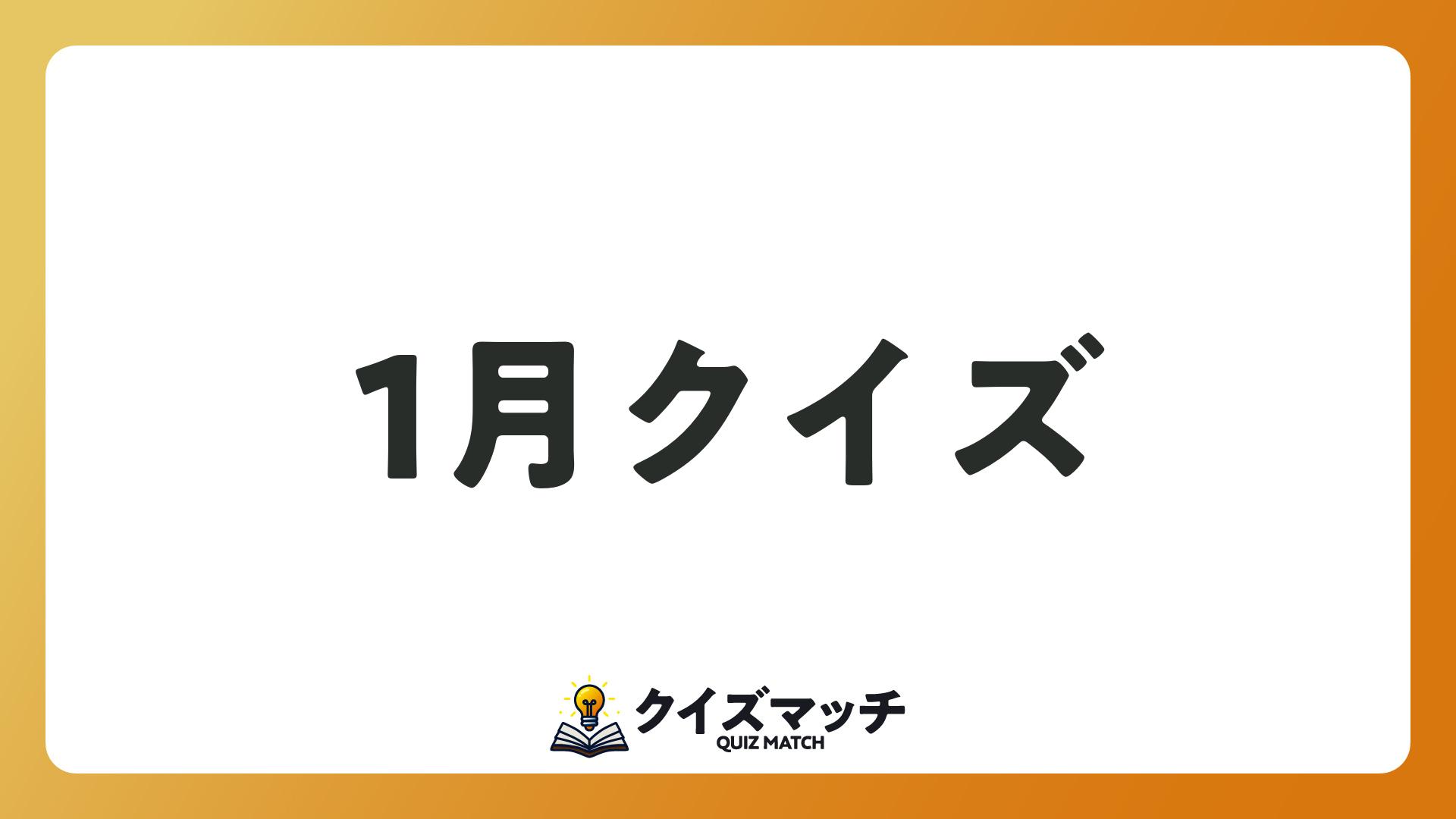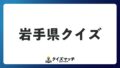新年あけましておめでとうございます。1月は日本の伝統的な祝日や習慣が多数見られる特別な月です。たとえば、1月1日の元日には初日の出を拝んだり、神社へ初詣に行くなど、日本全国で様々な行事が行われます。本記事では、そんな1月にまつわるクイズを10問ご用意しました。日本の歴史や文化に詳しくなれる良い機会になると思います。正解と解説をお楽しみください。
Q1 : 1月の干支が「辰」だった年は、令和何年ですか?
2024年(令和6年)は干支が「辰(たつ)」です。干支は12年ごとに巡る動物で、辰年にあたるのは令和6年です。令和5年は卯、令和4年は寅、令和7年は巳となります。この干支は年賀状のデザインや、様々な行事でもよく使われます。
Q2 : 1月11日に行う、鏡餅をおろし食べる行事を何と呼ぶ?
1月11日に鏡餅をおろし、無病息災を願いながら家族で分けて食べる行事を「鏡開き」と呼びます。これは本来武家社会から広まった行事で、祝い事に鏡餅を割ることが縁起が良いとされました。雛祭りや端午の節句、秋祭りは他の季節に行われます。
Q3 : 1月に各地の神社で行われる、その年の幸せを祈願する行事は?
1月1日から3日にかけて多くの人が神社や寺を参拝し、その年の健康や幸福を祈る「初詣」が行われます。日本の伝統的な年始の行事で、家族や友人と訪れるのが一般的です。他の選択肢のお盆や花見、節分は時期が異なります。
Q4 : 1月に使われる和風月名は何ですか?
1月の和風月名は「睦月(むつき)」です。睦月は、親族や知人が集まり睦み(仲良く)合う月という意味が含まれています。2月は「如月」3月は「弥生」、7月は「文月」、11月は「霜月」と称されます。
Q5 : 1月の季語として適切なのはどれ?
俳句などで使われる季語には季節を表す言葉があり、1月(新春)を代表する季語のひとつが「鶴」です。鶴は縁起物とされ、特に正月の飾りや絵柄に使われます。桜や入道雲、紅葉は、それぞれ春・夏・秋を代表する季語となります。
Q6 : 1月に日本で行われる入試イベントはどれ?
1月には全国の大学受験生が受験する大学入学共通テスト(旧センター試験)が行われます。従来の「センター試験」から「大学入学共通テスト」へと2021年度から名称変更されました。卒業式や体育祭、クリスマスは1月の行事ではありません。
Q7 : 1月に成人の日として祝日となるのは、どの曜日ですか(2024年時点)?
成人の日は、2000年から「1月の第2月曜日」と定められています。それ以前は1月15日が固定日でしたが、ハッピーマンデー制度により現在の形式となりました。新成人が大人の仲間入りを祝う行事で、多くの自治体では成人式が行われます(2024年は1月8日月曜が成人の日です)。
Q8 : 1月7日に食べる風習がある、季節の行事食はどれ?
1月7日は「人日(じんじつ)の節句」と呼ばれ、この日に「七草がゆ」を食べる習慣があります。七草がゆとは、春の七草(せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ)を入れて炊いたおかゆで、正月のごちそうで疲れた胃腸を休める意味や、無病息災の願いが込められています。
Q9 : 1月に行われる日本三大祭りに含まれないのはどれ?
日本三大祭りに1月に実際行われるものは含まれていません。京都の葵祭は5月、東京の靖国神社のみたままつりは7月、大阪の天神祭も7月に開催されます。1月に有名なのは札幌の雪まつりですが、これも正式な日本三大祭りには含まれていません。ただし、雪まつりも2月開催が基本です。
Q10 : 日本の元日は何月何日に祝われますか?
日本の元日は毎年1月1日に祝われる、日本の伝統的な祝日です。新年の始まりを祝福する日で、日本全国で様々な行事や習慣が行われます。例えば初日の出を拝んだり、神社へ初詣に行くことが習慣となっています。旧暦時代は異なる日だったこともありましたが、明治改暦以後は現在のグレゴリオ暦に合わせて1月1日となりました。
まとめ
いかがでしたか? 今回は1月クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は1月クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。