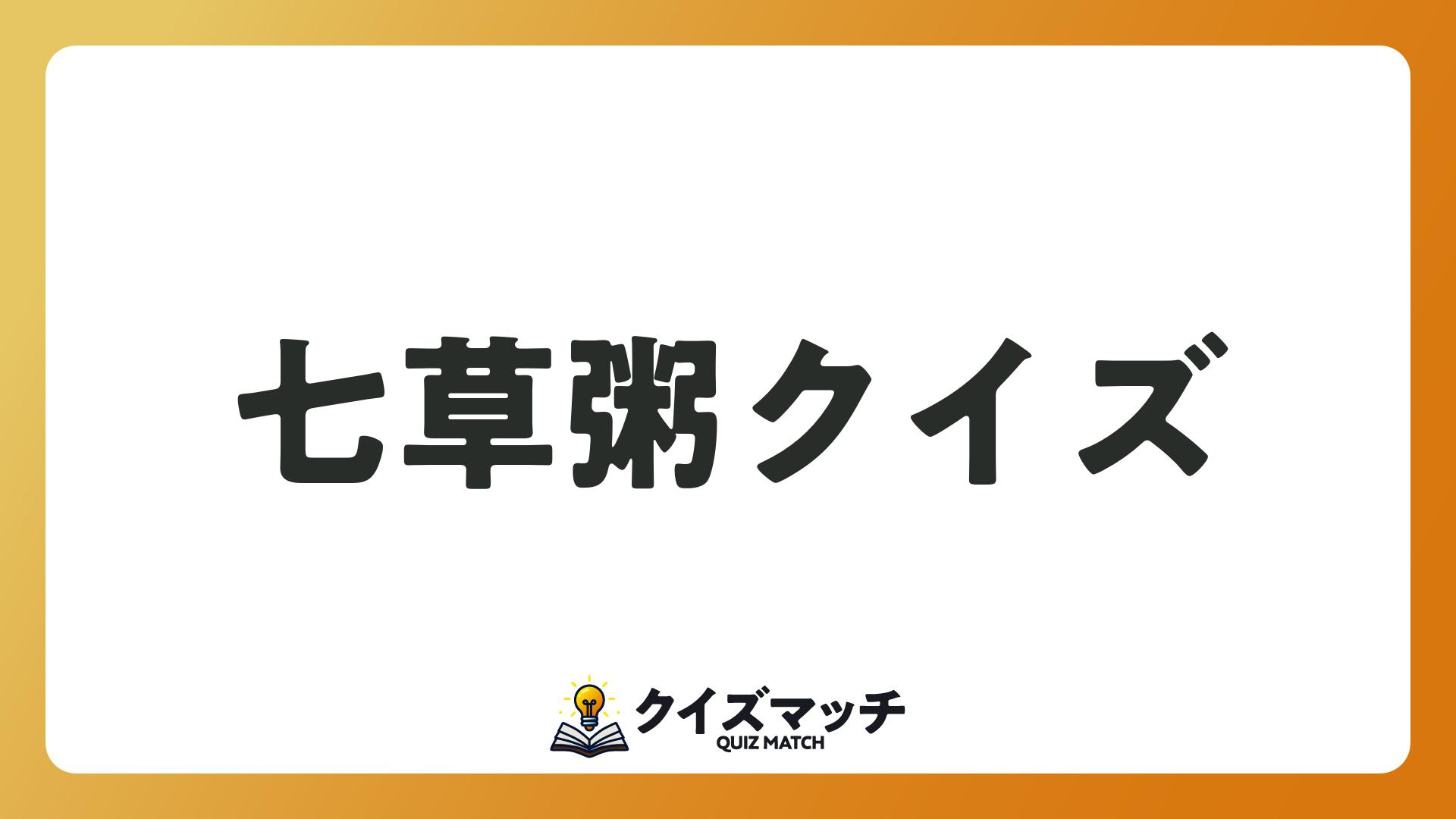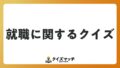七草粥クイズ: 新年の健やかな幕開けを祈る伝統行事
正月三が日が過ぎ、1月7日には「人日の節句」と呼ばれる七草粥の行事が行われます。この七草粥は、古くから日本人が新年の健康と幸せを願う伝統的な行事のひとつです。今回は、七草粥にまつわるクイズを用意しました。七草の種類や由来、そして七草粥の意味や歴史について、クイズを通してご紹介します。新年の健やかな幕開けを祈る、この伝統行事について、ぜひお楽しみください。
Q1 : 七草粥の材料として用いられる『ナズナ』が別名で有名なのはどれでしょう?
七草粥に用いられる『ナズナ』は、別名「ペンペン草」として広く知られています。三味線のバチのような形をした種のさやが特徴です。若葉には苦みが少なく、古くから食用や薬草として親しまれています。
Q2 : 「七草粥」の風習が中国から伝来したと言われていますが、伝わった時期はどの時代でしょう?
七草粥の風習は、古代中国の「人日(じんじつ)」の習慣が日本に伝わったのが始まりとされています。日本では飛鳥時代に伝来し、宮中行事として定着した後、徐々に庶民にも広まっていきました。
Q3 : 七草のうち『ホトケノザ』ですが、七草粥に入れるホトケノザは一般的に野原に咲いている『ホトケノザ』と同じですか?
七草粥に使われる「ホトケノザ」は、「コオニタビラコ」という植物で、春に食用とされます。一般的に野原でよく見かけるシソ科の「ホトケノザ」とは別種で、混同しないよう注意が必要です。
Q4 : 七草粥を食べる意味で最も正しいものはどれでしょう?
七草粥を食べる意味は、一年の無病息災や健康を願うことです。新春の7日に若菜を食べることで邪気を払い、健康に過ごせるよう祈る日本の風習です。もちろん長寿や家族の健康など幅広い願いも含まれますが、総合的に無病息災を願う行事です。
Q5 : 春の七草のうち唯一黄色い花を咲かせるのはどれでしょう?
春の七草の中で唯一黄色い花を咲かせるのはゴギョウ(母子草)です。他の七草は白や淡い色の花を付けますが、ゴギョウは小さな黄色い花を咲かせることで知られています。
Q6 : 七草粥に入れる『ゴギョウ』は、別名なんと呼ばれている植物でしょう?
ゴギョウは、七草粥に入れる春の七草の一つで、別名「母子草(ハハコグサ)」です。この植物は柔らかな葉をもち、かつては草餅の材料としても使われていました。柔らかな若葉を粥に入れて利用します。
Q7 : 次のうち『ハコベラ』の特徴として正しいものはどれでしょう?
ハコベラは春の七草のひとつです。漢字では「繁縷」と書き、白い小さな花をつけます。毒性はなく、むしろ昔から薬草として用いられてきました。七草粥では若葉を刻んで使うのが一般的です。「草家鴨」は間違いです。
Q8 : 七草粥に入れる『スズナ』は、一般的にどんな野菜として知られているでしょう?
スズナは、七草粥で使われる春の七草の1つで、『カブ』のことです。よく似ている『スズシロ』は『大根』を指します。この二つは七草の中でも特に知られている比較的大きな野菜ですが、伝統的には名前が区別されて呼ばれています。
Q9 : 春の七草に含まれていないものはどれでしょう?
春の七草は、セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ(カブ)・スズシロ(ダイコン)ですが、ホウレンソウは含まれていません。七草にはそれぞれ健康を願う意味が込められており、昔から日本で受け継がれてきた伝統的な野草や野菜が選ばれています。
Q10 : 七草粥を食べる行事が行われるのは日本の何月何日でしょう?
七草粥は、日本の正月行事のひとつで、1月7日に食べられます。これは五節句の一つである「人日(じんじつ)の節句」に当たり、お正月で疲れた胃を休め、無病息災を願って古くから行われてきた風習です。七草を刻んで粥にして食べることで、1年の健康を祈る意味も込められています。
まとめ
いかがでしたか? 今回は七草粥クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は七草粥クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。