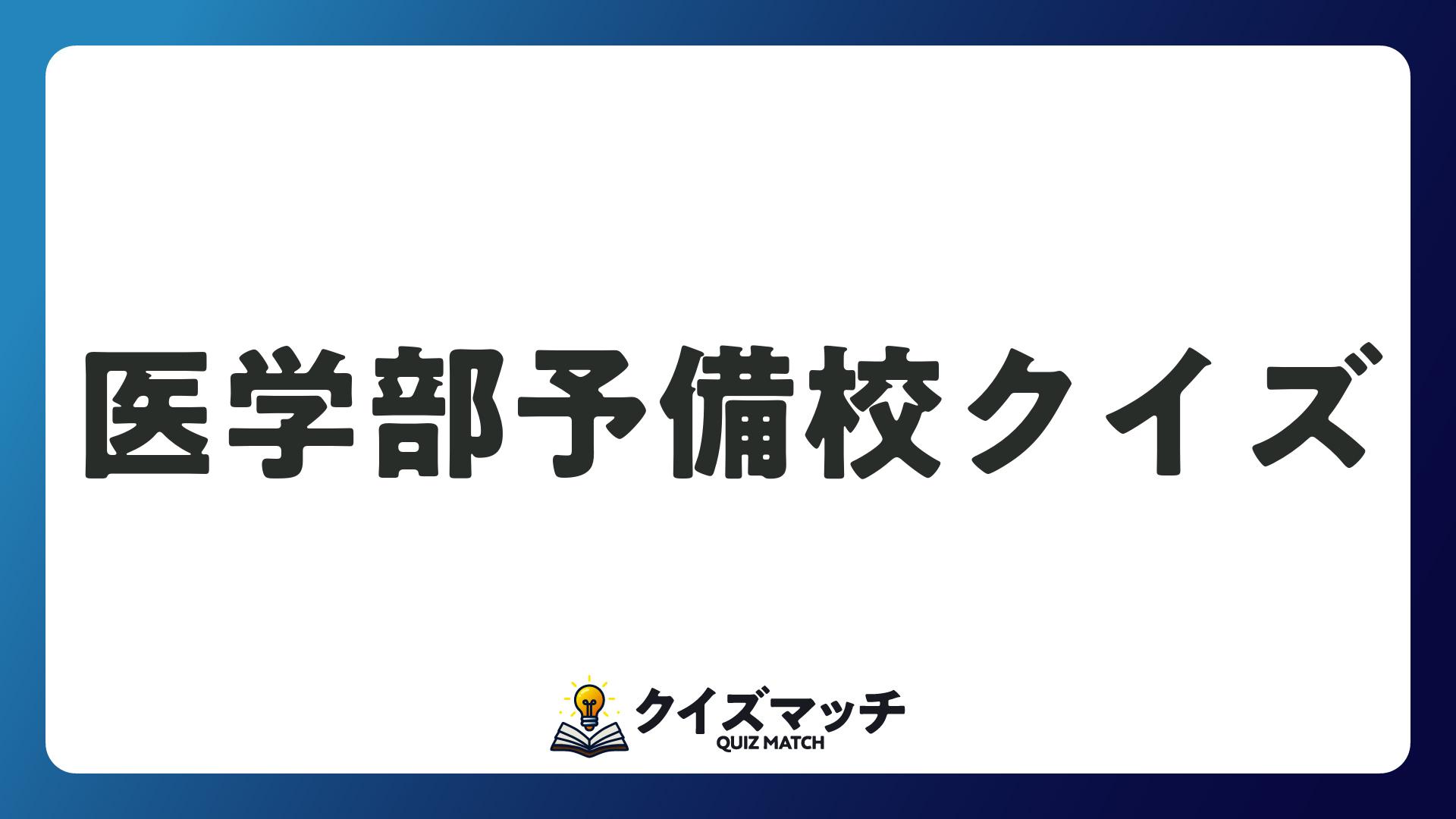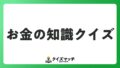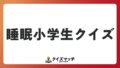医学部を目指す受験生のみなさん、この記事では医学部予備校クイズという形式で、医学の基礎知識について確認できる10問をご用意しました。人体の構造や機能、医療制度など、医学部入試に欠かせない重要なトピックを網羅しています。この機会に自分の理解度を確認し、苦手分野の克服につなげていきましょう。医学は幅広い分野にわたるため、予備校のサポートを活用しながら、着実に力をつけていくことが合格への近道です。是非、熱心に取り組んでいただければと思います。
Q1 : 人体の細胞数はおよそどれくらいか?(オーダーで)
人体を構成する細胞の数はおよそ「数十兆個」といわれています。最新の推定では約37兆個とされますが、個人差があります。生物学的な理解を深めるためには“オーダー(桁)”での数を把握しておくことが重要です。なお、細胞の種類も200種以上存在します。
Q2 : 医学部受験における英語の配点は理科よりも高いことが多い。
多くの医学部入試では、理科の配点が英語よりも高い、または同等である場合が多いです。理科は2科目が課されるため、合計点で見ても理系科目が占める比重が大きいです。一方、私立大学では英語の比率が高い場合や均等配点もあるため、大学ごとの入試傾向を確認することが重要です。
Q3 : 心筋梗塞の主な原因とされる動脈の変化はどれか?
心筋梗塞の主な原因は「動脈硬化」です。冠動脈などの動脈がコレステロール等の蓄積により狭く硬くなり、血流が遮断されて心筋細胞の壊死が生じます。静脈瘤や毛細血管は主原因ではなく、動脈硬化の理解が循環器疾患対策の基本です。
Q4 : インスリンを分泌する臓器はどれか?
インスリンは「膵臓」から分泌されるホルモンです。膵臓のランゲルハンス島という部分でβ細胞が産生しています。インスリンは血中のグルコース(ブドウ糖)濃度を下げる働きがあります。糖尿病など膵臓関連の疾患の理解のために必須の知識です。
Q5 : 血圧の収縮期血圧と拡張期血圧、どちらが低いか?
一般的に「拡張期血圧」の方が低いです。心臓が収縮して血液を全身に送り出すときが収縮期血圧(最大血圧)、心臓が拡張し血液を受け入れている間が拡張期血圧(最小血圧)です。血圧の表記は「収縮期/拡張期」(例:120/80mmHg)が一般的です。この基本的な値の意味を正確に把握することが求められます。
Q6 : 脳の“言語中枢”がある部位はどこか?
脳の言語中枢(主にブローカ野)は「前頭葉」に位置しています。これは、言語の生成や文法、発語に関与している部分です。これに対し、聴覚野やウェルニッケ野(言語の理解)は側頭葉にあります。言語野の障害による失語症タイプの理解に不可欠な知識です。
Q7 : 日本の医師国家試験の実施主体はどこか?
日本の医師国家試験は「厚生労働省」が実施主体です。試験の合否判定や試験問題の作成も厚生労働省が所管しています。文部科学省は高等教育や学校運営に関連しますが、医師資格の発行や国家試験の管理は行いません。この区別は進路選択や試験対策を考えるうえで重要です。
Q8 : 赤血球の主な働きは何か?
赤血球の主な役割は「酸素の輸送」です。赤血球の中にはヘモグロビンというタンパク質が多量に含まれており、このヘモグロビンに酸素が結合して体の隅々まで運ばれます。免疫は主に白血球、血液凝固は血小板が担っています。赤血球は血液中の細胞の中で最も多く、生命維持に不可欠な細胞です。
Q9 : “骨”の中で最も大きいものはどれか?
人体で最も大きい骨は「大腿骨(だいたいこつ)」です。大腿骨は太ももにあり、長さと太さ共に最大の骨です。この骨は体重を支える役割が非常に大きく、歩行や走行など大きな負荷にも耐えられるようにできています。また、骨髄で血球を作る機能も有しています。脛骨も大きいですが、大腿骨ほどではありません。
Q10 : ヒトの体内で最も多い元素はどれか?
ヒトの体内で最も多い元素は「酸素」です。体内では水として存在する酸素が全体の元素重量の約65%を占めており、次いで炭素が約18%です。水素も10%程度ありますが、酸素の割合が最も高いです。このことは、人体の約60%が水分で構成されているためで、水分中の酸素原子が人体に占める元素比率を高めています。医学生はこの基礎的な体の構成要素を理解することが重要です。
まとめ
いかがでしたか? 今回は医学部予備校クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は医学部予備校クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。