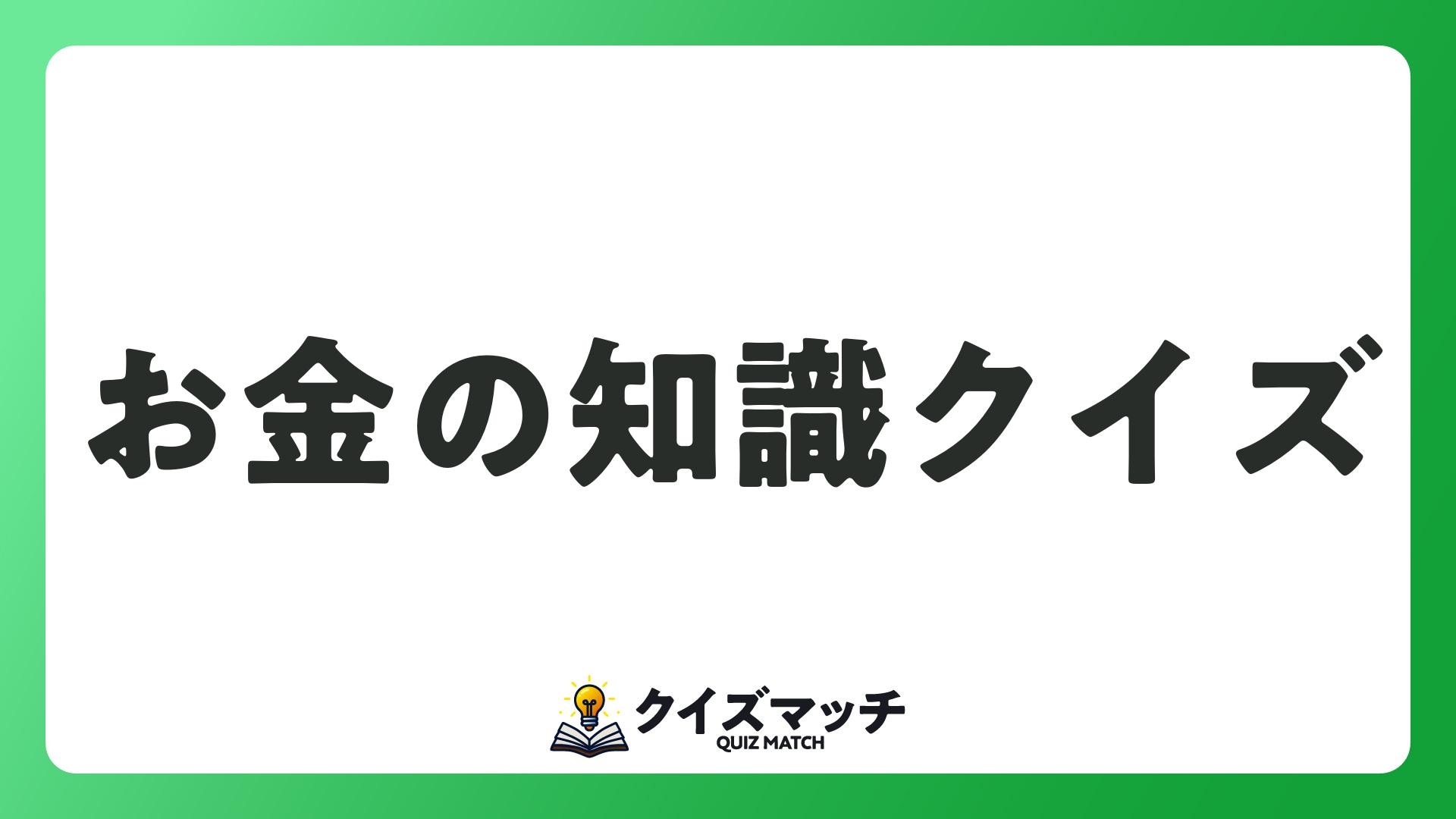お金に関する基礎知識が身につくクイズに挑戦しましょう。日本銀行券や消費税率、信用情報管理、金融商品の特徴など、生活に密接に関係する知識を確認できる全10問のクイズをご用意しました。日本の金融制度やお金の仕組みについて、楽しみながら理解を深めていきましょう。
Q1 : 預金者保護の観点から、銀行が破綻した場合に預金が保護される上限額はいくら?
ペイオフ制度により、1金融機関ごとに預金者1人あたり1,000万円とその利息までが元本保証で保護されます。これを超える金額は、銀行破綻の場合に損失が生じる可能性があります。この仕組みは預金者の資産を守るための重要な制度です。
Q2 : 日本で発行されている電子マネーのうち、交通系ICカードの例はどれ?
交通系ICカードの代表格が「Suica」です。主にJR東日本のサービスエリアで利用できますが、他のJR系ICカードと相互利用も可能です。一方、nanacoやWAON、QUICPayは主にコンビニやスーパー、電子決済用のサービスです。
Q3 : 20歳以上が利用できる少額投資非課税制度の名前は?
NISA(少額投資非課税制度)は、20歳以上の個人が指定口座で一定額までの株式や投資信託への投資による運用益が非課税になる制度です。通常は運用益や配当金に課税されますが、NISA口座を利用すると一定限度内は税金がかかりません。
Q4 : 確定申告が必要となる主なケースはどれ?
会社員でも年収2,000万円を超える場合や、複数の収入源がある場合には自分で確定申告を行う必要があります。一方、ほとんどの会社員は年末調整で済みますが、高額所得者は例外です。年金や家賃、年齢が理由で確定申告が必須となることはありません。
Q5 : 日本で使われている1円硬貨の材質として正しいものは?
日本の1円硬貨は純アルミニウム製です。非常に軽く、質量はわずか1グラムです。他の硬貨は素材が異なり、五円や十円は真鍮・銅が主成分となっています。アルミは加工しやすく低コストであるため、1円硬貨に採用されています。
Q6 : 個人の信用情報を登録・管理している機関は?
信用情報機関は、金融取引に際して各個人のクレジットカードやローンなどの返済履歴や契約情報を集約・管理しています。CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センターなどが有名です。これにより、金融機関は個人の信用力を評価できます。
Q7 : 金融商品の中で、原則元本割れがないと言われているのはどれ?
定期預金は通常、預け入れた元本と利息が保証されます。ただし、ペイオフ(金利や元本の保証額)制度があり、破綻金融機関の場合、一部を超える預金が保証されないこともあります。しかし、株式や投資信託、FXは元本が保証されていません。
Q8 : 日本の消費税率(2024年時点、標準税率)は何%?
2024年時点で日本の標準的な消費税率は10%です。2019年10月に8%から10%へ引き上げられました。軽減税率制度により食品や新聞には8%が適用される場合がありますが、一般的な商品やサービスには10%が標準として課されています。
Q9 : 株式投資で得られる利益のうち、配当金はどのタイミングで受け取れる?
配当金は、企業の業績に基づき株主総会で決定され、通常は年1回または中間・期末の2回に分けて支払われます。株主名簿に記載された株主がその時点で保有していれば配当を受け取れます。一方で、毎月や株購入時に自動的に支払われるものではありません。
Q10 : 日本銀行が発行している紙幣のことを何と呼ぶ?
現在、日本で流通している紙幣は日本銀行が発行しているため「日本銀行券」と呼ばれます。明治時代以降、日本銀行が紙幣の発行を独占し、政府紙幣や他の銀行券は廃止されました。日本銀行券は日銀の負債として位置付けられており、法律によって発行と管理が厳しく制限されています。
まとめ
いかがでしたか? 今回はお金の知識クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回はお金の知識クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。