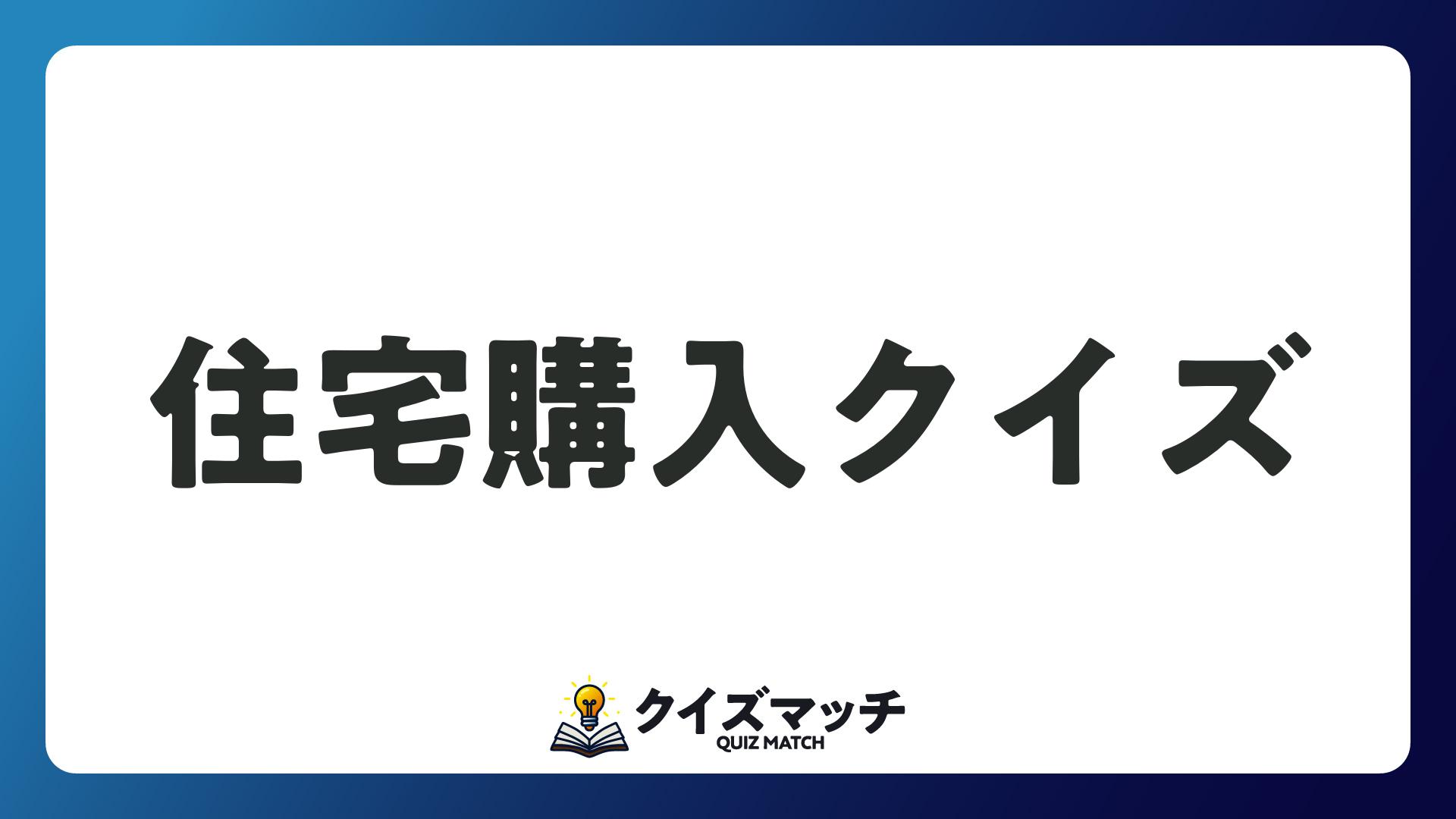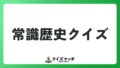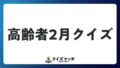近年の住宅市場の活況を受け、住宅購入を検討する人も増えてきています。しかし、住宅購入には様々な制度や諸費用など、初めての人には分かりづらい要素が多数あります。この記事では、そんな住宅購入に関する基礎知識を10問のクイズで確認していきます。住宅ローン控除の期間設定や手付金の相場、マンション管理費用など、購入時によく知らされていない重要なポイントが出題されています。住宅購入を検討中の方は、この機会に自身の知識をチェックし、安心して次のステップに進んでいただければと思います。
Q1 : 土地を購入する際に現地で必ず確認しておくべきポイントとして不適切なのはどれか?
土地購入時には境界確認や現地の地盤、周辺環境などの実地確認が重要です。一方で登記簿上の所有者は現地では確認できず、法務局などで書類として調査する内容です。よって現地確認ポイントとしては不適切です。
Q2 : 新築住宅の「住宅性能表示制度」で定められていない項目はどれか?
住宅性能表示制度は、耐震・省エネ・耐火・劣化対策などの性能項目を第三者が評定し、消費者が選びやすくするための制度です。しかし、間取りの利便性やデザインなど主観的な項目については定められていません。
Q3 : 金融機関で住宅ローンの事前審査を受ける際に必要な主な書類はどれか?
住宅ローンの事前審査には、借入希望者の属性や収入を示す「源泉徴収票」や「住民票」などの個人情報が重要です。物件の登記事項証明書や火災保険証券は本審査や契約段階で必要ですが、事前審査時点では本人確認と収入が主な審査項目です。
Q4 : 中古マンション購入時に確認しておきたい重要事項に該当しないものはどれか?
中古マンション購入時は、管理組合の運営状況や修繕積立金の残高、共有部分の修繕履歴などが建物の資産価値や住み心地に大きく影響します。周辺の学校の偏差値も生活上の検討要素にはなりますが、マンションそのものの重要事項説明には含まれません。
Q5 : 戸建て住宅の「建ぺい率」とは何を示す数値か?
建ぺい率は、敷地面積に対して建築面積(建物を上から見たときの面積)が占める割合を表す規制値です。これにより、建物の大きさや周囲とのバランスが保たれるよう都市計画がなされています。建物の高さや延べ床面積とは直接関係ありません。
Q6 : 住宅ローンの返済負担率(年収に対する年間返済額)は一般的に何%以下が望ましいとされているか?
返済負担率とは年収に対するローン返済額の割合のことです。金融機関によって判断基準はやや異なりますが、一般的には年収の25%〜30%以下に抑えるのが望ましいとされています。これ以上高くなると生活費や他の支出に支障が出るリスクがあるため、無理な借入は禁物です。
Q7 : マンション購入時にかかる毎月の費用として正しいものはどれか?
マンション購入後にかかる代表的な毎月の費用は「修繕積立金」です。これは共用部分の将来の修繕に備えて積み立てるものです。駐車場代はオプションで契約した場合のみ必要です。印紙税や登記費用は購入時に一度払うもので、毎月発生するものではありません。
Q8 : 住宅購入にかかる諸費用のうち「印紙税」はどの契約書に必要か?
印紙税は、主に売買契約書やローン契約書などの課税文書に課されますが、住宅購入においてまず発生するのは「売買契約書」です。印紙を貼ることで契約書の効力が正式に認められるため、売買契約書には印紙税が必須となります。土地謄本や火災保険証券には印紙税は不要です。
Q9 : 物件を購入する際に必要となる「手付金」は、通常売買価格の何%程度が目安とされているか?
手付金は売買契約締結時に支払う費用で、通常売買価格の5〜10%程度が一般的です。手付金は契約解除時の違約金ともなりうるため、過剰な額を設定しないことが望ましいです。1〜2%ということは少なく、逆に20%以上もの高額の手付金は一般的ではありません。
Q10 : 住宅ローン控除の適用期間は2024年時点で最長何年か?
住宅ローン控除は住宅取得時の一定期間、年末残高の一部を所得税から控除できる制度です。2024年時点では原則13年が最長となっています(新築や条件により異なるが、長い場合で13年)。ただし、中古住宅・リフォームの場合や2021年以前の契約などでは異なるため、現行制度と自身の契約時期を確認することが重要となります。
まとめ
いかがでしたか? 今回は住宅購入クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は住宅購入クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。