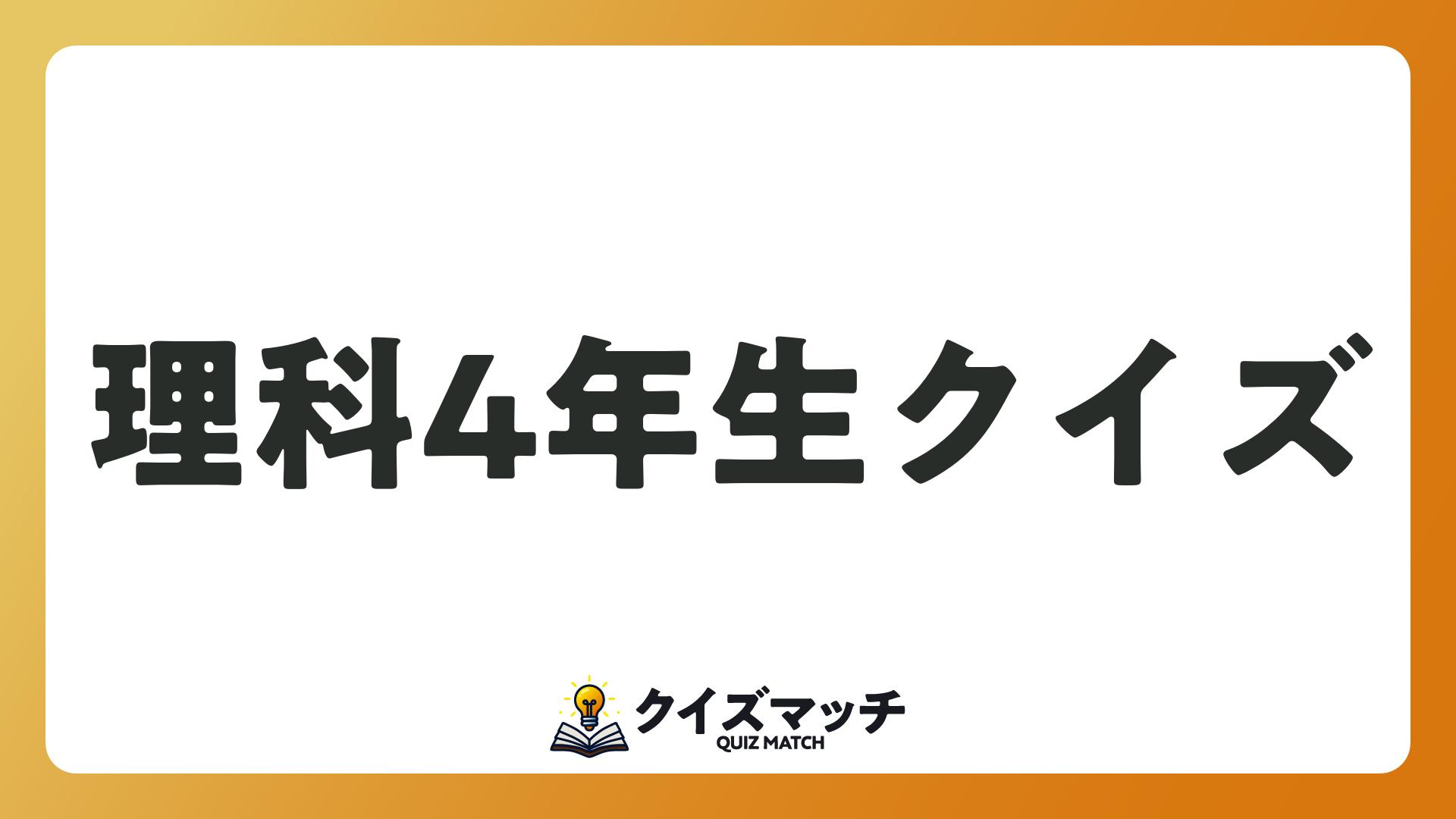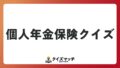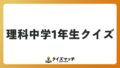私たちの身の回りには、とてもふしぎな現象がたくさんあります。月の動きから植物の不思議な仕組み、地球を取り巻く大気の役割まで、自然界にはまだまだ探求の余地がいっぱい。今回のクイズでは、理科の基礎的な知識を問いながら、子どもたちの探究心を刺激していきます。楽しみながら、自然のしくみに少し迫れるかもしれません。4年生のみなさん、自然の不思議を一緒に解き明かしていきましょう!
Q1 : 星座は夜空にどのように動いて見える?
星座は地球の自転のため、夜空で東から西へ動いていくように見えます。太陽も同じく東から西へ動いてみえます。星座が動くように見えるのは、実際には地球が自転しているからです。また季節によって見える星座がちがうのも、地球の公転によるものです。
Q2 : 次のうち卵からうまれる動物は?
犬やねこ、さるはお母さんから直接生まれますが、かえるは卵から生まれます。卵の中でオタマジャクシとなり、その後、えらを持った状態から手足が生え、成長してかえるになります。卵から生まれる動物は他にも魚や昆虫などがいます。
Q3 : 電池をつなげて豆電球を明るくしたいとき、どうすればいい?
電池を真っすぐに(+-+-のように)直列でつなぐと、電圧が足し算され、豆電球はより明るくなります。一方、並列につなぐと電圧はかわりませんが、長持ちします。実験では豆電球の明るさが変わるのをよく観察します。
Q4 : 地球をとりまく空気のことをなんと言う?
地球をとりまく空気を大気(たいき)といいます。大気は窒素約8割、酸素約2割で成り立っています。また、天気や気温なども大気の動きによって変わります。大気がなければ、地上で生きることはとてもむずかしくなります。
Q5 : 人の体で、食べたものを一番最初に通る場所は?
食べものはまず口でかみくだき、だ液とまじわってかたまりになります。その後、のどから食道を通って胃に送られ、そこで消化が進みます。口は食べものが体の中に入るいちばん最初の場所です。
Q6 : 磁石のN極とS極を近づけるとどうなる?
磁石にはN極とS極があります。N極とS極は引き合い、同じ極同士(NとN、SとS)ははねかえします。これは、磁力というふしぎな力のためです。この性質を利用して方位磁石などがつくられています。
Q7 : 次のうち、冬になると落葉する木を何という?
冬に葉を落としてしまう木を落葉樹(らくようじゅ)といいます。桜やイチョウ、ナラなどがその例です。常緑樹は一年中葉があります。落葉することで、水などの不足や寒さをしのぎます。
Q8 : 地球の表面で一番多いのはどれ?
地球の表面の約7割は海でおおわれています。陸地はのこりの約3割しかありません。海は私たちにとって水や食料、気候など、たいせつな役割を果たしています。もし海がなかったら、地球は今のような住みやすい星にはなっていません。
Q9 : 植物が酸素を作るはたらきを何という?
植物は日光をあびて、自分のからだででんぷんや酸素を作り出します。このはたらきを光合成(こうごうせい)といいます。光合成によって、二酸化炭素と水から酸素とでんぷんを作るのです。動物や人は、この酸素を使って呼吸しています。
Q10 : 月が地球のまわりを1周するのにかかる日数はどれくらい?
月が地球のまわりを公転する周期は約27.3日ですが、新月から次の新月までの周期(朔望月)は約29.5日です。カレンダーで新月から新月までを数えてみると、約29日かかることがわかります。1か月のおよそ長さもこの月の動きからきています。
まとめ
いかがでしたか? 今回は理科4年生クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は理科4年生クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。