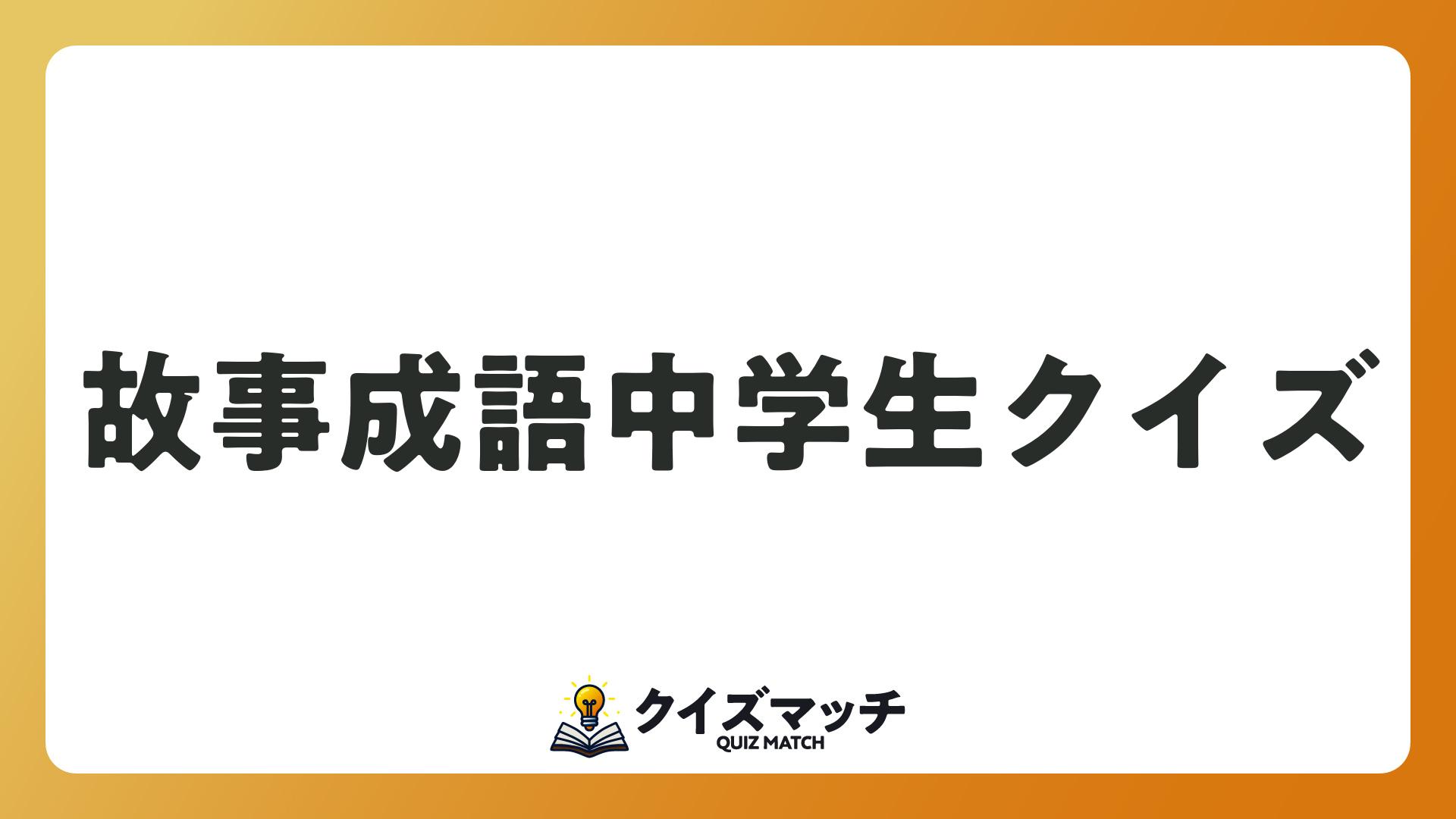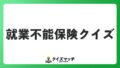夏休みも近づき、中学生の皆さんが待ちに待っているのが学校のクイズ大会です。勉強の息抜きとなるこの企画は、中学生の知的好奇心を刺激し、楽しみながら学べる良い機会になります。今回は、中学生の皆さんに向けて、故事成語をテーマにしたクイズ10問をご用意しました。これらの問題は、中国の古典文学から生まれた言葉の意味や背景を問うものばかり。歴史と文化に興味のある皆さんは、ぜひ挑戦してみてください。
Q1 : 「逆鱗に触れる」とは誰に関連した故事成語か?
「逆鱗に触れる」は、中国の秦の始皇帝の伝説が元で、龍には逆さに生えた鱗(逆鱗)があり、それに触れると怒り狂うとされていました。始皇帝が自分にも逆鱗があると語ったことから、特に目上の人や権力者を激しく怒らせることを「逆鱗に触れる」と言うようになりました。
Q2 : 「虎の威を借る狐」という言葉が表す意味はどれか?
「虎の威を借る狐」の故事は、狐が虎と一緒に歩き、他の動物が逃げるのを見て自分の力だと勘違いする、というものです。実際には虎の力を恐れて逃げているだけで、狐は自分の力ではない権威を利用しています。これがそのまま「他人の権勢を利用すること」を意味します。
Q3 : 「登竜門」はもともと何を表した言葉か?
「登竜門」の故事は中国の黄河の激流に滝(竜門)があり、これを登り切った鯉が龍になるという伝説から来ています。これは、難関を突破すれば立身出世できることをたとえるために使われ、「成功のための関門」の意味となりました。
Q4 : 「馬耳東風」という言葉の意味を表すものはどれか?
「馬耳東風」とは、『馬の耳に東風』という言葉からきており、意味も中国の故事にあります。馬の耳に東から吹く風が当たっても何も気にせずにいることから、人の話や忠告を全く気にかけず聞き流す意味となりました。
Q5 : 「漁夫の利」という言葉の元になった故事の内容として正しいものはどれか?
「漁夫の利」は、シギとハマグリが争っていたところを通りかかった漁師がどちらも捕まえて得をした、という中国の故事に由来します。このことから、二者が争っている間に第三者が利益を得る、という意味で使われています。
Q6 : 「杞憂」という言葉の意味に最も近いものはどれか?
「杞憂」とは、中国、杞の国の人が天が落ちてきやしないかと心配した故事から生まれました。周囲の人がどんなに大丈夫だと説明しても、杞の人はやはり心配していました。ここから、実際には全く心配する必要のないことを気に病むことを「杞憂」といいます。
Q7 : 「蛇足」という言葉が意味するものはどれか?
「蛇足」は中国の戦国時代の故事に由来します。ある人たちが酒を争い、蛇の絵を一番早く描いた人が酒をもらうことになりました。ある人が最初に描き終わり、さらに蛇に足まで描こうとしている間に他の人に酒を取られてしまいます。この話から、余計なことを付け加えて台無しにする意味で使われます。
Q8 : 「四面楚歌」という言葉はどんな状況を表しているか?
「四面楚歌」は、楚の項羽が漢軍に包囲された際、四方から楚の歌を聞いたという故事が由来です。これにより、助けがなく味方もいなくなり、周囲がすべて敵である状況となりました。したがって「孤立して敵に囲まれること」という意味になりました。
Q9 : 「破竹の勢い」という言葉の意味として正しいものはどれか?
「破竹の勢い」は、三国時代の中国での蜀軍の呉との戦いから生まれた故事成語です。竹を一度割り始めると、後は簡単に一気に割れていく様子から、物事の勢いがとまらず進む様子を表しています。したがって、意味は『物事の進行が速く止められないこと』になります。
Q10 : 「矛盾」の故事に由来する言葉の意味として正しいものはどれか?
「矛盾」という故事は、中国の戦国時代、楚の国の武器商人が「自分の盾はどんな矛でも通さない」「自分の矛はどんな盾も貫く」と同時に言ったことから生まれました。これは、同じ人が言ったことが互いに食い違い、筋が通らなくなることから、「言っていることが食い違っていること」の意味で使われるようになりました。
まとめ
いかがでしたか? 今回は故事成語 中学生クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は故事成語 中学生クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。