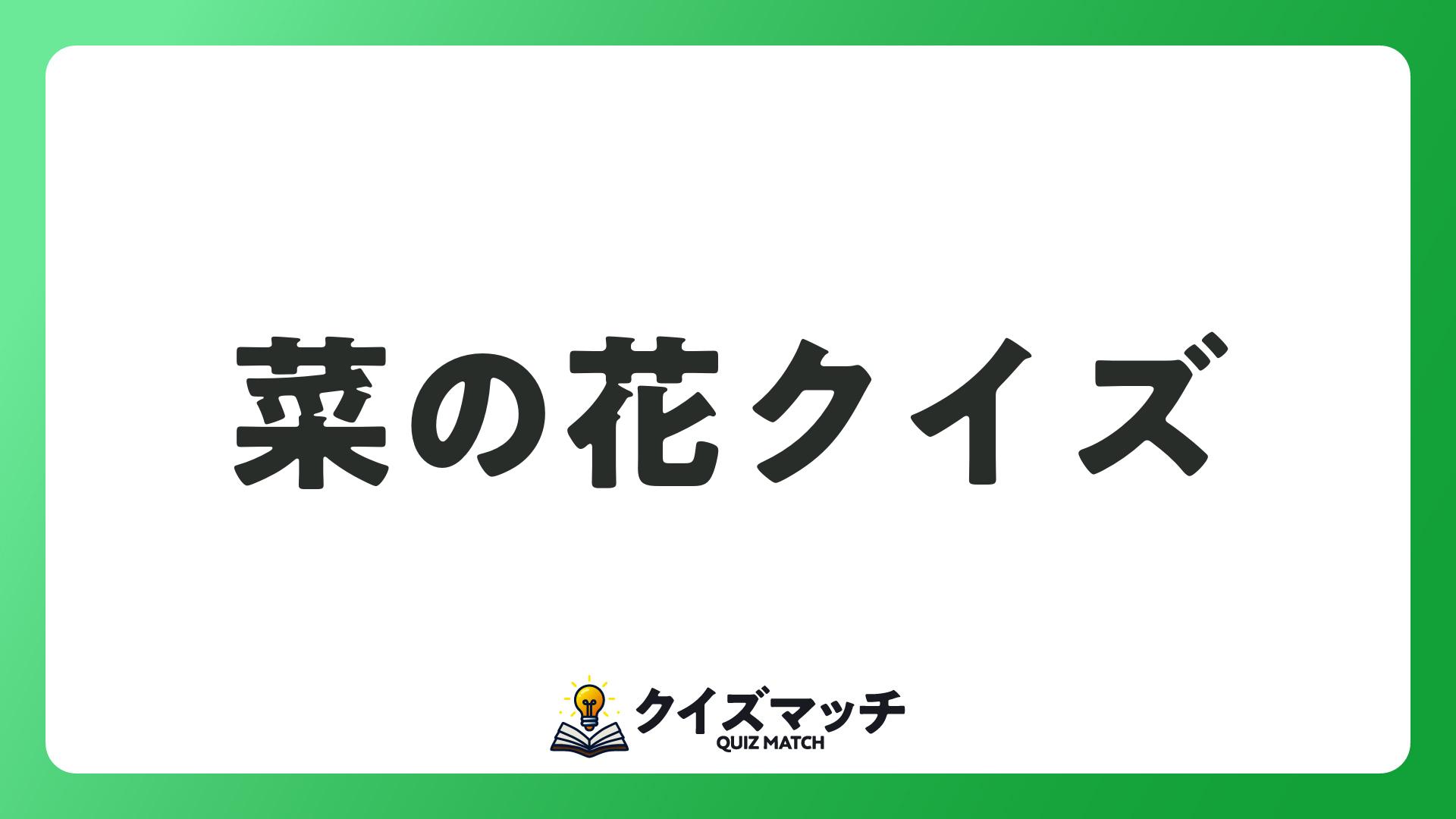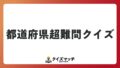春の訪れを告げる華やかな黄色い花。その名も「菜の花」。日本では古くから親しまれ、食用はもちろん、油や色素としての活用など多様な用途を持つ、魅力あふれる春の食材です。本記事では、菜の花に関する10の興味深いクイズを紹介します。菜の花の別名や栄養素、歴史など、意外な事実が満載。菜の花の魅力を再発見できるはずです。あなたも菜の花クイズに挑戦してみませんか。
Q1 : 菜の花は古くから日本でどう活用されてきた?
菜の花(ナタネ)は、江戸時代以降、主に食用と油用で日本国内で広く栽培されてきました。若い花芽は食用となり、種子は搾油してナタネ油となり照明や食用油に使われていました。建築材や香料、医薬品として使われることはごく稀です。
Q2 : 菜の花の学名「Brassica napus」のBrassicaとは何を指す?
「Brassica」はアブラナ科アブラナ属のことを指します。アブラナ属には、菜の花(ナタネ)のほか、ブロッコリーやカリフラワー、キャベツなども含まれています。ユリ属はユリ、キク属は菊、ラン属は蘭を指します。
Q3 : 日本の菜の花の名所として有名な千葉県の地域はどこ?
千葉県南房総市は、菜の花畑が広範囲に広がることでも知られ、「菜の花まつり」も開催されるなど、県内外から多くの観光客が訪れる名所です。特に春には黄色い花畑と青空のコントラストが絶景として有名です。
Q4 : 菜の花として親しまれる若い花芽の部分、これをなんと呼ぶ?
菜の花として食べられる部分は、「花蕾」と呼ばれる、まだ開花前のつぼみとその周りの若い茎や葉の部分です。これをおひたしや和え物、天ぷらなどにして食べることが多いです。葉柄や根茎、茎頂は植物の他部位を表す言葉です。
Q5 : 菜の花が歌詞に登場する日本の有名な童謡は何でしょう?
「おぼろ月夜」は、菜の花畑を詠んだ有名な日本の童謡です。「菜の花畑に入日薄れ」と始まる春の美しい情景を描いています。ほかの選択肢にも春や自然を歌った歌はありますが、特に菜の花が歌詞に登場するのは「おぼろ月夜」です。
Q6 : 菜の花がつくられる「ナタネ油」の用途として正しいものはどれ?
ナタネ油はその名の通り、菜の花から採れる種子を搾って作られる植物油で、食用油として広く使われています。炒め物やドレッシングの材料など、幅広い料理に利用されている他、マーガリンなどの原料にもなります。
Q7 : 菜の花の原産地として有力な地域はどこでしょう?
菜の花の原産地については諸説ありますが、最も有力なのはヨーロッパとされています。その後、アジアや中国経由で日本にも伝わり、食用や観賞用として広まったと考えられています。
Q8 : 菜の花に含まれる栄養素として、特に多く含まれているものはどれ?
菜の花にはビタミンCが特に豊富に含まれています。ビタミンCは美肌効果や免疫機能を高める作用があるため、春の健康食材としても注目されています。他にもビタミンAや鉄分、食物繊維も含まれていますが、ビタミンC含有量が特に多いです。
Q9 : 菜の花が最も多く咲く季節は日本のどの時期でしょう?
菜の花は春を代表する花のひとつで、3月から5月ごろにかけて日本各地で見頃を迎えます。菜の花畑が一面に広がる景色は春ならではで、「春の風物詩」としても有名です。夏や秋、冬には咲かないため、春こそが菜の花が最も咲く季節です。
Q10 : 菜の花は、アブラナ科の植物ですが、次のうち別名として正しいものはどれ?
菜の花はアブラナ科の植物で「ナタネ」とも呼ばれています。ナタネは、植物の種子から「ナタネ油」が取れることからこの名前があるのです。他にもアブラナ(油菜)、ハナナなど地域によって呼び名が変わる場合もありますが、ダイコン、キャベツ、カブは同じアブラナ科ではあるものの、菜の花の別名ではありません。
まとめ
いかがでしたか? 今回は菜の花クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は菜の花クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。