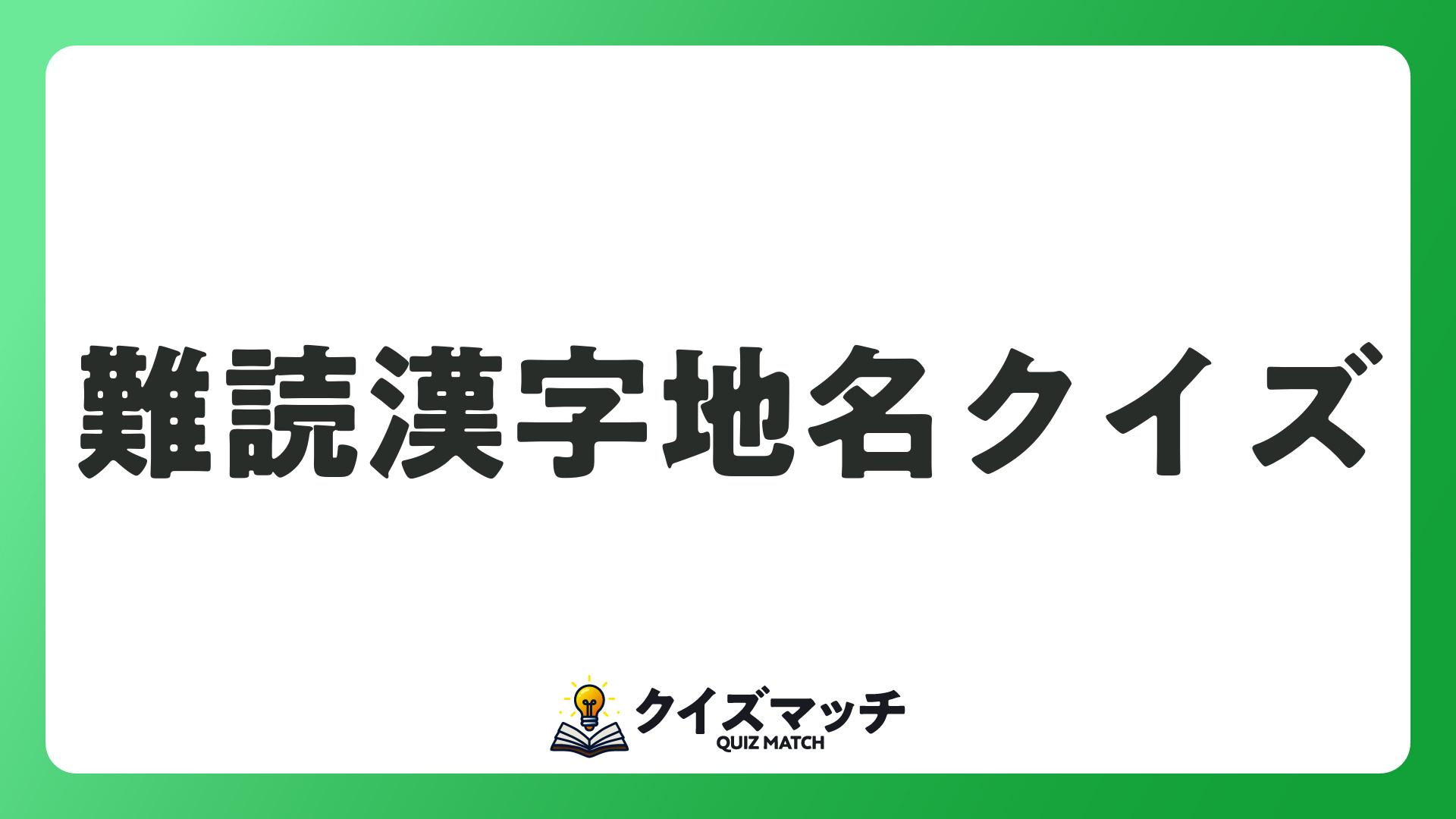難読漢字や読み間違いが多い地名クイズにチャレンジしてみましょう。この10問のクイズは、ご当地ならではの歴史や文化が隠されています。いったいどのように読むのが正解なのでしょうか? 意外な読み方に驚かされるかもしれませんが、地域の特性を知る良い機会になるはずです。じっくりと問題文を読み解いて、一問一問楽しみながら答えを見つけていきましょう。
Q1 : 「青谷」(京都府)はどのように読む?
「青谷」は京都府や鳥取県にみられる地名で、正しい読み方は「あおや」です。字面から「あおだに」と読んでしまいがちですが、古くから「あおや」と呼ばれています。現在では地域名や駅名などで使われており、地元の人にはなじみの深い名前です。
Q2 : 「不破」(岐阜県)はどのように読む?
「不破」は岐阜県不破郡などの地名で、正しい読み方は「ふわ」です。「ふば」と読みがちな字ですが、歴史的な「不破関(ふわのせき)」の名残りです。古くから交通の要衝であり、地名として全国的に知られています。
Q3 : 「生駒」(奈良県)はどのように読む?
「生駒」は奈良県北部にある地名で、正しい読み方は「いこま」です。生駒山や生駒市として知られ、古くから交通・文化の要所となっています。漢字から「いきうま」などの読みも想像できますが、「いこま」と読むのが正解です。
Q4 : 「十和田」(青森県・秋田県)はどう読む?
「十和田」は青森県と秋田県にまたがる湖および周辺地域の地名で、正しい読み方は「とわだ」です。数字の「十」ですが「とう」ではなく「と」と読みます。十和田湖だけでなく、十和田市という市名にも使われています。由来は諸説ありますが、アイヌ語説などが有力です。
Q5 : 「百舌鳥」(大阪府)はどのように読む?
「百舌鳥」は大阪府堺市にある難読地名で、正しい読み方は「もず」です。『百舌鳥・古市古墳群』などで知られます。百舌鳥(モズ)は鳥の名前でもあり、この地に多く生息していたのが地名の由来とされています。地元では地名と鳥の両方の意味で広く親しまれています。
Q6 : 「箱守」(大阪府)はどのように読む?
「箱守」は大阪府堺市にある地名で、正しい読み方は「はこも」です。見たまま「はこもり」と読んでしまいがちですが、「はこも」と略して呼びます。大阪周辺ではこうした略読みによる難読地名が多く存在し、地元民でなければ読み間違えやすい地名です。
Q7 : 「玉造」(茨城県)はどのように読む?
「玉造」は茨城県行方市の地区の名前で、正式な読み方は「たまつくり」です。一見「ぎょくぞう」と読んでしまいそうですが、歴史的には古代より勾玉などの玉を作る「玉作り(たまつくり)」が語源とされています。現在も地名や鉄道の駅名などに残っています。
Q8 : 「勿来」(福島県)はどのように読む?
「勿来」は福島県いわき市にある地名で、正しい読み方は「なこそ」です。一見「のぞき」や「もちき」と読んでしまいそうですが、「なこそ」と読むのが正解。「なこそ関」という歴史的な関所もあり、「来ることなかれ」との意味合いから名付けられたとの説があります。
Q9 : 「忍路」(北海道)はどのように読むのが正しい?
「忍路」は北海道小樽市にある地名で、正しい読み方は「おしょろ」です。アイヌ語由来とされており、古くから漁村として知られています。「しのじ」や「にんじ」とは読まず、北海道独特の難読地名の一つです。現在でも港や自然景観の美しさで観光客に知られています。
Q10 : 「鰍沢」はどのように読むのが正しい?
「鰍沢」は山梨県南巨摩郡富士川町にある地名で、正しい読み方は「かじかざわ」です。鰍(かじか)とは、淡水魚のカジカに由来するといわれています。地元では「カジカガワ」とも呼ばれることがありますが、正式には「カジカザワ」と読みます。この地名は徳川幕府時代から知られ、歌舞伎の演目にも登場するなど、文化的にも知名度の高い難読地名です。
まとめ
いかがでしたか? 今回は難読漢字 地名クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は難読漢字 地名クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。