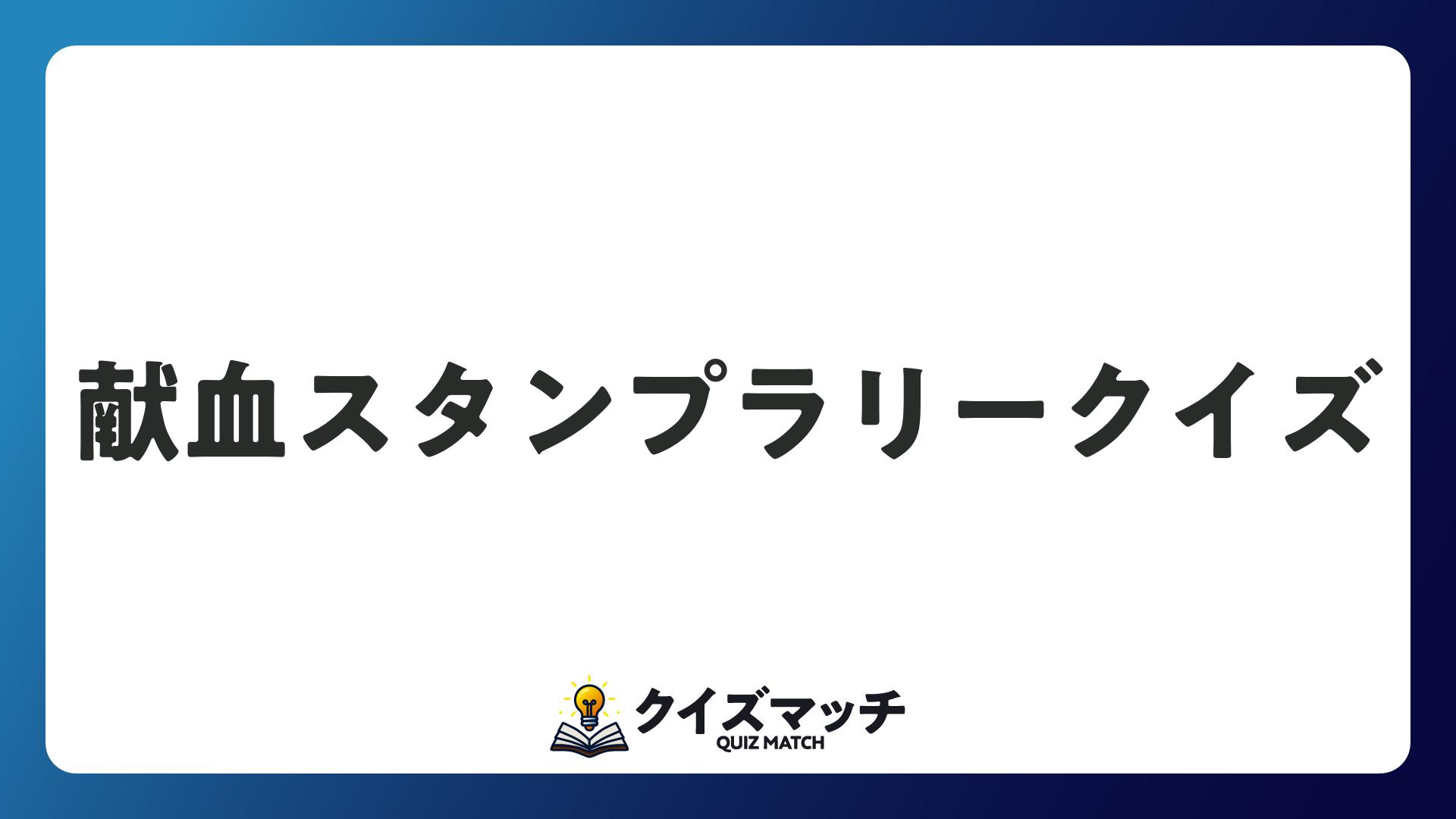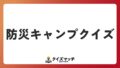日本の献血制度は、国民の健康と命を守るうえで欠かせない重要なシステムです。このキャンペーンでは、献血の基準や仕組みについて10問のクイズを通して理解を深めていただきます。採血量、保存条件、感染症対策など、献血に関する基本知識を確認しながら、安全で安心な献血体験につなげていただければと思います。専門家の解説とともに、ぜひ全問挑戦してみてください。
Q1 : 献血後や輸血用血液検査で導入されている検査のうち、ウイルスの核酸を直接検出して感染の「ウィンドウ期」を短縮するのはどれか?
核酸増幅検査(NAT: Nucleic Acid Testing)は、ウイルスの遺伝子(RNAやDNA)を直接検出する検査であり、従来の抗体や抗原検査に比べて感染検出のウィンドウ期間を短縮できます。これにより輸血・献血由来の感染リスク低減に寄与します。多くの血液センターではHIV、HBV、HCV等についてNATを導入しており、スクリーニングの精度向上に役立っています。
Q2 : タトゥー(刺青)やボディピアスを入れた後、一定期間献血を見合わせる要因となるが、日本の一般的な基準で献血を受けられない待機期間はどれか?
日本の一般的な献血基準では、タトゥーやボディピアス施術後は感染リスク確認のため一定期間献血を見合わせることが求められ、代表的には6か月間の待機期間が設けられています。これは施術に伴う血液感染症リスク(例:B型肝炎、C型肝炎など)を考慮しての措置で、施術場所の衛生管理状況等によっては基準が異なる場合があります。
Q3 : 日本国内で献血の運営や血液の安定供給を中心的に担っている組織は次のうちどれか?
日本における血液事業の中心は日本赤十字社であり、全国の血液センター・採血班を通じて献血の実施、検査、血液製剤の製造と供給を行っています。厚生労働省は法規や基準の監督を行いますが、実際の採血運営と血液製剤の供給は日本赤十字社が担っているのが現状です。民間企業は一部製剤の製造や検査支援を行うことがありますが、中心的主体は日本赤十字社です。」
Q4 : 日本における全血(400 mL)献血の安全な採血間隔は次のうちどれか?
日本では400 mLの全血献血を行った場合、次回の同種献血までの推奨間隔は約12週間(約3か月)とされています。これは献血による血液成分の回復に必要な時間を考慮したもので、頻繁な採血による献血者の貧血や健康リスクを避けるためのガイドラインです。200 mL献血の場合はもっと短い間隔が設定されることがありますが、400 mL献血ではこの間隔が一般的です。
Q5 : 血小板製剤(プレートレット)は常温で保存されるが、その保存条件として正しいものはどれか?
血小板は冷蔵保存すると機能が低下しやすいため、常温(一般に20~24℃)で振盪(揺動)しながら保存するのが標準です。多くの国や血液センターでは保存期間は5日間とされており、この条件は細菌増殖リスクや機能維持のバランスを踏まえた運用です。一方、赤血球や新鮮凍結血漿とは保存温度や期間が大きく異なるため、用途に応じた管理が重要です。
Q6 : O型赤血球(O型Rh陰性、O−)について正しい記述はどれか?
O型Rh陰性の赤血球は、赤血球表面にA抗原・B抗原・RhD抗原を持たないため、緊急時や相性が不明な場合にはほとんどの血液型の受血者に用いることができます。そのため「ユニバーサルドナー」と呼ばれることがある一方、完全な万能薬ではなく、長期的には適合した血液型を優先するなどの注意が必要です。また血漿成分では適合が逆となる点にも注意が必要です。
Q7 : 止血や血友病の補助治療で用いられることが多い成分で、フィブリノーゲンや第VIII因子を比較的多く含むのはどれか?
クリオプレシピテート(略してクリオ)は、新鮮凍結血漿を解凍する過程で得られる濃縮成分で、フィブリノーゲン、VIII因子、vWF(フォン・ウィルブランド因子)などが比較的高濃度に含まれます。したがって、重度の低フィブリノーゲン血症や特定の出血性疾患、または血友病の補助治療などで利用されます。FFPは広範な凝固因子を含みますが、クリオは特定因子を濃縮した製剤です。
Q8 : 日本で通常行われる全血献血の採血量の組み合わせとして正しいものはどれか?
日本の献血方式では、主に200 mLと400 mLの全血採血が標準的に行われています。200 mLは主に体重等の理由で400 mLが適さない場合に選ばれることがあり、400 mLは成人で一般的に行われる容量です。採血量は献血者の安全を最優先に、年齢・体重・健康状態などの基準に基づいて決定されます。
Q9 : 失血や重度の貧血で酸素運搬能を回復させる目的で最も頻繁に使われる血液成分はどれか?
酸素運搬能を直接補うのは赤血球(赤血球濃厚液)です。赤血球はヘモグロビンを含み、全身に酸素を運ぶ役割を持つため、出血や重度の貧血で酸素供給能力を回復させたい場合に優先して輸血されます。血小板は止血、FFPは凝固因子補充、クリオは特定の凝固因子補充に用いられる、という使い分けが一般的です。
Q10 : 献血の際、採血前の血色素(ヘモグロビン)基準として日本の一般的な基準で男性に求められる最低値は次のうちどれか?
日本の献血基準では、全血献血に際して貧血の有無を確認するためヘモグロビン値が用いられます。一般的に成人男性の最低基準は13.0 g/dL以上、成人女性は12.0 g/dL以上とされており、これを下回ると献血は見合わせます。これは献血者自身の安全(採血による貧血悪化防止)と、採血後の健康管理のために設けられた基準です。個別の判断は問診や医療スタッフの判断で行われますので、基準値は目安ですが実務上重要な指標です。
まとめ
いかがでしたか? 今回は献血スタンプラリークイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は献血スタンプラリークイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。