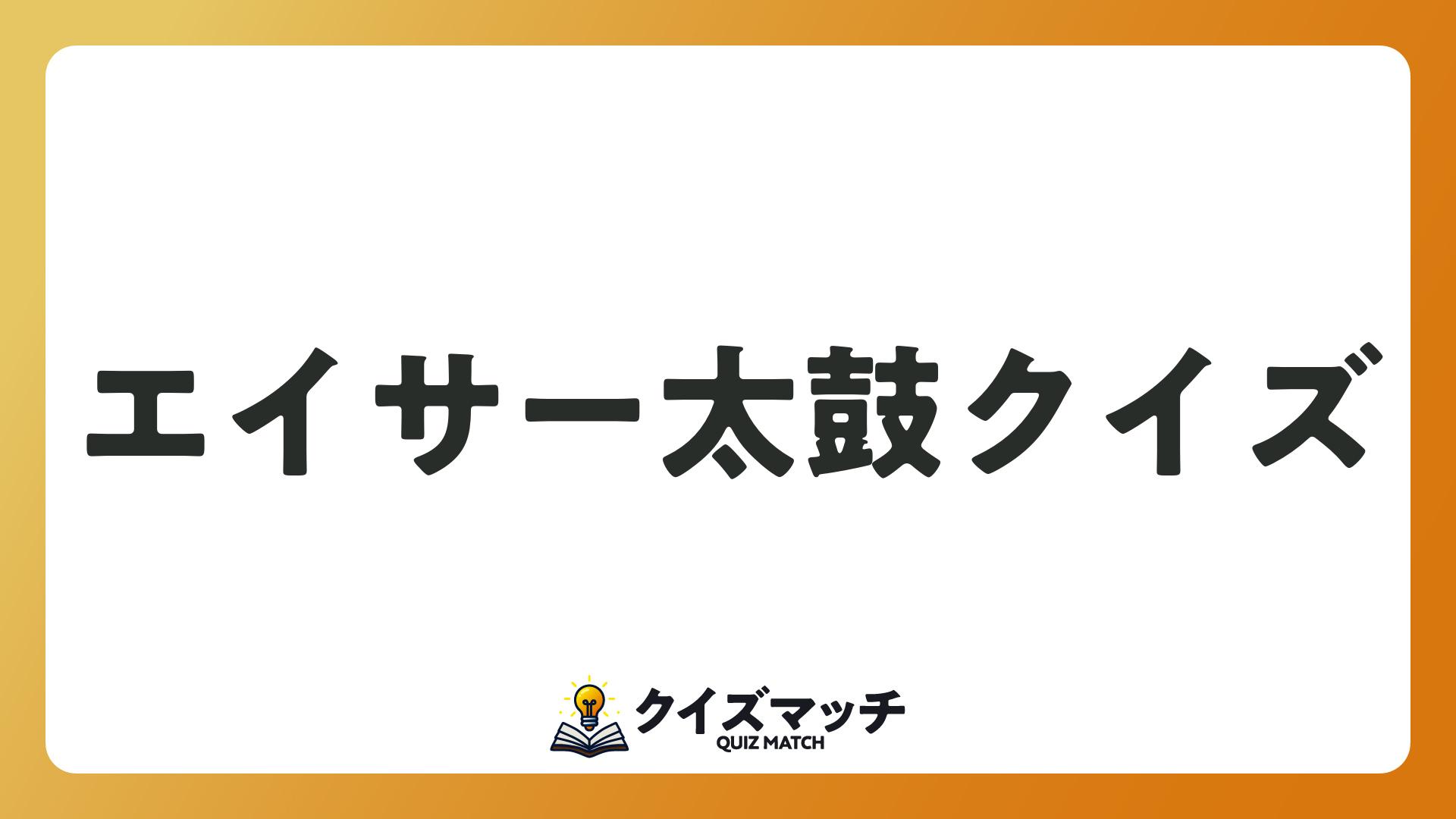沖縄の伝統行事「エイサー」をテーマとしたクイズ10問をお届けします。エイサーは旧盆(旧暦の盂蘭盆)に合わせて演じられる伝統的な民俗芸能で、青年たちが太鼓や歌、踊りを通して先祖を迎え送る様子を再現します。沖縄の歴史と文化に根付いたこの行事について、その特徴や意義、関連する楽器や祭りなどを問う全10問。エイサーの魅力に迫る充実のクイズをお楽しみください。
Q1 : エイサーの主な目的・意味として最もふさわしいものはどれか?
エイサーは先祖を迎え供養する盆行事としての性格が強い民俗芸能で、旧盆に合わせて行われることが多い点が特徴です。地域の人々が太鼓や歌、踊りで先祖を慰めるとともに、共同体の絆を深める役割を果たしています。一方で雨乞いや豊作祈願、豊漁の祝いは別の民俗儀礼に該当し、エイサーの主要な目的とは区別されます。エイサーは宗教的側面と娯楽的側面が混在しますが、中心にあるのは先祖供養です。
Q2 : 地域で組織されるエイサーの演者グループとして伝統的に使われる呼び名はどれか?
伝統的にエイサーを担ってきたのは地域の青年団や青年会であり、地域コミュニティの若者が中心になって太鼓や踊りを行います。選択肢の中で『青年団(青年会)』が正しく、これらの団体が運営や練習、祭礼時の演舞を担ってきました。里神楽や能楽、雅楽はそれぞれ別の日本の伝統芸能に関わる用語であり、エイサーの運営主体とは性格が異なります。
Q3 : エイサーの演奏や伴奏でしばしば用いられる沖縄の弦楽器はどれか?
三線は沖縄音楽を代表する三弦の撥弦楽器で、エイサーの歌や民謡の伴奏に用いられることが多い楽器です。選択肢の中でエイサー伴奏に最も関連が深いのは三線であり、琴や西洋楽器のヴァイオリン、ギターも現代的なアレンジで使われることはありますが、伝統的・民族音楽的な文脈では三線が中心的役割を果たしてきました。
Q4 : 現代において、エイサーが組織的に大規模に披露される代表的な祭り『全島エイサーまつり』が主に開催されるのはどの市か?
沖縄全島エイサーまつりは沖縄県内各地のエイサーを一堂に集めて披露する大規模なイベントで、伝統的な演目から若者団体による現代的な演出まで幅広く紹介されます。主会場は沖縄市(旧コザ)で行われることが多く、市が持つ戦後の復興史や地域文化の中心性と結びついて発展してきました。那覇市や名護市、石垣市でもエイサー関連の行事は行われますが、全島エイサーまつりの主要会場は沖縄市が知られています。
Q5 : エイサーは主にいつ行われる沖縄の伝統行事でしょうか?
エイサーは沖縄で先祖供養のために行われる盆踊り系の伝統行事で、特に旧暦の盆(旧盆)にあわせて各地で演じられます。旧盆は本土の新暦の盂蘭盆と日にちがずれることが多く、地域ごとの先祖供養のために青年団や地区の団体が太鼓や歌、踊りで盛大に供養を行う習慣が残っています。エイサーは祖先の霊を迎え、送るための芸能として位置づけられており、祭礼の性格が強いことから、行事の時期がまず旧盆と結びついている点が特徴です。
Q6 : エイサーで特徴的に使われる小さな手持ち太鼓の名前はどれか?
パーランクーはエイサーで広く用いられる小型の手持ち太鼓で、片手で持って打つ形やスティックで打つ形などで演奏されます。三線は沖縄音楽の代表的な弦楽器でエイサーの伴奏に使われることも多いですが、問題文は『小さな手持ち太鼓』を問うているため、パーランクーが正解です。パーランクーは軽快なリズムを出し、踊り手の身振りと一体になって演奏されるのが特徴で、太鼓の大きさや音色によって演出が異なります。三線は太鼓とは異なる種類の楽器なので注意が必要です。
Q7 : 次のうち、伝統的にエイサーの演奏であまり用いられない楽器はどれか?
尺八は主に本土の能・邦楽系で使われる縦笛であり、沖縄のエイサーで伝統的に用いられることはほとんどありません。エイサーでは太鼓類(パーランクーや大太鼓など)や歌、掛け声が中心で、必要に応じて三線が伴奏に加わることがある一方で、尺八は曲風や発生背景が異なるため通常の編成に含まれないのが一般的です。したがって選択肢の中でエイサーの伝統的演奏に馴染みにくいのは尺八です。
Q8 : エイサーが発祥した地域はどこか?
エイサーは琉球王国時代から沖縄を中心に発展してきた民俗芸能で、盆供養に由来する踊りとして地域社会で受け継がれてきました。選択肢の中では『沖縄(琉球)』が正しい発祥地です。なお、ここで注意したいのはエイサーが現代に至るまで各地で形を変えながら伝承・再編されてきた点で、戦後には地域の青年会を中心に集団演舞としての形式が整えられ、観光文化としても発展しています。
Q9 : 歴史的に見て、伝統的なエイサーを主に演じてきたのはどの層か?
伝統的なエイサーは盆の供養を担う地域の青年たち、つまり青年団や青年会が中心となって演じてきたのが歴史的特徴です。若者が太鼓を打ち鳴らして町内を練り歩くことで先祖を迎え送り、共同体の結束を示す役割を果たしてきました。高齢者や婦人会、僧侶や職人的組織も祭礼に関わることはありますが、太鼓を主体にした踊り手としての主役は伝統的に青年層であり、戦後の地域復興期にも青年会がエイサーを担い続けました。
まとめ
いかがでしたか? 今回はエイサー太鼓クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回はエイサー太鼓クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。