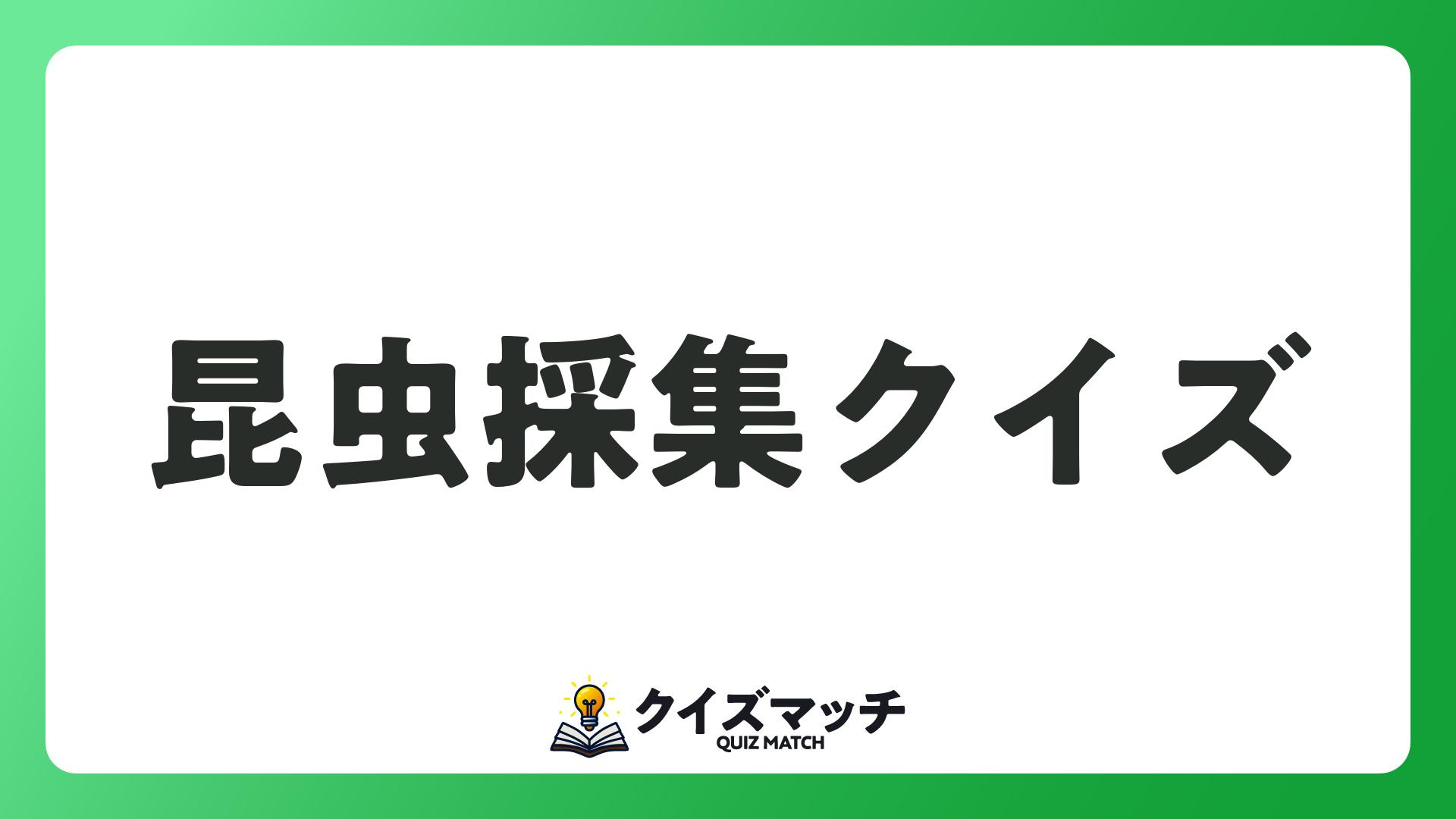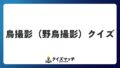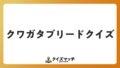昆虫採集クイズ – 虫捕りの達人を目指そう!
昆虫採集は野外観察の醍醐味の一つ。虫取り網の選び方から採集場所の選定、保存方法まで、熟練した技術と知識が必要です。本記事では、そんな昆虫採集の醍醐味を存分に味わえる10問のクイズをご紹介します。虫捕りのテクニックや知識をチェックしながら、あなたも昆虫採集の達人を目指しましょう!
Q1 : 採集した昆虫の標本ラベルに必ず記載すべき事項として正しいものはどれか?
標本の学術的価値を保つために最も重要なのは採集地(地名や座標)、採集日、採集者、採集方法など基本情報の記録です。採集地は生態や分布を理解する上で必須の情報であり、欠けていると標本の利用価値が著しく低下します。飼育方法や食草などは補足情報として有用ですが、必須項目ではありません。ラベルは将来の研究で参照されるため丁寧に記載します。
Q2 : 採集時に毒性や刺傷のある昆虫を扱う際、まず最優先で注意すべき行動はどれか?
毒や刺し傷のある昆虫を扱う際はまず自分の安全を最優先にし、素手で触らないことが基本です。ピンセットや長いハンドルの網、容器など適切な道具を使って距離を保ちつつ採集・移送します。事前に当該地域で危険な種がいないか確認し、必要なら手袋や保護具を着用、刺された場合やアレルギー反応の可能性に備え応急処置と連絡手段を確保しておくことが重要です。
Q3 : 蛾類をより強く引き寄せやすい光の波長はどれか?
蛾類は紫外線や近紫外・青に近い波長に対する感受性が高く、これらの波長を含む光源に強く引き寄せられます。市販のブラックライト(UV-A)や蛍光灯の特定波長を利用したライトトラップは多くの種に有効です。赤色光は蛾にはあまり効果がなく、白色光は成分によっては有効ですが紫外線を含まないと誘引効果が低下します。研究や採集ではUV光源の選択が重要になります。
Q4 : 日本の国立公園や自然保護区内で昆虫を採集する場合、一般的な扱いはどれか?
国立公園や自然保護区、保護林などでは生態系保全の観点から採集が原則として制限されていることが多く、研究目的等で採集する場合には管理者への事前申請や許可が必要になります。種の保護区や絶滅危惧種が含まれる地域では更に厳格な規制があり、違反すると罰則が科されることもあります。現地での採集を行う前には必ず自治体や管理者のルールを確認してください。
Q5 : 樹上の枝を布や棒で叩いて葉の虫を落として採集する『ビーティング』で特に効率よく採れる昆虫の代表はどれか?
ビーティングは樹上や低木の枝を叩いて葉や枝にいる昆虫やクモ類を落とし、布やトレーで回収する方法です。特に甲虫類、例えばカミキリムシやコガネムシ、ハムシ類などの樹上性の甲虫が多く採れるのが特徴です。ハチ類は飛び回って逃げやすく、トンボは枝上にとまっていることが少ないためビーティングでは効率が落ちます。
Q6 : ライトトラップ用の発電機が使えないとき、夜間に蛾を採集するための代替方法として有効なのはどれか?
発電機が使えない場合でも、発酵ジュースや果実、酒粕などを用いたベイトトラップや樹液トラップは夜間に飛来する蛾や甲虫を誘引する有効な代替手段です。特定種にはフェロモントラップが有効なこともあります。懐中電灯や手網での採集は一時的に有効ですが広く誘引するには限界があります。ベイトは準備が簡単で自然光源なしでも一定の成果が期待できます。
Q7 : 虫取り網の網部分(メッシュ)に使われる材質で、軽く乾きやすく通気性と耐久性のバランスが良いのはどれか?
ナイロン製メッシュが最も一般的です。ナイロンは軽量で強度があり、濡れても乾きやすく通気性も良いためカビが生えにくく手入れが簡単です。一方、綿は水を吸いやすく乾きにくいため湿気で劣化しやすく、絹は強度が落ちやすく高価で扱いにくいです。金属メッシュは重く、昆虫採集用としては一般的ではありません。したがって実用面と耐久性のバランスからナイロン製が適しています。
Q8 : 夜間に樹上や花周辺に集まる蛾類を効率よく採集する方法はどれか?
夜間の蛾類採集ではライトトラップが特に有効です。紫外線や特定の波長の光は多くの蛾を強く引き寄せ、白布を張ってそこに集まった個体を採集します。ビーティングや樹液トラップも有効な場合がありますが、夜行性で飛来する蛾を広く誘引するのは光による方法です。実際の運用では発電機や電球の種類、風除け、電源確保と安全対策を考慮します。
Q9 : カブトムシやクワガタの幼虫が主に摂食するものはどれか?
多くのカブトムシやクワガタの幼虫(蛹化前の大型の白い幼虫)は、腐朽した木材や豊富な有機物を含む腐葉土を主に摂食します。成虫は樹液や花蜜を利用する種があるのに対して、幼虫期は土中や朽木の中で微生物分解された有機物を食べて成長するのが一般的です。種によって餌の好みは異なりますが、腐朽材や腐葉土が重要な栄養源である点は共通しています。
Q10 : 採集した昆虫を長期間、資料として保存する際に最も一般的に用いられる保存方法はどれか?
長期保存や標本館での資料化において一般的なのは乾燥標本、つまり展翅やピン刺しによる乾燥保存です。甲虫や蝶類など外骨格の硬い昆虫はピンで固定し乾燥させることで長期保管が可能になります。エタノール保存は軟体の昆虫(昆虫以外の節足動物や幼虫など)や分子解析用に用いられ、冷凍は短期的或いは遺伝子解析前処理で使われることが多いです。
まとめ
いかがでしたか? 今回は昆虫採集クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は昆虫採集クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。