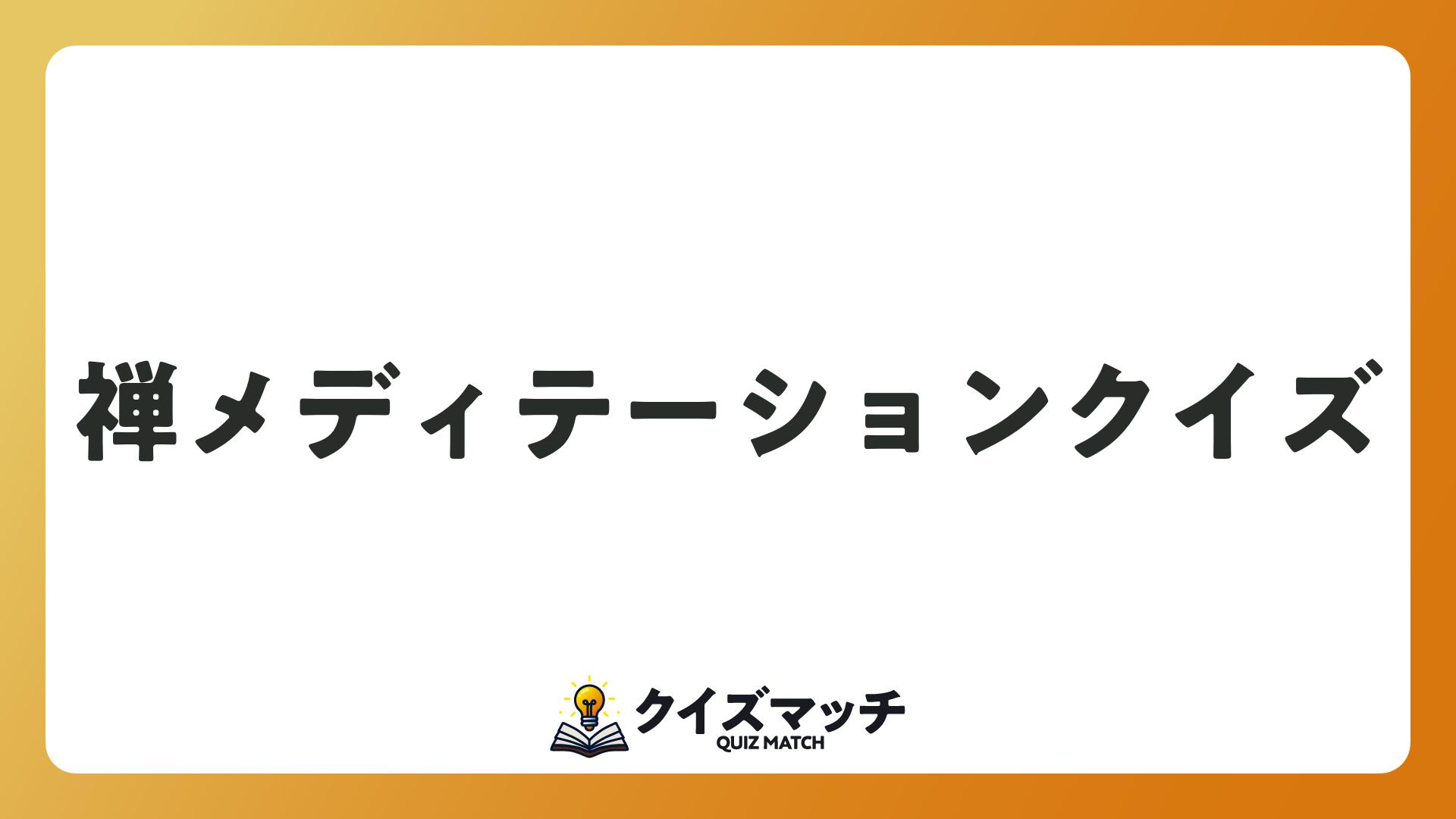「ただ坐る」ことを重視する日本の禅メディテーション。呼吸や公案に縛られず、思考や感情を追わず自然体で座り続けることで、本来の自己に目覚めることを目指します。見性の体験や公案修行、独参などの独特の実践が知られる一方で、初心者にも取り組みやすい只管打坐の技法など、禅にはさまざまな側面があります。こうした禅の世界をより深く理解するために、本記事では10の基本的な問題を用意しました。禅への入門にも、既存の修行者の方の理解深化にもお役立てください。
Q1 : 「独参(どくさん)」とは禅の修行で何を示すか?
独参(どくさん)は修行者が師と一対一で面談する場で、坐禅や公案の進捗、日々の実践について直接指導や検討を受けます。臨済系では公案の提示や切迫した問いを受けることが多く、曹洞系でも実践の指導や生活の諸問題に関する助言が行われます。独参は修行を個別に深化させる重要な機会で、師の眼を通した確認が得られます。
Q2 : 曹洞宗の只管打坐における呼吸の扱いについて正しいのはどれか?
曹洞宗の只管打坐では呼吸を特別に操作したり数えたりすることを目的とせず、自然な呼吸をそのまま観察してとどまらない点に特徴があります。呼吸は坐る過程の一部であり、呼吸に執着して対象にすると妨げになるため、自然の流れを受け入れて姿勢と心の安定を保つことが重視されます。
Q3 : 「無(む)」という言葉は禅の公案でどのような意味合いを持つか?
「無(む)」は禅の古典的な公案に登場する語で、最も有名なのは趙州(じょうしゅう・中国語名:曹州)の「狗子有仏性」への答としての「無」です。ここでの『無』は単なる否定ではなく、言語的・概念的二分法を超えるための指示であり、修行者に直観的な突破(見性)を促す道具です。思考を停止させるための焦点となり得ます。
Q4 : 「袈裟(けさ)」とは禅宗において何を指すか?
袈裟(けさ)は僧侶や修行者が着用する法衣で、仏教の僧階や宗派によって形や色、着付け方が異なります。元来は修行者の衣であり、奉公や戒律を象徴すると同時に出家の身分を示すものです。日本の禅宗では独特の折り畳み方や紐の結び方があり、儀式や日常の修行の中で着用されます。
Q5 : 「只管打坐(しきゃんたざ)」とは何を指すか?
只管打坐は日本の曹洞宗で強調される坐禅の実践で、文字通り「ただ坐る」ことを意味します。道元が唱えた思想と結び付き、特定の対象(呼吸や公案)に固執せず、思考や感情の生起を追わずそのまま座ることで本来のあり方を深める実践です。坐ること自体を目的とし、結果や悟りを追わない姿勢が特徴で、呼吸は自然な流れに任せます。
Q6 : 「見性(けんしょう)」とは何を意味するか?
見性(けんしょう)は直訳すると「性を見る」、すなわち自己の本性や仏性を直に認める体験を指します。禅では悟りの初期の顕現とされ、完全な悟り(大悟)と区別されることが多いです。一時的である場合もあり、そこから継続的な修行を通じて理解を深め、日常の行為に根づかせることが求められます。
Q7 : 禅の諸流派のうち、公案(こうあん)修行を特に重視するのはどれか?
臨済宗(りんざいしゅう)は公案を用いる修行で広く知られています。公案は師が与える短い問答や事件で、論理的な回答を超えた悟りの契機を生むために用いられます。禅堂での担当師との面談(独参)や激しい問い込みを通じて、理屈を外した直観的な理解を促す点が臨済の特色です。曹洞は主に只管打坐(しきゃんたざ)を重視します。
Q8 : 「経行(きんひん)」とは禅の実践で何を指すか?
経行(きんひん)は坐禅と坐禅の合間に行われる歩行瞑想で、一定のリズムでゆっくりと歩きながら呼吸や足の感覚に注意を向ける実践です。静坐の後に行うことで身体をほぐし、姿勢を保つ訓練にもなります。緩やかな歩幅と一定の呼吸に合わせた歩行が推奨され、雑念を連続して坐禅に持ち込まないための移行手段でもあります。
Q9 : 坐禅における「法界定印(ほっかいじょういん)」とはどのようなものか?
法界定印は伝統的な坐禅の手印で、左手を上にして右手の上に重ね、両親指を軽く合わせて小さな楕円形(母指の円)を作る形です。手は腹の前、丹田のあたりに置き、過度な力を入れず自然に形を保ちます。これは心身の安定と集中を助ける象徴的な手の位置で、姿勢の均衡や呼吸の自然さを促進します。
Q10 : 「接心(せっしん)/摂心(せっしん)」または「摂心会(せっしんえ)」が指すものは?
摂心(せっしん)とは数日から一週間、あるいはそれ以上の期間にわたって行われる集中坐禅会を指します。日中ほぼ終日坐禅・作務・食事は静かにとるなど厳格な日課が組まれ、師による独参(面談)や転座、作務を通じた実践が行われます。雑念を落とし続けるための強化期間で、内部に深く入るための重要な機会とされます。
まとめ
いかがでしたか? 今回は禅メディテーションクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は禅メディテーションクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。