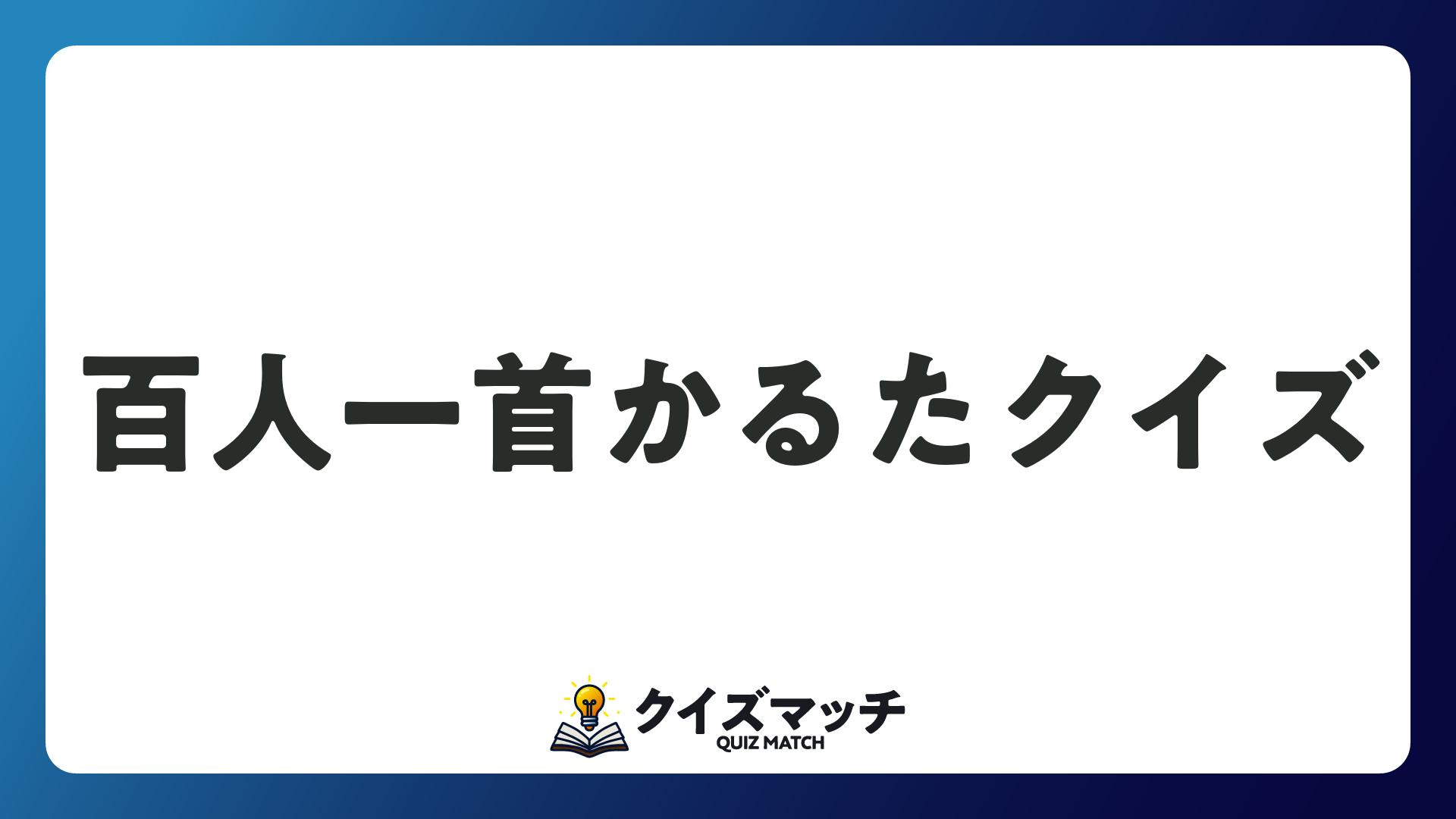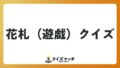百人一首かるたは古来より日本の伝統文化の一部として親しまれてきました。その原典は鎌倉時代初期に歌人・歌学者の藤原定家が編纂した『小倉百人一首』です。定家は古今和歌集以降の名歌を厳選し、100人の詠み人を振り分けた独自の撰集を作りあげました。この集は後に「百人一首」の呼称で知られるようになり、現代に至るまでかるた遊びの定番作品として愛され続けています。本記事では、この『小倉百人一首』にまつわる10の基本的なクイズを紹介します。和歌の歴史や文化を理解を深める良い機会になるでしょう。
Q1 : 「田子の浦に うち出でてみれば 真白にぞ 富士の高嶺に 雪は降りける」という歌の詠み人は誰か?
この歌は富士山の雪景色を詠んだ名歌で、詠み人は奈良時代の歌人・山部赤人(やまべのあかひと)です。田子の浦から見る富士の頂が真っ白に雪で覆われている様子を素直に詠んでおり、景物描写の美しさが際立ちます。山部赤人は万葉歌人の代表の一人で、自然や山川の叙景歌に優れた作品を多く残しており、この歌もその典型とされています。
Q2 : 「あしびきの 山鳥の尾の しだり尾の 長々し夜を ひとりかも寝む」という歌の詠み人は誰か?
この歌は古風な言い回しと哀感を帯びた表現で知られ、詠み人は柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ)と伝えられています。あしびき=山の意味を背景に、山鳥の尾が長く垂れているような長い夜を一人で過ごす寂しさを詠んだ歌で、古代の歌語や比喩を用いた技巧的な作風が特徴です。柿本人麻呂は万葉集を代表する歌人で、格式高い叙情と技巧を兼ね備えた歌を多く残しています。
Q3 : 「花の色は 移りにけりないたづらに 我が身世にふる ながめせしまに」という歌の詠み人は誰か?
この歌は恋や美のはかなさを詠んだ代表的な和歌で、詠み人は平安時代の女流歌人・小野小町と伝えられています。花の色が移り変わってしまったように、わが身にも時の移ろいが訪れ、長雨のように涙を流して眺めているうちに美しさが失われたと詠む内容は、人生や容貌の儚さを象徴的に表現しています。小野小町は色鮮やかな恋歌で特に有名で、この歌もその代表作の一つです。
Q4 : 小倉百人一首の『小倉』は小倉山のことを指すが、小倉山は現在どの都の近くにあるか?
『小倉百人一首』の『小倉』は京都の嵐山にある小倉山を指します。藤原定家が小倉山に邸を構え、その山麓で歌を選んだことから『小倉百人一首』という名称が定着しました。小倉山は古くから和歌や文芸の舞台として知られ、現在も京都嵐山の観光地の一部として有名です。したがって小倉百人一首の『小倉』は京都にある小倉山を意味します。
Q5 : 藤原定家(百人一首の撰者)が活躍した主な時代はいつか?
藤原定家(1162–1241)は平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて活躍した歌人・歌学者です。父は俊成で、定家自身は院政期から鎌倉時代の成立期にかけて活動し、『小倉百人一首』の撰や続勅撰歌集への関与、日記や注釈書の執筆などで知られます。時代区分としては鎌倉時代に代表される人物であり、武家政治が台頭しつつある時代背景の下で和歌の伝統を維持・発展させました。
Q6 : 百人一首を編纂したのは誰か?
百人一首(小倉百人一首)は鎌倉時代初期の歌人・歌学者である藤原定家(藤原俊成の子、1162–1241)が、京都嵯峨の小倉山で編んだ撰集として知られます。定家は古今和歌集以降の名歌を中心に一首ずつ選び、歌人人数を百人に限って詠み人を一人ずつ割り当てたことから『百人一首』と呼ばれます。後世これがかるた遊びの元になり、現在の形の「小倉百人一首」は定家の撰によるものとされています。したがって正解は藤原定家です。
Q7 : 和歌(短歌)は一般に何句(何行)で構成されるか?
和歌、特に古典和歌(短歌)は伝統的に五つの拍(句)で構成され、それぞれの長さは五七五七七の形式を取ります。これを便宜上「五句」や「五行」と表現することが多く、五つのまとまりで一首が成り立ちます。百人一首に収められている歌もすべてこの短歌形式で、感情や景色を凝縮して表現するために五句の配列が重要な役割を果たします。そのため選択肢の中では「五句(五行)」が正解です。
Q8 : かるたで読み上げる人を何というか?
かるた競技や遊びにおいて、札に書かれた歌を声に出して読み上げる役割の人を一般に『読み手(よみて)』と呼びます。読み手は読み札を読み上げ、他のプレイヤー(取り手)が対応する取り札を素早く取るのがルールです。読み手は中立であることが求められ、音程や間の取り方、句切れの示し方などでゲームの公正さに影響を与えるため熟練が必要です。取り手は札を取る側のプレイヤーを指す別の用語です。
Q9 : かるたでプレイヤーが実際に取るカードを何というか?
百人一首かるたでは二種類の札が用いられます。読み手が持ち読み上げるカードを『読み札(よみふだ)』、床に並べてプレイヤーが取り合うカードを『取り札(とりふだ)』と呼びます。取り札には通常、歌の下の句(または上の句と下の句の全体)が印刷されており、読み手が読み札を読み終える前後に取り札を素早く掴んだ方が得点となります。したがって実際に手で取るカードは『取り札』です。
Q10 : 「秋の田の かりほの庵の 苫をあらみ わが衣手は 露にぬれつつ」という歌の詠み人は誰か?
この歌は百人一首の第1番に収められている有名な歌で、詠み人は天智天皇(中大兄皇子)です。歌の内容は収穫期に仮小屋(かりほの庵)で過ごす農作業の風景を詠んだもので、苫の目が粗いため衣(ころも)の袖が露に濡れてしまうという実景を詠み込んでいます。天智天皇は皇族でありながら感性的な和歌を残し、この一首は百人一首の冒頭を飾る代表的な作品として広く知られています。
まとめ
いかがでしたか? 今回は百人一首かるたクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は百人一首かるたクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。