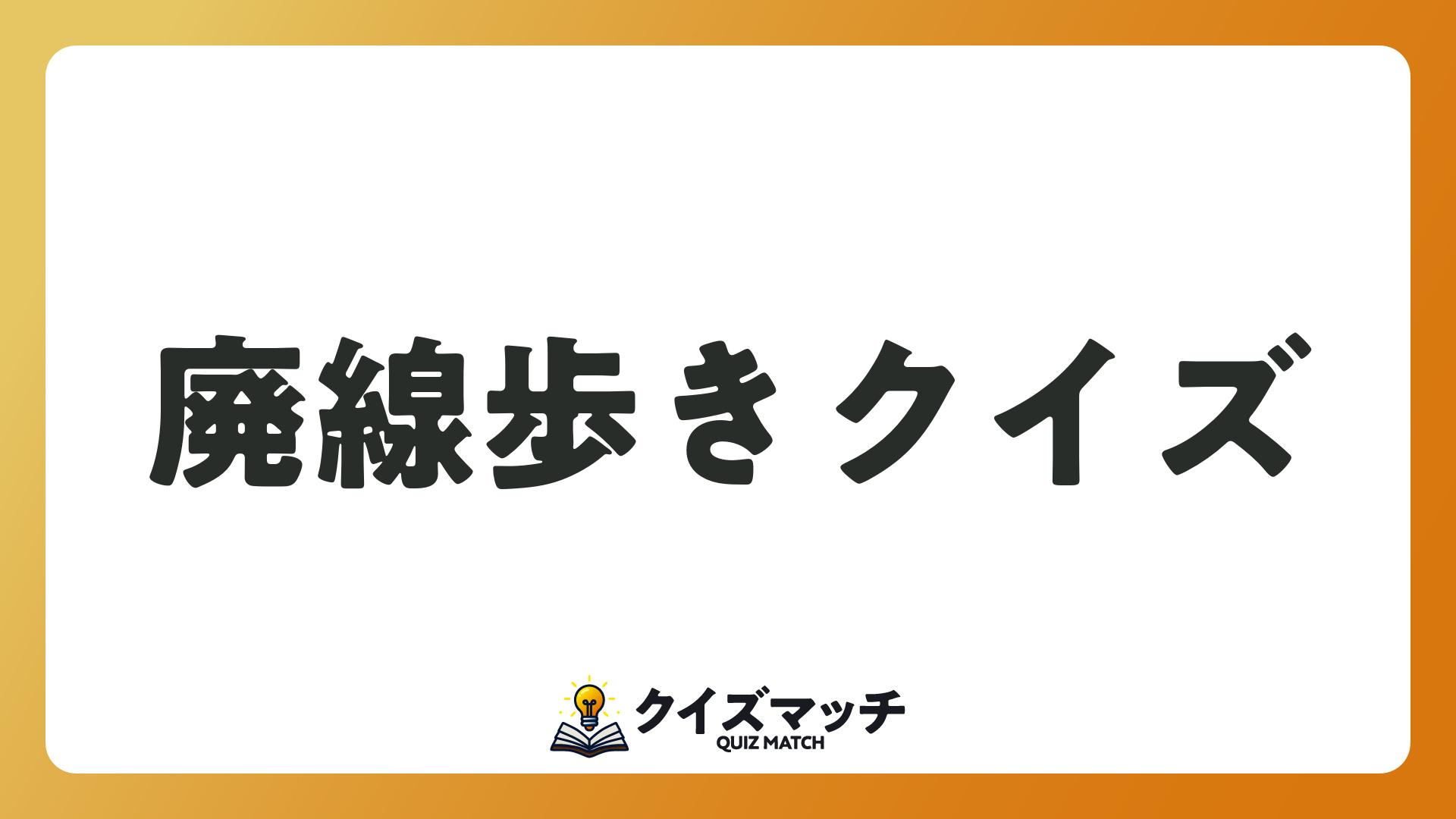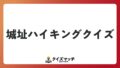三江線(さんこうせん)は中国地方を走っていた地方路線で、長距離にわたる区間を持ちながら過疎化と利用者減少が続き、2018年3月31日にJR西日本の運営により全線で旅客営業を終了しました。この廃線跡には、トンネルや橋梁、ホーム跡など歴史的な鉄道遺構が残されており、地域の文化財として保存・活用されることが期待されています。旧線の魅力を再発見し、鉄道ファンや地域の方々に知ってもらうべく、10問の「廃線歩きクイズ」をお送りします。
Q1 : 廃線跡の保存や活用を行う団体の一般的な活動として『あまり行われないもの』はどれか?
保存団体や自治体による廃線活用は、軌道や駅舎の保存・移築、保存車両の展示、看板や解説の整備、写真展や講演会による啓発などが一般的です。しかし『現役列車の運行を継続する』ことは、廃線となった路線で通常は許可も設備もなく極めて稀であり、高額な整備や法的手続きが必要なため一般的な活動とは言えません。
Q2 : 観光用途で廃線跡の線路上を自転車のように漕いで走るアトラクションの名前として一般的なのはどれか?
廃線跡の軌道上を専用の小型台車や客車状の台車に乗って、手やペダルで駆動して走行する観光アトラクションは一般に「レールバイク」と呼ばれます。国内外で観光資源として活用される事例があり、廃線のトンネルや橋梁、沿線の景観を間近に楽しめるのが特徴です。運行には土地所有者の許可や安全対策が必要です。
Q3 : 英語で「廃線跡を利用した遊歩道」を指す一般的な言葉はどれか?
廃線跡を整備して歩行者・自転車用の道に転用したものは英語圏では一般に「rail trail」と呼ばれます。これは鉄道路線(railroad)の廃止後に線路跡をトレイル(散策路・自転車道)として再利用する概念を示す言葉で、アメリカやヨーロッパで広く使われており、日本でも同様の転用事例に対してこの用語が当てられることがあります。
Q4 : 三江線が公式に廃止(運行終了)された年はいつか?
三江線は人口減少と利用者数の著しい減少を理由に、JR西日本が運行を終了し2018年3月31日をもって全線での旅客営業を終えました。廃止にあたっては沿線自治体との協議や代替交通の検討が行われ、廃線後は遺構の保存や沿線の活用に関する議論が続いています。2018年が公式な運行終了年として記録されています。
Q5 : 三江線(さんこうせん)はどの鉄道会社が運営していたか?
三江線は中国地方を走っていた地方路線で、正式にはJR西日本が運営していました。路線は島根県江津市の江津駅と広島県三次市の三次駅を結ぶ幹線で、長距離にわたる区間を持ちながら過疎化と利用者減少が続き、2018年3月31日に全線で旅客営業を終了しました。JR西日本はローカル線の運営主体であり、三江線も同社路線として廃止まで運行されていた歴史的事実があります。
Q6 : 群馬県にある、碓氷峠の旧線を中心に資料や車両を展示している施設の名称は何か?
碓氷峠に関する資料や実物車両、軌道遺構を保存・展示している施設は「碓氷峠鉄道文化むら」です。群馬県安中市(旧碓氷峠周辺)に位置し、峠越えで使われた機関車や保線用車両、往時の写真や運行史料などを展示している点が特徴です。碓氷峠は急勾配区間として知られ、保存施設は峠や旧線の歴史を学ぶ場として地域の遺産保全に寄与しています。
Q7 : 廃線跡で歩く際によく見られる遺構として、誤っているものはどれか?
廃線跡にはトンネル、橋梁、ホーム跡、枕木や駅舎の基礎、信号施設跡など鉄道固有の遺構が多く残ります。これらは線路跡を辿ることで確認でき、保存・展示されることもあります。一方で「空港の滑走路」は鉄道遺構とは無関係で、廃線跡に見られるものではありません。したがって設問の誤った選択肢は空港滑走路になります。
Q8 : 廃線跡を歩く際の法的・安全上の注意で最も正しいものはどれか?
廃線跡は管理者が残る私有地や旧鉄道敷地であり、立ち入りに法的制限がある場所が多くあります。トンネルや橋梁は崩落・落盤・雨水による浸食などで危険が伴い、無断立ち入りは事故や法的問題につながるため、立ち入り禁止の標示がある場合は従い、歩行する際も事前に所有者や自治体に確認を取るなど安全対策を徹底することが重要です。
Q9 : 北海道小樽市の旧手宮線の廃線跡は現在どのように整備されているか?
小樽市の旧手宮線跡は一部区間が保存され、公園や遊歩道として整備されています。線路跡には保存されたレールやプラットフォームの遺構、解説板などが置かれ、地域の歴史や港湾都市としての鉄道史を伝える場となっています。廃線跡の一部が緑地や散策路として再生される例は全国的にも多く、文化財的価値の保存と市民の憩いの場として活用されています。
Q10 : 日本の廃線跡で、レンガ造りのトンネルや橋台が多く見られるのは主にどの時代に建設された路線の遺構か?
明治から大正期に敷設された多くの鉄道遺構はレンガ積みのトンネルポータルや橋台、アーチ構造が特徴で、当時の土木技術や材料事情を反映しています。産業化初期に洋式土木が導入されたことからレンガ造りが多用され、後年は鉄筋コンクリートやプレキャスト部材へと変化していきました。したがってレンガ遺構は主に明治〜大正期のものが多く見られます。
まとめ
いかがでしたか? 今回は廃線歩きクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は廃線歩きクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。