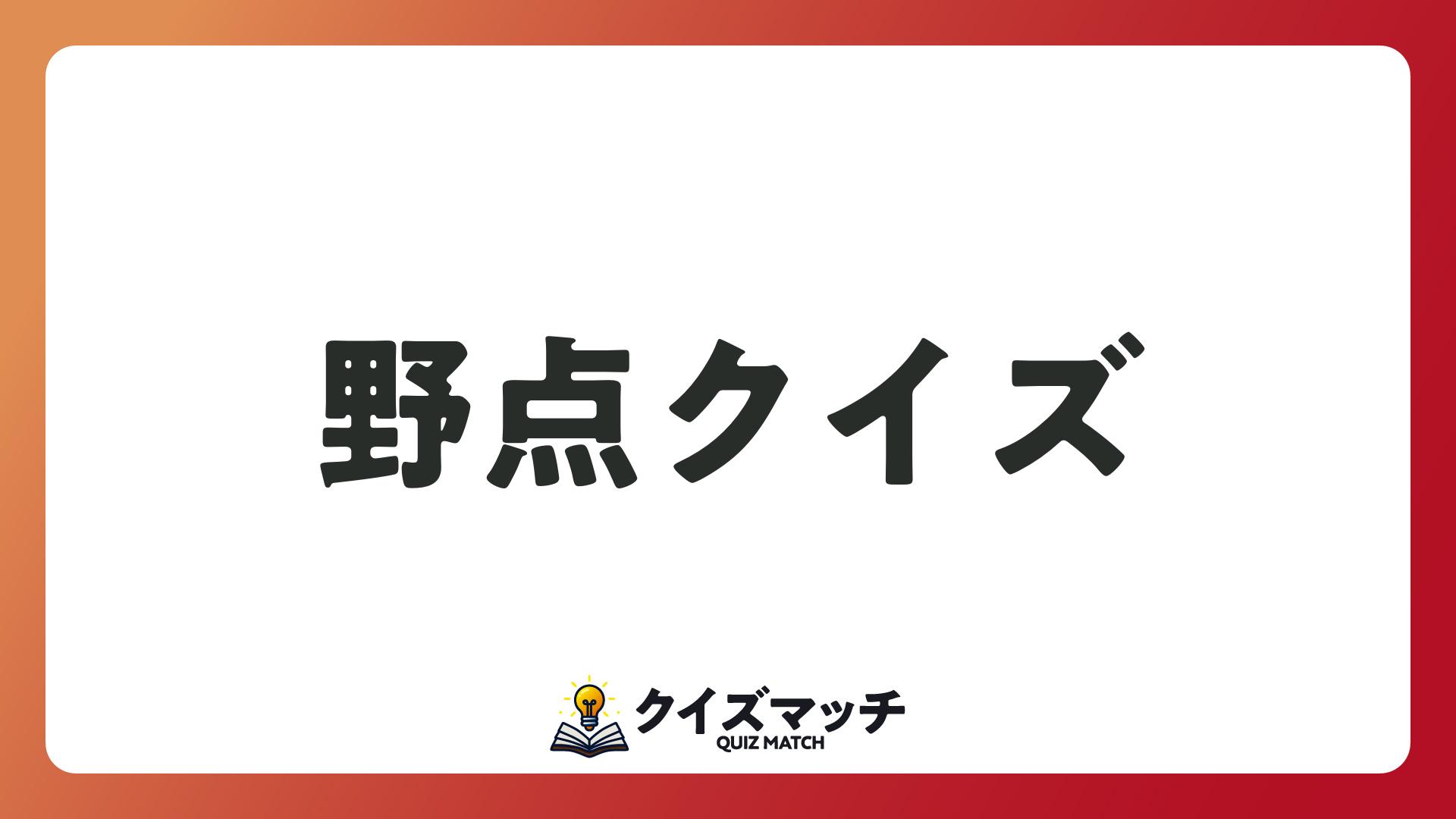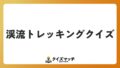野点は、自然の中で気軽に楽しむ茶の湯の会です。しかし、その裏には緻密な作法や道具の選び方があります。本記事では、野点の際に用いられる特有の茶道具や作法について、10問のクイズを通して解説します。抹茶の種類や茶筅の使い方、茶碗の回し方など、野点ならではの知識を確認することができます。茶道の奥深さを感じつつ、楽しみながら読み進めていただければと思います。
Q1 : 茶席で使われる建水(けんすい)の主な役割は何か?
建水は茶道具の一つで、点前の際に茶碗をすすいだり余った湯や茶筅を洗った水を一時的に溜める器です。野点・室内いずれの席でも用いられ、清潔に保つことが重要です。点前の流れの中で建水に水を捨てることで席周りを清潔に保ち、器物の扱いにも気を配るという茶の心が表れます。建水の位置や扱い方には流派ごとの作法があります。
Q2 : 客が茶碗を回して飲む作法で、その理由として正しいのはどれか?
茶碗を回す作法は、茶碗の正面(高台脇や作者の意匠がある部分)を客自身の正面に向けないために行います。これは茶碗の正面を主役にせず、亭主や他の客への敬意を示す配慮です。また回すことで飲みやすい位置に持ってくるという実用的な意味もあります。流派や席の格式により回す方向や回数の作法が細かく定められていることがあります。
Q3 : 茶筅(ちゃせん)を作る素材として伝統的に最も一般的なのは何か?
茶筅は伝統的に竹で作られます。竹はしなやかさと弾力があり、細く裂いて穂先を多数作ることで抹茶を素早く攪拌して泡立てるのに適しています。地域や作り手によって節の取り方や穂の本数に差があり、それが茶筅の使い心地や泡立ちに影響します。金属や陶器は茶筅の素材としては適しておらず、現代でも竹製が主流です。
Q4 : 茶入れ(ちゃいれ)を包むための仕覆(しふく)は主に何に使われるか?
仕覆は茶入れ(特に茶入、茶壺など)を包む小さな袋状の装飾品で、持ち運びや保護、また見た目の装飾として用いられます。絹や綿などで作られ、茶会の趣向や季節、席主の好みに応じて色柄や縫い方が選ばれます。仕覆には茶入れを衝撃や汚れから守る役割と、茶具全体の調和を図る役割があり、茶道具の扱いや流派の美意識が反映される重要な小物です。
Q5 : 野点で屋外に持ち出して使われる携帯用の炉の名称はどれか?
風炉は茶席で用いる携帯可能な炉で、主に夏季や屋外の野点で湯を沸かしたり湯をわかすために使われます。対して「炉(ろ)」は床に切った炉口に据える冬季用の暖炉式の設備で、屋内の茶席で用いられることが多い点が異なります。火鉢は暖を取る器具で構造や用途が異なり、釜は湯を沸かす器具そのものを指します。野点では持ち運びしやすく設置が簡便な風炉が一般的です。
Q6 : 野点で日除けや雨除けに立てられる、茶席用の傘の名称はどれか?
野点傘(のだてがさ)は、屋外で茶会を行う際に日よけや急な雨よけとして茶席のそばに立てられる傘の呼称です。伝統的には和傘の形式を基にしており、竹骨や和紙、あるいは藁を用いるものもあります。茶席の雰囲気を壊さないように配慮された素材や色が選ばれ、来客の動線や道具の保護を目的としています。茶傘や唐傘と混同されがちですが、屋外茶会で用いる専用の傘を指す語として「野点傘」が用いられます。
Q7 : 野点で主に点てられることが多い抹茶の種類はどれか?
野点では一般的に薄茶(うすちゃ)が主に点てられます。野点は屋外で気軽に茶を楽しむ性格の席が多く、薄茶は一服ずつ客に振る舞う形式に適しているためです。濃茶は正式で格式の高い場面や主に濃茶を交えた茶会(例えば寄付や濃茶の席)が設定される場では使われますが、屋外での簡便さや人数の多さを考えると薄茶が用いられることが多いです。
Q8 : 野点で客が茶をいただく前に用いる懐紙(かいし)の主な用途はどれか?
懐紙は茶席において客が携える専用の紙で、口を拭いたり茶器の縁を軽く清める、茶菓子を受けてそのままいただく、あるいはごみを包むなど多目的に使われます。畳の上での扱い方や懐に入れて携行する作法も定まっており、礼儀や衛生面で重要な役割を果たします。懐紙は柄や厚さが様々で、席の格式に合わせて使い分けられることもあります。
Q9 : 抹茶を点てる際に欠かせない道具で、茶をすばやく攪拌して泡を立てる器具はどれか?
茶筅は竹を細く割いて穂先を整えた道具で、抹茶を湯で溶かし均一にし、表面に適度な泡を立てるために不可欠です。茶筅の形状や本数(穂数)によって泡立ちや扱いやすさが変わり、薄茶用と濃茶用で使い分けられることもあります。茶杓は茶粉を取るための匙、棗は薄茶の容器、建水は余った湯や洗い水を入れる器であり、茶筅とは用途が明確に異なります。
Q10 : 茶杓(ちゃしゃく)に伝統的に使われる主な材料は何か?
茶杓は抹茶を抹茶入れ(棗や茶入)から取る際に用いる匙状の道具で、伝統的には竹が主な材料です。竹は軽くて適度な弾力があり、扱いやすく茶粉をすくうのに適しています。茶杓は一本一本手作りされることが多く、節や木目の風合いが鑑賞の対象にもなります。金属や陶器製のものは一般的ではなく、形式や流派によっては素材や形に独自の決まりを持つ場合があります。
まとめ
いかがでしたか? 今回は野点クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は野点クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。