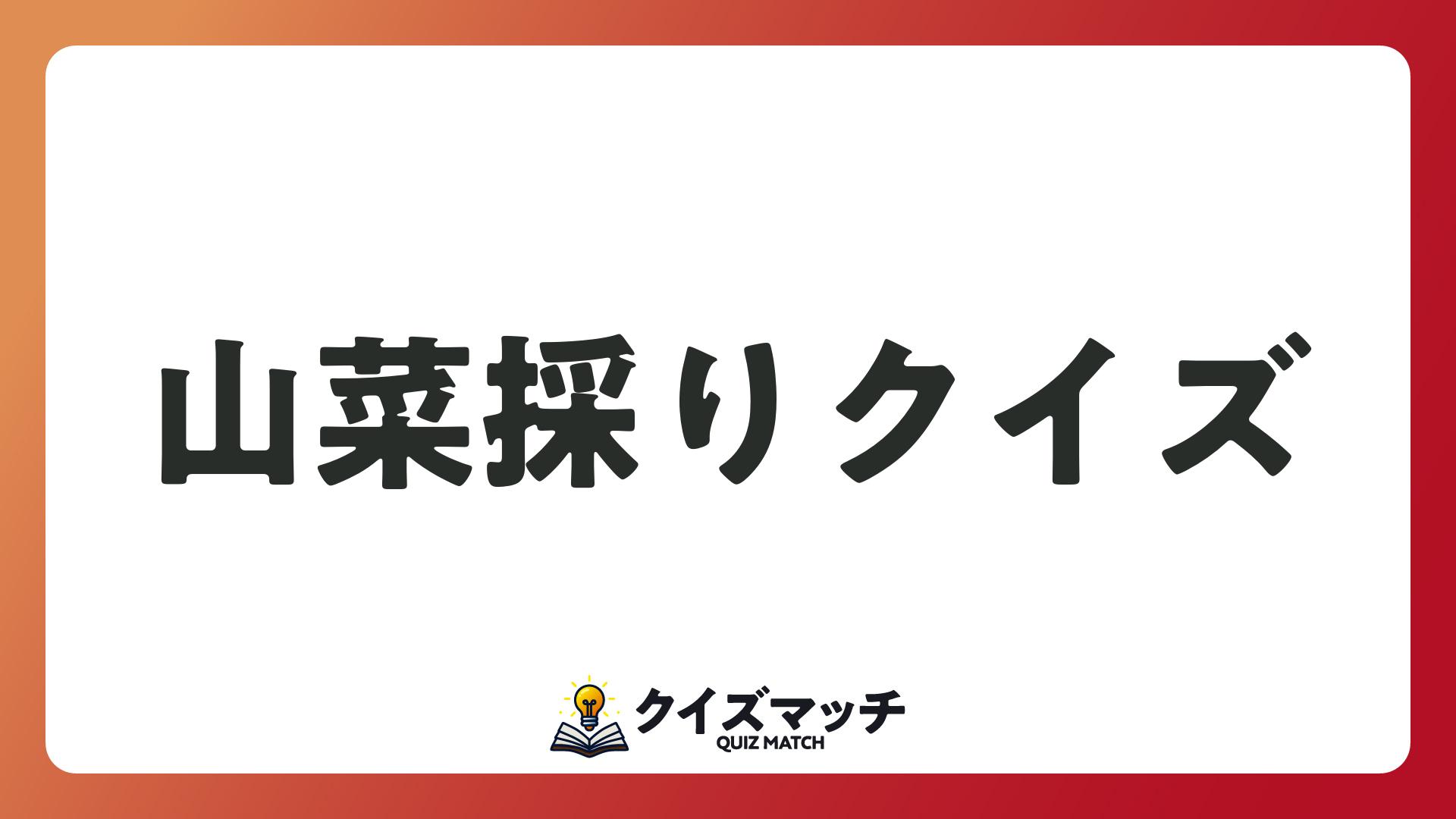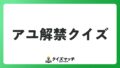春の山菜を楽しむ前に、まずは基本から学びましょう。山菜採りに欠かせない「山菜クイズ」を10問ご用意しました。タラノキの見分け方から、コシアブラの調理法、ゼンマイの保存方法まで、山菜の特徴や食べ方について、楽しみながら知識を深めていただけます。春の訪れを感じながら、自然の恵みを味わう山菜の世界を探検してみましょう。
Q1 : ウド(独活)の見分け方や特徴として正しいものはどれか?
ウドは春に地上に伸びる太い新芽で、独特の風味と香りがあり、主に若い茎や葉柄を食用とします。皮をむくと白っぽい内部が出ることが多く、根元からの太い茎を食べるのが一般的です。生食や和え物、天ぷら、炒め物などで利用されます。多年草であり、春の目的の旬の山菜として採取されることが多い点が特徴です。
Q2 : つくし(スギナの胞子茎)を調理する際の適切な手順として正しいものはどれか?
つくしはスギナの胞子茎で、袴(はかま)と呼ばれる鱗片状の部分は苦みやえぐみの原因になるため、調理前に取り除くのが一般的です。取り除いた後は下茹でをしてから和え物や炒め物、佃煮などに調理します。生ではえぐみが強く食感も硬いため、適切に下処理と加熱を行うことで美味しく食べられます。
Q3 : ミツバ(三つ葉)の分類と特徴として正しいものはどれか?
ミツバはセリ科の多年草で、葉が三つに分かれた三出複葉が特徴の香味野菜です。香りが良く、吸い物や和え物、薬味として利用されることが多く、春から秋にかけて採取・栽培されます。セリ科の植物らしく独特の香りを持ち、山菜として採る場合も若い葉や茎を使うのが一般的です。イネ科やシダ、球根性の植物ではありません。
Q4 : 山菜採りの適切な採取時期として一般的に正しいのはどれか?
多くの山菜は春先に地上に新芽や若葉を出し、その若い状態で最も柔らかく風味が良いため、葉が開く前後の春の時期に採取するのが一般的です。夏や秋では成長して硬くなるか風味が失われるものが多く、冬期に採るものは限られます。採取時には生育環境や保護の観点、適切な量と方法を守ることも重要です。
Q5 : タラノキ(タラの芽)の見分け方として正しいものはどれか?
タラノキの新芽(タラの芽)は春先の山菜として親しまれ、芽は枝先に複数つくことが多く、茎や枝に小さな棘や突起がある点が特徴です。葉は羽状に分かれた複葉で、芽のうちに採取して天ぷらなどで食べるのが一般的です。茎に刺があるため触れると痛いことがあり、見分けの手がかりになります。根元の球根を掘って食べるようなものではなく、葉が完全に展開した後は硬くなり風味が落ちるので若芽のうちに採るのが適切です。
Q6 : コシアブラの食べ方として一般的で最も適しているのはどれか?
コシアブラは春の山菜の代表で、柔らかい新芽や若葉に独特の香りとほのかな苦みがあります。最も一般的で風味を引き出す調理法は天ぷらで、衣をまとわせて揚げることで香りが立ち、苦みも和らぎます。もちろん軽く茹でて和え物やおひたしにすることも可能ですが、生でそのまま食べると苦味やえぐみが強い場合があり、煮くずれると風味が落ちるため天ぷらが特に好まれます。
Q7 : 「こごみ(クサソテツ類)」の特徴として正しいものはどれか?
こごみはシダ植物であるクサソテツやマルバベニシダなどの新芽(胞子葉の若い展開部)を指し、渦巻き状に丸まった「こごみ(fiddlehead)」の形が特徴です。春に地面から出てくる若い葉柄と葉の先端がくるくると巻いた状態を食用とし、弾力があり食感が良いことから和え物やおひたし、天ぷらなどに利用されます。シダの仲間なので葉や構造が被子植物とは異なります。
Q8 : ワラビを扱う際に注意すべき点として正しいものはどれか?
ワラビには天然に含まれる有害成分(ブラッシング系の物質やピラクロシド類など、長期摂取で問題となる可能性が指摘される成分)があり、伝統的に灰や重曹であく抜きや湯通しをしてから調理・摂取することが推奨されています。生食は避け、適切な下処理をすることで風味を保ちつつ安全に食べられます。大量に生で食べるなどの方法は健康リスクを高めるため避けるべきです。
Q9 : ゼンマイ(乾燥ゼンマイ)の扱いとして正しいものはどれか?
ゼンマイは山菜の一種で、採取後に乾燥させて保存することが一般的です。使用する際は乾燥ゼンマイを水や熱湯で戻し、ぬかや重曹を用いたアク抜きを併用することもあります。戻した後は煮物や和え物に使われ、独特の食感を楽しめます。生のまま刻んで食べることはなく、正しく戻して下処理したうえで調理するのが安全で美味しく食べるための基本です。
Q10 : フキ(蕗)の食用にする主な部位はどれか?
フキは春の山菜で、食用とされるのは主に葉柄にあたる茎の部分です。葉は大きく観賞用の側面もありますが、一般的に食べるのは茎の白っぽい部分で、きゃらぶきのように甘辛く煮たり、アク抜きをして和え物にしたりします。茎は繊維質があるため下処理(皮むきや下茹で)でえぐみや苦みを取り除いてから調理します。根茎や花序は通常食用になりません。
まとめ
いかがでしたか? 今回は山菜採りクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は山菜採りクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。