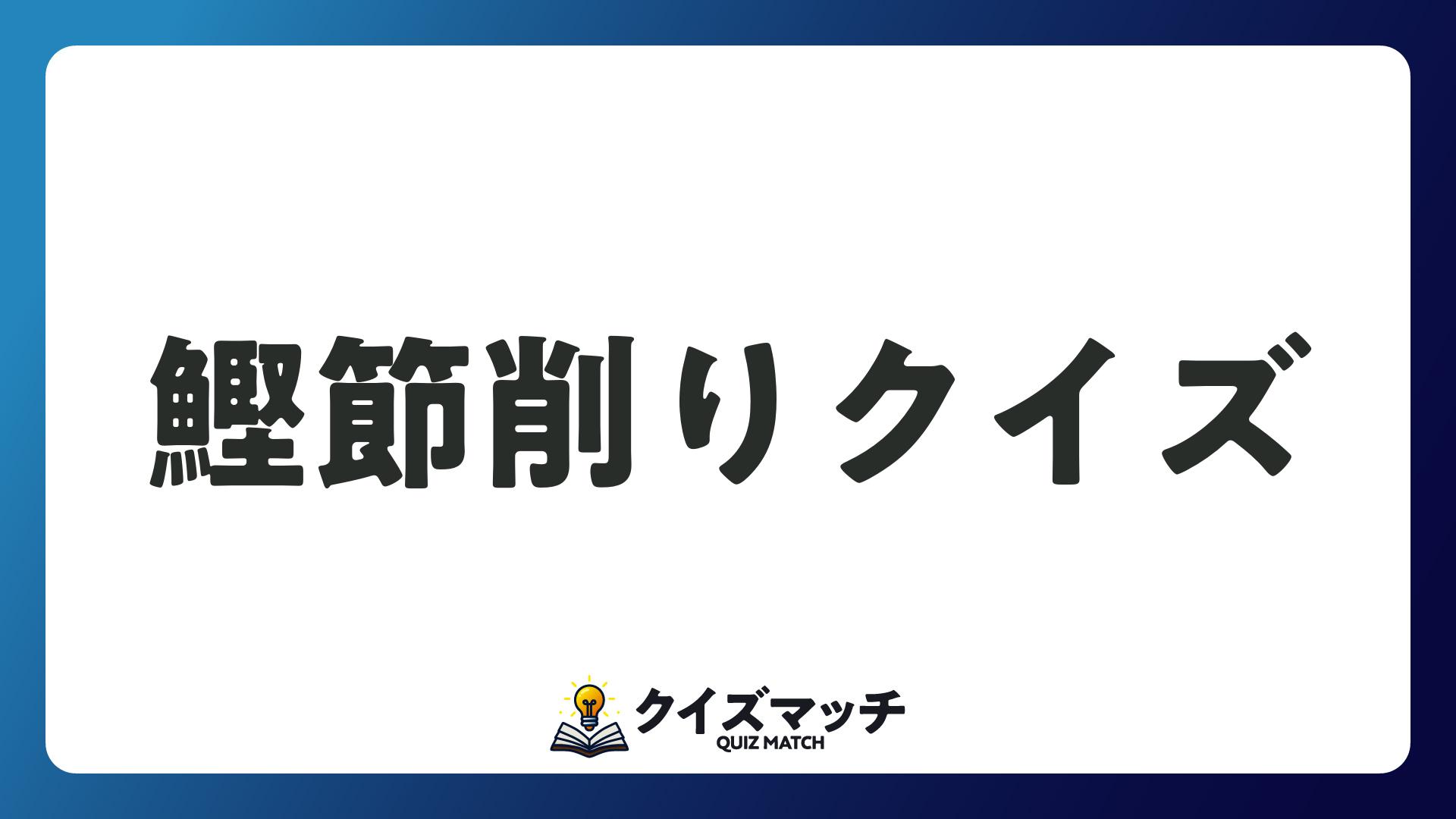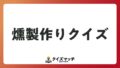鰹節削りクイズ:カツオの魅力を堪能しよう!
鰹節は和食の原点とも言える重要な食材です。その製造工程や特徴、活用方法には多くの知られざる魅力が隠されています。このクイズでは、鰹節の原料から保存方法、出汁の取り方まで、鰹節の魅力に迫ります。鰹節を愛する人も、これから鰹節の魅力に出会う人も、この10問のクイズを通じて、鰹節の奥深さを感じ取ってみてください。鰹節の新たな一面が見えてくるかもしれません。
Q1 : 鰹節を削る際に専用で使う伝統的な道具は次のうちどれか?
伝統的には木製の鰹節削り器(けずり器、削り器)を用いて鰹節の表面を薄く削り取ります。近年は電動の削り器もありますが、手動のけずり器は刃の角度や力加減で削りの厚さを調整しやすく、香り高い花かつおが得られます。
Q2 : 鰹節の削りの厚さと出汁の抽出時間について正しいのはどれか?
削り節は表面積が大きいほど短時間で成分が溶け出すため、薄く削れば短時間で旨味と香りが抽出されやすく、澄んだだしが取りやすくなります。厚めに削ると抽出に時間がかかる一方、濃厚な味になることもあります。用途に応じて削りの厚さを選びます。
Q3 : だしを取った後の鰹節の「だしがら」を有効活用する方法として適当なのはどれか?
だしがらは旨味成分や香りが一部残っているため、佃煮にして保存食にしたり、細かく刻んでふりかけや混ぜご飯の素にするなど二次利用が一般的です。栄養も残るため無駄が減り、風味のある調味素材として有効活用できます。
Q4 : 鰹節の原料となる魚は次のうちどれか?
鰹節は一般にカツオ(学名:Katsuwonus pelamis を含むカツオ類、通称「かつお」)から作られます。カツオの身を下ごしらえして煮て、天日乾燥や燻製、さらに熟成(枯らし)を施すことで硬い節状になり、削って出汁や薬味に用いられます。他の魚は別製品になります。
Q5 : 本枯れ節(ほんかれぶし)と荒節(あらぶし)の製法上の最も大きな違いは何か?
荒節は主に煮て乾燥・燻煙を繰り返したものであるのに対し、本枯れ節はさらに「カビ付け(枯らし)」という工程を行います。カビ(伝統的にはアスペルギルス属などの微生物)を付けて乾燥・除去を繰り返し旨味を増し、保存性と風味を高めて硬化させます。
Q6 : 鰹節の旨味成分で特に重要とされるものは次のうちどれか?
鰹節の主要な旨味成分はイノシン酸(イノシン酸塩)です。昆布のグルタミン酸と組み合わせると相乗効果で強い旨味を生み、和食のだしの基本である「昆布+鰹節」の組合せが成立します。イノシン酸は加熱や熟成で増えることも知られています。
Q7 : 削った鰹節(花かつおなど)を風味を保って保存する最も適切な方法はどれか?
削り節は湿気や高温、酸素で香りや旨味が劣化しやすいため、乾燥した状態を保つことが重要です。密閉容器に入れて冷暗所で保存すると酸化や吸湿を防げます。冷蔵は結露で湿る恐れがあるため、密閉状態での長期保管が望ましいです。
Q8 : 「花かつお」とは何を指すか?
花かつおは削り節を薄く削った状態のことで、かつお節を削った後に得られる薄い削り片を指します。だし用の厚めの削りや、だしを取った後の「だしがら」とは用途が異なり、かつお節の香りを楽しむトッピングやお好み焼き、冷奴の薬味などに用いられます。
Q9 : 「一番だし」として一般的に用いられる組み合わせはどれか?
一番だしは通常、昆布を水に浸して低温で旨味成分を引き出し、その後に鰹節を加えて短時間で旨味を抽出して漉す方法が一般的です。昆布のグルタミン酸と鰹節のイノシン酸の相乗効果により風味豊かなだしが取れます。
Q10 : 鰹節製造における「燻煙(くんえん)」工程の主な目的は何か?
燻煙工程は単に香り付けだけでなく、肉の乾燥を促進して水分を減らし、微生物の発育を抑えて保存性を高める役割があります。複数回の燻煙と乾燥を繰り返すことで、独特の香ばしさと長期保存可能な状態が作られます。
まとめ
いかがでしたか? 今回は鰹節削りクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は鰹節削りクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。