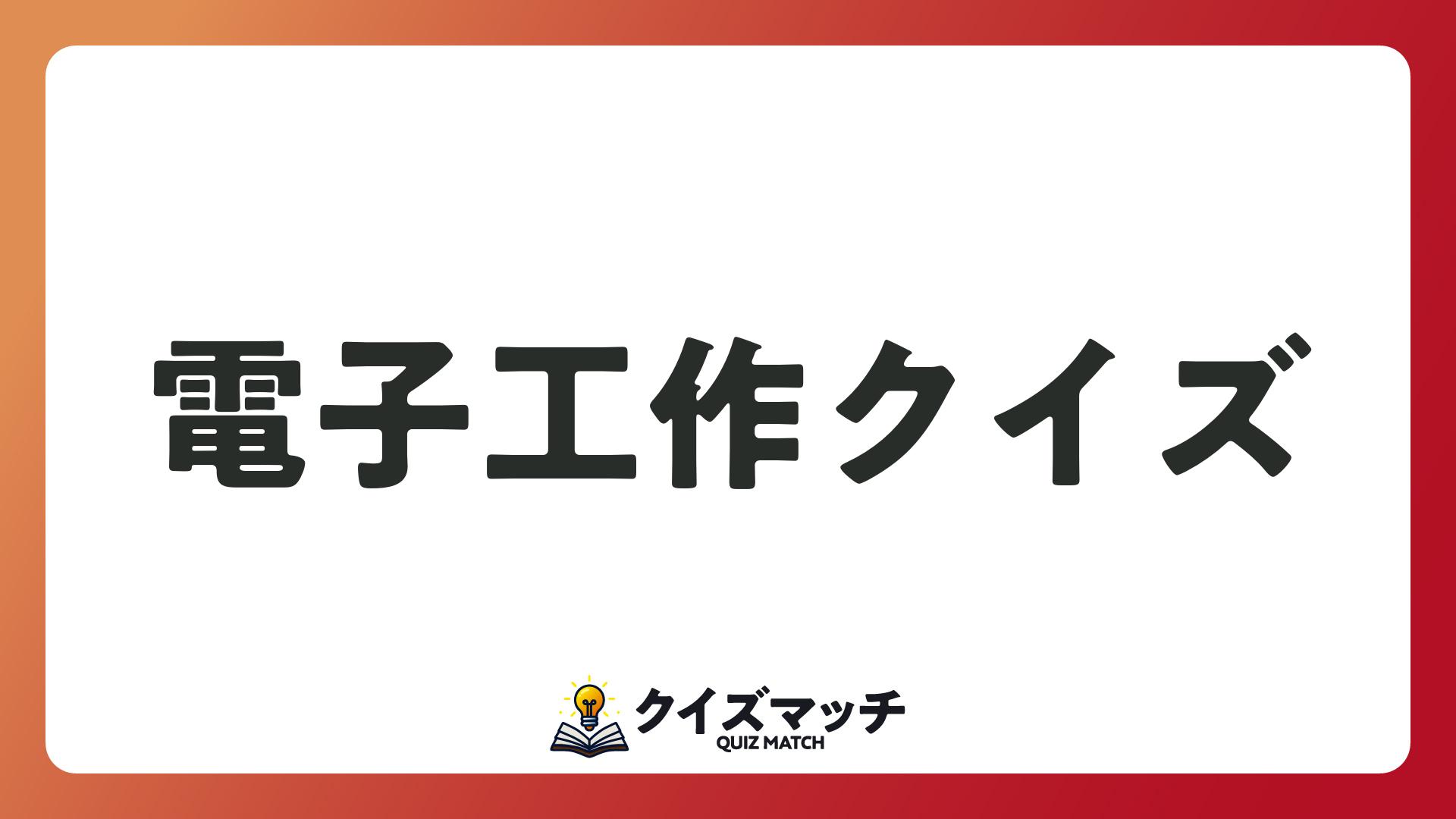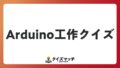電子工作の基礎から応用まで、全10問のクイズに挑戦してみましょう。コンデンサのESR、マイコンのADC、トランジスタの使い方、フィルタの設計など、電子回路の基本概念から応用技術まで幅広くカバーしています。電子工作の初心者から経験者まで、この機会にあなたの知識を試してみてください。正解率の高い方には特別な賞品もご用意しています。電子工作の楽しさと奥深さを感じていただければ幸いです。
Q1 : PWM(パルス幅変調)のデューティ比と平均電圧の関係として正しいのはどれか? 平均電圧はデューティ比に比例して供給電圧に掛けた値になる(Vavg = Vcc × デューティ比) デューティ比が変わっても平均電圧は常に一定である 平均電圧はPWM周波数にのみ依存する デューティ比が0%か100%の場合を除いて平均電圧は非線形に変化する
PWMでは高速にオン/オフを繰り返すことで平均電圧を制御します。理想的にはオン時間の割合(デューティ比)に供給電圧を掛けたものが平均電圧となり、Vavg = Vcc × Dutyで表されます。実際の負荷のインダクタンスやフィルタによって平滑されると直流成分として見えます。周波数が低く負荷が応答しきれない場合は振幅変動やトルク脈動などが出るため適切な周波数選定とフィルタが重要です。
Q2 : NPNトランジスタを低側スイッチ(GND側)として使う利点として最も適切なのはどれか? ゲート駆動が簡単で高電圧に直接接続できるため ベース駆動電位が基準(GND)に近く駆動が容易で、ハイサイドより回路が単純になるため 低側では温度特性が正規化されるため常に効率が高くなるため 低側スイッチではコレクタ−エミッタ間が逆方向になるため保護が不要になるため
NPNトランジスタやNチャネルMOSFETを低側(負荷とGNDの間)に配置すると、ベース(またはゲート)をGND基準で扱えるため駆動回路が単純になります。ハイサイドスイッチでは負荷側の電位に合わせて駆動電圧をブートストラップやレベルシフタで持ち上げる必要があることが多く、回路が複雑になります。低側利点は駆動が簡単な反面、負荷がGNDに常時接続されるため安全やノイズ対策は別途必要です。
Q3 : RCローパスフィルタの遮断周波数(3dB周波数)fcの式として正しいのはどれか? fc = 2πRC fc = R / (2πC) fc = 1 / (2πRC) fc = √(R/C)
単純な一次RCローパスフィルタ(抵抗とコンデンサの直列接続でコンデンサ側を出力としたもの)のカットオフ周波数はfc = 1/(2πRC)で表されます。この周波数で出力は入力に対して-3dBの減衰を示します。設計ではRとCの組合せで目標fcを決め、フィルタの位相遅れや実際の素子誤差(抵抗値許容、コンデンサの温度係数やESRなど)も考慮して選定します。
Q4 : UART(シリアル通信)とSPIの違いとして正しい組合せはどれか? UARTは同期式通信でクロック線が必要、SPIは非同期でスタートストップビットを持つ UARTは非同期通信でスタート/ストップビットを使いボーレートが設定される、SPIはマスター・スレーブ間でクロックを共有する同期通信である UARTはフルデュプレックス不可、SPIは常に1ビットずつしか送れない UARTはI2C互換、SPIはCAN互換である
UARTは非同期シリアル通信で、送信側と受信側が事前にボーレートを合わせることでクロック線を使わずデータを送受信します。データはスタートビットとストップビット、オプションのパリティを持ちます。一方SPIはクロック線(SCLK)をマスターが供給し、MOSI/MISO/SSなどの信号でデータを同期的に送る高速なバスです。用途と利点が異なるため用途に応じて選択します。
Q5 : ショットキーダイオード(Schottky diode)の主な利点はどれか? 逆方向耐圧が非常に高いこと 順方向電圧降下が小さく、高速スイッチング特性を持つこと 電流増幅率が高いこと 温度に対して全く特性変化しないこと
ショットキーダイオードの特徴は金属半導体接合による動作で、順方向電圧降下(フォワードVf)がシリコンダイオードより低く、スイッチング速度が速いことです。そのため整流損失が少ないことや、高周波スイッチング回路の回復特性に優れるためスイッチング電源の出力段や保護回路で多用されます。逆耐圧は一般的なシリコンダイオードほど高くない製品も多い点に注意が必要です。
Q6 : 次のうち極性(+/−)に注意が必要なコンデンサはどれか? セラミックコンデンサ(積層セラミック) 電解コンデンサ(アルミ電解、タンタル等) フィルムコンデンサ(ポリエステル等) ガラスコンデンサ
電解コンデンサ(アルミ電解やタンタルなど)は電極構造のため極性があり、逆接続や過電圧で破損や発熱、最悪の場合破裂や発火の危険があります。これに対し積層セラミックやフィルムコンデンサ、ガラスコンデンサは基本的に無極性(非極性)で両方向の電圧に耐えられるため極性を気にせず使えます。回路設計では直流バイアスや定常電圧、リプル等を考慮して適切な種類と定格を選ぶ必要があります。
Q7 : コンデンサのESR(等価直列抵抗)が意味するものは何か? 等価直列抵抗(内部で直列に存在する抵抗成分) コンデンサの導電率を示す値 交流電流に対する位相差を表す値 コンデンサの容量許容誤差
ESR(Equivalent Series Resistance)はコンデンサ内部に存在する直列の抵抗成分を表す値で、単位はオーム(Ω)です。ESRが大きいと高周波やリプル電流通過時に電力損失(発熱)が生じ、平滑性能が低下します。スイッチング電源や高周波回路では低ESRのコンデンサを選ぶことが重要で、電解コンデンサは一般にESRが高め、セラミックは低めです。また温度や周波数でESRは変化しますので設計時に注意が必要です。
Q8 : マイコンのADCで基準電圧(Vref)を変更すると何が起きるか? ADCの計測分解能のスケールが変わる(同じビット数でも入力電圧に対応する値が変わる) サンプリング周波数が自動的に上がる 入力インピーダンスが低下する A/D変換のビット数が変わる
ADCの出力はデジタル値であり、基準電圧Vrefに対する入力電圧の比で決まります。Vrefを小さくすると同じビット数でより小さい電圧変化を分解できるように見えますが、フルスケール電圧が下がるため入力レンジも狭くなります。サンプリング周波数や内部のビット数はVrefで変化せず、ノイズや入力ソースの精度、アンチエイリアスや参照の安定性が測定精度に影響します。
Q9 : マイコンの入力ピンにプルアップ抵抗やプルダウン抵抗を接続する主目的は何か? 入力ピンの保護のために電流制限するため 回路全体の消費電力を下げるため 未接続(フローティング)状態の入力を確定させるため 外部ノイズを完全に除去するため
プルアップ/プルダウン抵抗はスイッチなどが開いたときに入力ピンがフローティング(不定)にならないように、既知の論理レベルに引き上げる/引き下げるために使います。例えばプルアップは通常は高(Vcc)に引き、スイッチでGNDに接続すると明確なLOWとなります。抵抗値は大きすぎるとノイズに弱く、小さすぎるとスイッチ動作時に過剰に電流が流れ消費電力が増えるため設計バランスが必要です。
Q10 : オペアンプをコンパレータの代わりに使うことの問題点として適切なのはどれか? 消費電力が増えるだけで機能的問題はない オペアンプは必ず高速で安定した比較動作をする オペアンプは入力インピーダンスが低くて使いにくい 出力段や入力保護が比較器用途に最適化されておらず、飽和や遅延、ラッチアップ的な振る舞いを起こすことがある
汎用オペアンプは増幅用途を前提に設計されており、内部に位相補償や出力段の制約があるため、開ループで高速に順位を切り替える比較器用途では出力の飽和から回復する時間が長かったり、入力段が大きな差動信号に対して不安定になりやすいです。また一部のオペアンプは入力保護が比較器とは異なるため、入力差の急変で期待しない動作やラッチアップを起こす可能性があるため専用のコンパレータを使うのが望ましいです。