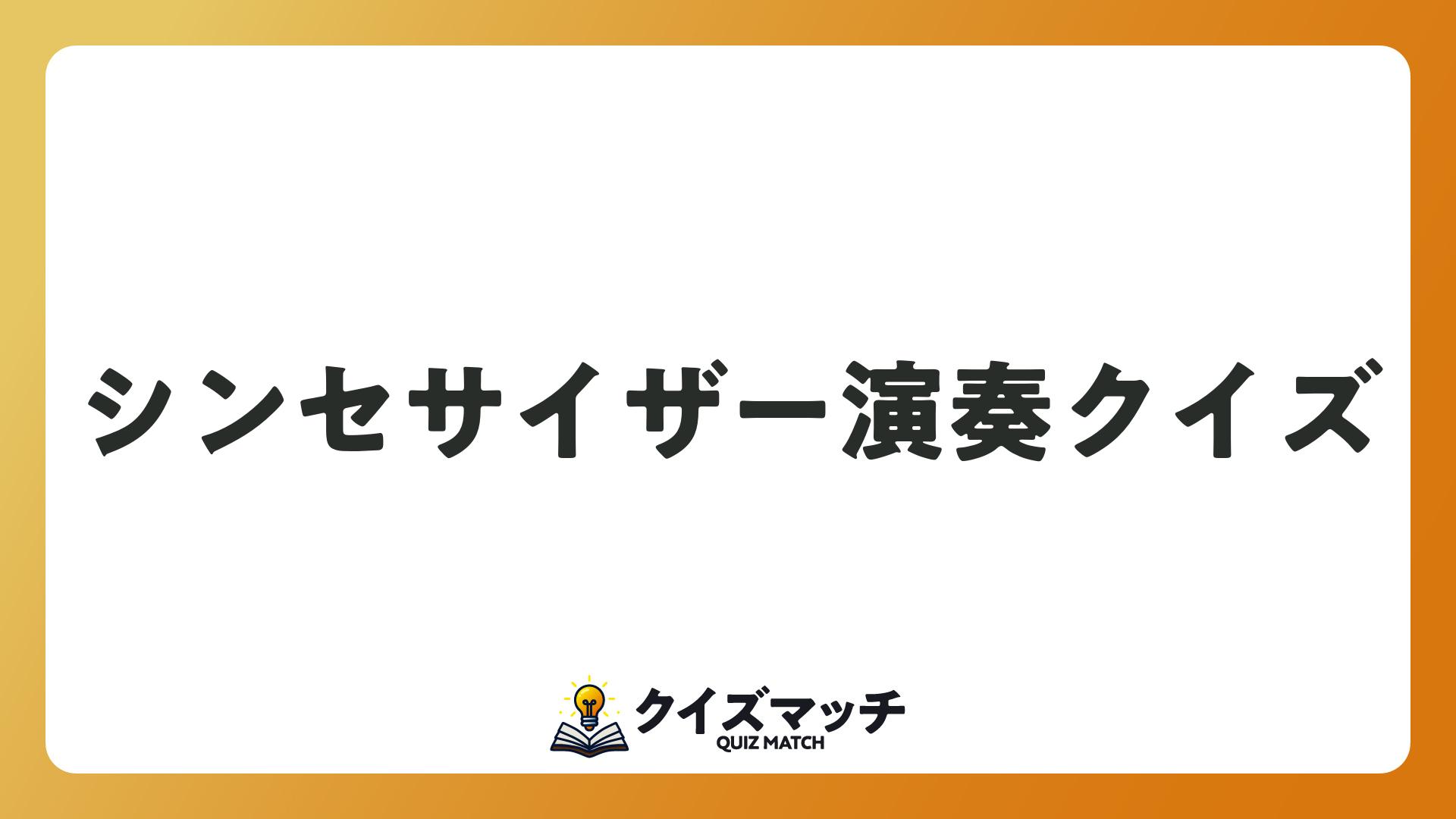次のリード文を提案します。
シンセサイザーの奥深い機能を探る10問のクイズ! シンセサイザーはアフタータッチやユニゾン、ポリフォニーなどさまざまな表現手段を備えており、それらの仕組みを理解することで音作りの幅が広がります。本記事では、シンセサイザーの基本的な動作原理から高度な機能まで、クイズ形式で楽しみながら学べる内容をお届けします。シンセ初心者からエキスパートまで、あなたのスキルアップに役立つ一冊となっています。
Q1 : シンセサイザーの“ポリフォニー(polyphony)”は次のどれを指すか?
ポリフォニーとはシンセが同時に発音できる声数、すなわち同時に鳴らせる音の最大数を指します。例えばポリフォニーが8なら同時に最大8音まで鳴らせます。これを超えるとボイススティーリング(古い音を切る)や音切れが発生することがあります。モノフォニック(1声)やパートに分けたマルチティンバーなどの概念と関連し、演奏表現やアレンジ設計、CPU/DSPリソース管理に影響します。
Q2 : モジュレーションホイール(mod wheel)に伝統的に割り当てられる表現はどれが多いか?
モジュレーションホイールは伝統的にビブラート(ピッチ揺れ)やフィルターやエフェクトのモジュレーション深度といった「表現的な揺れ」をリアルタイムで加えるために割り当てられてきました。多くのシンセはデフォルトでモジュレーションホイールをLFOの深さやビブラート量にマップしており、演奏中に徐々に変化させることでダイナミクスや表情を与えます。もちろんユーザーが任意のCCに再割り当てできる機種も多く、用途は柔軟です。
Q3 : ADSRエンベロープの 'R'(Release)が担う役割はどれか?
ADSRのR(リリース)はノートオフ後に音がどのくらいの時間をかけてゼロ(無音)に減衰するかを決定します。アタック(A)は立ち上がり速度、ディケイ(D)は最大到達後の減衰時間、サステイン(S)は鍵を押し続けている間の保持レベルを指します。リリースが短ければ音は即座に消え、長ければ余韻が長く残るため、パッドやストリングス系では長いリリースが好まれる傾向があります。
Q4 : “オシレーター・シンク(oscillator sync)”の一般的な説明として正しいのはどれか?
オシレーター・シンク、特にハードシンクはマスターオシレーターのサイクルごとにスレーブオシレーターを強制的にリセットし、スレーブの周波数が変化してもマスターの周期に同期した形で波形が切り替わるため、リッチで鋭い倍音や金属的なサウンドが得られます。スレーブを微妙にデチューンしたりマスターの周波数を変えることで独特のリズム的・倍音的変化が得られ、モジュレーションとの組み合わせで多彩な音作りが可能です。
Q5 : MIDIのコントロールチェンジ番号(CC)で“モジュレーションホイール”が通常割り当てられているのはどの番号か?
MIDI規格でモジュレーションホイールは通常CC番号1に割り当てられています。CC64はサステイン(ダンパー)ペダル、CC7はマスター/チャンネルボリューム、CC10はパンニングに使われるのが一般的です。機器やソフトによってはCCの割り当てを自由に変更可能ですが、デフォルトや互換性を考えるとCC1をモジュレーションホイール用として扱うのが慣例です。
Q6 : フィルターの“レゾナンス(共振)”つまみは何を操作するか?
フィルターのレゾナンス(Q)はカットオフ周波数付近の周波数成分を強調してピークを形成するパラメータです。レゾナンスを上げるとカットオフ周辺の倍音が目立ち、音が鋭く際立ったり“ピーキー”になったりします。極端に上げると自励発振を起こし、シンセによってはサイン波に近いトーンが生成されます。カットオフは周波数位置自体を決めるパラメータであり、レゾナンスはその周波数帯の増幅度を制御します。
Q7 : “ボイススティーリング(voice stealing)”とは何を意味するか?
ボイススティーリングはシンセのポリフォニー数を超えて新しいノートが発音されたときに、どの既存の声を切るかを決める挙動を指します。一般的な戦略には「最も古い声を切る」「最も弱い声を切る」「近接したピッチの声を切る」などがあり、これによりCPUやDSPリソースの制約内で演奏を続けられます。ボイススティーリングの動作は演奏感や音楽表現に影響するため、機種や設定で最適な方式を選ぶことが重要です。
Q8 : シンセサイザーの“アフタータッチ(aftertouch)”とは主に何を指すか?
アフタータッチは鍵盤を押し続けた際に発生する追加的な圧力情報で、シンセ内部やMIDI経由でモジュレーション深度・フィルター・ビブラートなどに割り当てて表現を付けるための制御信号です。注意点としてベロシティは鍵を押し下げた瞬間の強さを表す一回限りの値であり、アフタータッチは鍵を押し続ける間に変化し得る継続的な値である点で異なります。またアフタータッチにはチャンネル・アフタータッチ(全鍵で一つの値)とポリフォニック・アフタータッチ(鍵ごとに独立した値)があり、表現の細かさや割り当ての自由度が変わります。
Q9 : 減算法(サブトラクティブ)シンセシスにおいて、音色の倍音成分(和音成分)を最も直接的に形作る回路はどれか?
サブトラクティブ方式ではまずオシレーターがリッチな倍音を含む波形を生成し、次にVCF(フィルター)で不要な周波数成分を除去したり特定帯域を強調したりして音色を作ります。フィルターはカットオフ周波数やレゾナンスで音の明るさや鼻にかかったようなピークを制御し、それによって倍音構成が直接変化します。VCAは最終的な音量を制御し、LFOは周期的変調や揺れを与えるため機能は重要ですが、倍音そのものを最も直接的に形作るのはフィルターです。
Q10 : シンセの“ユニゾン(unison)”機能は何をするものか?
ユニゾンは一つの鍵に対して複数の発音(声)を同時に立ち上げ、各声を微妙にデチューン(ピッチをずらす)したり位相を変えたりして音に厚みや幅を持たせる機能です。多声を重ねることで単音でも和音的な広がりが得られ、リードやパッドでよく使われます。ユニゾン時には各声のボイス数やデチューン量、パンニングを調整できることが多く、モノ/ポリの挙動やCPU負荷に影響します。
まとめ
いかがでしたか? 今回はシンセサイザー演奏クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回はシンセサイザー演奏クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。