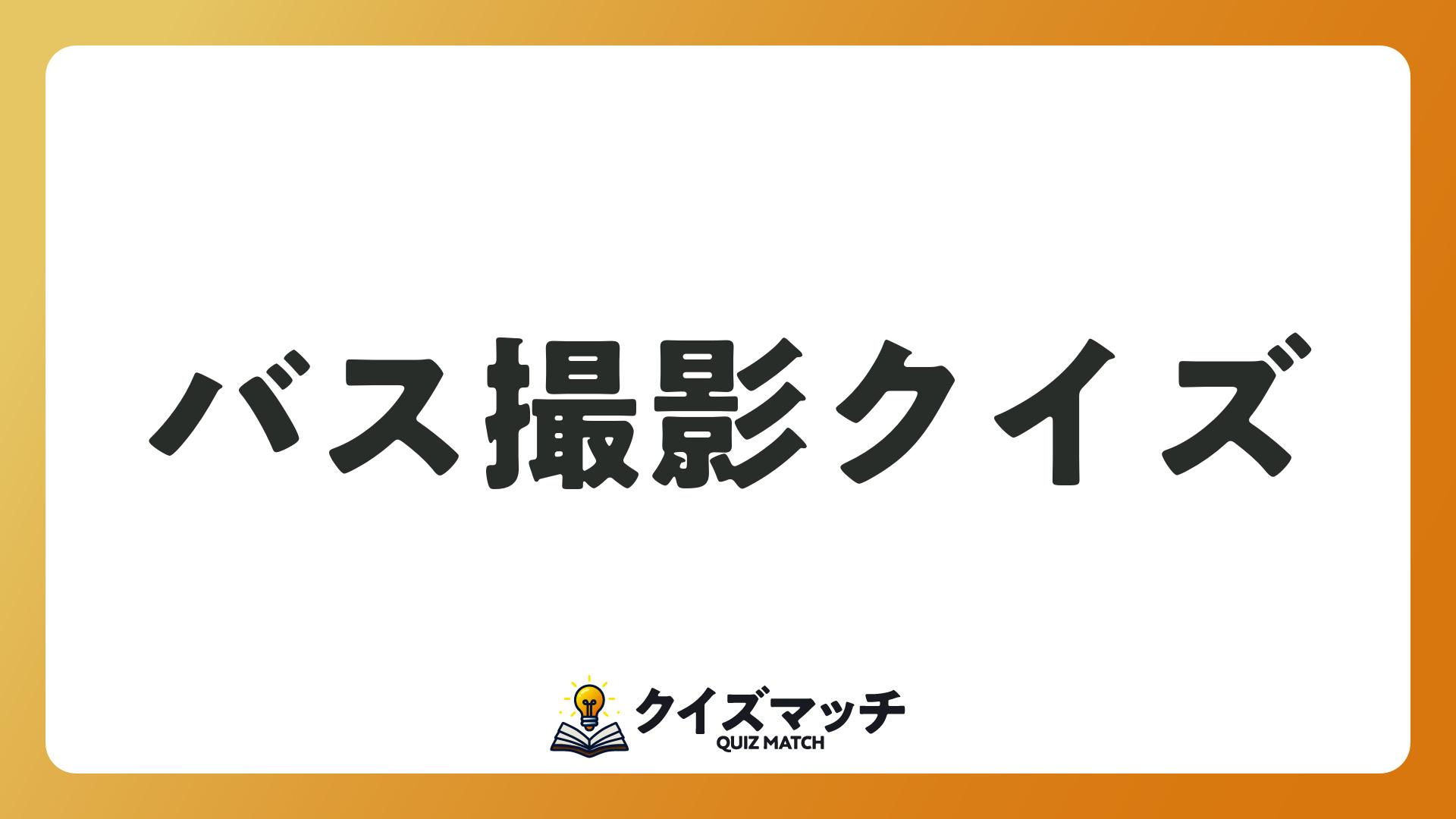バス撮影を楽しむ人のために。撮影のテクニックからマナーまで、必見のクイズに挑戦!
バスというダイナミックな被写体を捉えるには、さまざまなテクニックが必要です。シャッタースピードの設定、ナンバープレートの扱い方、望遠レンズの活用など、撮影にはコツがたくさん。そして何より、乗客やバス会社への配慮も忘れずに。次のクイズに答えて、バス撮影の奥深さを探ってみましょう。
Q1 : 「ノンステップバス(ノンステップ車)」とはどのようなバスを指すか?
ノンステップバスは乗降口から車内までの段差を無くし、床面を低くした設計のバスを指します。高齢者や車椅子利用者、ベビーカーを押す乗客に優しいバリアフリー仕様であり、スロープや車椅子固定装置を備えることもあります。都市部の路線バスで普及が進み、乗降時間の短縮や安全性向上にも寄与します。
Q2 : バス車内や停留所でフラッシュ撮影を行うことについての適切な対応はどれか?
フラッシュ撮影は強い光で運転手の視界を阻害したり他の乗客に不快感や安全上の問題を与える可能性があるため、公共交通機関内では原則控えるのがマナーです。どうしても必要な撮影は運転手や乗客、あるいはバス会社に事前に了解を取るべきです。地域や事業者によっては撮影ルールが定められている場合もあるため確認が必要です。
Q3 : 日本で営業用の大型バスに多く見られるナンバープレートの色はどれか?
日本国内では車両の用途によってナンバープレートの色が異なります。営業用の大型車両(路線バスや貸切バスなど)は商用車扱いとなり、緑地に白文字のナンバープレートが用いられるのが一般的です。これに対して乗用車の自家用は白地に緑文字、小型車や軽は黄色地に黒文字、といった分類があります。撮影時にナンバーの扱いに注意する場合もあります。
Q4 : 次のうち「エルガ(Erga)」を製造しているバスメーカーはどれか?
「エルガ(Erga)」は日本のいすゞ自動車(Isuzu)が製造する路線バスの代表的な車種名です。いすゞは長年にわたり商用車・バスのラインアップを持ち、エルガは都市型路線バスとして多くの事業者で採用されています。他の選択肢にある日野の「ブルーリボン」、三菱ふそうの「エアロスター」などと並んで、日本の主要路線バス車種の一つです。
Q5 : 「連節バス(アーティキュレーテッドバス)」の特徴として正しいものはどれか?
連節バス(アーティキュレーテッドバス)は車体が前後または複数に分かれ、それらを連結シャーシと可動の関節(アーティキュレーション)で繋いだ構造を指します。これにより車体長を大きくしつつ旋回性を確保し、一度に多くの乗客を輸送できる点が特徴です。選択肢の「電気駆動」は駆動方式であり連節の定義ではありません。
Q6 : 低床バス(ロー・フロアバス)の主な利点は何か?
低床バスは床面を低く設計して車内の段差を少なくした車両で、乗降口から車内までのステップが減るため高齢者、乳幼児連れ、車椅子利用者などの乗降がしやすくなります。ノンステップ構造やスロープの併用によりバリアフリー性が高く、市街地の路線バスで広く採用されています。座席数や高速適性、荷物室の有無は車種や用途によって異なります。
Q7 : 行き先表示に関して、幕式表示(ロールサイン)と比べたときのLED表示の主な利点はどれか?
LED表示は文字サイズや表示パターン、色や明るさをフレキシブルに変更できるため、行先や系統番号、注意表示などを即座に切り替えられる点が大きな利点です。夜間や悪天候でも視認性が良く、アニメーションや多言語表示も可能です。一方で幕式はレトロな雰囲気や簡便さがあるものの、表示の変更に物理的操作が必要で視認性が劣る場合があります。
Q8 : バスを撮影する際、公道での撮影は原則として可能だが、乗客の顔がはっきり写り識別できる場合の注意点として最も適切なのはどれか?
公道での風景や車両の撮影自体は原則として許容されますが、個人が識別できる状態で写っている場合は肖像権やプライバシーの問題が生じます。趣味での非商用利用でも配慮が必要であり、商用利用や肖像を強調する用途では本人の許諾が求められることが多いです。またバス事業者のロゴ利用や社内撮影は別途許諾が必要なことがあります。
Q9 : 望遠レンズを使ってバスを撮影することの表現上の主な利点はどれか?
望遠レンズは遠くの被写体を視覚的に近づける効果があり、背景との圧縮効果(遠景が引き寄せられ距離感が詰まる)により被写体が際立つ表現が可能です。バス撮影では停留所から離れた車両や走行中のバスを構図良く切り取ったり、背景を大きくぼかして被写体を強調するのに適しています。運用上は手ブレ対策や追焦点が重要です。
Q10 : バス撮影で被写体を横方向に流して背景をブレさせる「パンニング撮影」に適したシャッタースピードはどれか?
パンニング撮影は被写体を追いながらシャッターを切り、被写体を比較的止めて背景に流れを出す手法です。一般的に車速や撮影距離によりますが、1/30〜1/125秒程度が目安とされ、なかでも1/60秒は街中の走行バスの速度で手持ちでも扱いやすく被写体が適度に止まり背景が流れるためパンニングの入門〜中級者向けに適しています。安定した追従と連写、ブレ補正の併用が効果的です。
まとめ
いかがでしたか? 今回はバス撮影クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回はバス撮影クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。