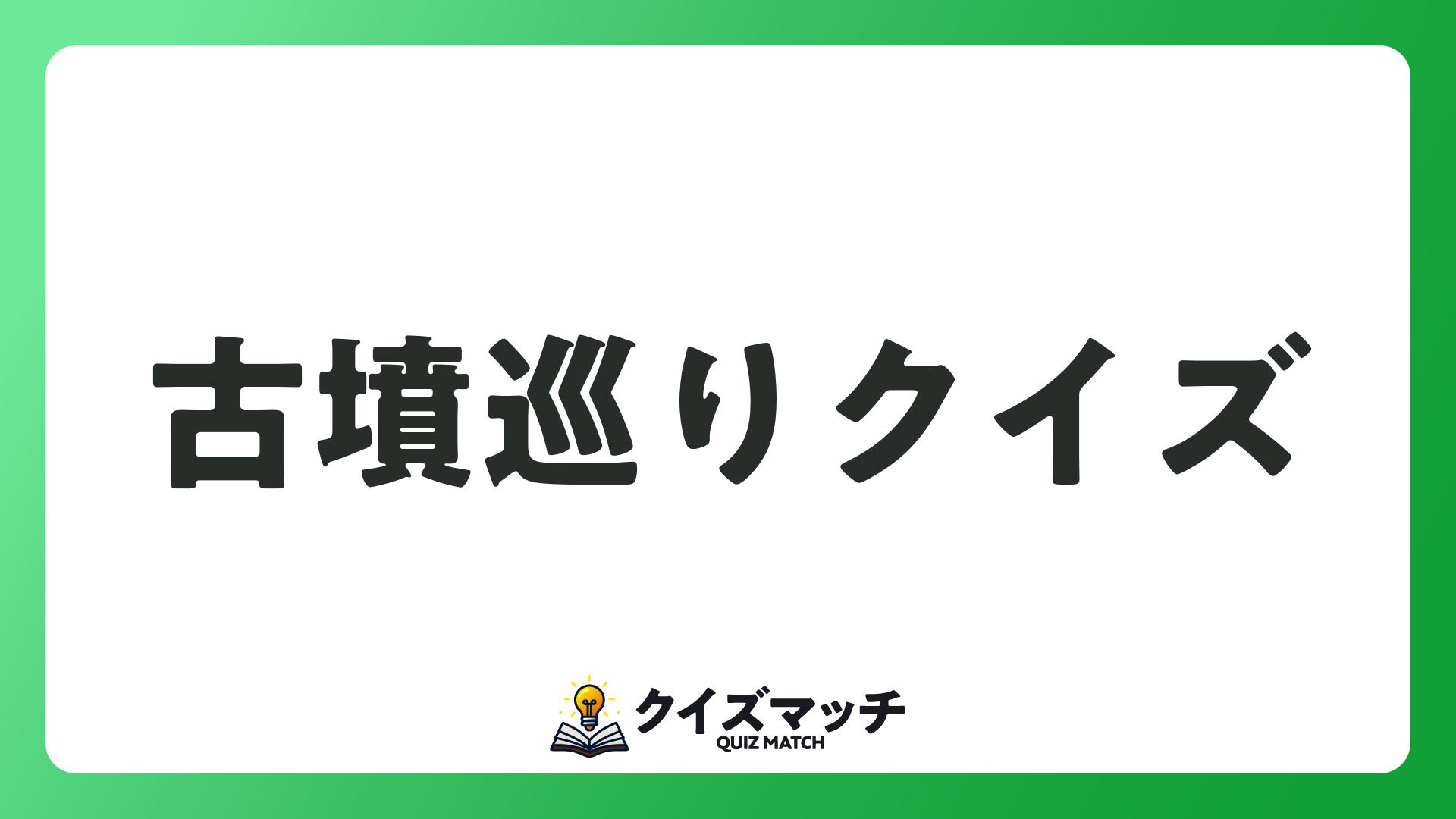古墳時代の巨大古墳や珍しい遺構、日本と海外の交流など、考古学の最新の成果が詰まった「古墳巡りクイズ」を10問ご用意しました。
日本の古代史を代表する遺跡群には、いまだ解明されていない謎が数多く残されています。古墳の構造や出土品、立地条件などから、当時の権力者の存在や社会構造、文化交流の実態に迫ります。
この機会に古墳時代の歴史と考古学的な知見について、楽しみながら学んでいただければ幸いです。
Q1 : 古墳から出土し、中国との交流を示すことが多い代表的遺物はどれか?
古墳から出土する遺物のうち、銅鏡は中国や朝鮮半島との交流・影響を示す代表的な品です。特に三角縁神獣鏡などの銅鏡は中国製または中国的影響を受けた製品で、権威の象徴や儀礼用途の副葬品として埋納されることが多く、古墳時代の外交関係や文化的交流を示す重要な手がかりとなります。鏡とともに鉄製品や馬具、漆器断片なども交流の痕跡を示します。
Q2 : 三角縁神獣鏡などの銅鏡が古墳に副葬される主な意義は何か?
三角縁神獣鏡を含む銅鏡が古墳に副葬される主な意義は、単に実用品ではなく権威や祭祀に関わる象徴的・儀礼的な役割にあります。鏡は古代中国で皇権や祭祀に結び付く重要な装飾品であり、それが日本列島に伝わると首長層の権威を示す副葬物として採用されました。鏡の文様や銘によって年代や交流関係を推定できるため、考古学的に重要な資料でもあります。
Q3 : 多くの前方後円墳では前方部はどの方角を向くことが多いか?
多くの前方後円墳では前方部が南向きである例が多いとされます。これは日照や祭祀上の方位、または周辺地形や河川・海岸との関係など複合的な理由が考えられ、南向きに配置することで前方部での儀礼を行いやすくした可能性があります。ただしすべてが南向きというわけではなく、地域差や築造時期による変化、地形に合わせた向きの違いも多く見られます。
Q4 : 大仙古墳(日本最大級の前方後円墳)は別名で何と呼ばれていることが多いか?
大仙古墳は一般に仁徳天皇陵と呼ばれることが多く、大阪府堺市に所在する巨大な前方後円墳です。宮内庁はこの古墳を仁徳天皇の陵墓に比定して管理していますが、考古学的には被葬者や築造年代について諸説があり、実際の被葬者は確定していません。それでも墳丘の大きさや周濠・葺石の存在、地域支配の象徴としての役割から、古墳時代のトップクラスの首長が葬られたと評価されています。}
Q5 : 前方後円墳はどの形をしているか?
前方後円墳は古墳時代に多く築かれた独特の形態で、前方部が方形、後円部が円形になっているため上から見ると鍵穴形に見えるのが特徴です。国内最大級の大型古墳にこの形式が多く、権力者の墳丘として築造されました。前方部は祭祀や儀礼に用いられたと考えられ、後円部に主体部や埋葬施設が置かれることが一般的です。地域差や時期による変化もあり、前期から後期にかけて形態や規模に変化が見られます。考古学的調査により、葺石や埴輪、周濠など前方後円墳特有の構成要素が確認されています。
Q6 : 日本で最も面積が大きい古墳はどれか?
日本で最大とされる古墳は大仙古墳で、通称は仁徳天皇陵とされることが多い大型前方後円墳です。全長は約486メートルとされ、墳丘と周濠を含む規模は国内最大級で、古墳時代中期から後期にかけての強大な首長の権力を示すものと考えられています。所在地は大阪府堺市にあり、宮内庁が管理する陵墓に指定されているため主体部の本格的な発掘調査は限定的ですが、周辺の遺物や構造から当時の墳墓築造技術や社会的階層のあり方が推定されています。
Q7 : 2019年にユネスコ世界文化遺産に登録された古墳群はどれか?
2019年にユネスコ世界遺産に登録されたのは「百舌鳥・古市古墳群」です。大阪府の百舌鳥古墳群と近接する古市古墳群の合わせて49基が登録対象となり、古墳時代の王権の発展や地域社会の形成を示す遺産として評価されました。これらの古墳群には大型前方後円墳や周濠、埴輪の遺構が残り、古墳築造技術や政治・宗教のあり方を示す重要な資料群です。登録にあたっては保存管理と調査の両立が課題となっています。
Q8 : 埴輪(はにわ)は主に何で作られているか?
埴輪は粘土(陶土)を成形して素焼きにした土製の像や円筒形の器材で、古墳の墳丘上や周辺に並べられたことが特徴です。円筒埴輪、家形埴輪、人物・動物形埴輪など多様な形態があり、墳丘の外縁や祭祀空間を示す標識・装飾・祭具の性格を持つと考えられています。材質が土であるため野外で風化しやすく、出土例から当時の服飾や習俗、建物形態を復元する手がかりになっています。
Q9 : 古墳時代は一般にいつ頃とされるか?
古墳時代は一般に3世紀頃のヤマト政権の成立過程から始まり、7世紀頃まで続く時期とされます。渡来系技術や大規模墳墓の出現、鉄器や馬具の普及、階層化した首長層の出現が特徴です。時期区分は前期・中期・後期に分けられ、前方後円墳の築造が盛んになったのは中期以降で、古墳時代の終わりは飛鳥時代の律令国家化とともに古墳の築造が減少していく流れであると考えられています。
Q10 : 石舞台古墳はどの都道府県にあるか?
石舞台古墳は奈良県明日香村に所在する代表的な古墳です。石舞台は大型の石材を積み上げて作られた石室が露出していることで知られ、古墳時代後期の石室構造を観察できる貴重な例です。被葬者については諸説ありますが、蘇我馬子やその一族に関連するとする説などが歴史・考古学で議論されてきました。周辺には飛鳥時代の寺院跡や古代の集落遺構も多く、考古学的に重要な地域です。
まとめ
いかがでしたか? 今回は古墳巡りクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は古墳巡りクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。