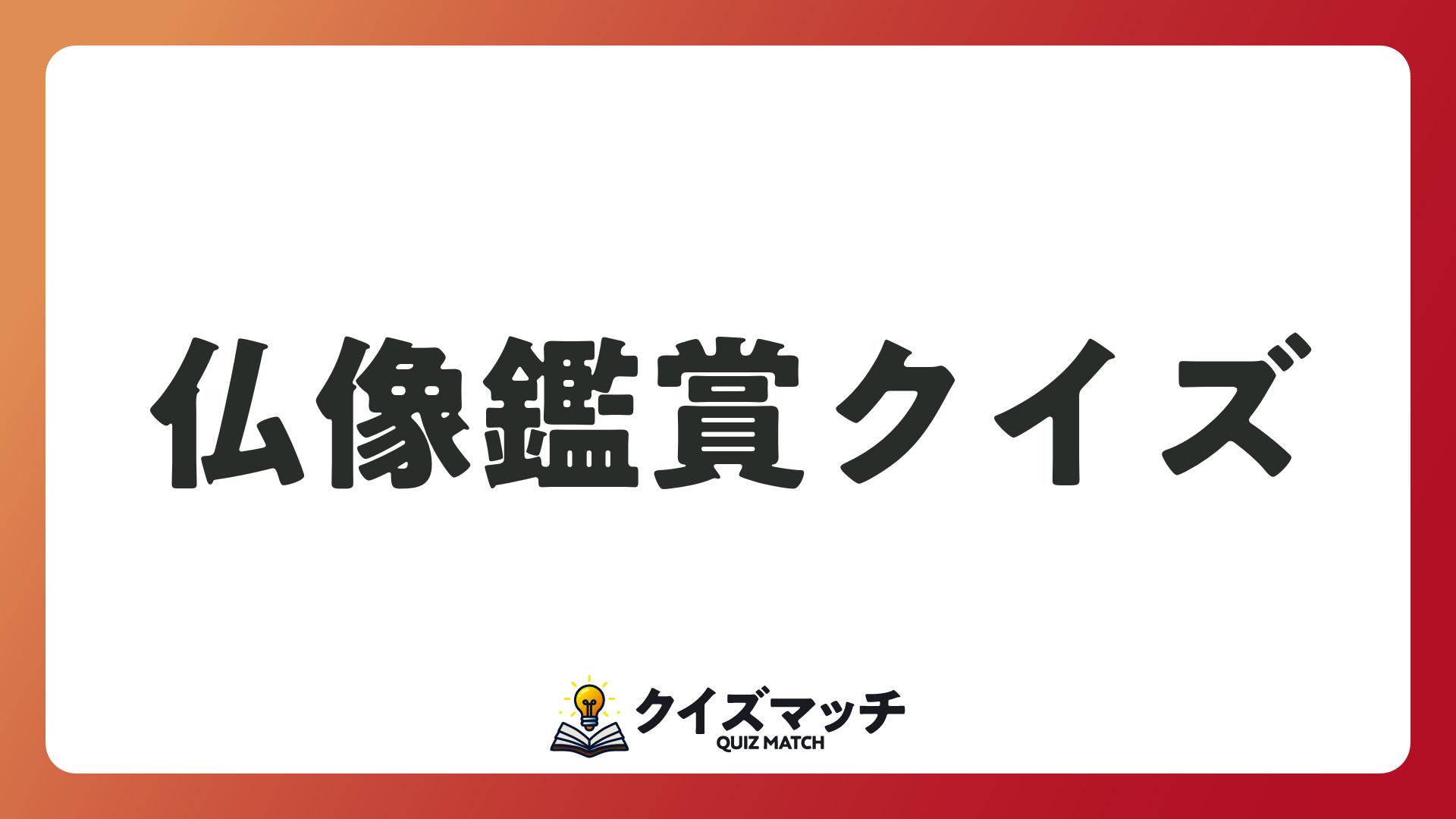仏像鑑賞クイズ – 知っているようで知らない仏教彫刻の世界
仏教の歴史と文化に造詣の深い読者の皆さん、ご来店ありがとうございます。今回は仏像鑑賞に欠かせない知識を深めるべく、10問のクイズをご用意しました。東大寺の大仏やインドに起源を持つ様々な仏像の造形と意味について、意外な事実やポイントをご紹介します。仏教芸術の奥深さを感じながら、ぜひ自分の仏像理解を確認してみてください。
Q1 : 東大寺の大仏が最初に開眼供養されたと伝えられる年は西暦何年か?
東大寺大仏の最初の大規模な開眼供養は西暦752年と伝えられています。聖武天皇の時代に国家鎮護と仏教振興のために盧舎那仏を建立し、多くの費用と技術を投入して鋳造が行われました。その後、火災や地震、修理のために補修や再鋳造が行われていますが、752年の開眼供養は奈良時代の国家的事業として仏教史上重要な出来事とされています。}
Q2 : ブッダが悟りを得た場面で地面を指して証拠とした印(手の形)は何と呼ばれるか?
触地印(しょくじいん)は、悟りを得た瞬間に仏が右手を下に伸ばして地面に触れるように示す印相で、ブッダが「地を証人とする」行為を表します。インド仏教の逸話に基づき、瞑想の末に魔障を退けるために地を指したとされ、その意味は悟りの正当性の主張と、地(大地)を証人にした救済の確認にあります。東アジアの仏像でも特に釈迦像にしばしば見られる重要な印相です。
Q3 : 薬師如来(薬師瑠璃光如来)が一般に手に持つ象徴的な物はどれか?
薬師如来が右手や左手に持つ象徴的な物は薬壺(やっこ、薬師用の薬の入った壺)です。薬師如来は病気を治し人々を救う仏として信仰され、薬壺はその具体的な働きである治癒と救済の象徴です。仏像表現では小さな壺を持つ姿が典型で、経典の薬師如来の誓願や医療的なシンボルとも関連づけられ、寺院の供養や祈願でも病気平癒の信仰対象になっています。
Q4 : 大きな木造仏像を複数の木材を継ぎ合わせて作る技法はどれか?
寄木造は複数の木材を継ぎ合わせ、部分ごとに彫って組み立てる技法で、大形仏像や複雑な造形を効率的に作るために用いられます。部材を接合して内側を空洞にすることで乾燥や収縮に強く、運搬や補修もしやすくなります。鎌倉時代の慶派(運慶・快慶など)をはじめ多くの木彫像で採用され、漆や金箔で仕上げることが多い点も特徴です。
Q5 : 法隆寺金堂の釈迦三尊像(釈迦如来と脇侍)は一般にどの時代の作とされるか?
法隆寺金堂の釈迦三尊像は飛鳥時代(7世紀頃)の代表作とされ、鞍作止利(止利仏師、一般に鞍作止利=止利)と伝えられる作例のひとつです。飛鳥時代はインド・朝鮮・中国の影響を受けつつ独自の造形が形成された時期で、金銅仏や木彫において写実と簡潔さが併存します。法隆寺の金堂像は日本における仏像史の起点の一つとされ、当時の技術と朝鮮半島や中国大陸との交流を示す重要な遺例です。
Q6 : 鎌倉時代の慶派(運慶・快慶・湛慶など)の彫刻に見られる特色はどれか?
鎌倉時代の慶派の彫刻は写実性と力量のある造形で知られ、人体の筋肉や衣文(衣のしわ)を力強く表現することが特色です。運慶・快慶らは写実的な表現で躍動感や表情の豊かさを追求し、寄木造や截金・彩色を組み合わせた大作を残しました。武士社会の需要と宗教的熱意が結びつき、説話の劇的表現や個性豊かな顔立ちが際立つ点も評価されています。
Q7 : 仏像の頭部に見られる「螺髪(らほつ)」とは通常何を指すか?
螺髪(らほつ)は仏像の頭部に表される渦巻状の髪の表現で、釈迦像など如来の頭部に特徴的に見られます。インドの伝統から受け継がれ、螺髪は悟りを得た存在としての特別性を示す身体的標識(相好)とされています。しばしば頭頂には肉髻(にっけい、頭の突起)を伴い、螺髪とともに仏の威厳や超越性を視覚的に伝える役割を持ちます。
Q8 : 仏像が蓮華座(蓮の台座)に座していることが象徴する意味はどれか?
蓮華座(蓮の台座)は泥の中に生じながら汚れに染まらない蓮の性質に基づき、清浄や悟り、煩悩からの離脱を象徴します。仏や菩薩が泥濘の世に在りながらも清らかであるという教理を視覚化したもので、浄土思想や清浄性の象徴として広く用いられます。蓮は仏教美術で非常に重要なモチーフであり、台座や光背と合わせて仏の聖性を強調します。
Q9 : 仏像の後方に取り付けられる「光背(こうはい)」は一般に何を表現しているか?
光背(光輪・光背)は仏像の背後に付けられる光の表現で、仏や菩薩の聖性、悟りの輝き、浄化された存在であることを象徴します。丸い光輪や業相円、あるいは全身を覆う火炎光背(光炎)や光背の文様は、視覚的にその対象が超越的な存在であると示す手段です。造形上は金箔や截金、彫刻で表現され、像の威厳や宗教的意味を強調します。
Q10 : 東大寺の大仏(盧舎那仏)は本来どの如来を表しているか?
東大寺の本尊である大仏は盧舎那仏(ルシャナ、梵語でVairocana)を表します。盧舎那仏は大日如来に近い宇宙的な仏で、奈良時代の国家仏教の中心的な位置を占めました。東大寺大仏は奈良時代の752年に開眼供養が行われたと伝えられ、当初の金銅像はその後の造営・修復を経ていますが、奈良時代の国家的な仏教信仰と彫刻技術を象徴する存在です。鋳造技術や大規模な建立事業の歴史的意義も大きく、日本仏教史上で重要な位置を占めます。
まとめ
いかがでしたか? 今回は仏像鑑賞クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は仏像鑑賞クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。