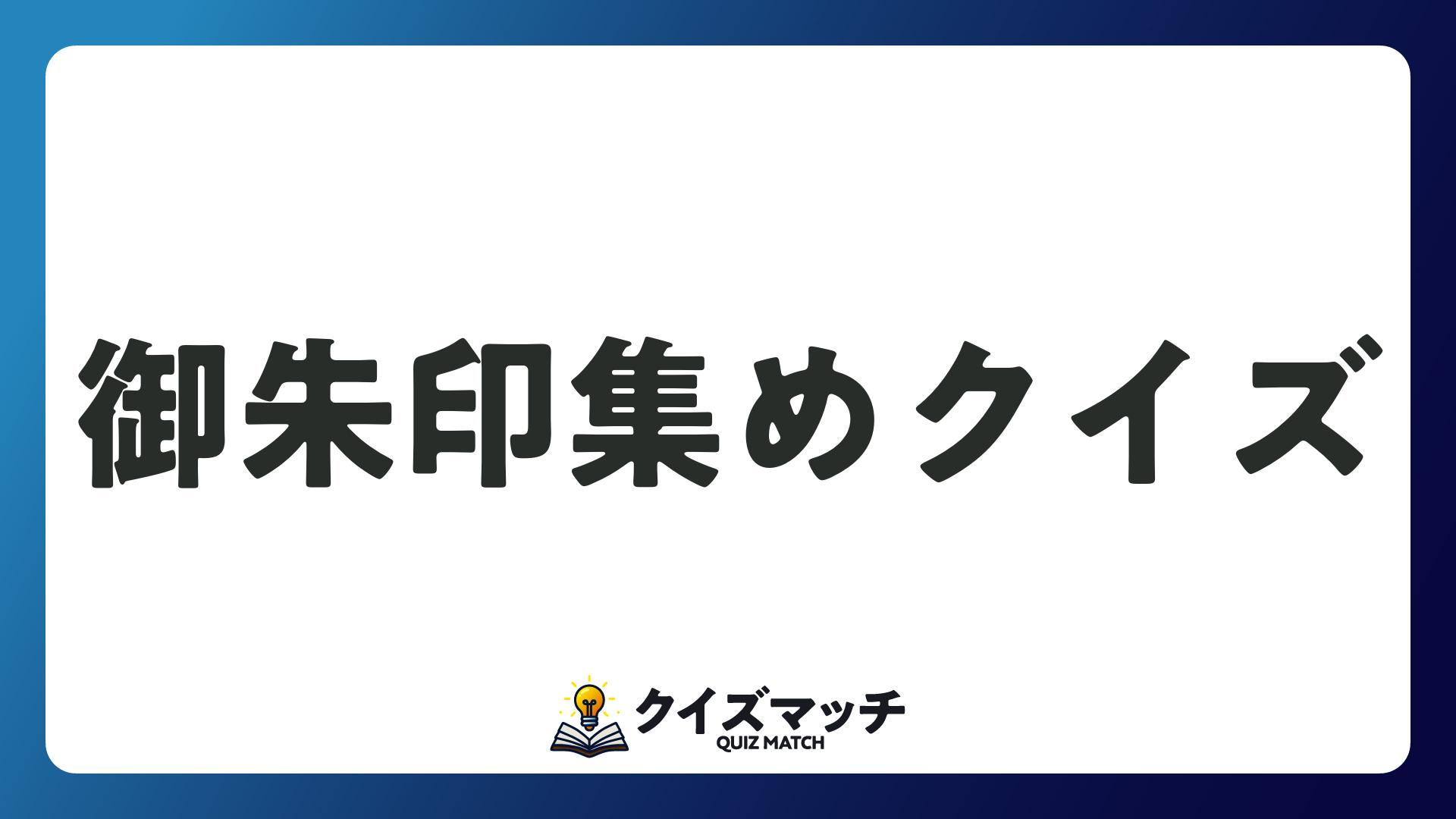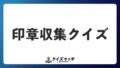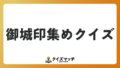御朱印は参拝の記念や信仰のしるしとして親しまれていますが、その起源は主に写経や経文の納入に対する受領印「納経印」にあります。参拝者が寺社を巡る中で納経帳に押印されるこの習慣が、次第に現在の御朱印の形式へと発展してきました。
御朱印を受ける際は、まず社寺で参拝を行ってから依頼するのが一般的なマナーです。神社と寺院の御朱印には、表現や文言の違いがあることにも注意が必要です。金額は概ね300〜500円程度の志納が多いですが、事前確認が重要です。
御朱印帳は神社・寺院共通で使える一般的な帳面ですが、巡礼で使う「納経帳」とは用途が異なります。また、押印方式も手書き以外の対応がある社寺もあることを知っておくと良いでしょう。
Q1 : 御朱印に記される日付は通常何を示すか?
御朱印に記載される日付は、一般的にその御朱印を受けた「参拝日」を示します。参拝の記念としていつ訪れたかを残すことが目的の一つであるため、訪問した日を墨書きで記入するか、日付印を押すのが通常です。寺社によっては日付を入れない場合や、書式が異なる場合もありますが、記録としての役割から参拝日を記すのが広く行われています。
Q2 : 御朱印を第三者に転売することについての考え方として最も適切なのはどれか?
御朱印は参拝の証や個人的な信仰の記録としての性格が強いため、第三者に転売する行為は一般的にマナー違反とみなされます。寺社側の意図や宗教的な意味合いを尊重する観点から、受けた御朱印を私的に保存し、転売や商用利用を避けるのが望ましいとされています。法的に必ず罰せられるという一般的な規定はありませんが、多くの寺社や参拝者の倫理観から転売は非推奨です。
Q3 : 御朱印を受ける際の一般的なマナーとして最も適切なのはどれか?
御朱印を受ける際の基本的なマナーとして、まず社寺で参拝を行ってから御朱印をお願いするのが一般的です。御朱印は参拝の証や記念とされるため、先に参拝の礼を尽くすことが礼儀とされています。もちろん各社寺により対応は異なりますが、先に御朱印を求めるよりも、一旦拝殿・本堂で参拝し、心構えを整えてから御朱印を依頼するのが望ましいです。
Q4 : 神社と寺院の御朱印に関して正しい説明はどれか?
神社と寺院の御朱印はともに朱印(印章)と墨書きが組み合わされることが多いですが、表現や文言には傾向の違いがあります。特に神社の御朱印では「奉拝」「参拝」など参拝行為を示す墨書きが入ることが多く、社名や祭神名、参拝日が書かれる場合もあります。寺院の御朱印は本尊名や宗派の題目、梵字などが墨書きされる傾向があります。ただし様式は社寺ごとに多様で一定ではありません。
Q5 : 一般的に多くの寺社で御朱印の受領に対して徴収される金額の目安として最も適当なのはどれか?
多くの寺社では御朱印を受ける際に志納(いわゆる初穂料)を受け取るのが一般的で、その相場はおおむね300〜500円程度であることが多いです。地域や社寺の規模、特別御朱印かどうかによっては金額が異なる場合がありますが、極端に高額であることは稀です。無料配布の例や、特別な限定御朱印で高額設定がある場合もあるため、事前に公式情報を確認するのが確実です。
Q6 : 「御朱印帳」と「納経帳」の使い分けに関する説明として最も適切なのはどれか?
御朱印帳は神社・寺院いずれでも御朱印を受けるための一般的な帳面として広く使われます。一方で「納経帳」は特に巡礼で用いられることが多く、写経や納経の受領を記録する伝統的な帳面を指すことが多いです。例えば四国八十八箇所の巡礼では納経帳(納経帳とも表記)に納経(納経印や書写)を受けて巡拝の記録とします。用途は重なる場合もありますが、巡礼専用の形式や仕様があることが違いです。
Q7 : 御朱印の現状に関する次の説明で最も事実に合っているのはどれか?
現在多くの寺社で、墨書きと朱印印章を組み合わせた手書きの御朱印が標準的ですが、授与数が非常に多い社寺や人手不足、コロナ禍の対応などの事情により、事前に用意した印刷物や直貼りシールで対応する事例も見られます。ただし、公式に「すべて印刷で良い」といった統一ルールがあるわけではなく、各社寺の判断で授与方法が変わる点に留意が必要です。
Q8 : 御朱印帳を扱う際のマナーとして正しいものはどれか?
御朱印帳は参拝の記録であり、宗教的・個人的な意味合いを持つものとして扱われます。そのため、地面に置いたりぞんざいに扱ったりするのは避け、清潔で敬意を払った扱いが望まれます。参拝時や御朱印受領時には袖や台の上などに置き、受け取ったら丁寧に保管するのがマナーです。他人に見せる際も相手の意向を考え、無遠慮に貸すのは控えるのが良いでしょう。
Q9 : 「朱印(しゅいん)」という語の意味として最も適切なのはどれか?
「朱印」という語はもともと朱(赤色)の印章やその印影を指します。御朱印はこの朱印(印章)と、それに添えられる墨書き(社名・寺名や参拝日、題目など)を組み合わせたものとして提供されることが一般的です。朱の印は古来、公的な押印や印章の色として用いられてきたため、現在でも朱色の印が重要な要素となっています。
Q10 : 御朱印の起源として最も近い説明はどれか?
御朱印は現在では寺社参拝の記念や信仰のしるしとして知られていますが、その起源は主に納経(写経や経文を納めること)に対する受領印、いわゆる「納経印」にあります。参詣者が写経を納めたり、巡礼で寺院を巡った際に、納経帳に押印・記帳を受ける習慣があり、これが次第に現在の御朱印の形式(墨書と朱印の組合せ)へと発展しました。近年は参拝記念として幅広く親しまれていますが、根底には経典納入や信仰の証としての歴史的背景がある点が重要です。
まとめ
いかがでしたか? 今回は御朱印集めクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は御朱印集めクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。