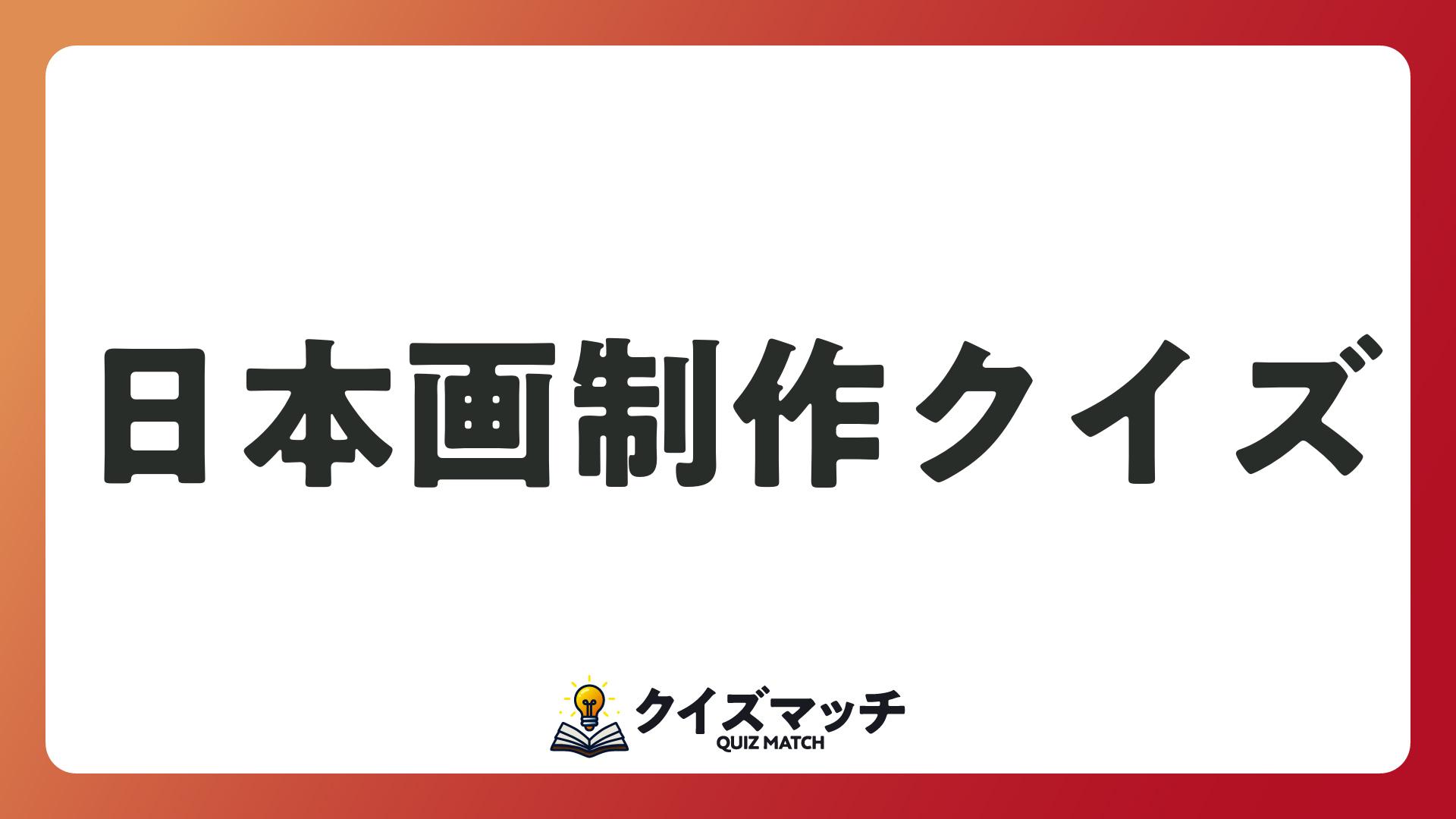日本画の魅力を堪能できるクイズにチャレンジ!
古来より根付く伝統的な日本画の技法や材料について、10問のクイズを用意しました。岩絵具の成分や膠の役割、裏彩色や箔押しなど、日本画ならではの表現手法を問います。絵画史の知識を深めるとともに、日本文化の奥深さを感じ取ってみてください。材料や道具の名称など、意外な答えにも注目です。日本画の魅力を再発見する良い機会になれば幸いです。
Q1 : にじみ止めや表面強化のため和紙に施す「ドーサ引き」に用いる液体の名称はどれか。
ドーサ液は膠水に焼明礬を溶かして作る媒剤で、和紙に薄く塗布するとアルミニウムイオンが繊維を収斂させ、絵具のにじみを抑えるとともに紙表面を適度に硬化させる。紙漉きの段階で混入する場合もあるが、制作前に自ら刷毛で引くことで吸水性を調整できる。胡粉や黄土は顔料であり、精油ワニスは油彩画用の保護層なので、にじみ止め剤としては機能しない。
Q2 : 岡倉天心とともに日本美術院を創設し、近代日本画の革新を推進した画家は誰か。
横山大観は1898年、岡倉天心と共に同志の菱田春草らを率いて日本美術院を設立し、伝統的水墨と西洋的空間表現を融合させた朦朧体など新様式を実験した。明治の廃仏毀釈や洋風化で衰退しかけた日本画を近代的芸術として再生させた功績は大きく、昭和に文化勲章を受章している。菱田春草や下村観山も美術院同人だが、組織運営の中心人物は大観であり、京都派の竹内栖鳳は直接関わっていない。
Q3 : 深い青色を得るため、ラピスラズリを砕いて作られる岩絵具の名称はどれか。
群青は古くは天然ウルトラマリンとも呼ばれ、アフガニスタン産ラピスラズリを粉砕・水簸し、比重分離によって純度を高めた高価な顔料である。奈良正倉院の宝物や伊藤若冲の作品にも使われ、日本画では澄んだ空や水面を象徴的に表す重要な色材となる。朱砂は硫化水銀の赤、岩黄はリモナイト系の黄色、緑青は孔雀石由来の緑で、いずれも色相が異なるため誤答となる。
Q4 : 日本画で極細の線描や人物のまつ毛を描く際に用いられる筆の名称はどれか。
面相筆は狸やイタチなどの細く弾力ある毛を芯に持ち、穂先が針のように尖ることで精密な線が引ける小筆の総称で、人物の面相描写に重宝される。穂の太さや毛質の違いで極細から中細まで多種類があり、墨線だけでなく彩色や金泥線にも対応する。渡辺筆は特定メーカー名、蒔絵筆は漆芸用、焼き筆は焦がし加工用であり、日本画の線描専用筆として一般的なのは面相筆である。
Q5 : 岩絵具の主原料として最も一般的に用いられるものはどれか。
岩絵具は、岩や鉱物を粉砕して粒度ごとに水簸分級したものを膠で溶いて用いる絵具で、古来から日本画の代表的な色材である。群青ならラピスラズリ、緑青なら孔雀石など、発色の要となるのは天然鉱石そのものに含まれる金属成分であり、人工的な合成顔料や貝殻由来の胡粉とは明確に区別される。石炭は顔料にはならず、合成樹脂も日本画の伝統的膠の代替とはされないため、不正解となる。
Q6 : 日本画で用いられる「膠」の主な役割は何か。
膠は動物の皮や骨を煮て抽出したゼラチン質で、水で溶かして絵具に混ぜたり下地に引いたりすることで、粉状の岩絵具粒子を支持体にしっかり固着させる働きを担う。日本画では顔料と膠水の比率調整により色の濃淡や表面のマット感をコントロールするため、いわば絵具と紙の橋渡し役である。防腐や光沢付与の機能は副次的で、発色そのものを化学的に変える成分でもない点が重要となる。
Q7 : 絹本作品で用いられる「裏彩色」とはどのような技法か。
絹本は繊維間に隙間があり、表からの彩色では色が浮きやすい。裏彩色は完成後に作品を裏返し、絹の裏面から淡い色を差して透過光を利用しながら全体の調子を整える高度な手法である。これにより絹特有の透明感を保ちつつ陰影やにじみを穏やかに制御できる。裏打ち紙で補強する工程や箔押しの下地とは別工程で、表面を削る技術とも異なるため選択肢3のみが正しい。
Q8 : 雲母を用いた装飾表現で活躍する「雲母刷毛」の目的として正しいものはどれか。
雲母刷毛は雲母粉を膠水に溶いたものを広い面に均一に引くための幅広刷毛で、乾燥後は淡く銀白色にきらめく地紋が現れる。光の角度によってのみ柄が浮かび上がるため、屏風や掛軸の下地に格調高い隠し模様を作る際に欠かせない道具である。線描用の細筆や胡粉の盛り上げ、岩絵具の磨きとは機能が全く異なるため、装飾的光沢を与える4が唯一正解となる。
Q9 : 水張りや洗いによる再制作に耐える強靱さから日本画で多用される紙はどれか。
雲肌麻紙は麻繊維を主体とした手漉き和紙で、紙肌が細かく雲のような微妙な凹凸を持つことから名付けられた。繊維が長く密に絡み合うため強度と耐水性に優れ、水張りによる伸縮や乾いた後の再度の濡らしにも紙が破れにくい。日本画ではたらし込みや洗い出しなど水分の多い技法を行っても寸法変化が少なく、色材の吸い込みも安定している点が評価される。他の紙種は書道向けや量産印刷向けであり、同等の耐久性は得にくい。
Q10 : 金箔を画面に貼る「箔押し」で、箔を支持体に定着させるために一般的に使われる接着剤は何か。
日本画の箔押しには「水押し」と呼ばれる方法が多く採用され、膠を薄く溶かした膠水を画面に塗布し、半乾き状態で金箔を乗せて押さえる。乾燥とともに膠が再固化して金箔が支持体に密着する仕組みである。米糊は表装や裏打ちには用いられるが、箔押しでは厚みや水分が多すぎてきれいに定着しにくい。蜜蝋やラッカーは洋画的技法で、日本画の伝統的箔押しには使用されない。
まとめ
いかがでしたか? 今回は日本画制作クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は日本画制作クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。