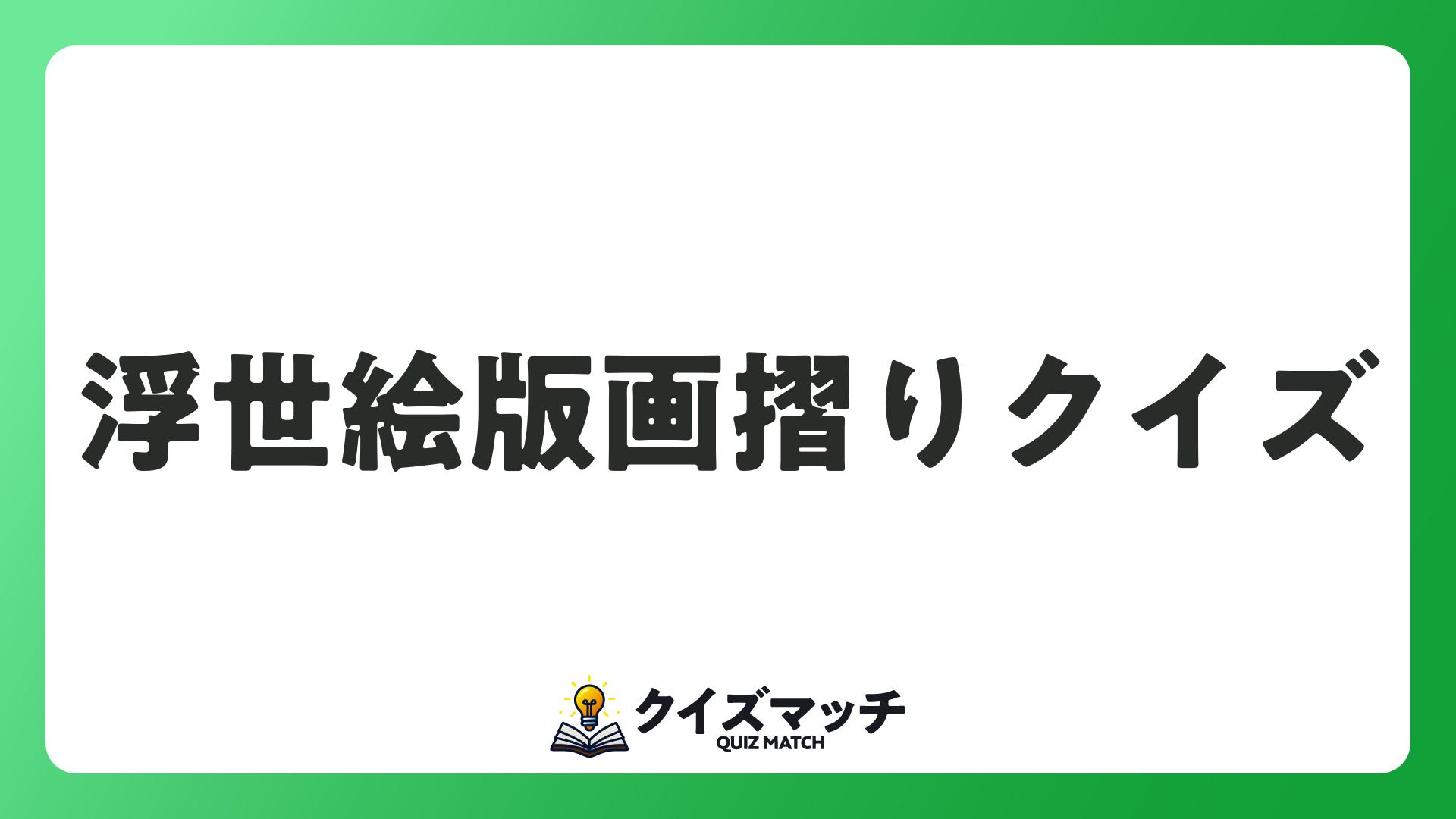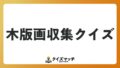江戸時代の浮世絵版画に隠された技の数々。「見当」による正確な重ね摺り、「馬連」の巧みな使い分け、煌びやかな「雲母摺り」など、摺師たちが磨き抜いた技法の秘密に迫る、10問の浮世絵クイズ。江戸の町に広がった錦絵ブームの舞台裏を探ります。版画制作の工夫と職人芸に注目しながら、江戸文化の粋を感じ取ってみてください。
Q1 : 葛飾北斎の『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』初刷で用いられたプルシアンブルーは当時『ベロ藍』と呼ばれたが輸入経路として正しいものはどれか
プルシアンブルーは18世紀ドイツで偶然合成された顔料で日本には19世紀前半に蘭学ルートで長崎に入ったため『ベロ藍』あるいは『ベルリン藍』と呼ばれた。輸入を担ったのは出島のオランダ商館で当時は輸入禁制の銅青に代わる高彩度で変色しにくい新顔料として浮世絵界に衝撃を与えた。北斎はこの鮮烈な青を大波や富士の影色に用い迫力と近代的色彩感覚を獲得した。英国やポルトガル経由の記録はなく清国から入ったのは後年のインディゴで別物である。
Q2 : 『のりぼかし』と呼ばれるぼかし摺りで顔料と混ぜてグラデーションを作る主材料はどれか
のりぼかしは色料に米糊を混ぜたペーストを版面に載せ馬連で引き伸ばし和紙に摺ることで濃から淡へ滑らかな階調を出す技法である。米糊は乾燥が遅く粘性があるため顔料の粒子を均一に保持し版面上で自然なグラデーションを形成する。葛飾北斎や歌川広重の風景画では空や水面の薄明かりを表現するため頻繁に用いられ江戸の摺師が磨いた繊細な水分と圧力のコントロールが不可欠であった。石膏や卵白は浮世絵のぼかしには通常使われない。
Q3 : 浮世絵版木に最も広く用いられ精緻な線刻に適した材質は次のうちどれか
江戸の版元は硬さと粘りを兼ね備えたミズメザクラを主に用いた。サクラ材は年輪が詰まり繊維が絡むため彫刻刀の刃当たりが滑らかで細密な線を欠けさせずに彫れる一方で繰り返しの摺りにも摩耗しにくい。さらに木目が比較的均一で薄い板にしても反りが少ないため多版を重ねても縮みの差が小さく見当精度を保てる。ヒノキやスギは柔らか過ぎて線が潰れブナは導管が粗く絵具が入り込みやすいので錦絵の主流にはならなかった。
Q4 : 江戸後期に星や水面の煌めきを表すため微粉を摺り込む技法で雲母を用いるものはどれか
雲母摺りは粉末状の雲母を糊で溶いて版木にのせ光沢のある層を和紙に転写する技法である。摺り上がりは光の角度で銀白色に輝き夜景や衣装の金糸の輝きを演出した。歌川広重の名所江戸百景『両国の花火』初刷などで背景の暗夜に星が瞬く効果を与えたことで知られる。雲母は無色透明の鉱物で顔料とは異なり下地の色を透かすため隠蔽度を変える刷り重ねにも応用された。蟹摺りは白い濁りを持つ鉛白の粒子を活用した別技法であり名称も効果も異なる。
Q5 : 多色摺の完成者とされ見当を実用化した絵師として知られるのは誰か
明和二年頃に登場した錦絵は従来の紅摺絵を飛躍させ十数色を重ねる華麗な多色摺を実現したがその中心にいたのが鈴木春信である。春信は版元や彫師摺師と協働し四角見当と隅見当を確立し彩色のずれを抑えた上で柔らかな淡彩と繊細な線を調和させた。結果として美人画を中心に薄物の透けや行灯の灯火など当時の流行を映した微妙な光の表現が可能となり江戸の町に錦絵ブームが巻き起こった。国芳や北斎はその後の世代である。
Q6 : 先に摺った色の上に別の色版を重ね新たな色調を作り出す浮世絵の技法を何というか
合い摺りは重ね摺りとも呼ばれ絵具の透過性を利用して前に摺られた色と後の色を光学的に混色し第三の色を得る方法である。同じ版木を二度用いる場合と別に彫った重ね色版を使う場合がありいずれも版木数を抑えながら豊富な色彩を実現できる。例えば黄の上に青を摺って緑を表現するなど顔料コストを節減しつつ色数を増やせるため商業的にも重要だった。適切な濃度管理と位置合わせがないと濁色やずれが生じるため摺師の高度な技能が問われる。
Q7 : 摺りの前に和紙を均一に湿らせ絵具の乗りと伸びを良くする工程を一般に何と呼ぶか
湿しは版木の作業前日に行うことが多く濡れ布で包んだ和紙を積み重ね適度な水分を紙全体に行き渡らせる工程である。乾燥し過ぎると色が乗らず濡れすぎると繊維が伸び見当が狂うため季節や湿度を読み摺り当日に最良の含水率となるよう調整する。江戸の摺師は指先の感覚で紙の腰と温度を確かめながら吸湿量を加減した。湿しによって顔料が紙内部まで染み込み発色が安定し重ね摺りをしても紙が波打ちにくくなる。見当取りや彫定めとは異なる前工程である。
Q8 : 色を用いず版木の凹凸だけで模様や布目を浮き出させる浮世絵特有の摺り技法はどれか
空摺りは版木に絵具を付けず馬連で強くこすって和紙に凹凸だけを写し出す手法で布地の織り模様や着物の刺繍表現に重宝された。主線や彩色とは別の版を作り木目や格子を彫り込むことで立体感を生み摺色が無いぶん控えめな陰影が上品さを引き立てる。美人画で衣装の縮緬や木版口絵の雲形などに用いられ観る者に手触りを想起させた。泥やぼかしを使う技法とも異なり紙面の白を活かすため摺師の圧力配分が出来栄えを左右する。
Q9 : 多色摺を正確に行うため摺師が紙と版木の位置合わせに使う『見当』は何を目的とした目印か
見当は版木の端に彫るL字形の隅見当と溝状の合見当から成り紙の角と辺をそこに合わせることで各版を寸分違わず重ねる。これにより色ずれを防ぎ江戸後期の錦絵に不可欠な十数版もの多色摺を可能にした。さらに見当は摺師と彫師が共有する座標系となり版を追加する際の基準線として機能するため複雑なぼかしや重ね摺りの高度な表現も成立する。
Q10 : 摺師が色をこすり込むために使う道具『馬連』の芯材として江戸期に最も一般的だったものはどれか
馬連は丸く編んだ竹皮の外皮の下に竹皮を剥いで撚った筋縄を渦巻状に巻き込んだ芯を入れその上から和紙と竹皮の合紙を被せて作られる。芯が縄であることで軽量ながら弾力と均一な圧が得られ版面の細部まで色料を押し伸ばせる。金属や木片を使う欧州のプレスと違い柔らかさを保つことで和紙の繊維を傷めずきめ細かな摺りを実現した。芯の締め替えや張り具合の調整で摩擦と圧力を細かく制御でき摺師の腕の見せ所となる。
まとめ
いかがでしたか? 今回は浮世絵版画摺りクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は浮世絵版画摺りクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。