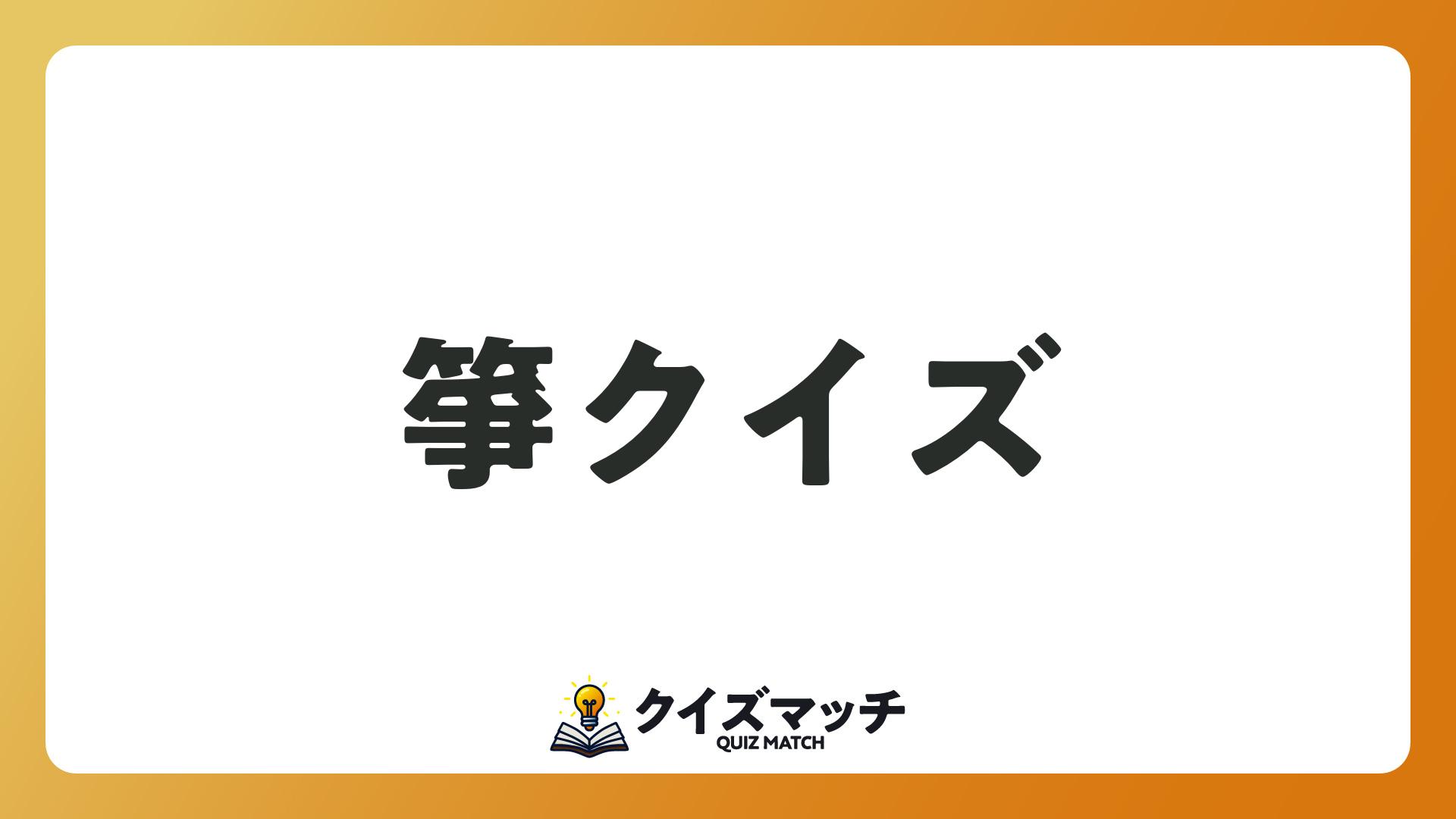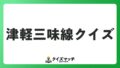箏クイズ
箏は日本の伝統楽器の代表格で、長い歴史と豊かな音楽性を誇っています。その構造や演奏法、作品などには多くの興味深い事実が隠されています。本記事では、箏に関する10の基本的な知識をクイズ形式で紹介します。箏の魅力を知ることで、この楽器への理解が深まることでしょう。箏という伝統楽器の奥深さを探っていきましょう。
Q1 : 箏・三味線・尺八による三曲合奏で、低音を補強する目的で用いられる17弦箏の一般的な呼称は?
十七絃は宮城道雄考案の17本弦を備えた大型箏で、十三絃より下のC音域まで演奏可能なため、三曲合奏ではコントラバスやチェロに相当する低音補強を担う。正式名称は「十七絃箏」だが、現場では略して「十七絃」と呼ばれ、作編曲の譜面にもその名が記される。従来、低音は三味線の太棹や尺八の低尺八で補っていたが、十七絃の導入により和楽器アンサンブルのハーモニーが一気に厚みを増した。低音箏や中箏は便宜的な俗称にすぎず、古代ハープの一種である箜篌とは全く別系統である。
Q2 : 現在、学校教育用の箏で主に用いられる弦の素材は?
かつて箏の弦は養蚕の盛んな日本の環境を背景に絹糸が主流であったが、擦過摩耗や湿度変化に弱く、張り替え頻度やコストが教育現場の負担になっていた。その解決策として昭和後期に登場したナイロン弦は、絹と近いしなやかさを保ちながら強度と耐候性に優れ、音量も安定しているため急速に普及した。金属弦や羊腸弦は他国の撥弦楽器で用いられるが、日本の箏では特殊例にとどまり、現在の学校備品の大半はナイロン弦で占められている。
Q3 : 箏曲『六段の調』を作曲した人物は誰か?
『六段の調』は江戸前期に活躍した筑紫箏の大成者、八橋検校(1614頃–1685)による代表作である。八橋は当時の雅楽由来の楽箏を世俗音楽へ転用し、地歌三味線の旋律を取り入れて十三絃箏のレパートリーを拡大した功績で知られる。同曲は六つの段から成る変奏形式で、箏独奏曲の古典として今日まで愛奏され続けている。後世の名手である宮城道雄や沢井忠夫も名演を残しているが、作曲者は八橋検校のみであることが文献・伝承の双方から確認されている。
Q4 : 伝統的な箏の演奏で、爪を装着する指の組み合わせはどれか?
箏の右手奏法では親指(拇指)・人差し指・中指の三本に象牙や合成樹脂製の爪をはめ、弦を手前から押し出すように弾くのが基本とされる。薬指にも爪を付ける流派はあるものの、古典曲では使用頻度が低く、現代曲でも補助的役割にとどまる。左手は爪を付けず、勘所を押さえて音程を変化させたりビブラートをかけたりする。親指と人差し指・中指という組み合わせは、音域全体に均等な加重と動作の自由度を確保できるため、江戸時代以来ほとんど不変で受け継がれている。
Q5 : 地歌箏曲の基本調弦「平調子」で一の糸が現代音高で最も近い音名は?
平調子は十三絃の基本調弦で、一の糸をD(レ)の音高に設定し、二の糸E、三の糸G…と五度・三度を組み合わせた独特のスケールを構成する。江戸時代の管絃合奏や三味線の本調子と親和性が高く、地歌・箏曲の多くがこの調弦を基準に作曲された。現代ではA=440Hzの平均律が標準だが、箏では伝統的にDを約293Hz前後に合わせる。CやGを基音とする調弦も存在するが、それぞれ雲井調子や雲井六段など別名で区別され、平調子とは異なる体系として扱われる。
Q6 : 弦の下に置いて音高を支える、箏の可動式ブリッジの名称は?
十三絃箏では弦ごとに独立した支点となる部材を琴柱(ことじ)と呼ぶ。Y字形の木製パーツで、脚部分を大胴面に滑らせて位置を変えることで弦長を調整し、半音単位の細かな音程設定を実現する。雅楽の楽箏に固定柱を用いる例を除けば、日本の箏音楽は琴柱の存在によって多様な調弦体系を成立させてきた。駒は三味線のブリッジの呼称であり、琴座や案は胴体や道具箱を指す用語で、箏の調弦操作に直接関与する名称ではない。
Q7 : 低音域を拡張する目的で考案された17絃箏(十七絃)を発明した人物は?
作曲家・箏曲家の宮城道雄(1894–1956)は、琴柱で拡張できない低音域を補うため1921年に17絃箏を創製した。従来の十三絃より胴を大きくし、弦を太くすることで低いC音までカバーし、合奏時のチェロ的役割を担わせた。宮城自身の代表作『春の海』や『瀬音』にも17絃が効果的に用いられ、戦後には沢井忠夫ら後進が独奏曲を作曲してレパートリーを拡大した。八橋検校や山田検校の時代には存在せず、宮城の革新的な発想が今日の箏合奏の音域豊富化をもたらした。
Q8 : 雅楽に用いられる六絃の古い箏の名称は?
和琴は日本古来の神楽や宮廷行事で用いられる六絃の横置き撥弦楽器で、奈良時代の『続日本紀』にも記述が見られる。胴は檜の一木造りで、柱は固定されており、十三絃箏のように可動式ではない。雅楽合奏では笙や篳篥とともに伴奏の和音を支え、祭祀では神楽歌の拍取りを行う。楽箏は十三絃を指し、筑前箏は近世の地域流派、琵琶は撥弦楽器だが撥で弾奏する別系統である。和琴の素朴で柔らかな響きは、現代の箏とも異なる重要な古層を伝えている。
Q9 : 箏の奏法「すり爪」で得られる主な音響効果はどれか?
すり爪は右手の爪を弦上に軽く当てたまま琴柱方向へすり上げ、複数の弦を連続的にこすることで、波のようにうねるグリッサンドを生み出す技法である。音の立ち上がりが柔らかく、滑らかな音列が一息で連なるため、情景描写や転調の橋渡しに多用される。スタッカートやビブラートとは異なる伸びやかさが特徴で、現代曲ではピアノのアルペッジョを模倣する際にも効果的。打弦的な効果を狙う場合は「はじき」や「押し手打ち」など別の奏法が指定される。
Q10 : 箏の標準的な弦の本数は?
箏は奈良時代には五絃・六絃など多彩な祖形があったが、17世紀に八橋検校が胡弓や三味線の音組織を取り入れて改良した十三絃箏が急速に普及した。以後、十三絃が地歌箏曲の基本形として定着し、学校教育や合奏指導でも基礎楽器とみなされている。17絃や25絃など低音・拡音域用の派生箏は存在するものの、あくまで主役は十三絃であり、楽譜の弦番号や琴柱配置もこの本数を前提に作られている点が決定的な証拠となる。
まとめ
いかがでしたか? 今回は箏クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は箏クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。