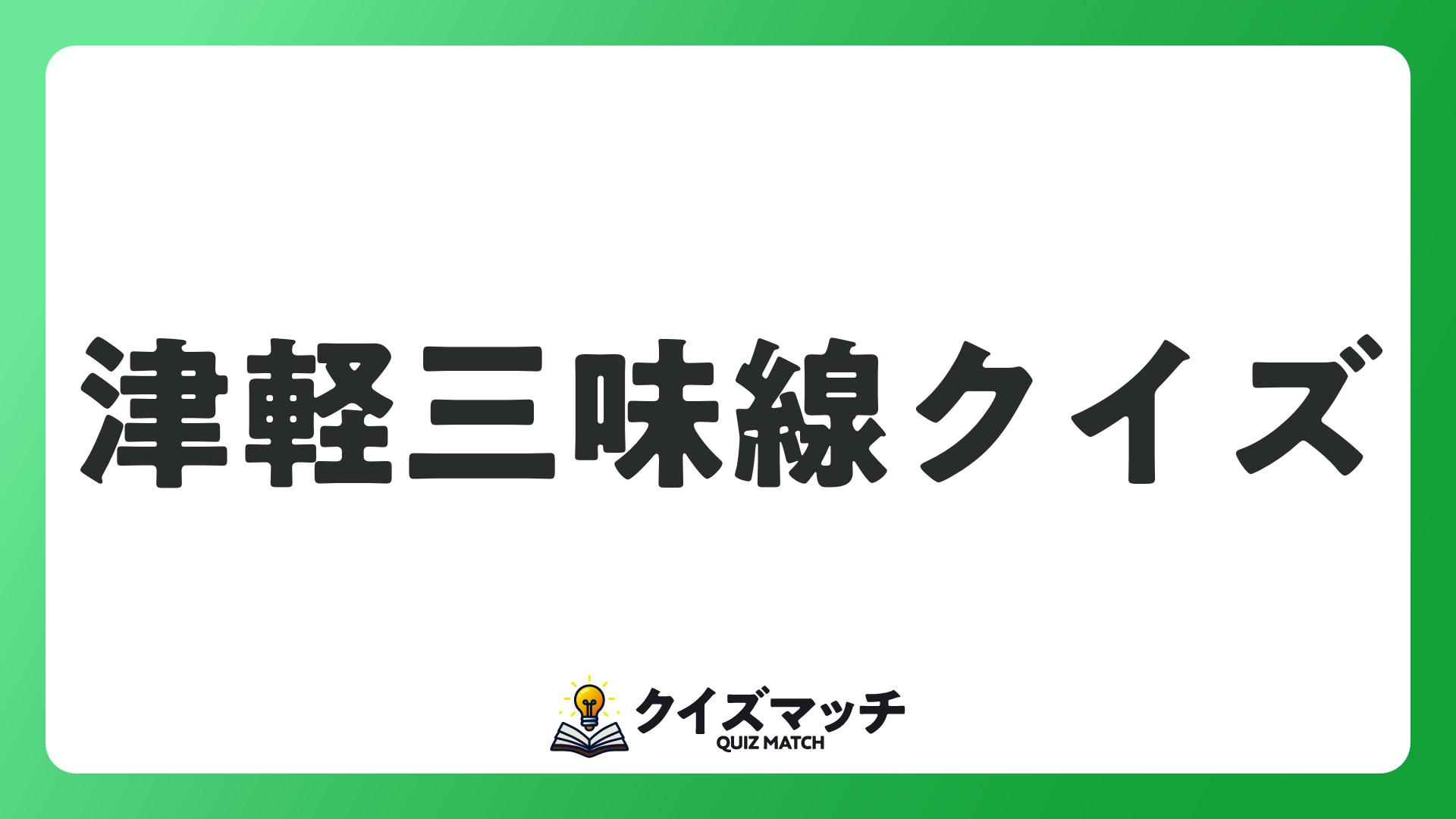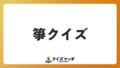津軽三味線は青森県の津軽地方で19世紀後半に民謡伴奏用として発達した民俗楽器です。厳しい寒風の中でも鳴りを確保するため胴を大型化し、撥で力強く叩く独特の奏法が特徴となりました。この10問のクイズでは、津軽三味線の構造、演奏技法、代表曲、そして歴史的な名人について学ぶことができます。津軽三味線の魅力に触れながら、この地域の音楽文化の奥深さを探っていきましょう。
Q1 : 津軽三味線の本体で太鼓のように皮を張った共鳴箱を指す名称は?
三味線の構造は胴 棹 糸の三要素から成り立つが 津軽三味線では特に胴が大型で厚みもあり 豚や犬の皮を強く張り打楽器のような低音と迫力を生む。長い棹や叩き付ける撥と合わせて津軽特有の重厚なサウンドを支える中心部位であるため 胴の材質と寸法選定が演奏家の音色に直結する重要部分である。
Q2 : 津軽三味線の棹の太さは三味線三分類のうちどれに該当する?
三味線は細棹 中棹 太棹の3種類に分類されるが 津軽三味線は最も太い太棹に属する。棹幅は約30ミリに達し 弦も太く張力が強いため 叩きつけるような撥さばきでも耐久性があり 音量も豊かになる。この太棹構造が激しい打ち込みや速弾きを支え 民謡伴奏から独奏へと発展した技術的背景の一つとなっている。
Q3 : 即興性が高く演奏者ごとに変化する津軽三味線の代表曲として最も知られる民謡は?
津軽じょんから節は津軽三味線を象徴する楽曲で 旧来の民謡を基にしつつ前弾き 中節 後弾きを通じて自由な変奏や速弾きを入れるのが通例である。演奏者の個性が顕著に出るため公式な定型はなく 全国大会でも独自アレンジが競われる。さくらさくらや六段の調は古典曲 ソーラン節は北海道民謡であり 津軽じょんから節ほど津軽三味線と結び付いてはいない。
Q4 : 津軽三味線で使用される大型の撥の高級材として伝統的に用いられてきたのは次のうちどれ?
撥の材質は音色や弾き心地を大きく左右するが 津軽三味線では先端がしなることで鋭い立ち上がりを生む鼈甲撥が古くから最上とされてきた。鼈甲はタイマイの甲羅を圧着した希少素材で 適度な弾力と軽さを備え 長時間の激しい打ち込みにも手首への負担が少ないといわれる。近年は国際規制で高価化しプラスチック製も普及しているが 伝統的最高級材という評価は揺るがない。
Q5 : 盲目ながら高度な即興演奏で戦後の津軽三味線ブームを牽引した名人は誰?
高橋竹山(一代目)は1910年青森県五所川原市生まれ。旅芸人として各地を流しながら津軽三味線を磨き 戦後に青森県民謡コンクールで注目された。津軽じょんから節の迫力あるアドリブで一般大衆を魅了し 1970年代には国内外でリサイタルを開催。ラジオやテレビ出演も多く 津軽三味線を全国区の存在へ押し上げた立役者として知られる。
Q6 : 弦を指で弾いて素早く離すことで装飾音を入れる津軽三味線の技巧を何という?
はじきは左指で弦を引っかけて素早く離すプルオフ的奏法で 右手の撥打ちと組み合わせることで複雑なリズムや装飾音を生む。津軽三味線は即興性が高いため 単音の合いの手やチョーキング効果を与え 聴衆を驚かせるアクセントとなる。すくいは撥で弦を上方向に払う動き たたきは胴を叩くパーカッシブ奏法であり 技術的意味が異なる。
Q7 : 津軽三味線が主に伴奏する音楽ジャンルとして正しいものは次のどれ?
津軽三味線は北国の民謡 いわゆる津軽民謡を中心に発達したため 民謡伴奏が原点である。歌い手の抑揚に合わせてテンポを自由に変えたり 胴を叩いてリズムを強調したりする奏法は民謡特有の味わいを支える。歌舞伎長唄や義太夫節は別系統の三味線が担当し 沖縄民謡では蛇皮線が用いられる。したがって北日本民謡との結び付きが最も強い。
Q8 : 現代の津軽三味線ユニットやソロが和洋融合で共演する打楽器として人気が高いのは?
津軽三味線は激しい撥さばきによる強靭なビートが特徴で それをさらに高揚させる演出として和太鼓との組み合わせが多用される。YOSHIDA BROTHERSやあがつまひろむつのライブでも大太鼓や締太鼓が加わり ロックやフュージョン並みの迫力を実現する例が多い。バイオリンや箏 平笛も共演例はあるが ビート面で最も定着した組み合わせは太鼓である。
Q9 : 演奏冒頭で奏者の感情を即興で示す前奏部分「前弾き」は通常どのようなリズムで演奏される?
前弾きはテンポや拍子を固定せず 奏者の息遣いで間を取りながら音の余韻や静寂を作り出す自由リズムで演奏される。この無拍的な序奏があることで続く中節や曲弾きのダイナミクスが際立ち 聴衆は津軽の音世界へ引き込まれる。決まった拍子がないため 初学者には呼吸と間を体得する難関部分として知られ 津軽三味線の表現力の要とも言える。
Q10 : 津軽三味線が生まれたとされる都道府県はどこ?
津軽三味線は青森県の津軽地方で19世紀後半に民謡伴奏用として発達した民俗楽器である。厳しい寒風でも鳴りを確保するため胴を大型化し撥で力強く叩く奏法が特徴となった。発生地を問う設問では青森県が正解であり他県は三味線の主要産地ではない。津軽地方の生活風土と祭りが音楽性を育み現代では全国的に知られる民俗文化財として評価されている。
まとめ
いかがでしたか? 今回は津軽三味線クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は津軽三味線クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。