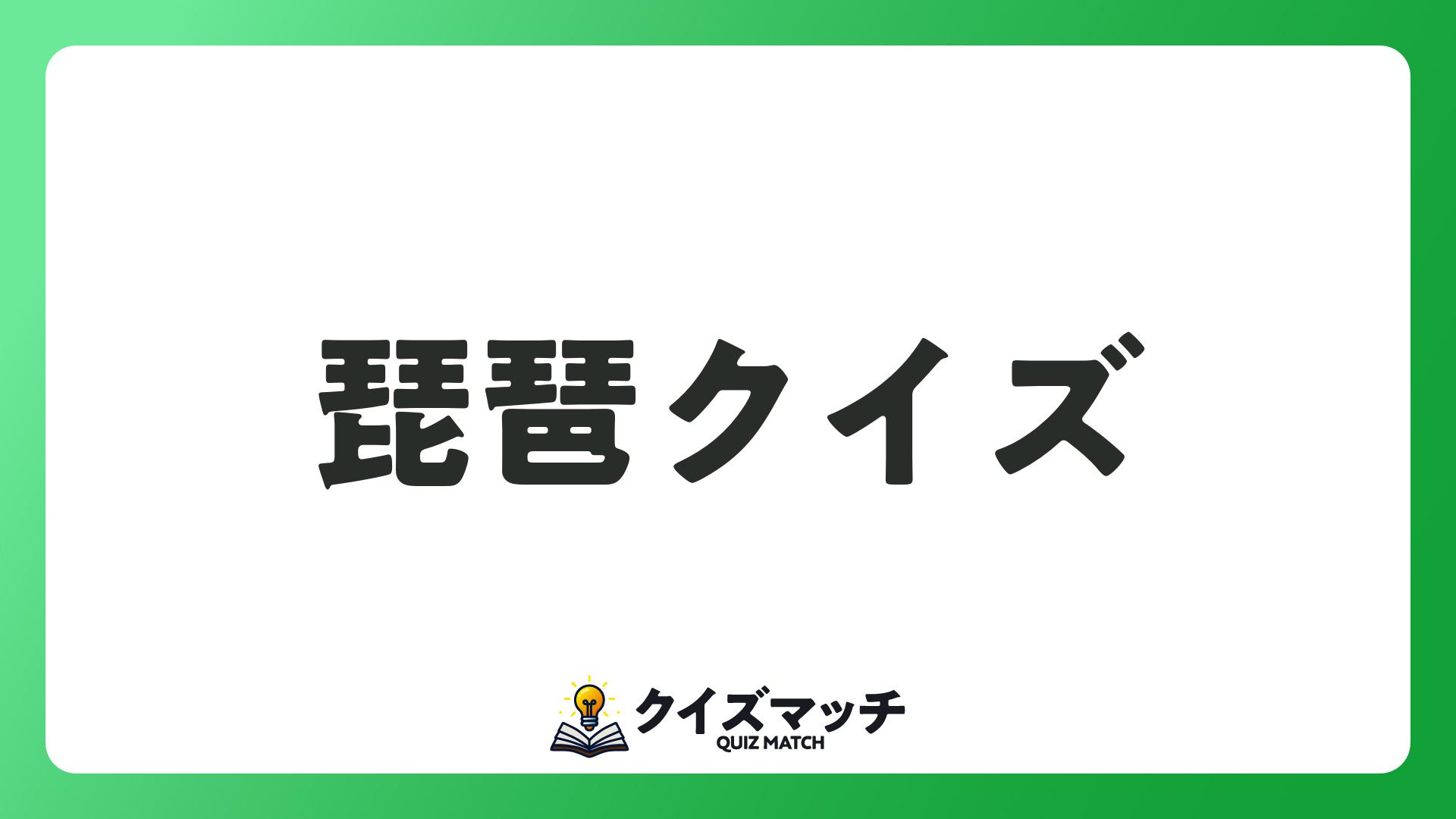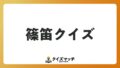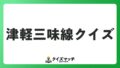琵琶は日本固有の伝統的な楽器ですが、その歴史は意外と古く奥深いものがあります。平安時代の雅楽に組み込まれ、そして中世の語り物音楽にも大きな役割を果たしてきた琵琶。その特徴的な音色と奏法は、今なおわが国の音楽文化の根幹をなしています。この記事では、琵琶の由来や楽器の種類、代表曲など、琵琶にまつわる10の興味深いクイズを紹介します。琵琶の歴史と魅力を、クイズを通じて探っていただければ幸いです。
Q1 : 盲目の琵琶法師が弾き語りで伝承してきた物語として最も代表的なものはどれか?
盲目の琵琶法師が語り継いだ物語として最も知られるのが『平家物語』である。鎌倉時代に成立した軍記物語で、壇ノ浦の合戦までの源平盛衰を七巻または十二巻で語る。平曲とも呼ばれ、琵琶は平家琵琶を用い、低い音域で語りの合間に撥音と打音を挟む。『源氏物語』は平安文学、『徒然草』は随筆、『奥の細道』は俳諧紀行であり、いずれも琵琶法師の語り物ではないため誤答となる。
Q2 : 雅楽用の楽琵琶で最上とされる撥(バチ)の伝統的素材はどれか?
雅楽で使われる楽琵琶の撥は形が扇形で、素材としては黄楊などの硬木もあるが、最上とされるのが象牙製である。象牙は密度と重量が高く、弦を打った瞬間の立ち上がりが鋭く音量が豊かで伸びやかな響きを生むため、宮廷や寺院の儀式で重宝された。桜や竹は練習用、近年の樹脂製は代替素材として用いられるが、伝統的に格式が高いとされるのは象牙であり、古器は厳重に保管される。
Q3 : 漢字の「琵」「琶」は本来何を表す語源とされるか?
漢字の「琵」「琶」は、それぞれ琵琶を演奏するときの右手撥の動きを示すとされる。「琵」は前方へ押し出す奏法、「琶」は手前に引く反復動作を指し、連続すると「前後に弾く楽器」という意味になる。中国語の琵琶でも同様の語源説があり、移入後の日本でも名称だけが保存された。他の選択肢である音域・弦素材・撥の大きさとは無関係であるため、正解は手の動きを表す4番となる。
Q4 : 正倉院に伝わる五絃琵琶など唐代の名器を所蔵している寺院はどこか?
奈良・東大寺の正倉院には聖武天皇ゆかりの宝物が多数保存されており、螺鈿紫檀五絃琵琶をはじめとする唐代の華麗な琵琶が伝世している。正倉院の校倉造構造が高温多湿を防ぎ、千年以上前の木製楽器を良好な状態で保管してきた。法隆寺や薬師寺にも古楽器は残るが、五絃琵琶のような国宝級の名器がまとまって現存するのは東大寺正倉院だけであるため、正解は東大寺である。
Q5 : 次のうち、日本の伝統的な琵琶の種類ではないものはどれか?
日本の伝統琵琶には武家精神を重んじる薩摩琵琶、平曲を語る平家琵琶、女性でも抱えやすい筑前琵琶などがある。いずれも撥で弦を弾く撥弦楽器で、胴が梨形でフレットを持つ。一方、胡弓は弦を弓でこする擦弦楽器で胴も円形に近く奏法も異なる。名称に「琵」の字を持たず琵琶系統には含まれないため、琵琶の一種ではない胡弓が正解となる。
Q6 : 薩摩琵琶の代表曲で、源平最後の合戦を描いたものはどれか?
薩摩琵琶の曲目は多くが歴史・軍記を題材とし、薩摩武士の士気高揚に用いられた。その代表が『壇ノ浦』で、源義経による平家追討の最終局面を勇壮な撥さばきで描写し、山川直章など歴代名手が十八番にした。『屋島』は同じ源平合戦でも屋島の戦を扱う別曲、『那須与一』は扇の的を射る場面、『鞍馬山』は牛若丸修行譚で、いずれも内容が異なるため壇ノ浦が正解となる。
Q7 : 昭和期に琵琶の近代化と国際的普及に貢献し、武満徹作品の演奏でも知られる女性琵琶奏者は誰か?
鶴田錦史は大正末生まれの女性琵琶演奏家で、古典を礎にしながら武満徹『ノヴェンバー・ステップス』のために琵琶奏者として世界的な舞台に立ち、現代邦楽の新境地を拓いた。黒澤明監督の映画『赤ひげ』『どですかでん』でも演奏を担当し、重厚な撥音で海外の聴衆を魅了した。選択肢の他の人物はいずれも琵琶と直接関係がなく、昭和期の琵琶復興と国際化に決定的役割を果たしたのは鶴田錦史だけである。
Q8 : 琵琶が日本に公的に導入され、雅楽の正式楽器として制度化されたのはいつか?
琵琶は大陸で発達した撥弦楽器で、遣唐使・遣新羅使が往来していた7〜8世紀に雅楽の楽器として公的に導入された。正倉院の唐木製楽器が証明するように国家的に受け入れられたのは平城京の時代であり、声明・舞楽の伴奏に不可欠な存在となった。飛鳥末期にも舶載例はあるが、本格的に制度化されたのは奈良時代であるため、この時期を伝来の時代とするのが一般的な見解である。
Q9 : 雅楽で用いられる大型の琵琶の名称はどれか?
雅楽で使われる琵琶は大型で胴の幅が広くフレットが少ない「楽琵琶」である。管弦の合奏では弦をかき鳴らして拍子を示し旋律を補強する。薩摩琵琶や筑前琵琶は明治以降の語り物や独奏用に改良された楽器で、構造も奏法も異なる。平家琵琶は平曲専用の中型楽器で宮廷雅楽の正式編成には含まれない。したがって雅楽の合奏で用いられるのは楽琵琶が正解となる。
Q10 : 筑前琵琶の標準的な弦の本数はいくつか?
筑前琵琶は明治期に黒田藩士の橘旭翁が女性や市民にも扱いやすいよう開発した流派で、撥を軽くし弦を絹の四本に限定したのが特徴である。後に五弦化された薩摩琵琶と違い、四弦四柱という仕様が標準で、調弦も独特の「本調子」「二上がり」などがある。弦が四本であることにより構えや押し手が比較的簡潔になり、語りと音色のバランスがとりやすい点が現在でも支持される理由となっている。
まとめ
いかがでしたか? 今回は琵琶クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は琵琶クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。