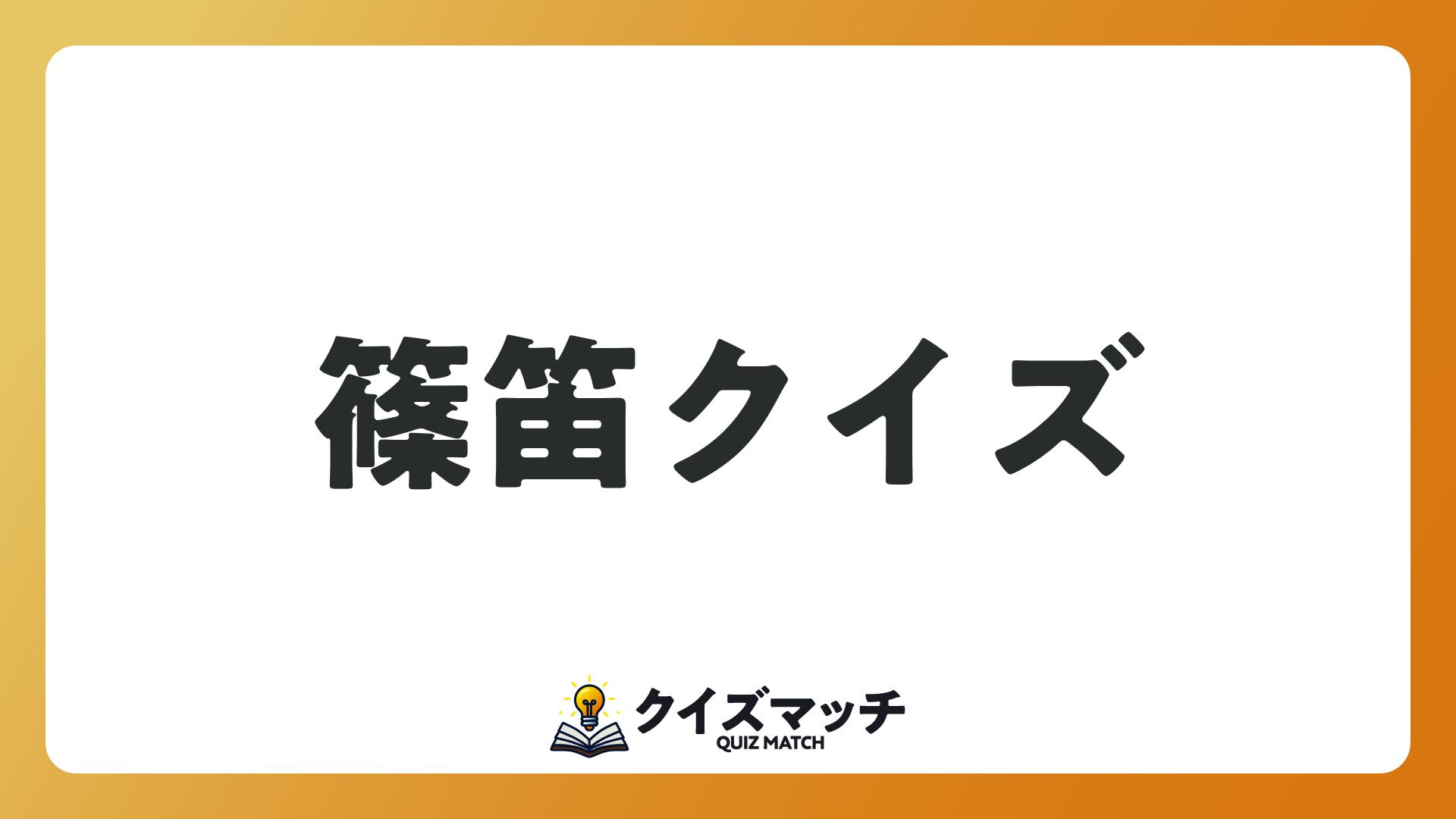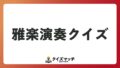【リード文】
篠笛は、日本の伝統的な管楽器の一つで、祭礼や芸能の世界で重要な役割を果たしてきました。その演奏に欠かせない素材や構造、特性について理解を深めるべく、この記事では「篠笛クイズ」と題してさまざまな問題に挑戦していきます。竹の種類から演奏法、楽器の歴史まで、篠笛の魅力に迫る10問をお楽しみください。篠笛の知識を深めながら、この伝統的な楽器への理解がさらに広がることを期待しています。
Q1 : ドレミ調と呼ばれる唄用篠笛が洋楽器との合奏に適している理由として正しいものはどれか?
ドレミ調篠笛は平均律に基づいて穴の位置を決め、A=440〜442Hzに合わせて作られているため、ピアノやギターなど西洋楽器との合奏でも音程がずれにくい。音量の大小は合奏適性の主因ではなく、指穴の数が少ないとかえって音程の自由度が落ちる。金属製は耐久性に優れるが素材による合奏適性の差は小さい。平均律対応こそが洋楽器との共演を容易にしている最大の理由である。
Q2 : 演奏後の篠笛の手入れとして最も推奨される方法はどれか?
演奏後の篠笛内部には水分が残りカビや割れの原因となるため、通気性のある布や笛専用のスワブで内壁を優しく拭き乾燥させることが推奨される。水洗いすると竹の油分が抜け割れや反りを招くうえ、急激な日光や熱風乾燥は割れを加速させる。特に暖房器具の前は高温低湿で危険である。柔らかい布での拭き取りと自然乾燥が最も安全で長持ちさせる手入れ法である。
Q3 : 唄用篠笛と囃子用篠笛を識別する要素として代表的なものはどれか?
唄用篠笛は西洋楽器や歌とのピッチ合わせを重視するため、管内に漆を塗り音程を細かく調整している。漆を塗ることで管内壁が硬化し、共鳴点が安定してピッチが正確になる。一方、囃子用は祭礼で大音量を求められるため素竹のままにして共鳴腔を広く保ち、鋭い音色を得るのが一般的である。径や指穴は両者で大差がなく、くぼみは装飾要素にすぎないので識別要素になりにくい。
Q4 : 一般的な唄用篠笛に設けられている標準的な指穴の数はいくつか?
篠笛の指穴は前面に六孔、背面に一孔の計七孔が最も普及している。この配置により日本伝統音階だけでなく西洋のドレミ音階も吹けるため汎用性が高い。囃子用や一部の民謡用に六孔のみの笛もあるが、音域や半音の操作性が制限される。五孔では演奏可能な曲がさらに絞られ、八孔は特殊製作で普及率が低い。したがって標準的な唄用篠笛は七穴である。
Q5 : 篠笛において、演奏者が息を吹き込む孔は何と呼ばれるか?
唄口はフルートのエンブシュアホールに相当し、演奏者が息を当てることでエッジトーンを発生させ音を作る最重要部位である。指孔は音程操作用の穴、管尻は管の終端、糸巻は糸を巻いて補強する装飾部分にすぎない。唄口の角度や幅、深さが少しでもずれると音程や倍音の出方が大きく変わるため、製作者は微細な調整を重ねる。演奏者も唇のあて方を調節して音色を作るので、息を吹き込む孔は唄口と呼ばれる。
Q6 : 篠笛の祖形とも言われ、雅楽で主旋律を担う竹製の横笛を何というか?
龍笛は平安時代から続く雅楽の三管の一つで、竹製の横笛として主旋律を担当する。篠笛とは管の太さや長さが異なるものの、横笛という形態や運指の基本が共通しており、篠笛の祖形に位置付けられる。能管は能楽に用いる高音の笛で構造が異なり、高麗笛は雅楽の高麗楽で使用され、柝竹は打楽器で笛ではない。これらの中で篠笛のルーツとして直接的に系譜が語られるのは龍笛である。
Q7 : 八本調子の唄用篠笛で、基本の筒音が属するキーはどれか?
八本調子の唄用篠笛は筒音がC、すなわちピアノのドに相当するように設計されている。そのため洋楽器の基本キーと一致し、譜面も読み替えなしで演奏しやすい。BやDは半音ずれるため移調が必要になり、Eでは音域が高くなりすぎる。製作時にはA=440〜442Hzを基準にし、管内の漆塗りや穴開けで微調整を行う。従って八本調子と結び付くキーはCが正しい。
Q8 : 祭囃子で最もよく使われる調子として知られる篠笛は次のうちどれか?
祭囃子で鳴り響く笛は人混みや太鼓の大音量に埋もれない明るい音色が求められるため、六本調子が定番とされる。六本調子はB♭付近のキーで、人の耳に届きやすい中高域でありながら、長さも持ち運びやすく操りやすい。三本調子や四本調子は管が長く音が低すぎ、十本調子は高音になり過ぎて安定した音程を保ちにくい。したがって祭囃子用として頻用されるのは六本調子である。
Q9 : 篠笛の管内表面を保護し、湿度変化から木質を守るために塗られることが多いのはどれか?
篠笛の内部は湿度変化や唾液による腐食から守る必要があるため、赤い色味の朱漆を塗ることが多い。朱漆には防水性と抗菌性があり、長期使用でも管内がカビたりささくれたりしにくい。段巻や糸巻は外側の補強、黒漆は外装や唄口周辺に使われる例が多い。蒔絵は装飾技法であり保護膜としては主用途ではない。よって管内保護の代表的な塗料は朱漆である。
Q10 : 篠笛の主な材料として最も一般的に用いられる竹の種類はどれか?
篠笛は細身で軽く、節間が長い竹で作る必要があるため、古くから真竹が第一選択とされている。真竹は肉厚が薄く加工しやすいうえ、乾燥後もひび割れにくい性質を持つ。高野竹や黒竹も管楽器に使われる例はあるが、節間の長さや音響特性が篠笛にはやや不向きとされている。孟宗竹は肉厚が厚く重量が増すため、尺八などには適するが、篠笛には重過ぎる。以上の理由から最も一般的なのは真竹である。
まとめ
いかがでしたか? 今回は篠笛クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は篠笛クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。