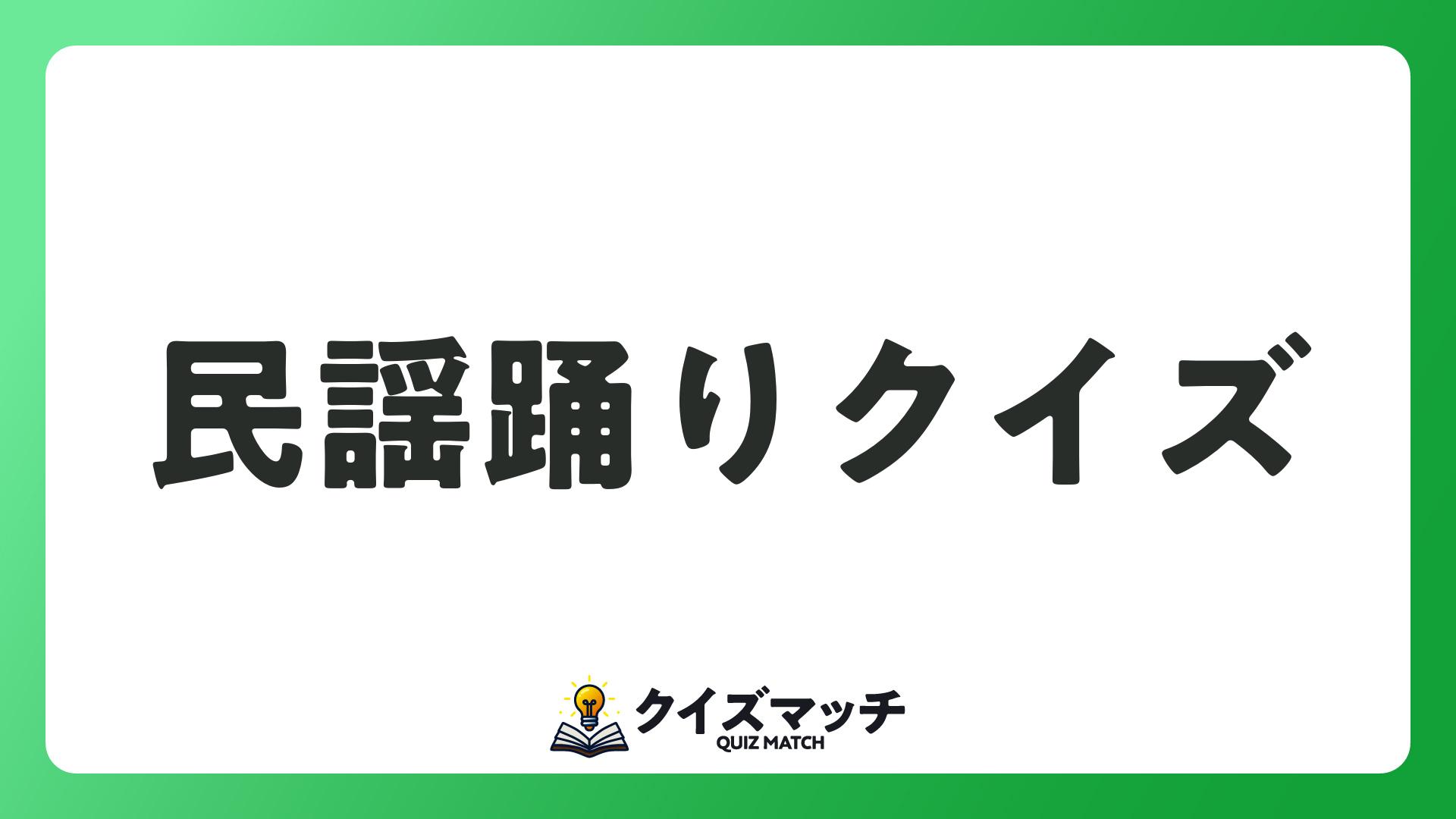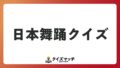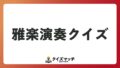徳島の阿波踊り、北海道のソーラン節、山形の花笠踊り…日本各地には魅力的な民謡踊りが数多く残されています。その歴史や特徴を知ることで、より楽しく鑑賞できるはずです。本記事では10問のクイズを通じて、日本の伝統的な民謡踊りの世界をさまざまな角度から紹介していきます。踊りのルーツや道具、キーワードなど、見逃しがちな小さな発見がきっと待っています。民謡踊りの魅力に触れ、夏の風物詩をより深く理解する一助となれば幸いです。
Q1 : 山形県花笠踊りで用いられる花笠の表面に主に飾られている造花の色は?
山形県の代表的な盆踊り「花笠踊り」で使用する笠は、和紙で覆った竹製笠の表面に色鮮やかな紅花を模したピンク色の造花をぐるりとあしらうのが基本形である。紅花は山形県置賜地方の特産で、江戸期には紅の染料として全国に知られた経済作物だった。その歴史的背景から、踊りの舞台となる山形市や尾花沢市では「紅花=ふるさとの誇り」を示すシンボルとしてピンク色が採用されている。踊り手は片手に花笠を掲げ、軽やかなステップとともに笠を回したり返したりして紅花の色彩を観客に見せるため、舞台は終始華やかな雰囲気に包まれる。青や緑の笠も地域行事で装飾的に用いられる例はあるが、正式な花笠踊りではピンクが基本とされている。
Q2 : 富山県五箇山の民謡踊り「こきりこ節」でリズムを刻む伝統的打楽器『ささら』は、56枚前後の薄い板を何で連結したもの?
『ささら』は大小の板を束ねて振る独特の鳴り物で、五箇山こきりこ節では「御神楽(みかぐら)」の流れを汲む神事芸能として用いられる。薄板はヒノキやサクラなどの硬木を用い、耐久性と柔軟性を両立させるために革ひもでしっかり連結されている。演奏者は両手で端を握り、うちわをあおぐように開閉して「シャラシャラ」という澄んだ音を響かせる。革ひもは湿気にも強く、手汗で滑りにくいため野外神事に適していたと考えられる。麻縄や絹糸では繰り返しの振動で切れやすく、鉄鎖では重量が増して軽快な演奏が難しい。こきりこ歌詞に登場する「ササラ」は村の豊穣と安全を願う奉納舞の象徴であり、革ひもで束ねた板の音色が稲穂の揺れや山風を想起させると伝えられる。
Q3 : 岐阜県の郡上おどりは日本三大盆踊りの一つとして有名ですが、毎年“徹夜踊り”が行われるのはいつの期間?
郡上おどりは7月中旬から9月上旬にかけて33夜開催される長丁場の盆踊りで、クライマックスとなる“徹夜踊り”は旧暦の盆に当たる8月13日から16日未明まで連続して踊り明かす。午後8時ごろ始まり翌朝4時頃まで太鼓と三味線が鳴り響き、踊り手も観光客も区別なく輪に入り続けるのが特徴だ。徹夜踊りは江戸時代、城下町八幡の町衆が藩主の許可を得て士農工商を越えた交流を図った歴史を起源とする。現在も道路を封鎖せず町の路地で開催するため、踊り子は提灯がわずかに照らす石畳を下駄で鳴らしながら通り抜ける独特の情緒を味わえる。徹夜という形態は全国でも珍しく、郡上おどりの代名詞として多くの踊り好きが旧盆に岐阜の山あいへ集う。
Q4 : 秋田県の西馬音内盆踊りで、踊り手が顔を隠すために用いる伝統的な覆いの名称は?
西馬音内盆踊りは秋田県羽後町で300年以上続くとされ、編笠姿の男踊りと彦三頭巾(ひこさずきん)をかぶった女踊りが幽玄な情景を生み出す。彦三頭巾は江戸末期の豪商・彦三郎が寄進したと伝えられる絹布でつくられ、こめかみから頬にかけてゆるく垂らし、目元だけがわずかに覗く。顔を隠すことで踊り手の年齢・身分を問わず盆の精霊に扮するという宗教的意味合いが強く、観光客にはミステリアスな魅力として映る。踊り子は藍染の絞りや久留米絣など古裂で仕立てた衣装を纏い、三味線と胡弓の哀調に合わせて足を小刻みに運ぶ。角巻は冬季の防寒用、スゲ笠は農作業用の笠、面は能楽などで使用されるが、西馬音内の女性踊りを象徴するのは「彦三頭巾」である。
Q5 : 新潟県佐渡島の民謡踊り『佐渡おけさ』で、代表的な手振り“おけさ船漕ぎ”が表す動作は次のうちどれ?
『佐渡おけさ』は江戸から明治期にかけて北前船の船乗りが伝えたとされる港町生まれの民謡で、踊りには沿岸の生活を彷彿とさせる所作が数多く盛り込まれている。中でも両腕を大きく前後に動かす“おけさ船漕ぎ”は、船頭が櫓を操りながら狭い入江を行き来する姿を写したものだ。踊り手は膝を軽く曲げ、腰を落としながら腕で弧を描くため、実際に水を押し分けるような力強さと流麗さが同居する。タコ壺や網を扱う動作もアレンジで登場するが、公式講習会でまず教えられる基本手振りは櫓漕ぎである。佐渡島はかつて金銀山の鉱山町として栄えた一方、漁業と航海技術も発達しており、踊りの振りは島民の海への敬意と暮らしを象徴している。
Q6 : 沖縄の伝統芸能エイサーで、列の先頭に立ち大きな旗で隊列を導く役目の名称は?
エイサーは旧盆の祖先供養のために青年団が太鼓や踊りで集落を練り歩く行事で、パーランクーや大太鼓の躍動感あふれる演舞が魅力である。その際、行列の最前列で高さ数メートルの旗を掲げ、進路や演舞開始の合図を示すのが「旗頭」である。旗頭には村名や団体名、吉祥文様が染め抜かれ、重さは数十キロに及ぶこともあるため熟練の担ぎ手が担当する。観客は旗頭の向きで次にどの方向へ移動するかを把握し、踊り手も旗の動きを見て隊形を整える。沖縄の大綱引きや運動会でも旗頭がシンボルとして登場するが、エイサーでは特に精神的支柱として機能し、夜空に映える旗が囃子と太鼓の音をさらに引き立てる。ウドゥンミャーは古来の屋敷名、カンカラは三線の別称、ハーリーは爬竜船競漕を指す。
Q7 : 福岡県発祥の民謡踊り『炭坑節』の歌詞に登場し、月が昇る舞台として歌われる炭坑はどこ?
『炭坑節』は大正末期から昭和初期にかけて福岡県三池地方で歌われた作業唄が原型で、冒頭の「月が出た出た 三池炭鉱の上に出た」というフレーズで広く知られている。三池炭鉱は江戸期から昭和後期まで国内最大級の出炭量を誇り、筑後地方の経済と文化を支えた。炭坑節は炭車押しや石炭切りの動作を取り入れた踊りが特徴で、戦後には全国の盆踊りで親しまれるスタンダード曲となった。夕張や池島など炭坑の名を替えて地域バージョンが派生したため混同されがちだが、原曲は三池炭鉱を歌い込んでいる点が決定的な違いである。歌詞に登場する月は、夜勤に従事する坑夫たちの休息と希望を象徴し、踊りで腕を大きく回す振りは炭車を押す力感を演出している。
Q8 : 高知県の『よさこい鳴子踊り』で、踊り手が手に持つ小道具『鳴子』はもともと何のために使われていた農具?
鳴子は竹や檜の板に舌板を取り付け、振るとカラカラと音が鳴る素朴な道具で、もともとは稲作の田んぼでスズメやカラスを追い払う鳥除けとして使用されていた。高知の「よさこい節」をもとに1954年に生まれた『よさこい鳴子踊り』では、この農具をカラフルに塗装し、リズムを刻む打楽器として転用した。踊り手は右手と左手で異なるタイミングで鳴子を打ち鳴らし、ステップや隊形変化にアクセントを与える。農村の生活道具を舞台芸能へ昇華した例として文化的価値が高く、現代のYOSAKOI祭りでも必携アイテムとされる。落花生の脱穀は千葉の農具「タコ」など別物、綿打ちは木槌、草刈りは鎌で行うため、鳴子の本来用途とは異なる。
Q9 : 徳島県の阿波踊りで、踊り手と観客が一体となるときに最もよく叫ばれる掛け声はどれ?
阿波踊りの掛け声として最もポピュラーなのが「ヤットサー」である。「ヤットヤット」とも呼ばれ、踊りの節目で囃子方が声を張り上げると踊り手や観客が呼応し、場の熱気が一気に高まる。ほかにも「ア、ヤットサーヤットサー」など変化形はあるが、共通しているのは拍子を取りながら互いを鼓舞する役割だという点である。徳島市の本祭では大半の連がこの掛け声を使用し、鳴り物や足拍子と一体になってリズムを作り出す。これにより踊り子は一層軽快な身のこなしとなり、観客も手拍子でリズムに乗る仕組みになっている。阿波踊りの歴史とともに受け継がれてきた「ヤットサー」は、いわば徳島の夏を象徴するサウンドアイコンといえる。
Q10 : 北海道の民謡踊り「ソーラン節」で、振り付けの中核をなす動作は何を模したもの?
「ソーラン節」は北海道日本海側のニシン漁で歌われた船漁歌が原型で、踊りでは漁師が海に仕掛けた網を力強く引き上げる「ニシンの網引き」の動作を大胆に取り入れている。踊り子は足を大きく開き、腰を落として両腕を前後に振り、実際に重い網を手繰り寄せる所作を表現することで豪快さを演出する。1992年に札幌で始まった「YOSAKOIソーラン祭り」でもこの網引きの振りは大切にされ、各チームがアレンジを加えながらも基本の力感を残している。農作業の稲刈りや茶摘みの所作を用いる民謡踊りも存在するが、ソーラン節の主題はあくまで海の男たちの労働であり、北の海とニシン漁の歴史を今に伝える要素として欠かせない。
まとめ
いかがでしたか? 今回は民謡踊りクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は民謡踊りクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。