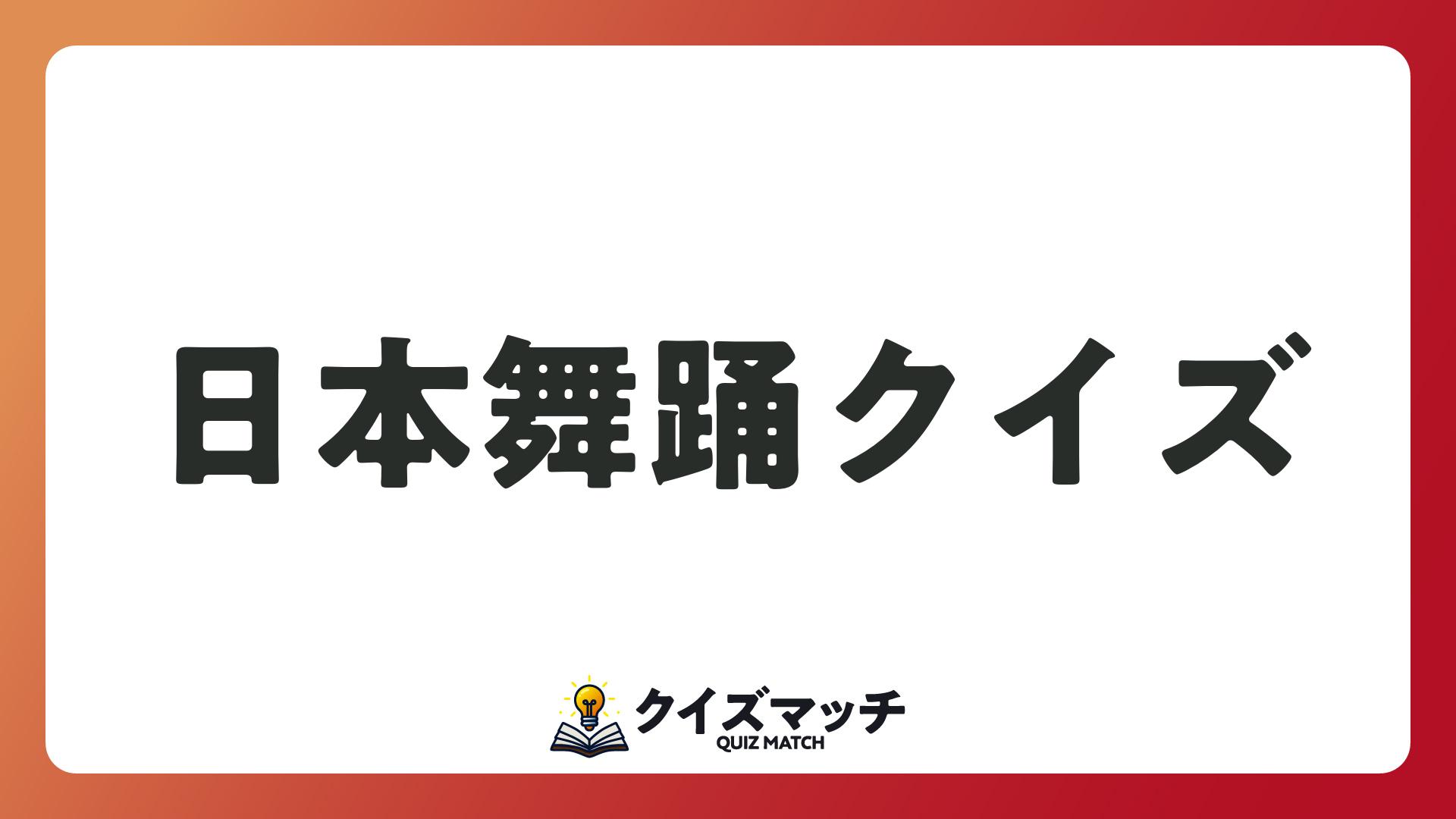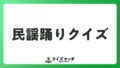日本舞踊は、長い歴史と伝統を持つ芸能で、その美しく繊細な所作や振付は世界的にも高い評価を受けています。本記事では、この日本舞踊についての知識を問うクイズを10問ご用意しました。歌舞伎や能楽などの伝統芸能との関係、流派の特徴、踊りの様式など、日本舞踊の奥深い世界に迫ります。日本文化に興味のある方はぜひお試しください。
Q1 : 江戸時代後期、歌舞伎の所作事が町人文化の中で独立し形成された舞踊形態はどれ?
江戸市中の芝居小屋で生まれた所作事は、幕間を彩る娯楽として人気を集め、次第に役者以外の町人や武家の子女が稽古を行う習い事へ発展した。三味線音楽と結びつきつつ振付が体系化され、師匠が免状を出す制度が整うことで歌舞伎から独立した芸能となり、日本舞踊と総称されるようになる。能楽は室町期成立、琉球舞踊は王府儀礼、剣舞は詩吟武芸系統で出自が違うため、設問の正解は日本舞踊である。
Q2 : 足裏を床から離さずに滑らせるように進む、日本舞踊特有の歩行法は何と呼ばれるか?
すり足は上体を揺らさず静かな情景を表出するための基本歩法で、膝を軽く曲げて腰を沈め、足裏全体を畳や板の間に密着させながら前後左右へ動く。裾が乱れず着物の柄も美しく見え、舞台の余韻や間合いを繊細にコントロールできる利点がある。かけ足は素早い移動、逆足は能で後退する歩み、ふみ込みは強く踏み鳴らす動作でいずれも性質が異なる。よって問われる歩法はすり足である。
Q3 : 座敷で正座姿勢のまま、繊細な手先の動きで情景を描く上方発祥の日本舞踊様式はどれ?
地唄舞は江戸後期の京都で地唄三味線の伴奏に合わせて発達し、狭い座敷という空間条件から立ち上がらずに踊る静謐な表現を確立した。舞手は膝行や手先の小さな角度変化で四季や恋慕を描写し、高度な間と呼吸で観客の想像力を喚起する。連舞は複数人数の群舞、奉納舞は神前への芸能奉仕、地方舞は民謡系統の舞踊で趣旨が異なるため、設問が求める上方座敷舞の名称は地唄舞となる。
Q4 : 歌舞伎俳優・坂東三津五郎の系統を継ぎ、扇を用いた力強い舞が特徴の流派はどれ?
坂東流は初代坂東三津五郎の芸風を継承し、扇子を大きく使った豪快な振付と早変わりを得意とする流派である。明治期に九世坂東三津五郎が正式に創流し、今日まで歌舞伎的な立役踊りを重視する路線を守っている。西川流は名古屋発祥で女方舞の優雅さ、花柳流は写実劇的な演目構成、山村流は地唄舞中心と特色が異なる。扇さばきの力強さを問う本問の条件に当てはまるのは坂東流だけである。
Q5 : 顔や視線を正面に据えたまま肩と上体を左右に回転させ、静止して見栄えを作る歌舞伎由来のポーズは何と呼ばれるか?
見得は歌舞伎の立役が感情の頂点で行う決定的ポーズで、日本舞踊でも芝居仕立ての演目や立役踊りで踏襲される。足を大きく開き重心を低くして腕を張り、目を見開いたまま数秒間静止し、拍子木や太鼓の強い音で観客の視線を集中させる。これにより物語の緊迫感や人物の内面が強調される。構えは準備姿勢、団扇は小道具、行儀は作法の総称であり、固有名詞として当てはまるのは見得である。
Q6 : 次のうち、日本舞踊の主要五大流派に含まれないものはどれ?
花柳・藤間・若柳・西川・坂東の五大流派は、江戸期から続く規模の大きな古典流派で、国立劇場の公演や歌舞伎舞踊の舞台でも中心的存在となっている。一方、西崎流は昭和後期に洋舞を学んだ西崎翠が創設した比較的新しい流派で、会員数や歴史的な上演実績が五大流派に及ばないため対象外となる。こうした成立年代・実演数の差異から、西崎流が五大流派に含まれないことが明確であり、本問の正答になる。
Q7 : 日本舞踊の演目「藤娘」や「鷺娘」の伴奏に最も多く用いられる歌舞伎音楽の流派はどれ?
長唄は江戸中期に三味線音楽として確立し、軽快で歯切れの良い節回しが踊りの振付と同期しやすい点から日本舞踊と密接な関係を築いた。代表曲には「藤娘」「越後獅子」「勧進帳」などがあり、いずれも舞踊家の稽古で最頻演される。常磐津や清元は語り物色が濃く義太夫は文楽由来で音楽の性質が異なるため、幅広い演目で汎用されるのは長唄である。したがって長唄が正解となる。
Q8 : 男性役の勇壮さを際立たせる日本舞踊の踊り方で、腰を低く構え大きな振りを見せる様式は何と呼ばれるか?
立役踊りは歌舞伎の立役に由来し、武士や荒事の人物像を力強い所作で示すことを目的とする。膝を深く割って低い重心を保ち、腕を直線的に伸ばして見得を切るなどダイナミックな動きが特徴。これに対し女方踊りは柔和な手先、しっとり踊りは情緒重視、はんなり踊りは上方の優美さを指す語で方向性が異なる。勇壮さと豪快な動きを問う設問条件に合致するのは立役踊りである。
Q9 : 長唄舞踊「京鹿子娘道成寺」で、白拍子花子が本舞台で用いる丸く彩色された被り物はどれ?
京鹿子娘道成寺は安珍清姫伝説を題材にした歌舞伎所作事で、踊り手は白拍子姿の花子として登場する。前半の華やかな場面で花子が頭上に被り、回転させながら踊るのが色鮮やかな造花で飾られた花笠である。花笠を用いることで季節感や女性の可憐さを強調し、後半の鐘入りの劇的展開との対比を作る。綾羅は布、手甲は腕具、大扇は終盤の小道具であり、設問の条件に当てはまるのは花笠だけである。
Q10 : 舞台用に骨組みが太く、重さで手先の動きを際立たせる日本舞踊の扇子を一般に何と呼ぶか?
舞扇は舞台上で遠目にも鮮やかに見えるよう骨を厚くし、金銀箔や大胆な絵柄を施した専用の扇子である。川・波・雪・月などを象徴的に表すシンボルとして頻繁に用いられ、重さがある分だけ手首のスナップが利き、動きの余韻が美しく見える効果がある。囃子扇は囃子方の指揮用、稽古扇は軽量で装飾が簡素、茶扇は茶道の礼法用と用途が異なるため、舞台表現に最適なのは舞扇である。
まとめ
いかがでしたか? 今回は日本舞踊クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は日本舞踊クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。