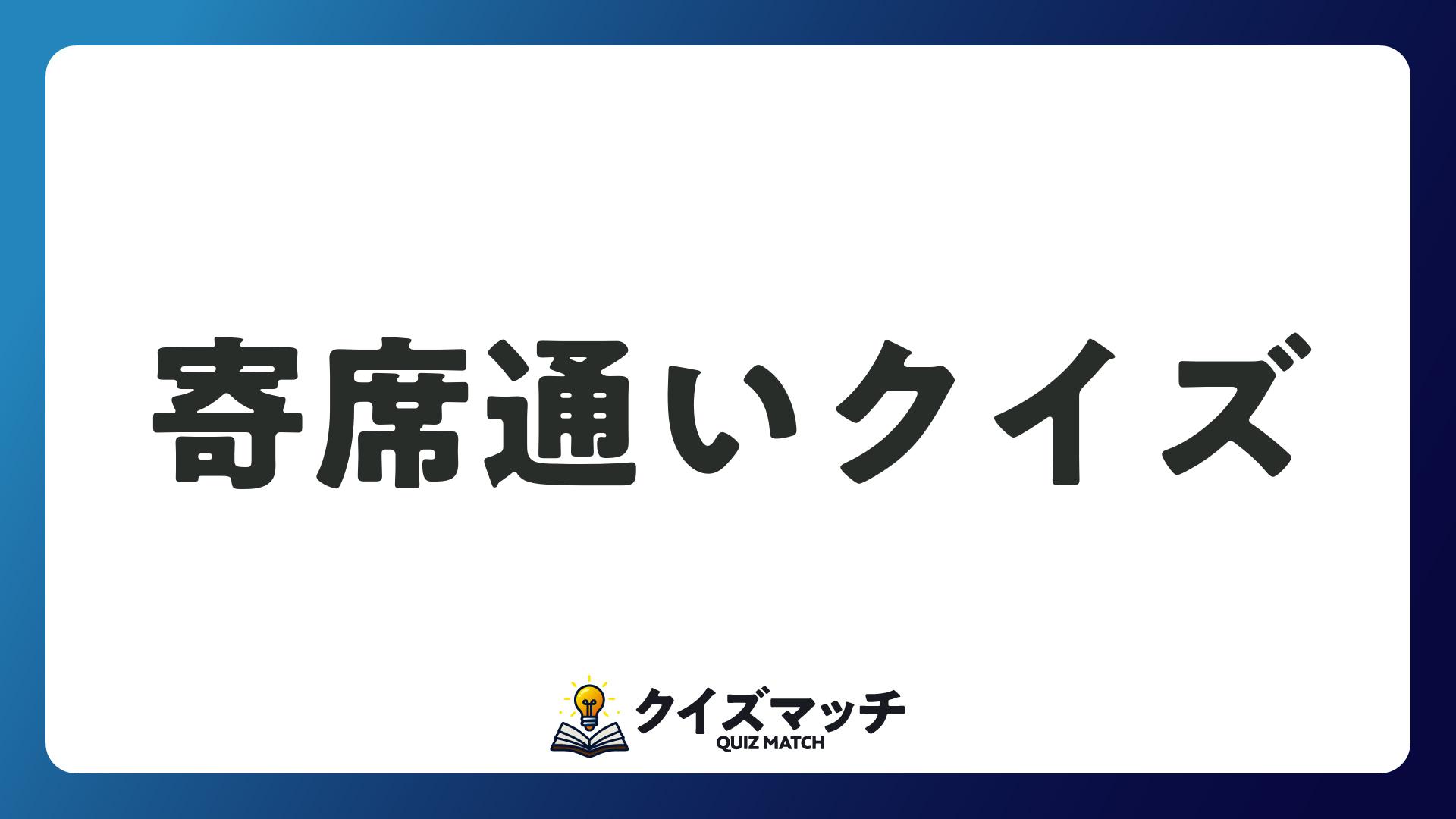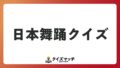昨今、テレビや動画配信サービスでは落語が注目を集めているが、落語の本場は間違いなく寄席だ。開口一番の前座から、中流派の二ツ目、そして実力派の真打に至るまで、寄席はさまざまな顔ぶれを楽しめる場所である。寄席の魅力を理解するうえで、ちょっとしたマナーや知識を身に付けておくと、寄席通いがより一層楽しくなるはずだ。そこで本記事では、寄席通いに役立つクイズを10問ご紹介する。寄席通いのコツをつかみ、定席や囃子、役柄といった寄席文化の奥深さを体感していただきたい。
Q1 : 寄席で使われる『橘流寄席文字』を現在の家元として継承している書家は誰か?
橘流寄席文字は戦後の名筆家・初代橘右近が考案し、太く迫力ある筆致で観客を呼び込む意匠として広まった。二代目を襲名したのが橘右門、現在は三代目の橘右橘が家元として看板やめくり、チラシを手掛ける。寄席文字は書き手ごとに画の跳ねや払いが微妙に異なり、常連はめくりを見ただけで誰の筆かを当てることもある。書家の系譜を知ると、文字から寄席文化の歴史も読み取れる。寄席文字のワークショップも開催されており、筆を持ってみると書体の難しさと粋の感覚を実感できる。
Q2 : 寄席で開場を知らせるために屋根に設置された太鼓で打たれる合図は何と呼ばれる?
寄席の開場45分前ほどに鳴る『一番太鼓』は、テンテンツクツクテンという独特のリズムで界隈に今日の興行開始を告げる。これを合図に木戸口が開き、常連客は好きな席を確保するため早足で向かう。『揚幕太鼓』は開演直前、『追い出し太鼓』は終演後に叩かれ役割が異なる。『寄せ太鼓』は総称だが、開場の合図としては一番太鼓と言うのが通例であるため覚えておくと便利だ。太鼓の音色を聞くと江戸から続く時間の流れを感じられ、耳で味わう寄席文化の奥深さに気づく。
Q3 : 落語『芝浜』で魚屋の勝五郎が拾う大金は何に入っていたか?
『芝浜』は年の瀬に語られることの多い名作人情噺。酔っ払った勝五郎が夜明けの芝浜で革の財布を拾い、中には30両の大金が入っていたと語られる。桐箱や風呂敷では砂浜で簡単に見つけづらく、重量感の描写にも不自然。信玄袋は巾着の一種で劇中には登場しない。革財布なら手ざわりや重みを表現しやすく、後に妻が夢だと諭す場面でも説得力が出るため、古今亭志ん生以来の定番描写となっている。オチでは財布を返す決断が描かれ、革の手触りが夢だったかどうかが曖昧に語られることで、聴衆に余韻と教訓を残す。
Q4 : 寄席で最初に登場する「開口一番」を務めるのは通常どの階級の落語家か?
寄席は一日を通して興行が続くため、客席が温まっていない開演直後には経験の浅い前座が短い時間で口火を切る「開口一番」を務めるのが慣例。前座は自分の高座だけでなく、太鼓の合図や座布団運びなど裏方仕事も担当し、修業の一環として場の空気や進行を学ぶ。二ツ目以上が開口を務めることは基本的にないため、階級を覚えておくと番組表が読みやすくなる。なお、開口一番の後は色物や中堅の落語が続き、仲入り、真打へと盛り上げていく構成が定番である。
Q5 : 東京四大定席の一つ「鈴本演芸場」があるのはどの街か?
東京には浅草演芸ホール・新宿末廣亭・池袋演芸場・鈴本演芸場という四つの定席があるが、1867年創業の鈴本演芸場はJR上野駅や東京メトロ上野広小路駅にほど近い上野に位置する。浅草演芸ホールは浅草寺雷門のそば、新宿末廣亭は新宿三丁目、池袋演芸場は池袋東口と所在地が異なる。寄席めぐりをするときは地名と最寄り駅を結び付けて覚えると移動がスムーズになり、はしご観覧も楽しめる。
Q6 : 寄席で終演を知らせる『追い出し』として最も一般的に演奏される寄席囃子はどれ?
寄席囃子には場面ごとに定番曲が決まっており、終演時に客を自然に出口へ誘導する『追い出し』で演奏されるのが『さわぎ』である。軽快なテンポと景気の良い掛け声が特徴で、客席に余韻を残しつつ切り替えを促す役目を果たす。『大名行列』や『勧進帳』も寄席囃子だが主に出囃子や幕間で使われ、『越天楽』は雅楽系の演目で用いられることが多い。曲調の違いを聴き分けられると寄席通いの楽しみが一段深まる。囃子まで耳を傾けると、終演間際のサインを聞き逃さずに荷物をまとめられるので、常連は太鼓と笛の入り方で帰り支度を始めるタイミングを計る。
Q7 : 寄席のプログラムで、落語と落語の間に漫才・奇術などを挟む演者を何と呼ぶ?
寄席では落語だけでなく多種多様な芸が楽しめるよう組まれており、落語以外の芸を披露する出演者全般を『色物』と呼ぶ。色物には漫才、曲芸、講談、紙切り、奇術、俗曲などが含まれ、観客の気分転換や舞台転換の役割を担う。前座は修業中の落語家、トリは番組最後の真打、中トリは中盤の目玉を務める落語家を指し、いずれも落語に分類される。色物の豊富さこそ寄席文化の醍醐味で、曜日によって顔ぶれが変わる点も常連の楽しみとなる。色物が充実した日を狙って足を運ぶと、普段見られない紙切りや珍芸に遭遇することもあり、寄席の幅広さを体感できる。
Q8 : 東京の寄席で午後と夜の部の境目に設けられる短い休憩時間は何と呼ばれる?
通し興行の寄席では中盤で10~15分ほど休憩を挟み、それを『仲入り』と呼ぶ。観客はトイレや売店、喫煙所に立ち寄り、演者は髪や衣装を整え、高座の座布団やめくりも入れ替わる。仲入りを境に後半は実力派や真打が続くため、番組の山場が一気に近づく。『昼休憩』や『寄席休み』といった語は使われず、『残業』は持ち時間を超えた場合の伸びを指す別の専門用語であることを覚えておくと会話に役立つ。仲入りを機に客席を回る飴売りや厳禁の飲食物案内など、寄席ならではの風景も見逃せないポイントだ。
Q9 : 上方落語の定席『天満天神繁昌亭』がある都市はどこか?
天満天神繁昌亭は2006年、大阪市北区の大阪天満宮参道に開業した戦後初の上方落語専用常設寄席で、上方落語協会が運営する。京都や神戸にも落語会場はあるが、毎日興行を行う定席の形態を取るのは繁昌亭のみ。名古屋には『大須演芸場』という寄席があるものの、運営主体も場所も異なる。遠征観覧の際に都市名を取り違えると開演時間に間に合わないので、所在地の確認は必須だ。大阪観光と絡めて訪れる場合は天満宮の祭事や天神橋筋商店街の食べ歩きと合わせると一層楽しめる。
Q10 : 寄席の舞台袖に掲げられ、出演者の名前が書かれた札を指す言葉はどれ?
寄席では今舞台に出ている演者を観客が把握できるよう、名前を書いた札を順に差し替える。この札を『めくり』と呼び、黒か紺の紙に太い筆で寄席文字が書かれるのが特徴。隣の『見台』に置く演目名『外題』や、舞台そのものを示す『高座』、建物正面の『かんばん』とは別物。めくりを目で追うと番組進行がわかり、誰が登場しそうか予測する楽しさが増すため、常連客は必ず確認する。寄席文字で書かれためくりが次に落ちる瞬間を眺めていると、舞台袖の緊張感まで伝わり、待ち時間さえ演出の一部になる。
まとめ
いかがでしたか? 今回は寄席通いクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は寄席通いクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。