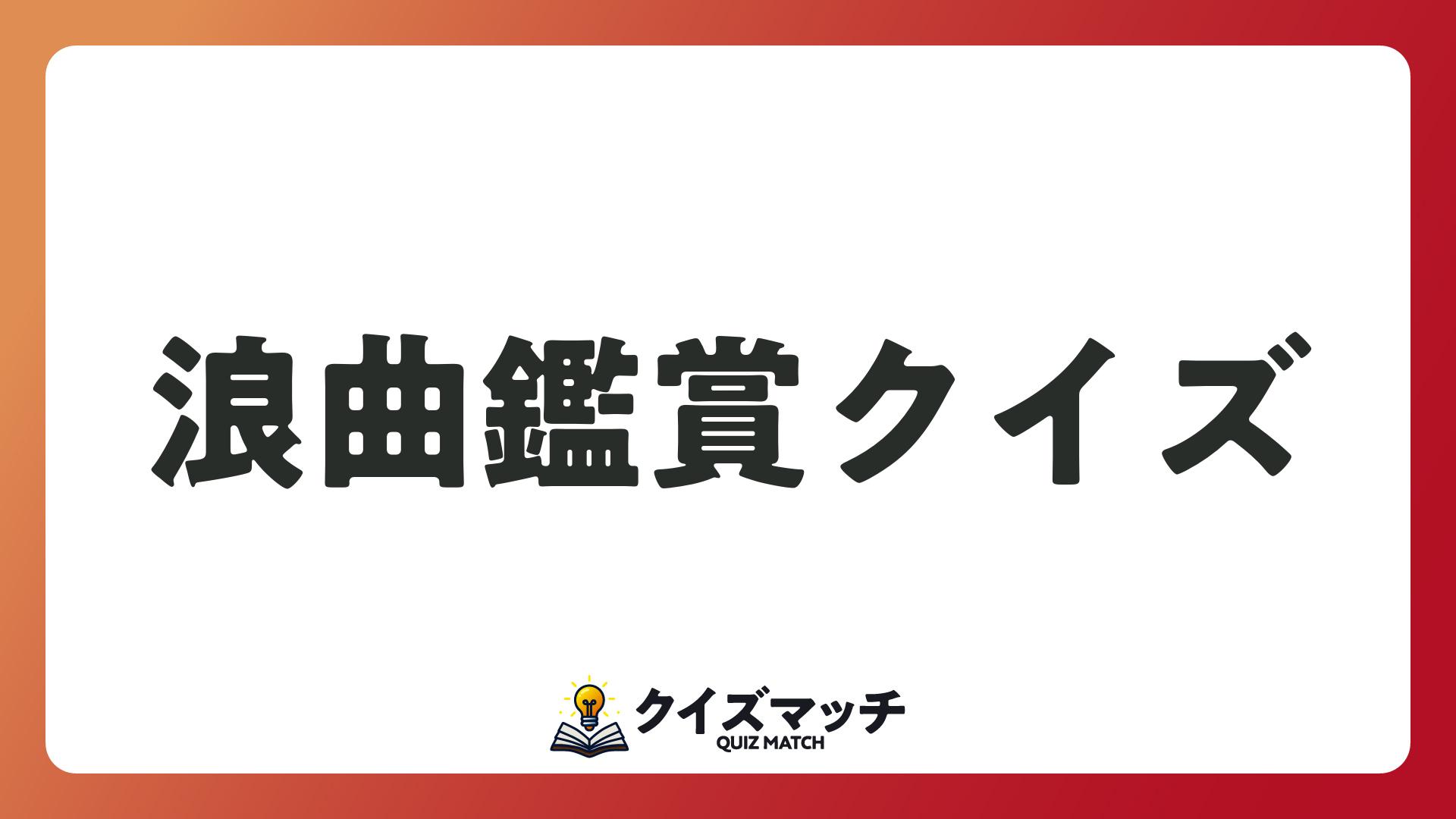浪曲は日本に古くから伝わる語り物芸能で、その歴史は長く多彩な魅力に溢れています。三味線の伴奏に合わせて語り手が物語を披露する浪曲には、独特の語り口調や躍動感があり、聴衆を熱狂させてきました。本クイズでは、浪曲の歴史や演者、特徴など、この伝統芸能の魅力に迫ります。浪曲のエッセンスを存分に味わえる内容となっておりますので、浪曲の世界を探検してみましょう。
Q1 : 浪曲師が多数加盟し、寄席や学校公演の斡旋、後進育成などを行う団体で、1949年に設立されたのはどれか?
日本浪曲協会は戦後の浪曲界の再建を目的に1949年に発足した全国団体で、東京・大阪・名古屋など地域を越えて浪曲師や曲師が所属する。会員に出演機会を提供する定席寄席「木馬亭」(浅草)の運営、地方巡業や学校芸術鑑賞教室の派遣のほか、若手の研修制度や音源・資料の保存事業も手がける。落語協会や日本漫才協会、上方演芸協会はそれぞれ落語、漫才、上方芸能の団体であり、浪曲師の公式団体として歴史と規模を持つのは日本浪曲協会である。
Q2 : NHKラジオの長期連続放送で『赤穂義士伝』を語り、高い聴取率を記録したことで知られる浪曲師は誰か?
二代目東家浦太郎は昭和20年代後半から30年代にかけてNHKラジオで『義士伝』を長期にわたって語り続け、一日平均20%を超える高聴取率を叩き出した名人である。義士一人ひとりの人間像を掘り下げる細やかな節と泣き節の巧みさが評価され、放送後にレコードや書籍も多数発売された。広沢虎造は清水次郎長もの、玉川勝太郎は『天保水滸伝』、伊丹秀敏は叙情浪曲の名手だが、義士伝で国民的支持を得たのは東家浦太郎である。
Q3 : 義太夫三味線を用い、人形劇として発展した芸能で、浪曲と同じく物語を語る要素を持つものはどれか?
文楽は三味線と太夫の語りで精巧な人形を操り物語を展開する日本独自の総合芸術で、正式には人形浄瑠璃文楽と呼ばれる。語り物としての性格や三味線伴奏という点で浪曲と共通項が多く、浪曲師が文楽や義太夫の語法を研究し節回しに応用する例も少なくない。能楽は笛や鼓を用いる歌舞劇、歌舞伎は役者が演じる芝居、新内節は浄瑠璃系の細棹三味線音楽でいずれも人形劇ではない。したがって条件に合致するのは文楽である。
Q4 : 津軽三味線やロックバンドとのコラボで知られ、現代的なアプローチで浪曲を広めた2000〜2010年代の浪曲師は誰か?
国本武春は「浪曲でもロックでもブルースでも語りは語り」という理念を掲げ、津軽三味線を抱えて自作曲を交えながら浪曲を語る“ニューウェーブ浪曲”を確立した。1987年デビュー後、ロックバンドとの共演や海外フェス出演を行い、若者層に古典芸能の入り口を開いた功績が大きい。神田伯山や春風亭一之輔は講談・落語の噺家、玉川奈々福は女性浪曲師として活躍するが、ロックコラボでメディアを沸かせたのは国本武春である。
Q5 : 「浪曲」という名称が『浪花節』に代わって一般化し始めたのは、社会やメディアの近代化が進んだどの時代頃か?
19世紀末から20世紀初頭の明治時代は、新聞・雑誌・レコード・演芸場など近代的媒体が急速に整備され、芸能も名称を統一しブランド化する動きが起こった。浪曲もそれまで大阪方言色の強い『浪花節』と呼ばれていたが、東京進出や全国巡業の拡大により、より洗練された印象を与える『浪曲』という表記が業界紙やポスターに採用され始める。大正期には完全に定着するが、呼称変化の端緒は文明開化の影響が色濃い明治時代に求められる。江戸期にはまだ芸能自体が成立しておらず、大正期は普及後であるため誤答となる。
Q6 : 浪曲で、語り手を支える三味線伴奏者は何と呼ばれるか?
曲師は浪曲師の語りの節回しや啖呵に合わせて即興的にリズムを刻む専門の伴奏者で、演目の盛り上がりや情景描写を音楽で補強する役割を担う。浪曲では語り手と曲師が二人で一体となった掛け合いを行うため、曲師の技量が演者の魅力を左右するといわれる。囃子方や鳴り物は主に歌舞伎や落語の寄席囃子を担当する奏者、太夫は義太夫節や浄瑠璃の語り手を指す語で、浪曲の伴奏者を示す呼称ではないことから誤答となる。
Q7 : 明治後期から大正期にかけ「浪花節の神様」と呼ばれ、浪曲の大衆的人気を決定づけた名人は誰か?
桃中軒雲右衛門は明治30年代にレコードと巡業を通じて全国的な爆発的ブームを起こし、観客から「浪花節の神様」と称された。張りのある高音と劇的な節回しは従来の語り物の枠を超え、庶民にカタルシスを与えたと評される。雲右衛門の成功によって浪曲は庶民の娯楽として定着し、スター制度や興行システムの確立にも大きく寄与した。浪花亭駒吉は幕末義士伝で知られるが規模は雲右衛門に及ばず、港家小ゆきは女性浪曲師、広沢虎造は後年の名人で清水次郎長もののヒットで知られるが「神様」とは呼ばれなかった。
Q8 : 浪曲の古い呼称として明治時代に広く用いられた言葉はどれか?
浪曲は発祥当初、大阪を中心に興行されたことから「浪花節(なにわぶし)」という呼称が一般的だった。明治末に東京進出が進むと、より洗練された印象を持たせる目的で「浪曲」という名称がポスターや新聞に用いられ、昭和期には公式名称として定着する。義太夫節は文楽や歌舞伎の浄瑠璃、江戸節は江戸端唄、琵琶法師は琵琶を伴奏に物語を語る盲僧のことで、浪曲の旧称ではない。したがって正解は「浪花節」である。
Q9 : 広沢虎造が得意とし、清水次郎長の子分・森の石松の活躍を描く代表的な演目はどれか?
二代目広沢虎造は昭和初期の放送ブームで一世を風靡した浪曲師で、特に『石松三十石船道中』を中心とする清水次郎長ものの連続口演が人気を博した。石松が大坂・八軒家から三十石船に乗り込み豪快な啖呵を切る場面は、虎造の歯切れのよい江戸弁とケレン味のある節回しで聴衆を熱狂させ、レコードやラジオでも高い売上と聴取率を記録した。赤穂義士伝や天保水滸伝、国定忠治も浪曲の定番演目だが、虎造の代名詞となったのは次郎長シリーズであり、とりわけ『石松三十石船道中』である。
Q10 : 浪曲の高座で観客が演者を激励する定番の掛け声として最も広く知られているものはどれか?
浪曲では観客が感情の盛り上がりに合わせて掛け声を発し、演者と一体になって舞台を作り上げる文化がある。中でも「日本一!」という掛け声は、明治期に桃中軒雲右衛門の人気が頂点に達した際に客席から自然発生し、最上級の賛辞として定着した。節が切れ味よく決まった瞬間や啖呵が気持ちよく響いた直後に飛ぶこの掛け声は、浪曲独特の躍動感を象徴する。ほかの掛け声も使われるが、全国的かつ歴史的な代表格は「日本一!」であり、寄席や舞台、録音にも頻繁に収録されている。
まとめ
いかがでしたか? 今回は浪曲鑑賞クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は浪曲鑑賞クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。