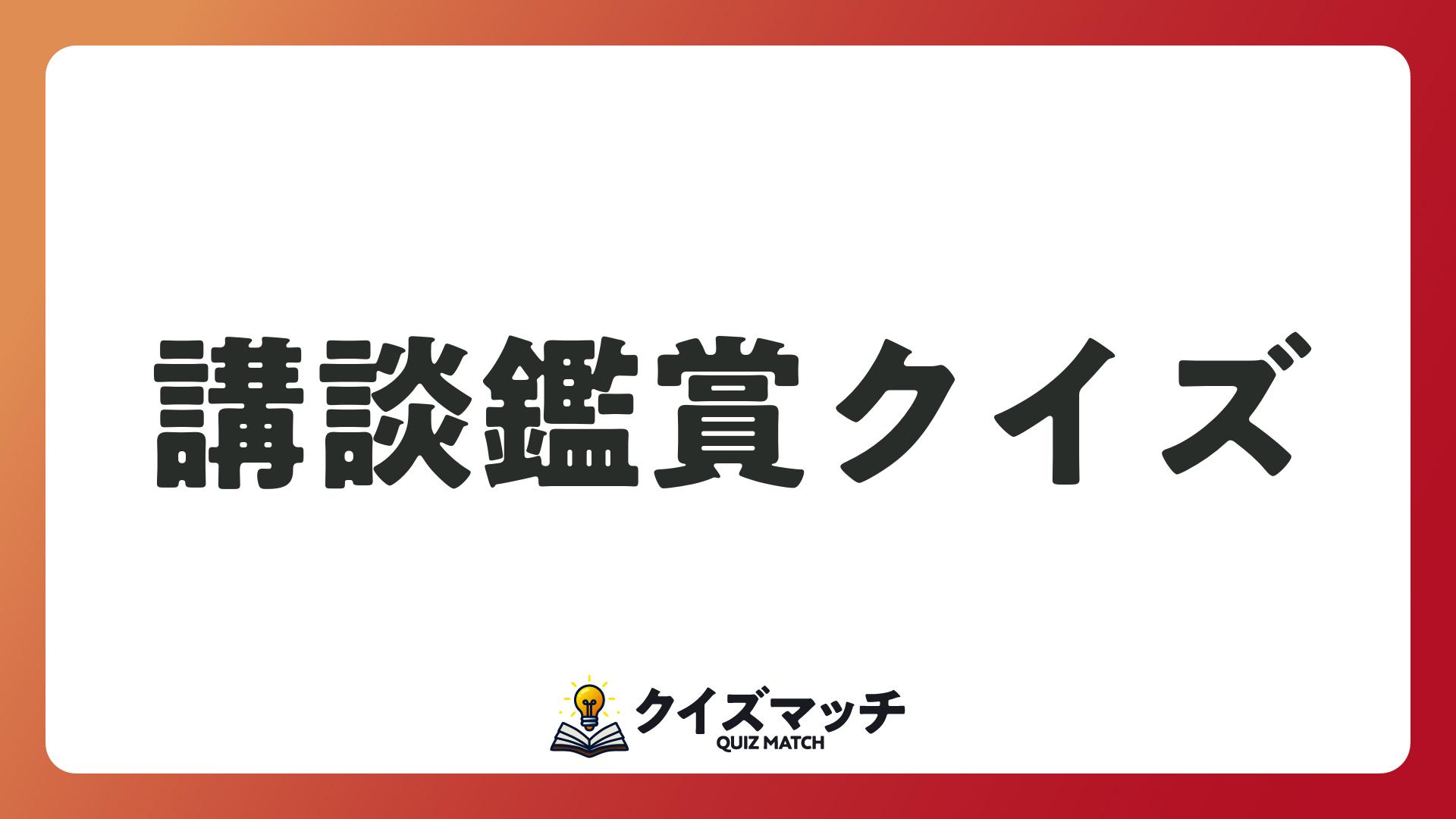講談は、日本の伝統的な語り物芸能の一つです。その独特の話芸と張り扇を使った演出は、聴衆の想像力を呼び起こし、心を引き付けてきました。本記事では、講談の魅力を知るための10問のクイズを取り上げます。演者が使う小道具、定席の呼称、名場面、話型の特徴、有名な講談師など、講談の世界を深く理解する良い機会になるはずです。講談ファンはもちろん、これから講談に興味を持つ人にとっても、充実した内容となっています。是非、楽しみながら講談の世界を探索してみてください。
Q1 : 講談で語られる『寛永三馬術』の一人に数えられる人物で、戸田の渡しで名高い武士は誰か?
寛永三馬術は徳川家光の頃、卓越した馬術を披露した曲垣平九郎、笹尾十郎三郎、大坪半九郎の三人を指す。講談では特に曲垣平九郎が荒川の戸田の渡しを愛馬で一息に駆け抜けた逸話が人気で、張り扇の連打で蹄の音を表現する。荒木又右衛門は鍵屋の辻の決闘、柳生十兵衛は剣豪譚、吉良上野介は忠臣蔵に関連する人物であり、寛永三馬術には数えられない。
Q2 : 講談で用いられる演台のことを何と呼ぶか?
講談師が経机状の台に向かって語るが、その台を釈台と呼ぶ。演者は釈台に膝をつけ、上に番付帳や張り扇を置く。張り扇で釈台を叩くことで鼓動のような音が響き、観客の想像力を刺激する。高座は寄席全体の舞台の呼称、膝隠しは茶道具や落語で使う板、見台は狂言や落語の道具立てを指し、講談固有の用語ではない。釈台こそ講談ならではの象徴的存在である。
Q3 : 明治時代、新聞連載で一大ブームを起こし講談人気にも火を付けた滝沢馬琴原作の長編はどれか?
滝沢馬琴の大長編『南総里見八犬伝』は江戸末期に成立したが、明治に入ると新聞連載や貸本で再ブームが起こり、多くの講談師が抜き読みして人気を博した。八犬士が仁義礼智忠信孝悌の珠を持ち、妖怪や宿敵と戦う波瀾万丈の筋は軍談・怪談・世話物の要素が混交し、聴衆を飽きさせない。東海道中膝栗毛は滑稽本、雨月物語は怪談文学、椿説弓張月は馬琴の別作品であり八犬傳とは別である。
Q4 : 講談の世界で、演者が物語に入る前に述べる挨拶やテーマ提示の部分を何と呼ぶか?
講談では物語の冒頭で演者が観客に挨拶し、演目の時代背景や登場人物を簡潔に示す部分を序口上という。ここで興味を引きつけたうえで「さてその後…」と本編に入るのが型。大団円は物語の最終段、サゲは落語用語でオチ、序口上が終わると本読みへ続く。序口上を巧みに行うことで軍談の難しい固有名詞や歴史的事件も聴衆にすんなり入り、話芸の緩急が一層引き立つ。
Q5 : 昭和期に“講談の神様”と称され、NHKラジオ番組『講談番組』で国民的な人気を博した名人は誰か?
昭和前期から中期にかけてラジオを通じて国民的人気を誇り、“講談の神様”と称されたのが一龍斎貞山である。歯切れのよい間と張り扇の冴えで軍談を立体的に聞かせ、『天保水滸伝』『赤穂義士伝』などの名調子は録音が今も語り草となる。NHKの講談番組では彼の声が昼下がりの茶の間に流れ、高度経済成長期の家庭に歴史ロマンを届けた。神田山陽や宝井馬琴も名人だが“神様”と呼ばれたのは貞山である。
Q6 : 講談で演者が使用する小道具として最も基本的なものは何か?
講談では演者は目の前の卓である釈台を打ち鳴らして調子を取るが、その際に用いるのが張り扇である。竹骨に和紙を張った扇で、語りの山場で「パン」と一打すると客席に緊張感が走り、武士の斬り合いや大岡越前の名裁きといった場面転換を強調できる。鼓や拍子木は歌舞伎、三味線は浄瑠璃や落語の出囃子で用いられるが、講談師は声と張り扇だけで世界を立ち上げる点が特徴。
Q7 : 江戸時代に講談師が集まって定席興行を行った寄席の呼び名として正しいものはどれか?
江戸後期、講談師は「講釈師」と呼ばれ、寺社の境内や辻説法から室内興行へと進出した。その定席が講釈場である。ここでは一日に数人の師匠が入れ替わりで高座に上がり、軍談や政談を語った。芝居小屋は歌舞伎、見世物小屋はサーカス的興行、落語茶屋は俗称で講談の専門施設ではない。講釈場が出来たことで語り物は安定した収入と固定客を得て、町人文化の大きな柱となった。
Q8 : 源平合戦を題材にした講談で、『扇の的』の名場面が登場する演目はどれか?
源平合戦期の名シーン「扇の的」を中心に描く講談は那須与一物語である。屋島の海上で平家が扇を掲げ、それを若武者那須与一が矢で射抜く瞬間の緊迫感は講談の醍醐味。語りでは張り扇の一打で矢が放たれる瞬間を演出し、観客の脳裏に水飛沫や風の音を呼び起こす。木曽義仲旗挙げや曽我物語にも弓矢の場面はあるが、扇の的が物語の核になるのは那須与一なので間違えないよう注意が必要。
Q9 : 講談の話型である『軍談』とは主にどのような内容を語るものか.
講談の演目は大きく軍談・政談・世話物などに分かれるが、その中でも軍談は戦国や源平など武家社会の合戦記を扱う。演者は武将の名乗りや軍勢の進軍を勇壮な口調で語り、張り扇で陣太鼓を模して臨場感を高める。町人の義理人情を描くのは世話物、奉行所の裁きや法廷を描くのは政談、怪談は別系統の怪談講談である。従って軍記物語を主題としたものが軍談である。
Q10 : 講談の名跡『神田伯山』が2020年に六代目を襲名した講談師は誰か?
2020年2月、若手のホープとして注目されていた講談師神田松之丞が真打昇進と同時に六代目神田伯山を襲名し大きな話題となった。伯山の名跡は大正期から続く大看板で、荷が重いとも言われたが、彼は古典演目の活性化と新規客層の開拓を進め、寄席のチケットを連日完売にする躍進を見せている。他の候補の宝井琴鶴や一龍斎貞橘、田辺一邑は実力者だが伯山の名跡を継いではいない。
まとめ
いかがでしたか? 今回は講談鑑賞クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は講談鑑賞クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。