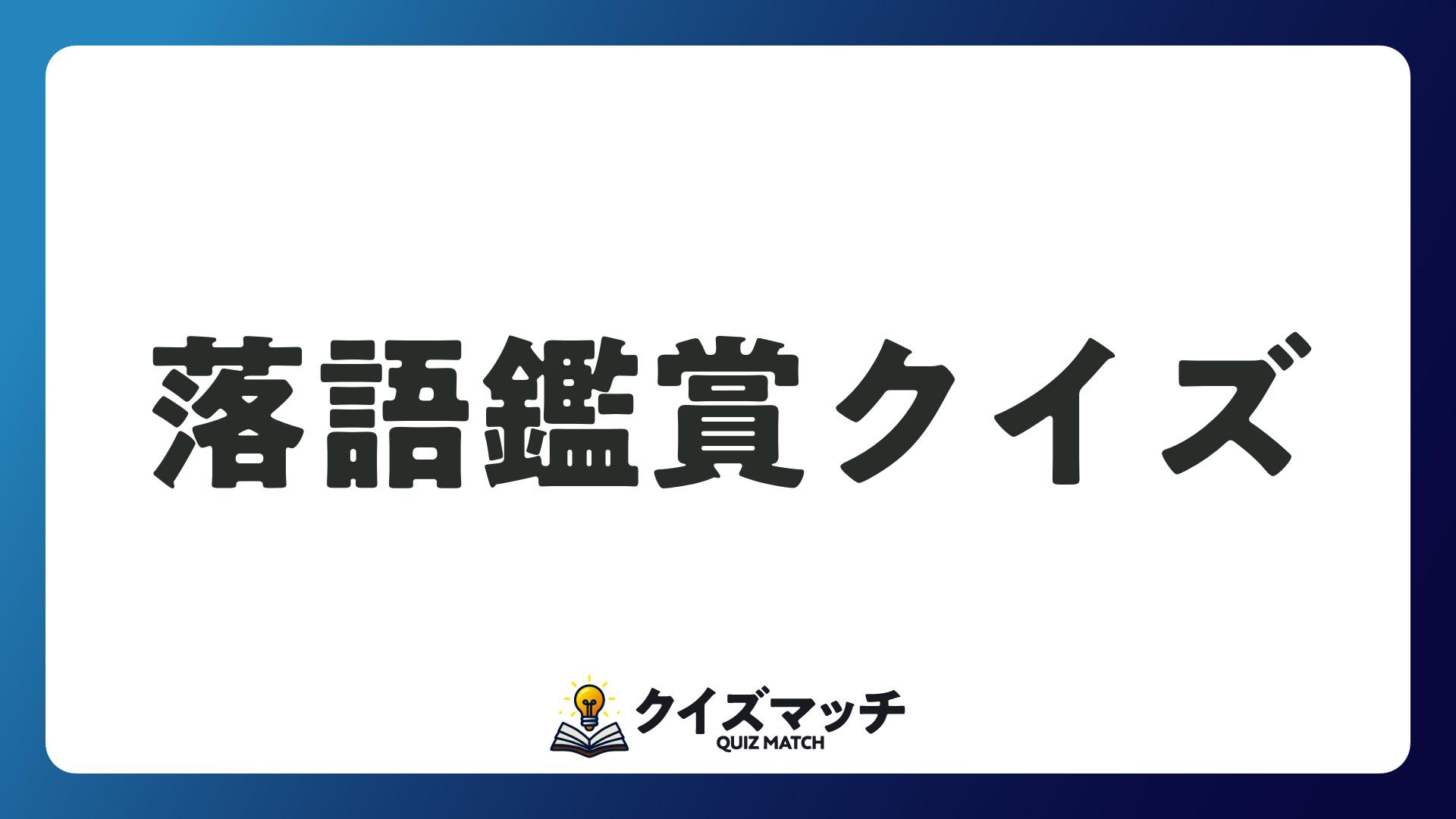落語は日本の伝統的な演芸の一つで、その愉快で哀しい人間観が多くの人々を魅了してきました。この記事では、落語の中に登場する有名なエピソードや隠れた見どころを、クイズを通して楽しく紹介します。江戸時代から受け継がれる落語の世界に、ぜひ足を踏み入れてみてください。落語ファンはもちろん、これから落語を知ろうと考えている方にも、きっと新しい発見がある筈です。
Q1 : 『目黒のさんま』で殿様が最初に秋刀魚を食べて感動する場所はどこ?
『目黒のさんま』は武家社会の身分差を笑いに変えた話で、美食家の殿様が馬で遠乗りした際に目黒の百姓家で焼かれていた庶民の庶菜・秋刀魚を初めて食べ、その脂の香ばしさに感激する。城へ戻った殿様は料理番に命じて高価な秋刀魚を出させるが、蒸して脂を落とした上品な味に失望し「やはりさんまは目黒に限る」と言って家臣を困らせるオチ。したがって殿様が最初に秋刀魚を口にした場所は目黒の野辺である。
Q2 : 『らくだ』で長屋の乱暴者“らくだ”が死んだ直後、香具師の半次に脅され葬儀の段取りをさせられる気弱な屑屋の名は?
『らくだ』は強烈なブラックユーモアと罵詈雑言で知られ、長屋一の乱暴者“らくだの馬”が死んだところから始まる。香具師の半次は面倒を避けるため、通りかかった気弱な屑屋・久六を脅して湯灌から香典集め、火葬場への運搬までこき使う。屑屋は怯えながらも嫌々従い、最後は棺を担いで酒盛りに付き合わされる。屑屋の人物名が久六である点は噺の中盤以降も繰り返し呼ばれ、酔った久六が狂乱する場面が聴かせどころ。ゆえに正解は屑屋の久六となる。
Q3 : 『天狗裁き』で夢見の真偽を決めるために男が連れて行かれる“裁判所”のような場所で裁きを下すのは誰?
『天狗裁き』は些細な夢の内容を巡る夫婦喧嘩が町内を巻き込み、ついには異界の天狗の法廷にまで発展するという荒唐無稽な噺。亭主は「夢の中で女と会った」と語り、女房が怒ったことから口論が拡大する。近所の連中も巻き込み、誰一人夢の真相を解明できずとうとう山中へ連行され、天狗が公正な裁きを行うという流れになる。裁判長役の天狗は両者の言い分を聞くが、夢の中のこととあって決着がつかず、最後は全員が目を覚まし“夢だった”と落ちる。裁きを下す主体が天狗であることが題名に対応している。
Q4 : 『子別れ』で酒癖の悪さから妻子に家を追い出される大工の名前(通称)は?
『子別れ』は“上・中・下”の三段構成で演じられる人情噺で、冒頭では大工の熊(熊五郎とも)が酒癖の悪さと遊郭通いで、妻おたきに三行半を突き付けられ幼い倅と離れて暮らす羽目になる。中では熊が改心を誓い、下では数年後に立派に成長した息子と偶然再会する展開が涙を誘う。熊五郎という俗な名が乱暴な性格を象徴し、また“熊”と“子別れ”のタイトル対比がドラマを際立たせる。呼称は“大工の熊”または“熊さん”が一般的で、正解は熊五郎である。
Q5 : 『転失気』で和尚が意味も知らずに使用し、医者に尋ねる言葉「転失気」とは実際には何を意味する?
『転失気』は言葉の意味を知らず権威に頼る人間の浅はかさを描く滑稽噺。和尚は小僧が転失気を出したと聞き咄嗟に叱るが、実は自分もそれが何か知らない。寺の恥になると医者にこっそり意味を尋ねるが、医者も分からず学者へ回される。最終的に学者が唐代医書から「転失気は屁を指す」と教え、和尚は己の無知を悟る。僧侶や医者といった知識層が笑いの対象になることで、庶民は痛快さを覚える。よって転失気とはおならであり、選択肢2が正解である。
Q6 : 『寿限無』で羅列される名前の中に実際には含まれない語句はどれ?
『寿限無』は長すぎる名をめぐるオチが有名な子供噺で、名称部分は口伝で多少差異があるものの「風来末」はあっても「風来松」という表記は伝統的な定型には登場しない。古典本文では「…雲来末風来末」と末が重なる形で韻を踏むため、松に置き換えると語感が崩れる。落語家によっては独自のアレンジを入れることもあるが、標準的な台本には「風来松」は含まれない。よって選択肢4が正しい。
Q7 : 『時そば』で男が“へい、今何時だい?”と聞いてそば代をごまかすが、本来の一杯の値段はいくらだった?
『時そば』では江戸時代の貨幣感覚や屋台そばのやり取りが笑いどころで、そば屋は一杯十六文と告げる。男は勘定を数える際に「今何時だい」と夜更けの刻を尋ね、その瞬間に一文を抜いて支払いをごまかす構造になっている。翌日真似した友人は昼間に同じ質問をして失敗し、そば屋に十六文きっちり払わされてオチになる。金額が十六文でなければ一文抜くギャグが成立しないため、正解は十六文となる。
Q8 : 『芝浜』で魚屋の勝五郎が砂浜で拾い、後に妻に夢だったと諭される財布に入っていたとされる金額は?
『芝浜』は人情噺の代表格で、飲んだくれの魚屋・勝五郎が芝の浜で大金の入った財布を拾い改心する物語。財布にあった額は演者により少し差があるものの、一般的な寄席で用いられる標準口演では「四十両」と語られる。勝五郎が四十両という当時では家が建つほどの大金を落としたと知り、欲に負けかける心理が描かれるのが聴きどころ。のちに妻が夢だったと嘘をつき、勝は酒を断ち真面目に働く決意を固める。四十両が大金である点が心情の転換装置となっている。
Q9 : 『饅頭こわい』の噺で、若者が仲間に嘘をついてまで最後に怖いと主張する飲食物は何?
『饅頭こわい』は人間の“好きなものほど怖いと言ってからかう”心理を笑いに転化した古典で、落語家によっては題名を『饅頭恐い』とも表記する。若者は本当は大好物の饅頭を思い切り食べるために「饅頭が怖い」と嘘をつき、仲間が大量に差し入れすると一人で平らげてしまう。満腹になった後、さらに恩を着せて茶まで飲もうとし「今度は熱いお茶が怖い」と言って締めくくる。この“熱いお茶”が新たな餌として提示されることで、観客は若者の貪欲さと狡猾さに二度笑う構造になるため、正解は熱いお茶となる。
Q10 : 落語『死神』で死神の居場所を判別するために使われる道具は?
『死神』は西洋の民話を下敷きに円朝が脚色した怪談噺で、貧乏な男が死神と契約し命を救う商売を始める。病の床の枕元に死神が立つ位置によって助かるかどうかが決まるが、それを可視化する象徴としてベッドサイドに灯る“ろうそく”が登場する。ろうそくの長さが命の残り時間を示しており、芯が短ければ早く消え寿命が尽きる。男は他人のろうそくと自分のろうそくを取り替えようとして失敗し、闇へ落ちる結末になる。よって死神の居場所=命の残りを知る鍵はろうそくである。
まとめ
いかがでしたか? 今回は落語鑑賞クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は落語鑑賞クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。