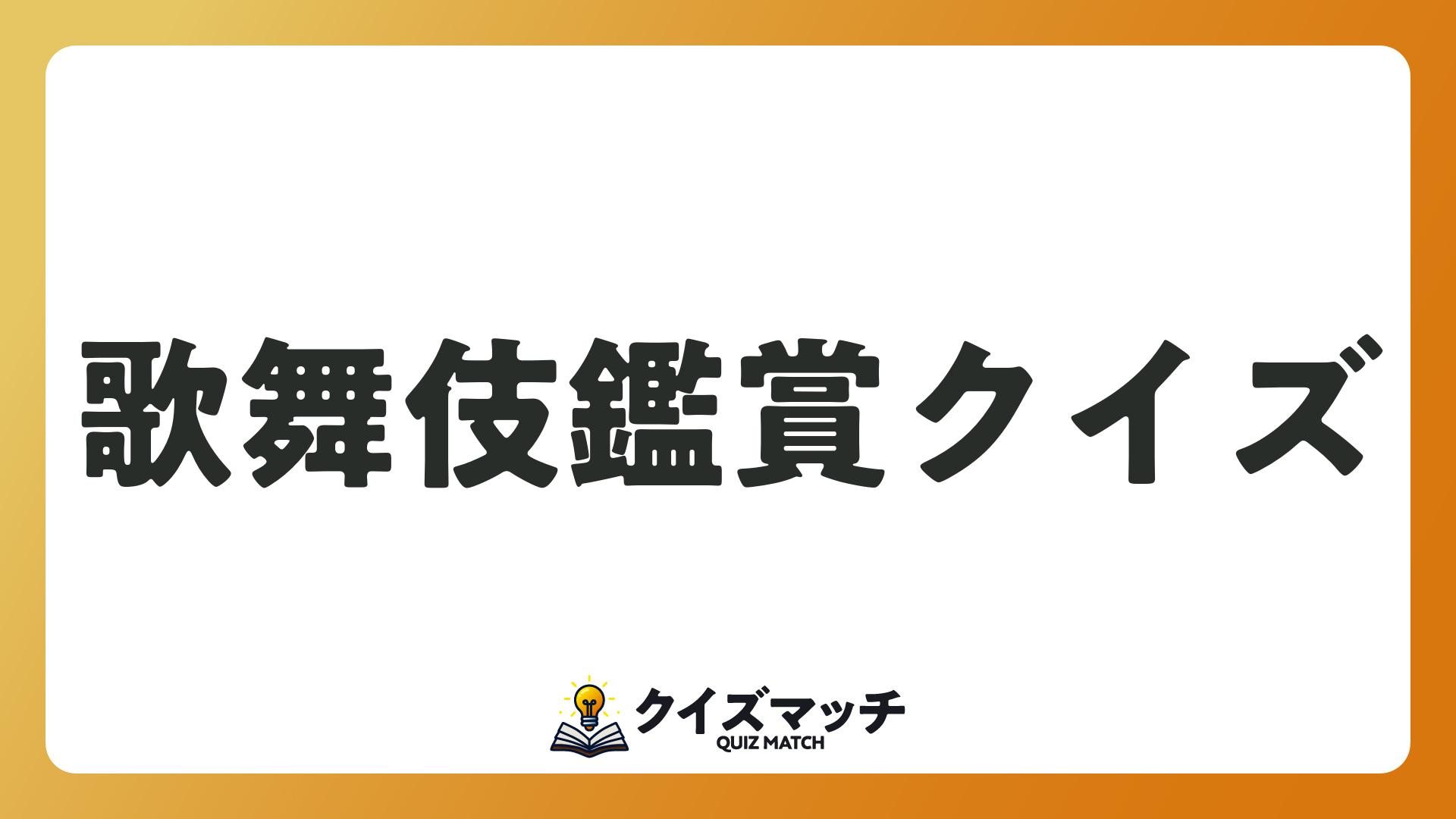歌舞伎の魅力を探る10問! 古来の伝統と粋を楽しもう
歌舞伎は日本の伝統芸能の代表格。華やかな舞台に映える歌と所作、登場人物の個性あふれる演技は見応えがあります。この記事では、歌舞伎ならではの演技様式や仕組み、観客との一体感など、この古典芸能の魅力に迫る10問のクイズをご用意しました。長い歴史の中で培われてきた独特の言葉やしぐさ、演出技法など、歌舞伎ならではの奥深さを楽しみながら学んでいただけます。歌舞伎の世界に思いを馳せ、舞台の魅力を堪能してみましょう。
Q1 : 歌舞伎の黒御簾の内側で演奏される下座音楽で、主に旋律を受け持つ中心的な楽器はどれか。
下座音楽は舞台の情景や心理を音で支える裏方の芸で、三味線が旋律と和声の要を担う。浄瑠璃系の語りや長唄、清元、常磐津などジャンルにより調弦や奏法を変え、曲想を的確に表現する。笛は情緒や合図、大鼓と小鼓はリズムと緊張感を加える役目だが、三味線が欠けると曲そのものが成立しないため「下座の柱」と言われる。太棹や細棹を使い分け、音域や響きを演目に合わせる工夫も重要である。
Q2 : 歌舞伎座などで開演前や場面転換で鳴らされる、拍子木を打ち鳴らす音を何と言うか。
柝は二枚の堅木を縦に打ち合わせて発する鋭い音で、幕が開く直前や暗転、転換の合図として客席に知らせる役目を持つ。江戸の芝居小屋では火事避難の信号も兼ねていたと伝わる。『つけ』は役者の動作を強調する床面の効果音、組太鼓や大鼓は長唄囃子の旋律・リズムを担当し、舞台の合図には用いられない。用途や鳴らし方が異なる点が歌舞伎通の鑑賞ポイントである。
Q3 : 歌舞伎の観客席で、決め所に掛け声をかけるファンのことを何と呼ぶか。
大向うは木戸銭の安い劇場最後方「大向こう」に陣取った通人の観客が語源で、舞台の見せ場で『成田屋!』『待ってました!』など屋号や決まり文句を絶妙のタイミングで放ち、劇場全体の高揚感を引き出す。現在は劇場公認の登録制となり作法が守られている。黒衣は舞台転換の黒装束係、お茶子は茶屋の給仕、差し金は小道具を操る棒のことで役割がまったく異なる。
Q4 : 歌舞伎において男性俳優が女性役を演じる専門の役柄を何と言うか。
女方は江戸期に女性の舞台出演が禁じられたことを受け、男性が女性役を演じるために成立した役柄である。歩き方は内股、襟足を見せる所作や指先の形、声の高さなど細部にわたり独自の型が持ち味。坂東玉三郎の『阿古屋』や片岡仁左衛門の『雪暮夜入谷畦道』などが名演として知られる。立役は男性役、敵役は悪役、子役は年少の役者が演じる場合で区分が異なる。
Q5 : 四代目市川團十郎が創始したとされる荒事の代表的な演目『暫』の主人公の名前は?
『暫』は元禄期に四代目市川團十郎が創出した荒事の集大成で、主人公は鎌倉権五郎景政である。真紅の筋隈と金の大鎧を身につけ、長刀を振りかざし『しばらく!』と大見得を切って悪家老を成敗する姿が圧巻。成田屋の家の芸として代々継承され、柝の合図、六方の花道引込みなど荒事の様式が凝縮されている。佐藤忠信は『義経千本桜』、与三郎は『与話情浮名横櫛』の人物で別演目である。
Q6 : 『助六由縁江戸桜』で助六の恋人として登場し、豪華な衣裳と高下駄が特徴の遊女は誰か。
花川戸助六と対を成す花魁揚巻は、紫地に桜模様の豪華な打掛や三枚歯の高下駄を履き、花道での出を華やかに演出する。揚巻は美貌だけでなく気風も良く、助六と息の合った啖呵の応酬が舞台の大きな魅力。女方の大役とされ、中村芝翫や中村魁春らが当り役として知られる。お嬢吉三は『三人吉三』、阿古屋は『壇浦兜軍記』、お軽は『仮名手本忠臣蔵』の登場人物で、衣裳や性格も全く異なる。
Q7 : 歌舞伎俳優の屋号として正しい組み合わせはどれか。
屋号は江戸時代の芝居茶屋や興行元の名残で、観客の掛け声にも用いられる重要な符号。市川宗家は初代團十郎が成田山新勝寺への願掛け成就にちなみ『成田屋』を名乗り、今日まで続く。播磨屋は中村吉右衛門、高嶋屋は尾上松緑、音羽屋は尾上菊五郎、松嶋屋は片岡仁左衛門などと家によって固定されるため、組み合わせを誤るとすぐに素人と見抜かれる。
Q8 : 花道から役者が袖へ去る際に、波を蹴立てるような足運びで大きく進む歩き方を何と呼ぶか。
六方は荒事の武者が大股で膝を高く上げ、両腕を大きく振りながら花道や舞台を進む足組で、海をかき分ける勢いや堂々とした力を象徴する。足拍子に合わせてつけ打ちが鳴り、囃子方の『ヨォーッ』の声も入り観客を惹きつける。六方には方向転換や速度の変化など複数の型があり、市川團十郎家や松本幸四郎家が得意とする。途中で見得を切る位置が『七三』、奈落からせり上がる装置が『すっぽん』であり混同できない。
Q9 : 歌舞伎の舞台で役者が視線を客席に向けて体を静止させる決めポーズを何と呼ぶか。
見得は歌舞伎に特有の演技法で、感情の頂点や物語の転換点で役者が体を大きく開き、片手を突き出したり首を傾けたりして静止しながら視線を客席に送る。長唄や柝の音が重なり観客は息をのんで注目する。これにより人物の心情や力感を誇張し、浮世絵にも多く描かれた。引抜きは衣裳早替り、六方は荒事の歩き方、つらねは長ぜりふで用途が異なる。
Q10 : 隈取(くまどり)と呼ばれる化粧法が主に用いられるのはどのような役柄か。
隈取は紅や藍などで大胆な筋や模様を描き顔貌を誇張する化粧で、主に荒事の立役、すなわち豪傑や武神など力強さを示す役柄に用いられる。色彩や形には意味があり、赤系は正義や勇気、藍や墨は悪、茶は妖怪を表す。特に『暫』の鎌倉権五郎や『勧進帳』の弁慶の紅隈が有名で、市川家が家の芸として継承してきた。女方は白塗りに紅差し、若衆は控えめな隅取り、老け役はしわ描きと化粧法が異なる。
まとめ
いかがでしたか? 今回は歌舞伎鑑賞クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は歌舞伎鑑賞クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。