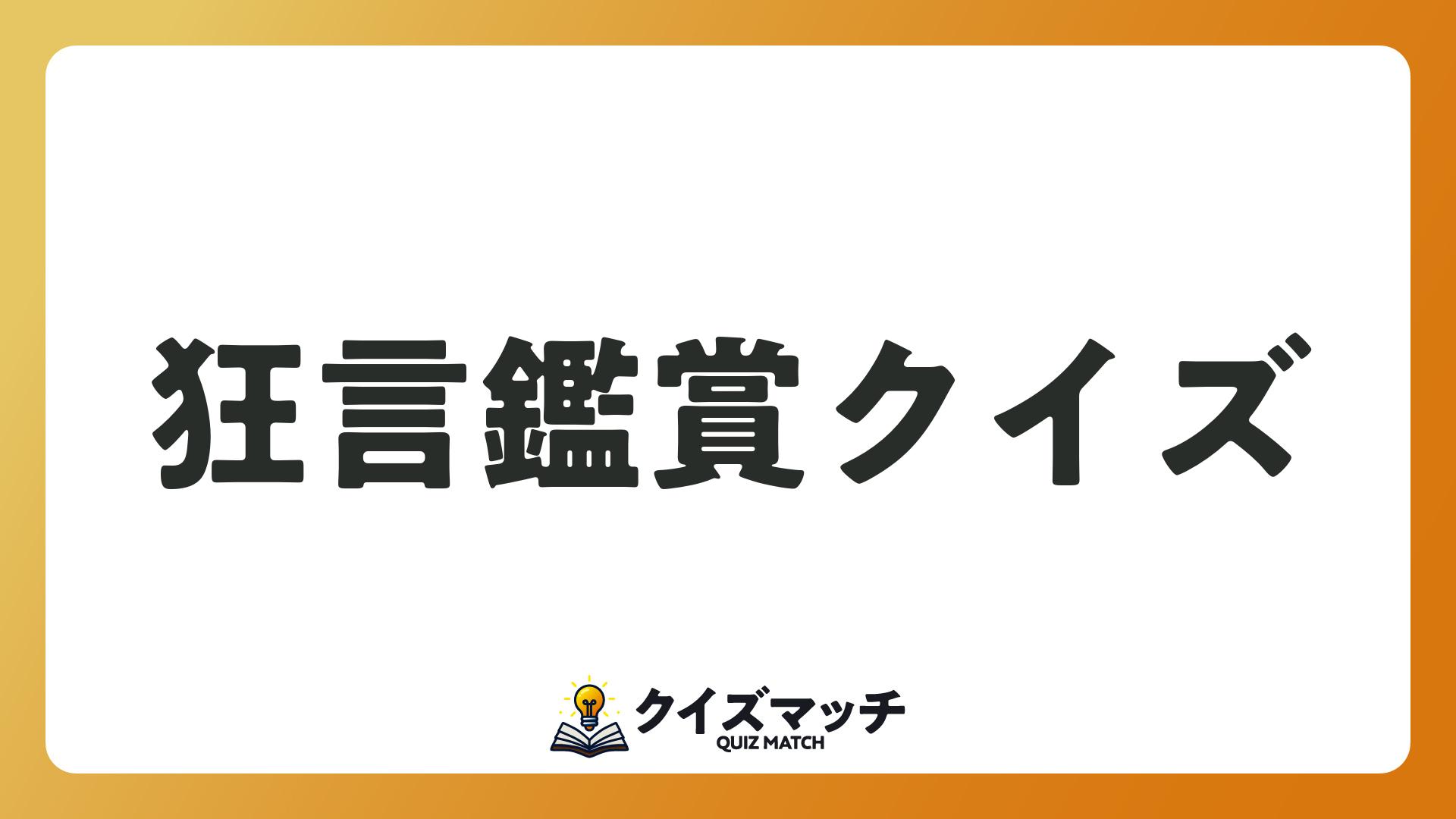狂言は、能楽の中でも特に庶民的でユーモア溢れる演目として知られています。この度は、そんな魅力あふれる狂言作品を題材にしたクイズをお届けします。狂言にまつわる様々な知識を問う全10問。舞台構造や衣装、登場人物、音楽など、狂言の奥深さを感じていただける内容となっております。狂言の世界をもっと楽しんでいただくきっかけとなれば幸いです。ぜひ、クイズにチャレンジしてみてください。
Q1 : 庶民の男役がよく着用する狂言独特の衣装で、袖を背中で結んだように見える膝丈の水色系の装束を何と呼ぶでしょうか。
水衣(みずごろも)は狂言で太郎冠者や次郎冠者など下層男性が着る代表的衣装。肩から袖を後ろに回して紐で結び、動きやすさと庶民性を示す。生地は浅葱・縹など水を思わせる色で、格調の高い狩衣や大口に比べ質素。狩衣は貴族や神職が用い、長袴は能の女性・貴族役の足元に用いる袴。着付けの違いにより役の位や性格を視覚的に伝えるのが狂言の衣装の大きな特徴で、水衣は軽快な所作と滑稽味を支える重要なアイテムとなる。
Q2 : 狂言でめったに用いられない面をあえて着け、狐と人間の化かし合いを描く名作はどれでしょうか。
狂言は能に比べ面を使用する演目が少ないが、『釣狐(つりぎつね)』は狐の精にふさわしい写実的な狐面を掛ける珍しい曲。老獪な猟師に化かし合いを挑む狐の悲哀と滑稽を兼ね備え、演者の高度な演技力が要求される。宇治の晒や昆布売、水掛聟はいずれも面を使わず生の表情で笑いを表現する典型的狂言。面を着けることで表情が隠れるため、『釣狐』では身振りや声色で感情を伝える必要があり、狂言師の力量が試される。従って正解は釣狐である。
Q3 : 狂言『棒縛』で、酒を盗み飲みしないよう主人が太郎冠者と次郎冠者に施す縛り方に用いられる道具はどれでしょうか。
『棒縛(ぼうしばり)』は主人が留守中の盗み酒を戒めようと太郎冠者らに棒を持たせ、両手を棒に縛り付けて動きを封じることで笑いを生む作品。縛られても踊りながら酒を飲む二人の所作が見どころ。鎖や帯では縛りの形が絵面的に弱く、手甲は腕当てで道具そのものが違う。棒は視覚的にも分かりやすく、縛られたまま踊る不自由さが滑稽を際立たせる。演者は片手が使えないため、バランスと呼吸が重要。ゆえに正解は棒である。
Q4 : 能楽堂で狂言が上演される際、地謡・囃子方などが座る位置として正しいのはどこでしょうか。
能舞台の客席から見ると舞台左手奥(舞台側からは右奥)に長いすが置かれ、そこに地謡が座る。囃子方はさらに後方に並び、狂言でも配置は基本的に同じ。橋掛かりはシテが出入りする通路で演奏者が陣取ることはない。常座はシテの定位置で演者が立つ場所であり、地謡や囃子が占有するわけではない。観客席脇に演奏者が入る様式は歌舞伎の黒御簾音楽などに見られるが、能狂言では採用されていない。したがって正解は舞台左後方に並ぶ地謡座である。
Q5 : 狂言の台詞に最も近い言語的特徴はどれでしょうか。
狂言は室町末期から江戸初期にかけて成立した台本が多く、台詞は当時の話し言葉を大幅に残す。発音や語尾、助詞の使い方は現代語とも古語とも異なる中世日本語で、観客は理解しやすいよう演者の間合いや身振りで意味を補う。奈良時代の万葉仮名は漢字仮名交じりで口語体系が違い、軍隊用語は時代も性質も異なる。現代語に近い部分もあるが、文法や語彙の相違が多い。古語注釈を読むと理解が深まり、室町の庶民生活が垣間見える。従って室町期の口語が正解である。
Q6 : 狂言が能と同じ舞台で演じられるとき、鏡板に老松が描かれ、観客から見て右手に橋掛かりが延びる独特の構造を持つこの舞台の呼称はどれか。
能楽の舞台は奈良県春日大社若宮御祭など神事に由来し、四本柱、大屋根、鏡板の松、橋掛かりという要素で構成される。狂言は能と同じ舞台を共有し、能舞台と総称される。歌舞伎座などは歌舞伎専用で構造も花道や回り舞台を備えるが、能舞台にはない。能舞台という語は劇場の固有名詞ではなく装置全体を指す点がポイントで、狂言鑑賞時に場所を確認すると能と狂言の演出上の近さが理解できる。以上の理由から正解は能舞台である。
Q7 : 狂言『附子』で主人に「毒だから決して蓋を開けるな」と言われた桶の中に実際に入っていたものは何か。
『附子』は附子=トリカブトの毒に見立てた甘味をめぐる滑稽劇で、太郎冠者と次郎冠者が留守中に誘惑に負けて桶を開け、中にあった砂糖を舐め尽くしてしまう。室町期の日本で砂糖は大変な高級品だったため、観客は二人の欲望に共感しつつも笑う。毒と言われても甘い香りに惹かれる人間の弱さを戯画化した作品で、甘酒や白味噌は用いられない。蜂蜜も当時は限られた人しか口にできず扱いが難しい。したがって桶に入っていたのは砂糖である。
Q8 : 狂言でシテ(主役)に対して補佐的に登場し、物語を動かすことも多い役柄「アド」の説明として最も適切なものはどれか。
能楽ではシテが中心人物だが、狂言ではシテとアドの掛け合いが笑いを生む。アドは主人や太郎冠者など役柄に応じて立場が変わるが、常にシテの相手役として行動し、話を展開させる。地謡は囃子方とともに舞台横で謡う歌隊でありアドとは異なる。舞台監督という裏方概念は伝統芸能に当てはめにくい。従ってアドを端的に表すなら「相手役・助演者」である。これを理解すると、配役表を見ただけであらすじの力関係が推測でき、鑑賞がより深まる。
Q9 : 能楽囃子は狂言にも用いられますが、次のうち狂言の伴奏で通常使われない楽器はどれでしょうか。
狂言の音楽は能と同じく笛・大鼓・小鼓・太鼓の四拍子から成る。必要に応じて太鼓を省くこともあるが、三味線はそもそも能楽囃子に含まれず、歌舞伎や浄瑠璃系統の楽器である。江戸期以降、三味線は日本音楽の主流となったが、能狂言は室町の形態を保持しているため導入されていない。大鼓・小鼓は肩当ての違いこそあれ必ず囃子方に登場し、太鼓は重厚な場面で響きを加える。よって狂言で使われないのは三味線である。
Q10 : 現在、日本の狂言には大蔵流ともう一つ大きな流派があります。それはどれでしょうか。
狂言は能と同じく流派制度をとり、江戸時代の幕府保護下で大蔵流と和泉流が確立した。観世・喜多・金春はいずれも能の流派で、狂言ではない。和泉流は江戸幕府の式楽となり京都・江戸で伝承されたが、明治維新後は太秦家・野村家などが中心となり現代へ継承している。大蔵流は東京では大藏彌右衛門家が宗家を務め、奈良春日大社の芸能を受け継ぐ。どちらの流派も型や詞が微妙に異なるため、同じ演目でも味わいが変わる。したがって答えは和泉流である。
まとめ
いかがでしたか? 今回は狂言鑑賞クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は狂言鑑賞クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。