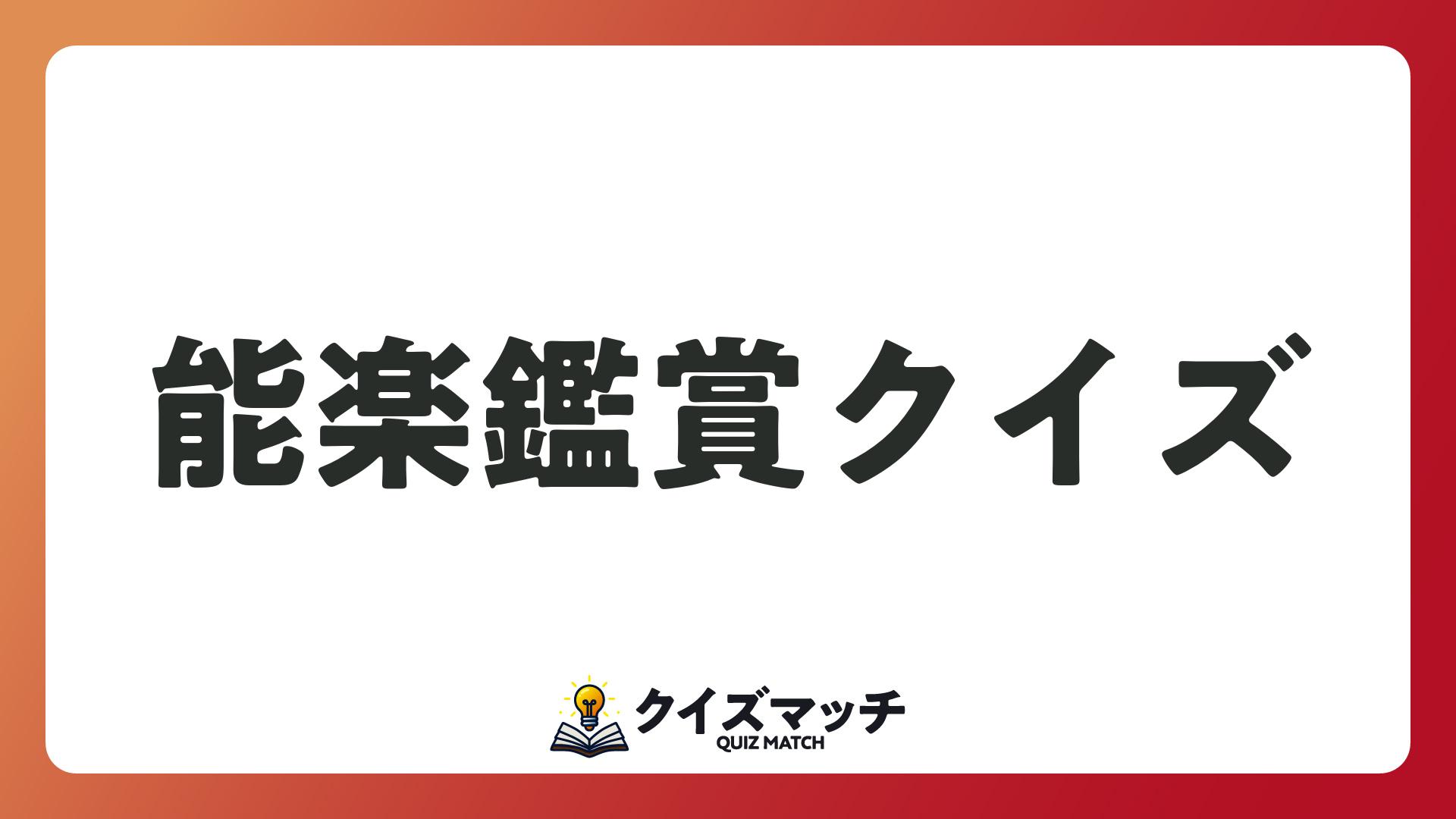能の奥深い世界に迫る能楽鑑賞クイズ
能の世界には、伝統的な演者集団による独特の音世界や表現手法、精緻な装束や仕草、そして幽玄な物語が息づいています。この記事では、そんな能の魅力に触れるべく、10問の能楽クイズをご用意しました。囃子方の役割、能面の表情、能舞台の特徴、代表的な演目など、能の奥深い世界をさまざまな角度から探ってみましょう。能の鑑賞をより深く楽しむための知識が、きっと皆様の心に響くはずです。
Q1 : 五番立の番組で、滑稽味や人間の狂気を扱い、終演後には祝言の舞で締めくくられる曲目分類はどれでしょうか。
五番立は古来、神物・男物(修羅物)・女物・狂物・鬼物の順で演じられ、一日を通じて宇宙観を表現しました。四番目の狂物(きょうもの)は狂気・滑稽・舞楽性を持ち、主人公が現実と妄想を行き来する筋が多いのが特徴です。『菊慈童』や『船弁慶』(前シテ)などに見られる祝言の舞や舞楽的要素が観客の気持ちを軽くし、次に来る鬼物との対比を作ります。神物は冒頭で荘厳に神を招き、鬼物は怨霊や妖鬼を描くため内容が異なります。
Q2 : 演目中に詞章を斉唱して舞台上の情景や心理を描写する地謡が着座する場所はどこでしょうか。
舞台正面やや下手寄りに横一列に設置された畳敷きのスペースを地謡座(じうたいざ)と呼びます。地謡は最大八名で構成され、シテやワキの心情、場面転換、季節の情景などを詞章と節で補完する重要な役割を担います。後見座は舞台奥下手にあり、衣装や小道具の補佐をする後見が控える場所であり、切戸口は楽屋と舞台を結ぶ出入り口、鏡の間は演者が装束を整える控室です。地謡座から発せられる声量とハーモニーが能の幽玄味を支えています。
Q3 : 能『船弁慶』の後シテとして出現し、壇ノ浦に沈んだ怨霊として義経一行を襲う武将は誰でしょうか。
『船弁慶』後場では、静御前と別れ西国へ逃れる義経を襲う怨霊として平知盛(たいらのとももり)が現れます。知盛は壇ノ浦の戦で入水し、屍を海に沈めた悲劇の平家武将で、能では甲冑姿の亡霊として船上に立ち現れ、義経に復讐しようとします。前場のシテは静御前であり、同一演目でシテが役替わりする趣向が大きな見どころです。平重盛は平家嫡男で生前没し、源義経・頼朝は源氏側であり後シテにはなりません。怨霊の凄惨さと法華経による成仏の対照がドラマを生みます。
Q4 : 大鼓奏者が強打と同時に発し、拍子の切れを高める独特の声を何と呼ぶでしょうか。
能の鼓方は楽器音とともに「掛け声」と総称される気合いを発します。大鼓方の「ヨー」「イヤー」など低く力強い声は音圧が高く、鼓皮の鋭い音と相乗して観客に緊張感を与えます。小鼓方はやや高音の「イッ」「ホウ」、太鼓方は打音に合わせ「ホウ」「トウ」などを出し、笛方は掛け声を出しません。これらの声は単なるリズム取りではなく、演者の気迫を具現化し、舞台のエネルギーを増幅させる重要な要素として長く継承されています。
Q5 : 観世・宝生・金春・金剛・喜多の五流派のうち、京都市上京区に本拠地を置く流派はどれでしょうか。
金剛流は奈良の興福寺に起源を持ちながら江戸時代以降京都を拠点に活動し、現在も京都市上京区の金剛能楽堂を本拠としています。息の長い謡と力強い所作が特色で、2013年には重要無形文化財保持者総合指定を受けています。観世流は東京渋谷の観世能楽堂を中心に、宝生流は文京区の宝生能楽堂、喜多流は目黒の喜多能楽堂が拠点で、いずれも京都ではありません。五流は互いに芸風を競いながら能の伝統を守り続けています。
Q6 : 能の囃子方は笛・小鼓・大鼓・太鼓の四役で構成されますが、このうち篠笛を演奏する人を何と呼ぶでしょうか。
能で使用される笛は篠竹製の能管で、能楽堂の空間に響き渡る鋭い音色が特徴です。笛を専門に担う囃子方は「笛方」と呼ばれ、観世流笛方、森田流笛方、一噌流笛方などの家元が存在します。小鼓方・大鼓方・太鼓方はいずれも鼓を打つ役ですが、リズムだけでなく掛け声でも演奏を彩ります。四役が揃うことで能特有の幽玄な音世界が生まれ、シテの舞や地謡の節と一体となって舞台を支えています。
Q7 : 世阿弥とともに能を大成させ、芸術論『風姿花伝』を著した人物は誰でしょうか。
『風姿花伝』は室町時代に書かれた能楽の根本的な芸術論で、役者の成長段階、花と幽玄の美学、稽古論など多岐にわたります。著者は観阿弥の子である世阿弥(本名・観世元清)で、将軍足利義満の庇護を受けて能を洗練させました。観阿弥は父として基礎を築きましたが執筆は行っていません。金春禅竹は後代の理論家、喜多七太夫は江戸期の喜多流祖であり正解ではありません。
Q8 : 若い女性の清楚さや可憐さを表現するために用いられる代表的な能面はどれでしょうか。
小面(こおもて)は滑らかな頬とわずかに上がった口角、澄んだ目元で少女から若い女性を象徴する能面です。肌の色もやや白みを帯び、内面の慎ましさを感じさせます。般若は嫉妬に狂う女性の鬼面、翁は祝祭性を帯びた老翁、猩々は酒好きの水の精を表す面で、いずれも表情や役柄が大きく異なります。小面の微妙な角度の変化で喜びや哀愁を演じ分けることが役者の腕の見せどころとなります。
Q9 : 能の拍子構成『序破急』のうち、舞が中盤の盛り上がりに入る「破」の切り替えを力強い打音で示す囃子方はどれでしょうか。
序破急は能だけでなく日本芸能に広く見られる構成ですが、能では大鼓方(おおかわかた)が強烈な一打と「ヨー」などの掛け声で『破』への移行を鮮明にします。大鼓は頭摺り皮を火であぶり締めて高い音を出すため、舞台上で最も鋭い衝撃音を生みます。笛は旋律、小鼓はしなやかなリズム、地謡は詞章を担いますが、破の入り口を強調するのは大鼓の役割とされています。これにより場面転換やシテの心情の高揚が観客に伝わります。
Q10 : 能舞台で客席正面奥に描かれている老松の絵がある板壁の名前は何でしょうか。
鏡板(かがみいた)は奈良・春日大社の影響を受けたとされる老松の彩色壁で、舞台に神聖な空間観を与えます。能では舞台そのものが神域と見立てられ、鏡板の松は常緑で永遠を象徴し、神が降り立つ依代とも解釈されます。橋掛りを進む演者は鏡板前で方向を変え、天地人の結節点として舞台が成立します。地謡座や後見座はいずれも床座ですが板壁ではありません。鏡板の存在が能舞台を他の劇場と一線画す大きな特徴です。
まとめ
いかがでしたか? 今回は能楽鑑賞クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は能楽鑑賞クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。